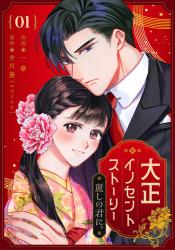屋敷を囲む築地塀の上に千人、屋根の上にも千人、弓矢をつがえた随身達が待機して、じっと夜空を見上げている。
帝から遣わされたこれ程の警護は、一人の姫君を守る為のものだった。
公達からの求婚に、その姫がことごとく断りを入れていたのは、この日を迎える事が、わかっていたからなのかもしれない。
ふっと、そうであったのかと、皆の脳裏をかすめるが、さて、これは、真の事なのかと、思ってもいた。
──天の月から迎えが来る。あちらへ、戻らなければならない──。
姫は、さめざめと泣き、育ての親である、翁と婆女を戸惑わせたという。
そして、姫の光り輝く美しさを目にしてしまった帝は、戻してはならぬ。迎えを追い返せ。と、命じられた。
天からの使いを、当の姫君は嫌がっている。
帰りたくはないが、仕方がないと涙する。
では、その迎えを追い払えばよいではないか。そうすれば、姫は、安寧に暮らすことができるであろう。
それが、帝のお考えだった。
確かに、天から下ってくる者など、人であって人でない。邪気にまみれているやもしれない。
弓を構える随身達も、受け入れてはならぬものと心得て、姫を守ろうとしていた。
昇る月が、輝きを増していく。
中秋の名月であるはずなのに、誰一人見惚れる者はおらず。
屋敷は数千の随身に取り囲まれているが、物音一つしなかった。
野の虫達も、可憐でか細い鳴き声を発することは無い。
周囲は、何かを察して息を潜めるかのように、沈黙ともいえる静かさを保っていた。
帝から遣わされたこれ程の警護は、一人の姫君を守る為のものだった。
公達からの求婚に、その姫がことごとく断りを入れていたのは、この日を迎える事が、わかっていたからなのかもしれない。
ふっと、そうであったのかと、皆の脳裏をかすめるが、さて、これは、真の事なのかと、思ってもいた。
──天の月から迎えが来る。あちらへ、戻らなければならない──。
姫は、さめざめと泣き、育ての親である、翁と婆女を戸惑わせたという。
そして、姫の光り輝く美しさを目にしてしまった帝は、戻してはならぬ。迎えを追い返せ。と、命じられた。
天からの使いを、当の姫君は嫌がっている。
帰りたくはないが、仕方がないと涙する。
では、その迎えを追い払えばよいではないか。そうすれば、姫は、安寧に暮らすことができるであろう。
それが、帝のお考えだった。
確かに、天から下ってくる者など、人であって人でない。邪気にまみれているやもしれない。
弓を構える随身達も、受け入れてはならぬものと心得て、姫を守ろうとしていた。
昇る月が、輝きを増していく。
中秋の名月であるはずなのに、誰一人見惚れる者はおらず。
屋敷は数千の随身に取り囲まれているが、物音一つしなかった。
野の虫達も、可憐でか細い鳴き声を発することは無い。
周囲は、何かを察して息を潜めるかのように、沈黙ともいえる静かさを保っていた。