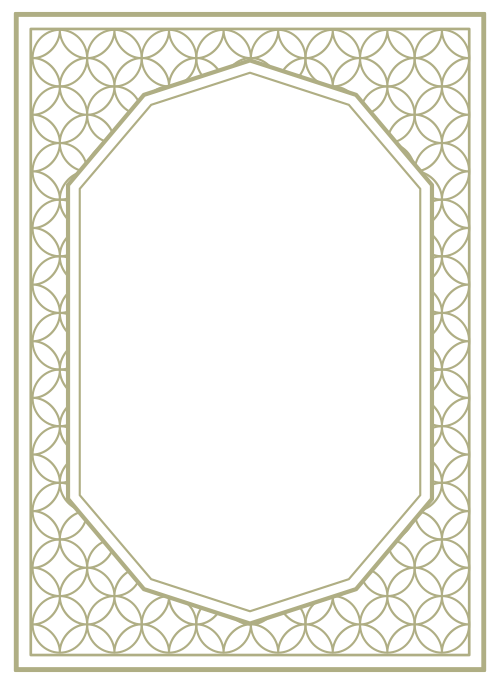柚月は自室の窓を開け、意味もなく景色を眺める。20年近く見慣れた景色に今更新鮮味を感じないが、もう見ることもないと思うと目に焼き付けておこうという気にもなった。柚月は窓から身を乗り出して下を見下ろす。ここは2階だから当然ながら高い。落ちたら大怪我を負いながらも助かるかもしれないし、打ちどころが悪ければ死ぬかもしれない。柚月は後者を望んでいた。
母が死んでから柚月は自分なりに努力し続けた。父親が自分を気まずそうに見ることも、再婚相手の義母が余所余所しいことも、3歳違いの妹にのみ両親の関心が向けられることも仕方がないと諦めた。それでも彼だけは柚月を見てくれるのだと、自分と同じ感情を抱いていないことは分かっていたけれどそれで良かった。結婚して、家族になればいつかはと淡い期待を抱いていた。だというのに、彼は柚月を裏切った。柚月を1番絶望に突き落とす方法で。
もっと早く打ち明けて欲しかった。恨み言の1つや2つ、いや自分の語彙力の限りを尽くし罵詈雑言をぶつけただろうが柚月の当然の権利であり、彼らは甘んじて受けるべきだ。しかし、今さっき告げられた事実は柚月の中からありとあらゆる気力を奪うには十分だった。そして彼が告げた一言。
「柚月は1人でも生きていけるだろ?美月には俺が居ないと…」
その瞬間心がポキリ、と折れる音がした。甘えるのが下手で人に頼るのが苦手な人間、それが柚月だ。しかし、好きでそうなった訳ではない。そうならざるを得なかっただけだが、言ったところで無駄だと黙りこくった。その後も彼らが何かを話していたが耳には入らなかった。方々への説明と報告を彼らに押し付け、柚月は部屋に閉じこもっている。
もう、疲れてしまった。この後柚月に向けられる憐憫や同情の眼差し、そして嘲笑の眼差しを想像するだけで身体が勝手に震えてくる。彼らには非難の目が向けられるだろうが、元々柚月よりもお似合いだと言われていた2人だ。意外と早く周囲に受け入れられるかもしれない。それも柚月には耐えられない。
すると襖をノックする音が聞こえる。既にあのことは邸中に知れ渡っているだろう。好き勝手使用人達が噂する中、唯一柚月に付いてくれている侍女が心配して様子を見に来たのだ。柚月は不意に、とても残酷なことを思い付く。彼女に証人になってもらうのだ。これから起こることは決して事故ではなく、柚月による意思なのだと。
「…柚月様、失礼致します…っ!何をなさっているのです!危ないからこちらにお戻りください!」
侍女の栞が叫び、窓に駆け寄ろうとする。柚月は無理矢理作った笑みを顔に張り付けると、何の躊躇いもなく窓から飛び降りた。栞の耳を劈くような悲鳴、あっという間に近づいてくる地面。
身体が地面に叩きつけられ、全身に凄まじい痛みを感じた。走馬灯が頭の中に流れていき、ふとある人の顔が浮かんだ。話したのは1度きり。それからは遠目で見かけただけ。それでも彼のことは柚月の記憶に深く残っていた。
死ぬ前に思い出すのが幼い日の記憶なんて自分の人生はなんと虚しいものだったのだろう。もしやり直せるなら、自分を捨てる婚約者も無関心な家族も捨てて好きなように生きていきたい。
柚月の意識は段々と闇へと消えていく。東雲柚月の22年の人生はこうして幕を閉じた、はずだった。
母が死んでから柚月は自分なりに努力し続けた。父親が自分を気まずそうに見ることも、再婚相手の義母が余所余所しいことも、3歳違いの妹にのみ両親の関心が向けられることも仕方がないと諦めた。それでも彼だけは柚月を見てくれるのだと、自分と同じ感情を抱いていないことは分かっていたけれどそれで良かった。結婚して、家族になればいつかはと淡い期待を抱いていた。だというのに、彼は柚月を裏切った。柚月を1番絶望に突き落とす方法で。
もっと早く打ち明けて欲しかった。恨み言の1つや2つ、いや自分の語彙力の限りを尽くし罵詈雑言をぶつけただろうが柚月の当然の権利であり、彼らは甘んじて受けるべきだ。しかし、今さっき告げられた事実は柚月の中からありとあらゆる気力を奪うには十分だった。そして彼が告げた一言。
「柚月は1人でも生きていけるだろ?美月には俺が居ないと…」
その瞬間心がポキリ、と折れる音がした。甘えるのが下手で人に頼るのが苦手な人間、それが柚月だ。しかし、好きでそうなった訳ではない。そうならざるを得なかっただけだが、言ったところで無駄だと黙りこくった。その後も彼らが何かを話していたが耳には入らなかった。方々への説明と報告を彼らに押し付け、柚月は部屋に閉じこもっている。
もう、疲れてしまった。この後柚月に向けられる憐憫や同情の眼差し、そして嘲笑の眼差しを想像するだけで身体が勝手に震えてくる。彼らには非難の目が向けられるだろうが、元々柚月よりもお似合いだと言われていた2人だ。意外と早く周囲に受け入れられるかもしれない。それも柚月には耐えられない。
すると襖をノックする音が聞こえる。既にあのことは邸中に知れ渡っているだろう。好き勝手使用人達が噂する中、唯一柚月に付いてくれている侍女が心配して様子を見に来たのだ。柚月は不意に、とても残酷なことを思い付く。彼女に証人になってもらうのだ。これから起こることは決して事故ではなく、柚月による意思なのだと。
「…柚月様、失礼致します…っ!何をなさっているのです!危ないからこちらにお戻りください!」
侍女の栞が叫び、窓に駆け寄ろうとする。柚月は無理矢理作った笑みを顔に張り付けると、何の躊躇いもなく窓から飛び降りた。栞の耳を劈くような悲鳴、あっという間に近づいてくる地面。
身体が地面に叩きつけられ、全身に凄まじい痛みを感じた。走馬灯が頭の中に流れていき、ふとある人の顔が浮かんだ。話したのは1度きり。それからは遠目で見かけただけ。それでも彼のことは柚月の記憶に深く残っていた。
死ぬ前に思い出すのが幼い日の記憶なんて自分の人生はなんと虚しいものだったのだろう。もしやり直せるなら、自分を捨てる婚約者も無関心な家族も捨てて好きなように生きていきたい。
柚月の意識は段々と闇へと消えていく。東雲柚月の22年の人生はこうして幕を閉じた、はずだった。