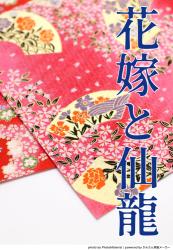照る月が中天に差し掛かる頃、御簾の下りた母屋の中、梓子は目を覚ました。胸元を軽く押さえながら身を起こすが、女房たちは熟睡しているのか、局から馳せ参じる気配はない。
唐突な目覚めは、夢見のせいだ。
熱病に侵される前夜、そして奇跡の快復を遂げたのち、梓子は時折、月夜の山中、巨大な鳥居の下に佇む人物の夢を見るようになった。
最初は、梓子と同じか、少し年少の少年だった。それが季節の巡りと共に成長し、今では梓子よりも年長に思える、均整の取れた体躯の青年である。
顔はよく判らない。彼はいつも後ろ姿で、稀に、振り向きかけた鼻筋が見える程度だ。だがその稜線の貴やかさだけで、自ずと造作の秀麗さが窺えた。
最初の夢では、彼は梓子と対面し、しかも何かを告げてきたはずなのだ。しかし直後の熱病のせいで記憶は混濁し、向かい合ったこと語りかけられたこと自体は覚えていても、容貌や内容は思い出せなかった。以降その背は沈黙を貫き、一瞥も一言もない。
そして彼の夢を見ると、決まって、胸元の羽根の形の痣が仄かに熱を帯びるのだった。
夢解きするまでもなく、夢の訪ね人は、自分を恋い慕う者。裳着を待っていたかのように当岐大社から婚文が届いたことでそれは確信に変わった。大社の若君こそが夢の君。三つ折れ羽は当岐の社紋、祀るのは翼持つ神である。
この縁は山神にも認められたもの。それどころか、山神こそが審神者を通じて梓子を望んでいるのかもしれなかった。古来より、神と人との婚姻譚は枚挙に暇がない。
……そうでなければ、二年も訪いのない相手など、とうに切り捨てている。
相変わらず文は頻繁に寄越すし、正月の卯杖卯槌や端午の薬玉、重陽の茱萸袋なども見事な品で、特に中秋には常にも増して、女房たちにもお裾分けできるほど大量の贈り物が届いた。
けれど、こちらがどれほど思わせぶりな文を返しても、当人は一度も訪ねて来なかった。
気に障るのはそれだけではない。暗闇の中、梓子は文箱を見遣る。
どういうわけか、若君の歌は、「あかねさす」という枕詞を詠み込んでいるものが多かった。確かに「日」「昼」「月」「君」など、かかる単語は多いが、数多ある中から、何故よりにもよってそれを選ぶのか。
たとえば。
あかねさす きみをみそめし かのよるの はなのかをこひ いまもかぐはし
初めてあなたを見た夜を忘れられない――――今一度会いたい
それに対し梓子は、敢えて己にゆかりある枕詞を用いた歌を返した。
あづさゆみ はるにたまひし はなふみは いまもかぐはし たどりきたらむ
春に初めて梅の枝と共に贈られた文を今も大切にしています、その残り香を辿り、訪ねてきてください――――
勿論名を記してはいないが、薄様の色は葉の青、梓の枝に結んで送った。しかしそれ以降も「あかねさす」ばかり散見し、「あづさゆみ」を詠んだ歌は一首もない。そもそも文を記す薄様も紅や紫がかった紙が多く、反物なども同様の傾向にあった。
しかも、「かの夜の 花の香を恋ひ」と焦がれていた歌も、次第に「朝をうらみ 夕を恋ひ恋ふ」などと夢での逢瀬を喜ぶようになっては、奥手にも程がある。夢を壊さないよう返歌を詠むのも一苦労だ。
(早く結婚して、この家を継ぐ子を成さなければならないのに)
幼い頃より「鬼祓う姫」として多少名が知れていたこともあって、若君のほかにも懸想文はいくつか届いた。けれどそれは、既に妻妾も子女もある公達のつまみ食いであったり、任地で私腹を肥やしただけの国司であったり、酷いものになると地下の判官や主典だったりと、凡そ梓子の目に適うものではなく、枕を共にした相手もいたものの、本気で三夜通ってくれる者はいなかった。
東北対で侘しく暮らすばけものの妹は、梓子ばかりが父母に愛され幸せだと思っているだろう。
けれど梓子は知っている。両親の、特に父尚方の親心は、そんな無償の愛ではない。
幼い姉妹が立て続けに熱病に倒れ、顔と胸に痕が残ってしまったとき、彼は嘆いた。揃ってこれでは婿取りも望めない、我が家はお終いだ、と。
それでも父は父。だから梓子は、己の価値が失われることを怖れ、無能な妹を過剰に貶めもした。そうすれば自分は、自分だけが、父の自慢の娘でいられる。
男にとって、所詮女は家のための駒。己の道具だと思うからこそ愛でるのだ。
それでも、京に生きる以上、その呪縛からは逃れられない。
目が冴えてしまい、梓子は褥を出た。衾としていた袿衣をしどけなく羽織り、黒髪の乱れもそのままに、御簾をくぐって枢戸から簀子縁に降り立つ。
振り放け見た空には薄く棚引く雲も浮かんでいるが、隈のない月は皓々と庭の木々や池の水面を照らしていた。
深まった夜の底に咲く藤の花群れに目を遣り、その手前に架かる反り橋で身じろぐ影に視線を向ける。
月明かりの中、闇に隠れたるものどもを見通す梓子の目に、それは金色に光る目を持つ一羽の大柄な烏のように見えた。
……違う。二羽の烏が、一羽に見えるほど睦まじく寄り添い合っているのだ。
傍ら寂しき一人寝の夜を幾つ数えたか知れない梓子は、互いを恋い番う烏に忌々しげに背を向け、枢戸の内へと戻っていった。
唐突な目覚めは、夢見のせいだ。
熱病に侵される前夜、そして奇跡の快復を遂げたのち、梓子は時折、月夜の山中、巨大な鳥居の下に佇む人物の夢を見るようになった。
最初は、梓子と同じか、少し年少の少年だった。それが季節の巡りと共に成長し、今では梓子よりも年長に思える、均整の取れた体躯の青年である。
顔はよく判らない。彼はいつも後ろ姿で、稀に、振り向きかけた鼻筋が見える程度だ。だがその稜線の貴やかさだけで、自ずと造作の秀麗さが窺えた。
最初の夢では、彼は梓子と対面し、しかも何かを告げてきたはずなのだ。しかし直後の熱病のせいで記憶は混濁し、向かい合ったこと語りかけられたこと自体は覚えていても、容貌や内容は思い出せなかった。以降その背は沈黙を貫き、一瞥も一言もない。
そして彼の夢を見ると、決まって、胸元の羽根の形の痣が仄かに熱を帯びるのだった。
夢解きするまでもなく、夢の訪ね人は、自分を恋い慕う者。裳着を待っていたかのように当岐大社から婚文が届いたことでそれは確信に変わった。大社の若君こそが夢の君。三つ折れ羽は当岐の社紋、祀るのは翼持つ神である。
この縁は山神にも認められたもの。それどころか、山神こそが審神者を通じて梓子を望んでいるのかもしれなかった。古来より、神と人との婚姻譚は枚挙に暇がない。
……そうでなければ、二年も訪いのない相手など、とうに切り捨てている。
相変わらず文は頻繁に寄越すし、正月の卯杖卯槌や端午の薬玉、重陽の茱萸袋なども見事な品で、特に中秋には常にも増して、女房たちにもお裾分けできるほど大量の贈り物が届いた。
けれど、こちらがどれほど思わせぶりな文を返しても、当人は一度も訪ねて来なかった。
気に障るのはそれだけではない。暗闇の中、梓子は文箱を見遣る。
どういうわけか、若君の歌は、「あかねさす」という枕詞を詠み込んでいるものが多かった。確かに「日」「昼」「月」「君」など、かかる単語は多いが、数多ある中から、何故よりにもよってそれを選ぶのか。
たとえば。
あかねさす きみをみそめし かのよるの はなのかをこひ いまもかぐはし
初めてあなたを見た夜を忘れられない――――今一度会いたい
それに対し梓子は、敢えて己にゆかりある枕詞を用いた歌を返した。
あづさゆみ はるにたまひし はなふみは いまもかぐはし たどりきたらむ
春に初めて梅の枝と共に贈られた文を今も大切にしています、その残り香を辿り、訪ねてきてください――――
勿論名を記してはいないが、薄様の色は葉の青、梓の枝に結んで送った。しかしそれ以降も「あかねさす」ばかり散見し、「あづさゆみ」を詠んだ歌は一首もない。そもそも文を記す薄様も紅や紫がかった紙が多く、反物なども同様の傾向にあった。
しかも、「かの夜の 花の香を恋ひ」と焦がれていた歌も、次第に「朝をうらみ 夕を恋ひ恋ふ」などと夢での逢瀬を喜ぶようになっては、奥手にも程がある。夢を壊さないよう返歌を詠むのも一苦労だ。
(早く結婚して、この家を継ぐ子を成さなければならないのに)
幼い頃より「鬼祓う姫」として多少名が知れていたこともあって、若君のほかにも懸想文はいくつか届いた。けれどそれは、既に妻妾も子女もある公達のつまみ食いであったり、任地で私腹を肥やしただけの国司であったり、酷いものになると地下の判官や主典だったりと、凡そ梓子の目に適うものではなく、枕を共にした相手もいたものの、本気で三夜通ってくれる者はいなかった。
東北対で侘しく暮らすばけものの妹は、梓子ばかりが父母に愛され幸せだと思っているだろう。
けれど梓子は知っている。両親の、特に父尚方の親心は、そんな無償の愛ではない。
幼い姉妹が立て続けに熱病に倒れ、顔と胸に痕が残ってしまったとき、彼は嘆いた。揃ってこれでは婿取りも望めない、我が家はお終いだ、と。
それでも父は父。だから梓子は、己の価値が失われることを怖れ、無能な妹を過剰に貶めもした。そうすれば自分は、自分だけが、父の自慢の娘でいられる。
男にとって、所詮女は家のための駒。己の道具だと思うからこそ愛でるのだ。
それでも、京に生きる以上、その呪縛からは逃れられない。
目が冴えてしまい、梓子は褥を出た。衾としていた袿衣をしどけなく羽織り、黒髪の乱れもそのままに、御簾をくぐって枢戸から簀子縁に降り立つ。
振り放け見た空には薄く棚引く雲も浮かんでいるが、隈のない月は皓々と庭の木々や池の水面を照らしていた。
深まった夜の底に咲く藤の花群れに目を遣り、その手前に架かる反り橋で身じろぐ影に視線を向ける。
月明かりの中、闇に隠れたるものどもを見通す梓子の目に、それは金色に光る目を持つ一羽の大柄な烏のように見えた。
……違う。二羽の烏が、一羽に見えるほど睦まじく寄り添い合っているのだ。
傍ら寂しき一人寝の夜を幾つ数えたか知れない梓子は、互いを恋い番う烏に忌々しげに背を向け、枢戸の内へと戻っていった。