すみません。「何の話だ」って思いますよね。
「きおく文学賞」の話は、これから読んでいただく文章の前座みたいなものでした。
ここからが本題です。
先日、会社終わりに小説を書こうとパソコンを開いたとき、デスクトップに大学時代のレポートがあるのが目に入りました。
レポート類は全てUSBに移して管理しているつもりだったのですが、そのレポートだけうっかりパソコンに置き去りにしていたようです。
手前味噌ですが読んでみたら思いのほか面白く、あなたにも知ってほしいと思ったので、「ノベマ!」にて公開することにしました。
見つけたのは、大学3年生のときに書いた心理学のレポートです。
講義で一番面白かった心理学の話題を一つとりあげ、それについて自由に書く……という感じのレポートで、私が選んだ題材は「偽りの記憶」でした。
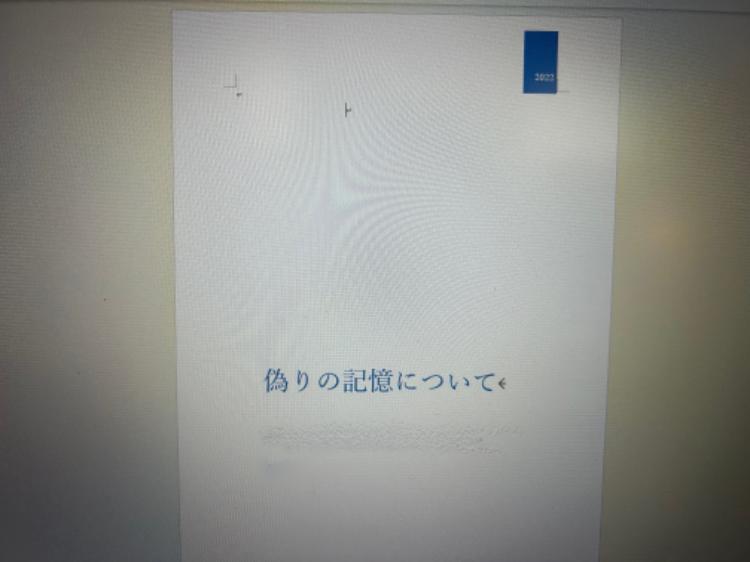
※個人情報にはモザイクを入れています。
「偽りの記憶」というのは、実際には起こっていない現象、経験していない事柄等をなぜか「記憶」として保有している状態を指す心理学用語です。
一例をあげてみます。
Aさんには、幼少期両親に人気のない山に置き去りにされた記憶があり、心のどこかでずっと両親を「怖い」と感じていた。
しかしそのような事実はなく、そもそも「小さい頃、家族で人気のない山に行った」というエピソードそのものが存在しなかった。
蓋をあけてみたら、「山に置き去り」というのは当時Aさんが見ていた映画の中の出来事だった。
あまりにもショッキングなシーンだったため、自分自身に起きた出来事として脳に定着していたらしい。
こんな例を見ると特殊な現象のような感じがしますが、大なり小なり誰もがこうした現実と食い違う記憶を持っているんじゃないかと思います。
例えば幼少期の写真を見たとき、自分の記憶と写り込んでいるもののギャップに驚いたことはないですか。幼少期住んでいたアパートの屋根が、白だと記憶していたのに、写真を見たら黒だった。これくらいのことなら、あなたにもあるはずです。
上記のような例であれば実害はありませんが、過去には「偽りの記憶」による冤罪事件が起き、何の罪も犯していない人が犯罪者として裁判にかけられた例もあるそうです。
実在しない事件でも、存在するものとして信じられてしまえば、実在した出来事として扱われてしまう場合があるんですね。
そう考えると、「偽りの記憶」を持っていることは想像以上に恐ろしいことなのかもしれません。自分の記憶はどこまでが本物で、それを証明する術はないのでしょうか。
レポートには、三人の友人や先輩に、自身の「偽りの記憶」に関して聞き取り調査した記録が残っていました。
文字起こししたものをそのまま記載すると読みづらいので、最後まで読んでいただけるよう話をわかりやすくまとめたものを、次ページ以降で紹介していきます。
「きおく文学賞」の話は、これから読んでいただく文章の前座みたいなものでした。
ここからが本題です。
先日、会社終わりに小説を書こうとパソコンを開いたとき、デスクトップに大学時代のレポートがあるのが目に入りました。
レポート類は全てUSBに移して管理しているつもりだったのですが、そのレポートだけうっかりパソコンに置き去りにしていたようです。
手前味噌ですが読んでみたら思いのほか面白く、あなたにも知ってほしいと思ったので、「ノベマ!」にて公開することにしました。
見つけたのは、大学3年生のときに書いた心理学のレポートです。
講義で一番面白かった心理学の話題を一つとりあげ、それについて自由に書く……という感じのレポートで、私が選んだ題材は「偽りの記憶」でした。
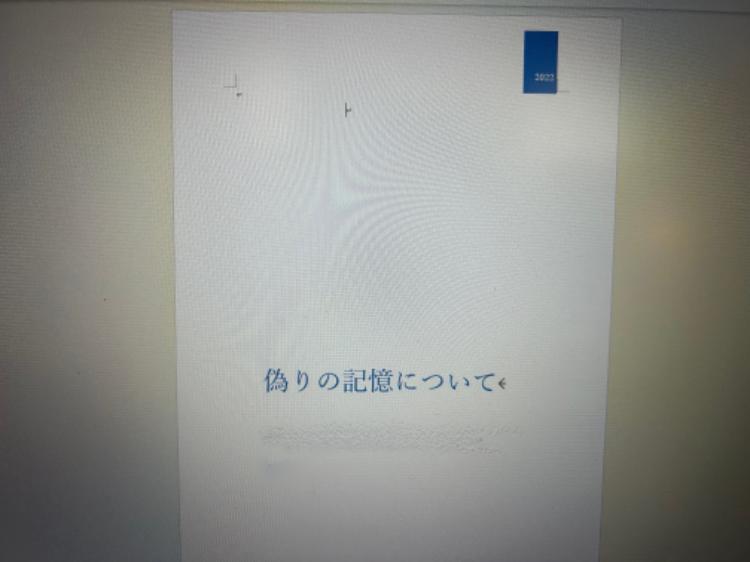
※個人情報にはモザイクを入れています。
「偽りの記憶」というのは、実際には起こっていない現象、経験していない事柄等をなぜか「記憶」として保有している状態を指す心理学用語です。
一例をあげてみます。
Aさんには、幼少期両親に人気のない山に置き去りにされた記憶があり、心のどこかでずっと両親を「怖い」と感じていた。
しかしそのような事実はなく、そもそも「小さい頃、家族で人気のない山に行った」というエピソードそのものが存在しなかった。
蓋をあけてみたら、「山に置き去り」というのは当時Aさんが見ていた映画の中の出来事だった。
あまりにもショッキングなシーンだったため、自分自身に起きた出来事として脳に定着していたらしい。
こんな例を見ると特殊な現象のような感じがしますが、大なり小なり誰もがこうした現実と食い違う記憶を持っているんじゃないかと思います。
例えば幼少期の写真を見たとき、自分の記憶と写り込んでいるもののギャップに驚いたことはないですか。幼少期住んでいたアパートの屋根が、白だと記憶していたのに、写真を見たら黒だった。これくらいのことなら、あなたにもあるはずです。
上記のような例であれば実害はありませんが、過去には「偽りの記憶」による冤罪事件が起き、何の罪も犯していない人が犯罪者として裁判にかけられた例もあるそうです。
実在しない事件でも、存在するものとして信じられてしまえば、実在した出来事として扱われてしまう場合があるんですね。
そう考えると、「偽りの記憶」を持っていることは想像以上に恐ろしいことなのかもしれません。自分の記憶はどこまでが本物で、それを証明する術はないのでしょうか。
レポートには、三人の友人や先輩に、自身の「偽りの記憶」に関して聞き取り調査した記録が残っていました。
文字起こししたものをそのまま記載すると読みづらいので、最後まで読んでいただけるよう話をわかりやすくまとめたものを、次ページ以降で紹介していきます。



