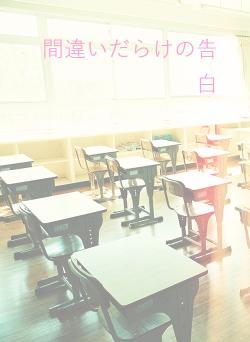「金ねーな」
田崎秀一郎と書かれた通帳を睨みながら、何もない部屋でため息をついた。
最後に入ったバイト代も底をつき、このままだと今月の家賃すら払えない。
「さすがに無職で家無しはヤバすぎだろ」
どこでどう間違えたのか。
ちゃんとした大学を出たものの、何社も受けた就職活動は全落ち。
そこからオレの転落人生は始まった。
うるさい親たちは地元に帰ってこいと言ったが、何もない田舎に今さら帰る気などなれなかった。
だからコンビニや日雇いバイトで食いつないでいたが、店長と喧嘩をしてコンビニはクビになった。
それがつい先月。
その後、短時間バイトばかりを繰り返していたらこの有様だ。
「どーすっかな」
実家に帰るのは最終手段として、なんとか食う金と家賃だけは稼がないと。
いつものように短時間バイトをスマホで漁り始めると、ふと一件の、おかしな募集に目がいった。
深夜の散歩好きな方必見!
夜、猫を探すだけのバイトです!
指定された道を通り、猫を探すだけ。誰でも出来る簡単な仕事です。
※情報漏洩防止のため、携帯電話等はスタッフがお預かりいたします。
時給3500円+深夜手当 募集数1名
「これって」
ちょっと前にSNSで噂になってたヤツじゃねーか。
猫探しとか言って、実はみたいな。
でも時給いいよな。
しかもこんな好条件なのに、誰も応募してない。
「でもなぁ……さがにこれは……どーすっかな」
スマホと睨めっこをしていると、大きく腹が鳴った。
空腹。
それは何物にも代えがたく、気づけばオレは応募していた。
田崎秀一郎と書かれた通帳を睨みながら、何もない部屋でため息をついた。
最後に入ったバイト代も底をつき、このままだと今月の家賃すら払えない。
「さすがに無職で家無しはヤバすぎだろ」
どこでどう間違えたのか。
ちゃんとした大学を出たものの、何社も受けた就職活動は全落ち。
そこからオレの転落人生は始まった。
うるさい親たちは地元に帰ってこいと言ったが、何もない田舎に今さら帰る気などなれなかった。
だからコンビニや日雇いバイトで食いつないでいたが、店長と喧嘩をしてコンビニはクビになった。
それがつい先月。
その後、短時間バイトばかりを繰り返していたらこの有様だ。
「どーすっかな」
実家に帰るのは最終手段として、なんとか食う金と家賃だけは稼がないと。
いつものように短時間バイトをスマホで漁り始めると、ふと一件の、おかしな募集に目がいった。
深夜の散歩好きな方必見!
夜、猫を探すだけのバイトです!
指定された道を通り、猫を探すだけ。誰でも出来る簡単な仕事です。
※情報漏洩防止のため、携帯電話等はスタッフがお預かりいたします。
時給3500円+深夜手当 募集数1名
「これって」
ちょっと前にSNSで噂になってたヤツじゃねーか。
猫探しとか言って、実はみたいな。
でも時給いいよな。
しかもこんな好条件なのに、誰も応募してない。
「でもなぁ……さがにこれは……どーすっかな」
スマホと睨めっこをしていると、大きく腹が鳴った。
空腹。
それは何物にも代えがたく、気づけばオレは応募していた。