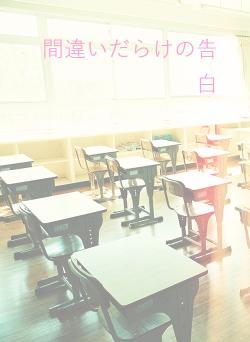闇バイトに応募した末に仲間を喰い殺した田崎秀一郎が、収監先で亡くなった。
何でも、自分で自分を食べたことによる止血死。
しかし解剖の結果、奴の胃の中は空っぽだった。
何をどうすればそんな状況になるのか。誰にも説明はつかなかった。
「先輩、なんか凄い事件でしたね」
調書を眺めながら一息ついたことろで、後輩が俺に声をかけてきた。
刑事になったかなり経つが、確かにこんな事件は初めてだった。
「ただ闇バイトに応募しただけだって、あんなに泣いてたのに」
「ただって、あの別荘に侵入したのにか?」
「まぁそうですが」
初めは確かにグレーだけだったのだろう。
しかしそれに満足することもなく、自分の欲に負けて奴らは闇に染まった。
「まぁ、刑事としては言ってはダメだが世の中は自業自得の世界なのさ」
「でも……それにしても何を見たんですかね、あの廃別荘で」
「さぁな。でも闇バイトって言うくらいだ。深淵を覗くものはまた深淵もこちらを覗いている。闇からナニカじゃねーか?」
「えー。先輩、そういうの信じる系ですか?」
「いや?」
そう答えたが、あの調書を見ていると信じるしかないように思えた。
奴は自分が仲間を喰ったと思っていたが、たぶん奴自身があの時すでに闇に喰われていたのだろう。
何でも、自分で自分を食べたことによる止血死。
しかし解剖の結果、奴の胃の中は空っぽだった。
何をどうすればそんな状況になるのか。誰にも説明はつかなかった。
「先輩、なんか凄い事件でしたね」
調書を眺めながら一息ついたことろで、後輩が俺に声をかけてきた。
刑事になったかなり経つが、確かにこんな事件は初めてだった。
「ただ闇バイトに応募しただけだって、あんなに泣いてたのに」
「ただって、あの別荘に侵入したのにか?」
「まぁそうですが」
初めは確かにグレーだけだったのだろう。
しかしそれに満足することもなく、自分の欲に負けて奴らは闇に染まった。
「まぁ、刑事としては言ってはダメだが世の中は自業自得の世界なのさ」
「でも……それにしても何を見たんですかね、あの廃別荘で」
「さぁな。でも闇バイトって言うくらいだ。深淵を覗くものはまた深淵もこちらを覗いている。闇からナニカじゃねーか?」
「えー。先輩、そういうの信じる系ですか?」
「いや?」
そう答えたが、あの調書を見ていると信じるしかないように思えた。
奴は自分が仲間を喰ったと思っていたが、たぶん奴自身があの時すでに闇に喰われていたのだろう。