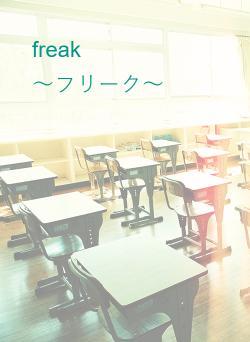触れた手は、瞬時に離れた。
わかっているから、余計に胸が痛んだ。
痛みにあらがおうともくろむ俺は、先にリーチを責めることで、それを回避しようと試みる。「なに? やましいことでも考えたのか」
俺の言葉に足を止め、俺が触れた部分をさするリーチがボヤく。
「バーカかおまえは。小悪魔チャンが言うようなセリフ、真顔でオレに聞かせるな」
「リーチが、言われるような素振り見せたくせに。強気だな」
魔が差した、とは思う。
自分でも驚くほど忠実に、リーチの手に触れてしまったのだから。
それでも、自分の行いを後悔するより、平静を装っていつもの調子で俺は続ける。
「意識しすぎの反応だろ。それは」
言ってリーチを追い越し、校舎へ続く道に沿ってゆっくりと歩を進めた。
「変だろその発想」
確固とした口調で主張するリーチも、やがて校庭脇を歩き出す。
俺とリーチ。行き先は、同じだ。
今から数分前。
リーチは美術の講師に呼ばれた帰りで、俺は事務室から教室に戻る途中で鉢合わせした。放課後の、しかも珍しいことに、周りには誰もいなかった。——だからだ。
ほんの少し前を歩くリーチに見とれていた時、ふと落とした視線の先で、そのしなやかな長い指が揺れていた。すぐ手の届く距離にあったから、思わず、手を伸ばしていた。
「ちょっと触れたくらいで。あんな反応するか、普通」
「急に触られたら誰だってするだろ、通常」
リーチは鼻筋に皺を刻み、並んで歩く俺にむっすりと抗議した。
鈍感を装っているだけかもしれないこのクラスメイトに、心中俺は、切ない気持ちを微苦笑の下で吐くしかない。
触れたいと望むのは、愛おしいと思うからだ。
そんな俺の気持ち、おまえにはまだ見えないのか?
「ならたまには、手をつなごう」
「たまには、って、意味ねえだろそんなの」
あらためて差し出した俺の手は、フンッ、と鼻先であしらわれた。仕方なく、行き場をなくした手を自分の正面に掲げ、ヒラヒラと左右に振って引っ込める。またしてもリーチから拒絶され、痛みで心が微弱に疼く。それでも、譲れない心内がある俺は、リーチと歩調を合わせながら提案した。
「だからだよ。手をつないで、ふたりで散歩しよう」
「なんでオレが、おまえと」
「ジョークじゃん」
「冗句?」
「ただの遊びだよ」
「そんなの面白いか?」リーチは、うげぇ、と渋い顔を添えた。
「俺たちだから、成り立つんだよ」
リーチの表情に胸を刺されながらも、俺は、もっともらしい物言いをした。
数秒の間ののち、リーチは首を軽くひねる。
「——ん? 落ちが見あたらないぞ?」
「『落ち』を説明させようとは、ヤボなやつだったか」
「オレ悪者かよっ」
納得がいかないとばかりにムッと口を尖らすリーチに、俺はしぶとく説得を試みた。
「女は仲いいと腕まで組むだろ。外国だったら、男同士でもするぞ」
「歩きにくいだろ。しかもオレら、日本男児ですからねえ」
「たかが手つなぎじゃん。俺の手握ってみろよ。外国人の気持ちわかるから」
「のおさんきゆう。知りたくないでええすっ」
両手をズボッとポケットに隠したリーチに、俺は、流れに任せて食い下がる。
「ちょっと冒険してみれば。もしくは、かたくなに拒絶するわけを聞かせろ」
「別に、ねえけど」
「なんでもないことができないなんて、おまえは本当に『横山理一』本人なのか?」
俺がせせら笑うと、イラっとした口調でリーチが続いた。
「オリジナル捕まえといてなに言ってんだよ」
「疑いたくもなるだろ。清水らとは手、握り合ってたくせに」
「あれは、指圧してやってたんだ」
「無理するな。いいさ、ガッカリしただけだから。男相手に意識して、手持ち無沙汰のジョークにもつき合えないとはな。天下の『人間ホイホイ』が」
「引田」
ピタリ、足を止めるリーチ。
「それ、言うなって言っただろ」
そうつぶやいて大股で俺の前に出るなり、こちらの行く手を阻むごとく、リーチは俺の前に勢いよく手を差し出した。
「必要とあれば手ぐらいつなげる」
そっぽを向いたままの、ぶっきらぼうな態度がリーチらしい。いじらしくて、無防備にほほ笑んでしまいそうだ。
「あ、そ」
俺は遠慮なく、右手でリーチの手の甲を握り込んだ。だがしかし、されるがままのリーチの指はピクリとも動かない。
「『つなぐ』って言えないぞ、こんなの」
本人公認の奇跡的なチャンスなのに、これじゃあいつもと変わらない。
「意識してるんだ。やっぱり」
ハッパを掛けられたリーチは、指にギュッと力を入れ、俺の手を強く握った。
「これで文句ねえだろ」
痛いとさえ思わせる明確な手応えに、俺の顔が綻ぶ。
このままリーチの手を引き、抱き寄せたい——衝動を、右手にぐっと集め耐える。リーチの様子を覗えば、まだそっぽを向いてふてくされていた。
ツンなリーチが見れて気をよくした俺は、余裕たっぷりの口調で告げる。
「妥協しましょう」
「そうか。よかった」
と、声を落としてすぐ、リーチの指は力を失った。
握力計かよ、俺の手は。
「……シラケル」
ぼそりともらした俺の不服をよそに、リーチがとぼけ顔して妙にうまい口笛を吹き始めるから、俺は、そっちがそうするならと強硬に出た。
「まあいい。このまま散歩だ」
「は? 本気かよ」
「とりあえず、裏門まで行こう」
リーチの手を持ったまま俺が歩き出すと、右隣のリーチも足を運ばざるを得なくなる。隣で深い息を吐くリーチの足取りが、見るからに重い。……ああ、かすり傷程度にダメージをくらった気分だ。
自らを慰めるべくリーチに尋ねた。
「なあ、女とも、こんなんかよ?」
「向こうからひっついてくるんだ。わざわざオレが、行動に移すまでもないだろ」
リーチは興味なさ気にのったりとこぼした。
——知ってる。
そんな時はいつだって、おまえ、目が笑ってないもんな。
「オレは、抱っコちゃん人形がぶら下がるための、しがない留まり木だから」
「さようですか」
リーチは人から触れられるのを好まないし、自分からも進んで人に触れたりはしない。社交的な気質や外見とは珍しく矛盾してはいるが、これはいうなれば、リーチ特有の『壁』だ。みんなの中心にいるリーチは、自分を独占しようと仕掛けられるスキンシップをことごとくきれいにはぐらかし、無言で自分のテリトリーを提示する。
それでも、仲間内でふざけあっている時はかろうじて、許しているふしがあった。きっと場の雰囲気を壊さないための妥協なんだろう、とは解釈している。
リーチの性格は、把握しているつもりだ。だからこそ俺は、なにかとリーチに絡む。際どいラインを陣取って、周囲に有無も言わせず俺の位置を確保するために。
横山理一を相手に、友達以上恋人未満の見込みもないんだ。せめて友達枠の頂点にでもならないと、俺の気持ちに収拾がつかない。だから今、俺がリーチの手を持っている状態であっても、さほど残念ではなかった。むしろほんの一瞬、リーチが俺の手を握ってくれた事実が、大きな喜びでさえある。それにしても。
「冷たいんだな。リーチの手」
「感情豊かな人間は、手が冷たいんだよ」
「ホントか? 初耳」
「てか、おまえは赤ん坊並みだな。体温高い」
「カイロみたいでいいだろ?」
「そうだなあ。これからの季節なら、手袋代わりにはなるかも」
意外にも肯定的な反応をみせたリーチに、俺は緩む口元で返す。
「よかったな。発見があって」
「うれしくもないけどなーっ」
つまらなそうにぼやく声も気にせず、俺はあたかも恩を売るかのように尋ねた。
「お蔭で、少しあったまってきただろ?」
「どうだかなあ……」
静かに呟きざま、リーチはつないだ左手を自分の顎上にヒョイとあてがった。組んでいる俺の手の甲が、リーチの口元に近づく。
「——お。意外とそうかも」
リーチが言葉を発すると、リーチの唇の端が、かすかに触れた。
——これは、俺に対する拷問かっ。
心臓は耳の中にあるものだと錯覚するほど、叩き鳴らすドラムのような動悸が内部から大きく響いてくる。耳朶だって、ジンジン熱い。火照っているのが自分でもわかるくらいだ、きっと顔面は真っ赤なはず……。握って浮かれたこの手を、だから今は、振りほどきたいとさえ思った。
「すげえなこのカイロッ」
「————」
リーチの言動に俺はうつむいた。
——無邪気に笑顔つくってんじゃねえぞコラ。さっきまでの嫌々はどうした!
そういう素振りが、俺を期待させるんだよっ。
「ツンデレ」
「ん?」
リーチがこちらへ耳を傾けるから、同じ磁極が反発し合うみたいに素早く顔を背けた。ついでに、つないだままの手を引っ張ってリーチの顔から離す。合わさったままのふたつ手は、ブランと重力に従った。
「なんだ? 言いたいことあるなら、はっきり言えよ」
俺は応える代わりに、歩みを緩めるリーチより先へ足を運ばせた。するとリーチは歩幅を広げ、追いつこうとこちらに寄ってくる。
「引田?」
俺の表情を窺う声に、しまった、と思った。リーチは、人間観察が趣味みたいな男だ。俺の態度に、おおよその推察をつけてくるかもしれない。
なんでもいい、なにか言わないと——っ早く。
「……っ…………」
だけど、声が出せない。
こんな大事な時に、喉が、絞まったような痛みでヒリヒリと苦しい。それでもなんとか気づかれまいと現状に耐えつつ、頭の中で策を問答するも一瞬で苦悩に陥る。
一呼吸置いた俺は、下を向いたまま頭を正面に戻した。爪先がうずくから、靴底を地面にこすりつけてわざと砂のザラつく音をたてて歩く間も、言葉が出掛かっては、発する前に消えていく。
俺に合わせるかのように、リーチも沈黙している。重苦しい空気を感じるなかで、次にくるリーチの言動が、怖い。自分から仕掛けたくせに、うろたえる脳ミソと焦る熱望とが、俺の心で交差する。堂々巡りのリアクション——完璧に、墓穴だ。
「おかしなやつだな。急にしおらしくなって」
「…………」
言葉が、見つからなかった。
顔の火照りと心拍の乱れを鎮めるべく、俺は息をひそめるばかりでいる。
「やっぱり変だ」
急にそう言われて、俺は、まばたきを忘れた目が左右に揺れているのを感じる。
「なあ、引田」
一歩前に踏み出したリーチが、ジャリッと地面を鳴らして俺を呼んだ。
吐き出してしまいたくなるほどの速さで心臓がフル稼働している。肩を強張らせきつく顔をしかめた俺に、リーチは、不確かな口調で振った。
「放課後って、こんなもんだったか」
「…………え?」
「今日はやけに静かだろ。だよなあ?」
校庭から校舎までを見渡しながら、のんきな声で問いかけてくるリーチ。さっきの重苦しい空気はどこへやら……。故意にわからぬフリをしているのか定かでなくとも、俺は、緊張した筋肉が緩むのを感じた。俺のこと、言ってたんじゃななかった……そう、今は、思えたから。
「おまえ、知ってる?」
「いまさら訊くな。担任が言ってただろ、朝のホーム・ルームで」
妙な安堵感に小さな怒りがわいた。
——こいつは、俺をおちょくっているのかっ。
「知ってるなら教えろよ」
「だからっ、修学旅行だろ、十二年は。十年は映画鑑賞で、映画館に直行直帰。登校してるのは、俺たち十一年だけ」と、口早に告げた。
「あー。そうだったかも。それでかあ」
首を上下に大振りして納得を見せたリーチが、ふとした様子で聞いてきた。
「おまえの取り巻き連中。今どうしてる?」
「英語の追試」
「おまえは?」
「今回はナシ」
「そりゃ珍しいな。あの引田が、試験クリアしてるなんて」
「うるせえよっ」
「……ん? あれぇ? そういえば放課後、なあんかあったような……」
急に止まるから、リーチの腕に軽くぶつかった。そんな俺のことなんか構いもせず、リーチは顎をひねる素振りを見せる——が。
「ま、いっか。そのうち思い出すだろ」
時間をかけずに解決させたリーチが、のんびりした速度でまた歩きだす。
俺も、手綱を引かれる馬のように、トボトボ遅れ足でついていく。
「しっかし、マジで誰も見かけないな」
「…………」
抑揚のない言葉に促されて、猫背のまま辺りへ目線を流した。
リーチの言う通り、金木犀が薫る学校敷地内にも、フェンス向こうにある公道にも、人の気配すら感じない。普段の喧騒がなくて、静かだ。『今日』が、俺に味方しているように思えてくる。
俺とリーチ。ふたりだけの時間が、ずっと続けばいいのに。
「こんなんだとさ」
と、リーチが突然、俺の耳元に顔を寄せた。
「オレとおまえだけが、この世界に取り残された気分になるよな」
吐息まじりの囁き。
俺の鼓膜は震え、ドクンッ、心臓が大きく跳ねる。思わず、リーチの手を離すとこだった。
「なんだよ引田~。ここ、ツッコミ入れるとこだぞお」
動揺する俺の顔をまじまじと見つめるリーチが、戯れるような口調で流れよくダメ出しをしてきた。
「ジョーク欲してたわりに、タイミング・ゼロだなおまえ」
軽快で明るいトーンは空気にユーモアを漂わせ、遊び心を宿した眼差しに鼻で笑われた。——ズキン、心が軋む。
「…………」
「どうした?」
狭い歩幅でぎこちなく歩く俺に、性懲りもなくリーチは話しかけてくる。
「まあたダンマリかよ?」
一言も発せない自分を、かなりの重症だと認識するしかなかった。
「…………」
「おまえってさ、急に黙る時あるよな」
「…………」
「理由は? 言えないことだったり、するのか」
——あたりまえだ。
おまえのせいで、寿命が現在進行形で縮んでんだよっ。
「無言になるの、そのうち直せな」
どんな顔で言っているのか気になって、横目でリーチを盗み見る。そこには、いつものひょうひょうとした姿があるだけだった。
——少しくらい、照れてみせろよ……。
俺は視線で訴え、地面に視線を落とす。そしてまた、上目遣いにリーチを窺った。
背、まだ俺のほうが少し高い。前髪がやや長めのミディアムショートの髪は、やわらかそうで触れてみたくなる。ワイルドな雰囲気なのに、不思議な透明感まで漂わせてさ。全体的に色素が薄いせいで、景色にとけてしまいそうだ。スッとした鼻筋から唇を通っての顎のライン。口元は優雅でほほ笑みを誘い、端整な風貌に見入ってしまう。
本人はいつも三枚目気取りのくせに、どう転んでも眉目秀麗だった。リーチは外国と日本の八分の一だから、どことなく日本人離れしているのが所以だろう。高二にあがって同じクラスになってからは、日常的に見慣れた存在のはずなのに。依然、リーチの表情に魅了されて落ち着かなくなる。
「そろそろ髪切らないとなあ」
リーチが、前髪を無造作にかき上げた。長いまつ毛ときりっと整った眉毛がぱっと覗く。精悍な顔立ちに、俺の鼓動がまたも速まった。
——おまえはいいよな。誰かに見とれて、命の心配するとかないだろ。
横から見る首筋の下で、古びたネルシャツを粋に着こなしている。エシカルファッション——わざわざくたびれた古着を選んで、どこか抜けた感があるように演出するリーチ。飾り気のない性質だから、外見で判断されて高根の花扱いされるのがとことん嫌なんだ。一方で、自然体でおごりないやつだから、何気ない仕草だって決まるんだろうな。
リーチの心を確認したいはずなのに、中毒者のようにぼんやりと俺は、リーチの横顔に視線を留めている。
叶うことのない願いを、手放す勇気がないがために。
「あっれーえ? 引田ああ」
————ッ!!
バチリと視線がかみ合った。とんだ不意打ちに、俺はウッと息を呑んだ。
「見とれちゃうほど男前か。オレは」
リーチが、薄笑いを浮かべてこちらをぐっと覗き込む。俺は、限りなく不自然に、反対側に顔を背けた。
「おいおい引田くん。それはエヌジーでしょ」
リーチは合わさる手を、俺の顔の高さまで持ち上げた。
「手、つないでるんだぜ? オレたち」
そしてほほ笑む。
「仲よしの証しなんだろ、コレ」
時々、思ってしまう。
実はもう、悟られているのではないか。——と。
「わかってんのか」
「…………」
「言い出したのは、おまえだぞ」
「…………」
「さっき言ってた『落ち』。しっかり披露してもらうかんな~」
口を開けないでいる俺を相手に、リーチは一方的に話しかけてくる。
「もっしもーし。引田くん?」
俺の気持ちを知った上で、知らんフリを決め込んで、こうして俺の反応を楽しんでいるんじゃないだろうか。
「おい、こら引田。ひとり喋りすぎるオレってアホいだろ」
もしそうなら、激烈に悪趣味だ。
「引田あ、なんとか言えよーお」
——ああでも。この想いを確信された勢いで、「俺たちの距離に名前をつけたい」と言ったら、どうなるだろう。不自然な糸口を紡いでリーチのすべてを束縛できたら。俺の心は、満たされるかもしれない。
「はあ……」
リーチは溜め息と一緒に、合わせた手をストンと下ろす。
「ノー返事かよ」
そのまま前後に、柱時計の振り子よろしく大きく動かし始めた。
隣り合う、リーチと俺の腕が、風をおこしながら時折触れる。こんなふうに、こちら寄りの偶然が重なると、これを『必然』だと思い込みたくなるのは、なぜだろう。つらくなるだけなのに、不確かな可能性にきっかけを求めてしまう。
「寝ながら歩いてますぅ、とか言うのナシだかんな~」
「…………」
「あーあ」
「…………」
「静かすぎて、オレだけが取り残された気分」
腕振りが止んでも、解こうと思えば簡単に解けてしまうくらいの力具合で俺たちはなんとなく、手指を合わせたままでいる。——拒絶されていないのなら、もっとリーチに近づきたい。さらなる鼓動を従えた誘惑が、頭をもたげ始める。
そんな時、少し冷たい風にのって、木々の重圧感ある香りが鼻腔に届いた。なにかを踏みつけた感覚に視線を向かわせた足元には、数枚の葉のわきに小さい実をつけた小枝が落ちている。顔を上げてみれば、俺たちはもう、学校の黒塗りゲートまで来ていた。
「裏門到着。どうする?」
そう聞かれて、返事をしなかった。俺に魔法をかけたのがリーチなら、それを解くのも、リーチがいい……なんて、思ったから。
リーチが、俺を見るのがわかった。俺は、口内の端っこを犬歯で噛みながら、リーチの言動に従う覚悟を決めた。
ふっと息を吐き、黙りこくる俺にリーチが言う。
「折り返すか」
その言葉に、心の中でガッツポーズをとる。リーチがするゆっくりとした方向転換に合わせて、落ち着かない心境できびすを返した。
誘惑が期待となり、期待は、この機会を試そうと俺を促す。
わかってはいるんだ。俺が望みを口にすれば、リーチは『今』を離れていく。だから、散歩を喜ぶだけでいい。わざわざ自分から、なくさないほうがいい。
でも……俺は、リーチの横にいて、リーチは俺との時間を共有している。声を出せば届くかもしれない。
昂る感情がふたりの髪を揺らす追い風に乗り、心を打つ速さを増していく。俺は左手で拳をつくり、勇気を込めた。
「……なあ。来いよ」
と、うつむき加減に切り出す。
「来れば、俺んち」
「おまえんち?」
今を壊すにはまだ早いのだと、そうわかっているはずなのに。俺の心理は、パブロフの犬を選ぶ。
小さく頷いた俺は、リーチを誘った。
「まえ、興味あるって言ってただろ。だから、来れば? 今週末とか。土曜クラスのあとに」
「急に言われてもなあ」
「海、好きなんだろ。ウチ来れば近いぞ」
「引田の家って、鎌倉だったよな」
「そう」
「こっからだと電車賃高いじゃん」
予感を否定したい俺は、なんとか、リーチを言いくるめようと試みる。
「片道くらいなら、おごってやってもいいぞ」
「ははっ」
リーチは軽く笑って、「そのうちなあ」と、いかにも曖昧なふわった言葉を落とした。
いつものようにあしらわれた俺は、意固地に食い下がる。
「来いよ」
「悪いな。他の誘いも断ってるからよ」
「だったら、みんな誘ってさ。それならいいだろ?」
「うーんまあ。そのうち考えるわ」
リーチは、こちらの思考とは反比例な温度差で言う。
ぼんやりと返答される俺は、自分だけのぼせている事実を婉曲的に打ち据えられるのを感じた。動揺と独占欲を抱えて、それでもなおもっと近づきたい、確かに得たい、というむき出しの願望を丸め込むのに必死になる。
「そればっかだな」
「しょうがないだろ。約束したら、守らないといけなくなる」
「じゃあそうしろよ」
「無理だって。おまえも知ってるだろ? 部活始めたから週末も試合あるし、他にもいろいろあるし。オレの予定はな、濃密かつ突発的なんだよ」
リーチの言い草に、俺は奥歯をきしませた。
クソっ。毎度毎度蹴りやがって頑固なやつ!
おまえの言うそれは、優先順位の何番目の話をしてるんだよ。……俺との約束より大事なのか。
心の中にモヤモヤが充満する。目を細め、前方に向かって投げつけるように言った。
「どんだけ忙しんだよ。つき合い悪すぎだぞ」
「そうかあ?」
「そうだよ! そもそも、クソ忙しいおまえが、なんで真面目に部活動してんだよ」
「ちょっこし青春しとこうと思って」
「似合わねえよ!」
あんなにどの部からも勧誘されていたのに、普通ならそろそろ引退を視野に入れるこの時期にバレー部の入部決めたのだって、なにかしらいわれがあるんだろ。なんのために、誰のためにそうしてるんだよ。
「来年俺たち、一応受験生だぞ。いま遊ばないでいつ遊ぶんだよっ」
「オレだって適度に気晴らししてるぞ。それにおまえには、遊び相手ならいくらでもいるだろ」
「いてもいなくても、俺はっ、おまえに言ってんだよ。映画誘っても、遊び誘っても、片っ端から断りやがって。ワーカホリックのサラリーマンかっつーの!」
俺の憤慨を横に、頭をかくリーチが言った。
「そんなにオレをご指名なら、応援来いよ。今週末は、海老原学園高等学校で練習試合だからさ」
「ヤダね」
「うわ。まさかの拒否」
「あたりまえだろ!」
尖るイラだちが沸騰して、俺の髪先までをさかなでる。
「どっかの体育バカじゃないんだ。休みの日に時間かけて、わざわざ学校なんかに来るかよっ」
「誰が『体育バカ』だ?」
「俺の隣にはおまえしかいないだろ!」
鋭い口調でぶつけた。
臆病を理由に掲げてわがままを糧にリーチの心情を量ろうとすれば、闘牛士がヒラリと身をかわすように、一瞬で俺は独りを強いられる。
手を握れたから、コイツの感情まで誘導できると思ったのか、俺は。リーチの隣にいるとして、俺が望むものを得る確証はないのに。
錯覚を繰り返す俺は、健気で懸命に、友情からあらがおうと必死な自分を傷つけていく。失恋の痛みさえも想像に任せて、トゲだらけの風船を膨らませながら、決まったとおりにジダンダを踏んでいるみたいだ。……なにをやっているんだ俺は。
「お」
なんの前触れもなく、リーチが足を止めた。
「なんだよっ」意図せず不機嫌が語尾に出る。
「あの色調が好きなんだよなー」
知れず自己嫌悪にさいなまれる俺を、のんきな声音が刺激する。
「ほれ、見てみろよ。空」
言われた視線の先では、少しのピンクをにじませながら、オレンジのグラデーションが暖かみを空に演出していた。
「夕陽がどうした」
「儚いものほど、繊細で美しい」
すっかりその場に立ち止まったリーチが、穏やかに言った。
「安心するんだ。夕焼け見ると」
「意外すぎ」
「いいんだよ。オレは、ノスタルジックな人間だから」
「自称ってのは恐ろしいな」
俺は、朝陽が好きだ。
ハジマリの光は、夢のような出来事を動かす希望の象徴。それはまるでリーチのようだから、本人も朝陽のほうを好むと思っていた。
「綺麗だな。久々に見たわ」
と、うれし気な声を発しながら、リーチは校庭の方角に向き直り空を仰ぐ。
「夕焼けは、やっぱ秋だよな」
しみじみと発するリーチに俺は思った。
遠くを見つめるその視線を、俺だけに向けてくれる日が来るのだろうか。
「建物の向こうに沈む夕陽より、水平線に沈む夕陽のほうが格段にいいけどな」
嫌みまじりに言うと、ささくれた俺の心がピリッと沁みた。
頭ではわかっている。リーチは、なにも悪くない。願わくは、俺だって解放されたい。……今なら、『友達』を装っていられる今なら、まだ間に合うかもしれない。無難な位置を保っている間、イビツな主張を誇示する細胞が、すべて生まれ変わればいい。そうすれば、ツライ悪循環な妄想から抜け出せるはずだ。……なのに一体なんだって俺は、こんなにも切望するのだろう。リーチといると、自分を偽りたくなくなる。
だからたとえ、それが蜃気楼に似ていると気づいていても、リーチにも俺と同じ気持ちでいてほしいと、俺がそうするように、リーチからも好かれたいと願ってしまう。
「あの太陽。このまま見てたら、あそこの建物にぶつかるな」
「残念。おまえに、じゃないのか」
「相変わらずオレにカラいなぁ、引田伊朔」
「当然だ」
俺は自分に驚く。リーチに対してこんなにも、純粋だということに。
そして同時にこうも思う。
想像上の見えない幸せを得ようとあくせくする俺は、曖昧な地図を逆さにしてさまよう冒険家みたいだ。
やるせない気持ちで、夕陽が民家の屋根にゆったりと沈んでいくさまに目を向ける。夕陽のゆらめきが心の縁と重なり、ほろりと切なくさせた。
ともすれば、リーチが俺を呼ぶ。
「なあ引田」
「……なんだよ」
「音、したか」
「おと?」
「聞いてなかったのか」
「なんのだよ?」
逆光に半分陰らす横顔で、リーチは俺に問いた。
「じゃあさ。夕陽が海に沈む時は、どんな音がするんだ?」
「…………」
詩人にでもなるつもりか、おまえは?
そんな突拍子もないこと、なんでわざわざ俺に訊いたりするんだよ。
リーチの意図を図りかねた俺は、無言で立ち尽くす。
「なんだ、そのアホな間は。おまえ、いつも見てんだろ?」
「そんなの、音までわかるかよ。大抵は、江ノ電ん中だし」
車窓から眺める夕陽は、俺にとっては切ない光景だ。
電車が揺れるたびに俺たちの時間からどんどん離されていく気がして、胸が苦しくなる。エンドロールのような景色を前に思うのは、————「ああ。今日も友達だった」という嘆きだ。
足元に目線を落として自分の靴先を見る。
「うるさいだろ、線路を走る音とか。それに、イヤホンしてる時もあるしな。仮に聞こえてきたとしても、その音は、俺まで届かない」
「……おまえなら、聞こえていると思ったんだけどな」
風に吹かれた校庭の砂がサアっと足をさらい、俺の耳を煩わせた。
「——じゃ、確かめるか」
「なにを?」と、俺は眉間に力を入れた。
「現地調査するしかない!」リーチが右拳を上に突きあげる。
「どうでもいいけど、謎の思いつきを、決定口調で言うな」
「ブウブウうっせえぞぉ」と、拳を下ろすリーチは、「切実な提案なんだから、おまえもつき合え」言ってそのまま、手を腰に添えた。
「なんで俺がっ」
「夕陽見に、今度行くから」
リーチの言葉にがく然とした。
なんだよ突然。
……でも、どうして。
「来るのか。本当に?」
「これよりも綺麗なんだろ?」
「そう、だけど」
「見てみたいじゃん。おまえが絶賛する夕陽ってのを」
「そんな理由で……スケジュールの調整、するのかよ。おまえは」
「あはははは」
「笑ってごまかすな」
口を尖らせて腑に落ちないとぼやいてみるものの、喜びで本心は無邪気にはずんでいた。
悪態をついても無理を要求しても、甘やかすように、リーチの壁を誰に対するよりも低く設定してくれていると感じてしまうのは、俺が自惚れているからだろうか。
今だって、こうして隣にいられるのは、俺だから許されているのだと思ってしまう。これだから、気まぐれなゲーム盤の上で踊る駒の気分に浸ってまでも、俺は懲りずに期待するんだ。
俺はおまえを知ってからずっと、こうして不安定な淡い想いを抱え続けている。いつまで温存すればいいのかコタエを導き出せないまま、宙ぶらりんな俺はおまえと、『友達』をして毎日を過ごしているんだ。
なあリーチ。切なすぎるだろ、こんなの。
こんな俺の、片想いは——。
「まあ変わらず、いつとは言えないけどさ。夕陽が綺麗に見える頃には行くよ」
「そのセリフ、絶っ対に忘れんなよ」
と、半信半疑でリーチにクギを刺す。
「了解しました」
刹那。触れているリーチの指が、俺のを強く引き寄せた。
それを合図に視線を移せば、あかね色に染まったリーチがふわりと笑っていた。
見渡せば、周りの景色同様、穏やかに佇む陽光が包むすべての中に俺たちもすっぽりとおさまっている。
片想いってのは優柔不断の塊だから、同じなにかを刻めるだけで簡単にのぼせてしまうんだ。——そう確信した時、心の真ん中がはじけてやさしい光が生まれた。
今は俺が、おまえの一番近くにいるんだよな。肩を並べた隙間を互いの手で結んで、同じ方向にある美しいものを眺めている。あてのない嫉妬に息切らすよりも、つかの間の幸せに感動したほうがずっといい。だから今は、深く考えるのはやめにしよう。
夕陽に色づく空を見上げながら、ようやく俺は、つないだリーチの手の温かさに気づき……それに惹かれた。
「リーチぃぃぃ!」
無慈悲にも体育館側から、こちらに向かって大声で呼ぶやつが現れた。黄色のビブスを大きく振り回している。
「試合ッ! バスケ! 助っ人頼んだだろおお!」
「やべぇ。そうだった」
さっきリーチが言っていた放課後の用事とは、このことだったのか。
そうして、あっけなく解かれる温もり。
「オレ、行くわ」
無言の俺を置き去りにして、これ幸いといわんばかりに走り出す。こうなると、俺はリーチの行方を目で追うだけだ。
「——で、放置かよ」
いいかげん慣れたぞ、このパターンに。光射したと安堵するとコレだ。
「掴まえたのは俺、だったのにな」
だけど気づいた時には、俺がリーチのペースにドギマギしていて。期待に喜びを錯覚しているうちに、当の本人は俺の前から姿を隠す。
現れては消え、手にしたと思ったら去られ。ぐるくるぐるぐるくるくるぐるぐる、そんなのが巡ってばかりだ。……だから、だろうか。俺のもとに、リーチをつなぎ留めておきたいと願ってしまうのは。こんなにも強い執着心を煩ってしまうのは、みんながリーチを求めているからかもしれない。
遠ざかる背中に想いを馳せる。
ついさっきまで俺と並んでいたのにな。振り返りもせずに、次の場所に一直線かよ。
「糸の切れた風船だな。おまえ」
小さい頃、店先で渡されたそれに、リーチは似ている。ふとした瞬間するりと手のひらから抜け出してしまう、あの、空飛ぶ風船だ。
「俺は、どうすればいい?」
どうしたらいいんだ。俺には、おまえみたいに翔ぶチカラはないんだよ。できないんだ、俺には。俺独りじゃダメなんだ。——なのに、また置いてけぼりにするのかよ。
「足、速いな。相変わらず」
とうとうリーチは、バスケ部員と体育館の中へ入ってしまった。
おまえが見えない。おまえの姿も……気持ちも。独りが不安で、途轍もなくつまらなくなる。おまえが好む夕焼けも、俺独りだと、憂鬱な色にしか映らない。
おまえから憧憬の念を抱いてほしいのに、それは、永遠の空想にすぎないのか。
それでも、待っていられたら、……またおまえに触れてもいいか?
すべてを伝えて、期待どおりのコタエを望めればいいのに。
「おまえとなら、どこまでだって翔べるんだよ。俺は」
まだ感触の残る右手に不平を漏らす。
可能性を見いだせないまま、想い出だけが増えていく。
いちずな俺はこの先も、平静を装っていられるだろうか。
————〝夕陽見に、今度行くから〟
大きなオレンジの下で交わした、指きり代わりの手つなぎ。
「忘れるなよ」
その手をポケットに突っ込んで、俺は、夕映えの校庭をあとにした。
☆★☆
わかっているから、余計に胸が痛んだ。
痛みにあらがおうともくろむ俺は、先にリーチを責めることで、それを回避しようと試みる。「なに? やましいことでも考えたのか」
俺の言葉に足を止め、俺が触れた部分をさするリーチがボヤく。
「バーカかおまえは。小悪魔チャンが言うようなセリフ、真顔でオレに聞かせるな」
「リーチが、言われるような素振り見せたくせに。強気だな」
魔が差した、とは思う。
自分でも驚くほど忠実に、リーチの手に触れてしまったのだから。
それでも、自分の行いを後悔するより、平静を装っていつもの調子で俺は続ける。
「意識しすぎの反応だろ。それは」
言ってリーチを追い越し、校舎へ続く道に沿ってゆっくりと歩を進めた。
「変だろその発想」
確固とした口調で主張するリーチも、やがて校庭脇を歩き出す。
俺とリーチ。行き先は、同じだ。
今から数分前。
リーチは美術の講師に呼ばれた帰りで、俺は事務室から教室に戻る途中で鉢合わせした。放課後の、しかも珍しいことに、周りには誰もいなかった。——だからだ。
ほんの少し前を歩くリーチに見とれていた時、ふと落とした視線の先で、そのしなやかな長い指が揺れていた。すぐ手の届く距離にあったから、思わず、手を伸ばしていた。
「ちょっと触れたくらいで。あんな反応するか、普通」
「急に触られたら誰だってするだろ、通常」
リーチは鼻筋に皺を刻み、並んで歩く俺にむっすりと抗議した。
鈍感を装っているだけかもしれないこのクラスメイトに、心中俺は、切ない気持ちを微苦笑の下で吐くしかない。
触れたいと望むのは、愛おしいと思うからだ。
そんな俺の気持ち、おまえにはまだ見えないのか?
「ならたまには、手をつなごう」
「たまには、って、意味ねえだろそんなの」
あらためて差し出した俺の手は、フンッ、と鼻先であしらわれた。仕方なく、行き場をなくした手を自分の正面に掲げ、ヒラヒラと左右に振って引っ込める。またしてもリーチから拒絶され、痛みで心が微弱に疼く。それでも、譲れない心内がある俺は、リーチと歩調を合わせながら提案した。
「だからだよ。手をつないで、ふたりで散歩しよう」
「なんでオレが、おまえと」
「ジョークじゃん」
「冗句?」
「ただの遊びだよ」
「そんなの面白いか?」リーチは、うげぇ、と渋い顔を添えた。
「俺たちだから、成り立つんだよ」
リーチの表情に胸を刺されながらも、俺は、もっともらしい物言いをした。
数秒の間ののち、リーチは首を軽くひねる。
「——ん? 落ちが見あたらないぞ?」
「『落ち』を説明させようとは、ヤボなやつだったか」
「オレ悪者かよっ」
納得がいかないとばかりにムッと口を尖らすリーチに、俺はしぶとく説得を試みた。
「女は仲いいと腕まで組むだろ。外国だったら、男同士でもするぞ」
「歩きにくいだろ。しかもオレら、日本男児ですからねえ」
「たかが手つなぎじゃん。俺の手握ってみろよ。外国人の気持ちわかるから」
「のおさんきゆう。知りたくないでええすっ」
両手をズボッとポケットに隠したリーチに、俺は、流れに任せて食い下がる。
「ちょっと冒険してみれば。もしくは、かたくなに拒絶するわけを聞かせろ」
「別に、ねえけど」
「なんでもないことができないなんて、おまえは本当に『横山理一』本人なのか?」
俺がせせら笑うと、イラっとした口調でリーチが続いた。
「オリジナル捕まえといてなに言ってんだよ」
「疑いたくもなるだろ。清水らとは手、握り合ってたくせに」
「あれは、指圧してやってたんだ」
「無理するな。いいさ、ガッカリしただけだから。男相手に意識して、手持ち無沙汰のジョークにもつき合えないとはな。天下の『人間ホイホイ』が」
「引田」
ピタリ、足を止めるリーチ。
「それ、言うなって言っただろ」
そうつぶやいて大股で俺の前に出るなり、こちらの行く手を阻むごとく、リーチは俺の前に勢いよく手を差し出した。
「必要とあれば手ぐらいつなげる」
そっぽを向いたままの、ぶっきらぼうな態度がリーチらしい。いじらしくて、無防備にほほ笑んでしまいそうだ。
「あ、そ」
俺は遠慮なく、右手でリーチの手の甲を握り込んだ。だがしかし、されるがままのリーチの指はピクリとも動かない。
「『つなぐ』って言えないぞ、こんなの」
本人公認の奇跡的なチャンスなのに、これじゃあいつもと変わらない。
「意識してるんだ。やっぱり」
ハッパを掛けられたリーチは、指にギュッと力を入れ、俺の手を強く握った。
「これで文句ねえだろ」
痛いとさえ思わせる明確な手応えに、俺の顔が綻ぶ。
このままリーチの手を引き、抱き寄せたい——衝動を、右手にぐっと集め耐える。リーチの様子を覗えば、まだそっぽを向いてふてくされていた。
ツンなリーチが見れて気をよくした俺は、余裕たっぷりの口調で告げる。
「妥協しましょう」
「そうか。よかった」
と、声を落としてすぐ、リーチの指は力を失った。
握力計かよ、俺の手は。
「……シラケル」
ぼそりともらした俺の不服をよそに、リーチがとぼけ顔して妙にうまい口笛を吹き始めるから、俺は、そっちがそうするならと強硬に出た。
「まあいい。このまま散歩だ」
「は? 本気かよ」
「とりあえず、裏門まで行こう」
リーチの手を持ったまま俺が歩き出すと、右隣のリーチも足を運ばざるを得なくなる。隣で深い息を吐くリーチの足取りが、見るからに重い。……ああ、かすり傷程度にダメージをくらった気分だ。
自らを慰めるべくリーチに尋ねた。
「なあ、女とも、こんなんかよ?」
「向こうからひっついてくるんだ。わざわざオレが、行動に移すまでもないだろ」
リーチは興味なさ気にのったりとこぼした。
——知ってる。
そんな時はいつだって、おまえ、目が笑ってないもんな。
「オレは、抱っコちゃん人形がぶら下がるための、しがない留まり木だから」
「さようですか」
リーチは人から触れられるのを好まないし、自分からも進んで人に触れたりはしない。社交的な気質や外見とは珍しく矛盾してはいるが、これはいうなれば、リーチ特有の『壁』だ。みんなの中心にいるリーチは、自分を独占しようと仕掛けられるスキンシップをことごとくきれいにはぐらかし、無言で自分のテリトリーを提示する。
それでも、仲間内でふざけあっている時はかろうじて、許しているふしがあった。きっと場の雰囲気を壊さないための妥協なんだろう、とは解釈している。
リーチの性格は、把握しているつもりだ。だからこそ俺は、なにかとリーチに絡む。際どいラインを陣取って、周囲に有無も言わせず俺の位置を確保するために。
横山理一を相手に、友達以上恋人未満の見込みもないんだ。せめて友達枠の頂点にでもならないと、俺の気持ちに収拾がつかない。だから今、俺がリーチの手を持っている状態であっても、さほど残念ではなかった。むしろほんの一瞬、リーチが俺の手を握ってくれた事実が、大きな喜びでさえある。それにしても。
「冷たいんだな。リーチの手」
「感情豊かな人間は、手が冷たいんだよ」
「ホントか? 初耳」
「てか、おまえは赤ん坊並みだな。体温高い」
「カイロみたいでいいだろ?」
「そうだなあ。これからの季節なら、手袋代わりにはなるかも」
意外にも肯定的な反応をみせたリーチに、俺は緩む口元で返す。
「よかったな。発見があって」
「うれしくもないけどなーっ」
つまらなそうにぼやく声も気にせず、俺はあたかも恩を売るかのように尋ねた。
「お蔭で、少しあったまってきただろ?」
「どうだかなあ……」
静かに呟きざま、リーチはつないだ左手を自分の顎上にヒョイとあてがった。組んでいる俺の手の甲が、リーチの口元に近づく。
「——お。意外とそうかも」
リーチが言葉を発すると、リーチの唇の端が、かすかに触れた。
——これは、俺に対する拷問かっ。
心臓は耳の中にあるものだと錯覚するほど、叩き鳴らすドラムのような動悸が内部から大きく響いてくる。耳朶だって、ジンジン熱い。火照っているのが自分でもわかるくらいだ、きっと顔面は真っ赤なはず……。握って浮かれたこの手を、だから今は、振りほどきたいとさえ思った。
「すげえなこのカイロッ」
「————」
リーチの言動に俺はうつむいた。
——無邪気に笑顔つくってんじゃねえぞコラ。さっきまでの嫌々はどうした!
そういう素振りが、俺を期待させるんだよっ。
「ツンデレ」
「ん?」
リーチがこちらへ耳を傾けるから、同じ磁極が反発し合うみたいに素早く顔を背けた。ついでに、つないだままの手を引っ張ってリーチの顔から離す。合わさったままのふたつ手は、ブランと重力に従った。
「なんだ? 言いたいことあるなら、はっきり言えよ」
俺は応える代わりに、歩みを緩めるリーチより先へ足を運ばせた。するとリーチは歩幅を広げ、追いつこうとこちらに寄ってくる。
「引田?」
俺の表情を窺う声に、しまった、と思った。リーチは、人間観察が趣味みたいな男だ。俺の態度に、おおよその推察をつけてくるかもしれない。
なんでもいい、なにか言わないと——っ早く。
「……っ…………」
だけど、声が出せない。
こんな大事な時に、喉が、絞まったような痛みでヒリヒリと苦しい。それでもなんとか気づかれまいと現状に耐えつつ、頭の中で策を問答するも一瞬で苦悩に陥る。
一呼吸置いた俺は、下を向いたまま頭を正面に戻した。爪先がうずくから、靴底を地面にこすりつけてわざと砂のザラつく音をたてて歩く間も、言葉が出掛かっては、発する前に消えていく。
俺に合わせるかのように、リーチも沈黙している。重苦しい空気を感じるなかで、次にくるリーチの言動が、怖い。自分から仕掛けたくせに、うろたえる脳ミソと焦る熱望とが、俺の心で交差する。堂々巡りのリアクション——完璧に、墓穴だ。
「おかしなやつだな。急にしおらしくなって」
「…………」
言葉が、見つからなかった。
顔の火照りと心拍の乱れを鎮めるべく、俺は息をひそめるばかりでいる。
「やっぱり変だ」
急にそう言われて、俺は、まばたきを忘れた目が左右に揺れているのを感じる。
「なあ、引田」
一歩前に踏み出したリーチが、ジャリッと地面を鳴らして俺を呼んだ。
吐き出してしまいたくなるほどの速さで心臓がフル稼働している。肩を強張らせきつく顔をしかめた俺に、リーチは、不確かな口調で振った。
「放課後って、こんなもんだったか」
「…………え?」
「今日はやけに静かだろ。だよなあ?」
校庭から校舎までを見渡しながら、のんきな声で問いかけてくるリーチ。さっきの重苦しい空気はどこへやら……。故意にわからぬフリをしているのか定かでなくとも、俺は、緊張した筋肉が緩むのを感じた。俺のこと、言ってたんじゃななかった……そう、今は、思えたから。
「おまえ、知ってる?」
「いまさら訊くな。担任が言ってただろ、朝のホーム・ルームで」
妙な安堵感に小さな怒りがわいた。
——こいつは、俺をおちょくっているのかっ。
「知ってるなら教えろよ」
「だからっ、修学旅行だろ、十二年は。十年は映画鑑賞で、映画館に直行直帰。登校してるのは、俺たち十一年だけ」と、口早に告げた。
「あー。そうだったかも。それでかあ」
首を上下に大振りして納得を見せたリーチが、ふとした様子で聞いてきた。
「おまえの取り巻き連中。今どうしてる?」
「英語の追試」
「おまえは?」
「今回はナシ」
「そりゃ珍しいな。あの引田が、試験クリアしてるなんて」
「うるせえよっ」
「……ん? あれぇ? そういえば放課後、なあんかあったような……」
急に止まるから、リーチの腕に軽くぶつかった。そんな俺のことなんか構いもせず、リーチは顎をひねる素振りを見せる——が。
「ま、いっか。そのうち思い出すだろ」
時間をかけずに解決させたリーチが、のんびりした速度でまた歩きだす。
俺も、手綱を引かれる馬のように、トボトボ遅れ足でついていく。
「しっかし、マジで誰も見かけないな」
「…………」
抑揚のない言葉に促されて、猫背のまま辺りへ目線を流した。
リーチの言う通り、金木犀が薫る学校敷地内にも、フェンス向こうにある公道にも、人の気配すら感じない。普段の喧騒がなくて、静かだ。『今日』が、俺に味方しているように思えてくる。
俺とリーチ。ふたりだけの時間が、ずっと続けばいいのに。
「こんなんだとさ」
と、リーチが突然、俺の耳元に顔を寄せた。
「オレとおまえだけが、この世界に取り残された気分になるよな」
吐息まじりの囁き。
俺の鼓膜は震え、ドクンッ、心臓が大きく跳ねる。思わず、リーチの手を離すとこだった。
「なんだよ引田~。ここ、ツッコミ入れるとこだぞお」
動揺する俺の顔をまじまじと見つめるリーチが、戯れるような口調で流れよくダメ出しをしてきた。
「ジョーク欲してたわりに、タイミング・ゼロだなおまえ」
軽快で明るいトーンは空気にユーモアを漂わせ、遊び心を宿した眼差しに鼻で笑われた。——ズキン、心が軋む。
「…………」
「どうした?」
狭い歩幅でぎこちなく歩く俺に、性懲りもなくリーチは話しかけてくる。
「まあたダンマリかよ?」
一言も発せない自分を、かなりの重症だと認識するしかなかった。
「…………」
「おまえってさ、急に黙る時あるよな」
「…………」
「理由は? 言えないことだったり、するのか」
——あたりまえだ。
おまえのせいで、寿命が現在進行形で縮んでんだよっ。
「無言になるの、そのうち直せな」
どんな顔で言っているのか気になって、横目でリーチを盗み見る。そこには、いつものひょうひょうとした姿があるだけだった。
——少しくらい、照れてみせろよ……。
俺は視線で訴え、地面に視線を落とす。そしてまた、上目遣いにリーチを窺った。
背、まだ俺のほうが少し高い。前髪がやや長めのミディアムショートの髪は、やわらかそうで触れてみたくなる。ワイルドな雰囲気なのに、不思議な透明感まで漂わせてさ。全体的に色素が薄いせいで、景色にとけてしまいそうだ。スッとした鼻筋から唇を通っての顎のライン。口元は優雅でほほ笑みを誘い、端整な風貌に見入ってしまう。
本人はいつも三枚目気取りのくせに、どう転んでも眉目秀麗だった。リーチは外国と日本の八分の一だから、どことなく日本人離れしているのが所以だろう。高二にあがって同じクラスになってからは、日常的に見慣れた存在のはずなのに。依然、リーチの表情に魅了されて落ち着かなくなる。
「そろそろ髪切らないとなあ」
リーチが、前髪を無造作にかき上げた。長いまつ毛ときりっと整った眉毛がぱっと覗く。精悍な顔立ちに、俺の鼓動がまたも速まった。
——おまえはいいよな。誰かに見とれて、命の心配するとかないだろ。
横から見る首筋の下で、古びたネルシャツを粋に着こなしている。エシカルファッション——わざわざくたびれた古着を選んで、どこか抜けた感があるように演出するリーチ。飾り気のない性質だから、外見で判断されて高根の花扱いされるのがとことん嫌なんだ。一方で、自然体でおごりないやつだから、何気ない仕草だって決まるんだろうな。
リーチの心を確認したいはずなのに、中毒者のようにぼんやりと俺は、リーチの横顔に視線を留めている。
叶うことのない願いを、手放す勇気がないがために。
「あっれーえ? 引田ああ」
————ッ!!
バチリと視線がかみ合った。とんだ不意打ちに、俺はウッと息を呑んだ。
「見とれちゃうほど男前か。オレは」
リーチが、薄笑いを浮かべてこちらをぐっと覗き込む。俺は、限りなく不自然に、反対側に顔を背けた。
「おいおい引田くん。それはエヌジーでしょ」
リーチは合わさる手を、俺の顔の高さまで持ち上げた。
「手、つないでるんだぜ? オレたち」
そしてほほ笑む。
「仲よしの証しなんだろ、コレ」
時々、思ってしまう。
実はもう、悟られているのではないか。——と。
「わかってんのか」
「…………」
「言い出したのは、おまえだぞ」
「…………」
「さっき言ってた『落ち』。しっかり披露してもらうかんな~」
口を開けないでいる俺を相手に、リーチは一方的に話しかけてくる。
「もっしもーし。引田くん?」
俺の気持ちを知った上で、知らんフリを決め込んで、こうして俺の反応を楽しんでいるんじゃないだろうか。
「おい、こら引田。ひとり喋りすぎるオレってアホいだろ」
もしそうなら、激烈に悪趣味だ。
「引田あ、なんとか言えよーお」
——ああでも。この想いを確信された勢いで、「俺たちの距離に名前をつけたい」と言ったら、どうなるだろう。不自然な糸口を紡いでリーチのすべてを束縛できたら。俺の心は、満たされるかもしれない。
「はあ……」
リーチは溜め息と一緒に、合わせた手をストンと下ろす。
「ノー返事かよ」
そのまま前後に、柱時計の振り子よろしく大きく動かし始めた。
隣り合う、リーチと俺の腕が、風をおこしながら時折触れる。こんなふうに、こちら寄りの偶然が重なると、これを『必然』だと思い込みたくなるのは、なぜだろう。つらくなるだけなのに、不確かな可能性にきっかけを求めてしまう。
「寝ながら歩いてますぅ、とか言うのナシだかんな~」
「…………」
「あーあ」
「…………」
「静かすぎて、オレだけが取り残された気分」
腕振りが止んでも、解こうと思えば簡単に解けてしまうくらいの力具合で俺たちはなんとなく、手指を合わせたままでいる。——拒絶されていないのなら、もっとリーチに近づきたい。さらなる鼓動を従えた誘惑が、頭をもたげ始める。
そんな時、少し冷たい風にのって、木々の重圧感ある香りが鼻腔に届いた。なにかを踏みつけた感覚に視線を向かわせた足元には、数枚の葉のわきに小さい実をつけた小枝が落ちている。顔を上げてみれば、俺たちはもう、学校の黒塗りゲートまで来ていた。
「裏門到着。どうする?」
そう聞かれて、返事をしなかった。俺に魔法をかけたのがリーチなら、それを解くのも、リーチがいい……なんて、思ったから。
リーチが、俺を見るのがわかった。俺は、口内の端っこを犬歯で噛みながら、リーチの言動に従う覚悟を決めた。
ふっと息を吐き、黙りこくる俺にリーチが言う。
「折り返すか」
その言葉に、心の中でガッツポーズをとる。リーチがするゆっくりとした方向転換に合わせて、落ち着かない心境できびすを返した。
誘惑が期待となり、期待は、この機会を試そうと俺を促す。
わかってはいるんだ。俺が望みを口にすれば、リーチは『今』を離れていく。だから、散歩を喜ぶだけでいい。わざわざ自分から、なくさないほうがいい。
でも……俺は、リーチの横にいて、リーチは俺との時間を共有している。声を出せば届くかもしれない。
昂る感情がふたりの髪を揺らす追い風に乗り、心を打つ速さを増していく。俺は左手で拳をつくり、勇気を込めた。
「……なあ。来いよ」
と、うつむき加減に切り出す。
「来れば、俺んち」
「おまえんち?」
今を壊すにはまだ早いのだと、そうわかっているはずなのに。俺の心理は、パブロフの犬を選ぶ。
小さく頷いた俺は、リーチを誘った。
「まえ、興味あるって言ってただろ。だから、来れば? 今週末とか。土曜クラスのあとに」
「急に言われてもなあ」
「海、好きなんだろ。ウチ来れば近いぞ」
「引田の家って、鎌倉だったよな」
「そう」
「こっからだと電車賃高いじゃん」
予感を否定したい俺は、なんとか、リーチを言いくるめようと試みる。
「片道くらいなら、おごってやってもいいぞ」
「ははっ」
リーチは軽く笑って、「そのうちなあ」と、いかにも曖昧なふわった言葉を落とした。
いつものようにあしらわれた俺は、意固地に食い下がる。
「来いよ」
「悪いな。他の誘いも断ってるからよ」
「だったら、みんな誘ってさ。それならいいだろ?」
「うーんまあ。そのうち考えるわ」
リーチは、こちらの思考とは反比例な温度差で言う。
ぼんやりと返答される俺は、自分だけのぼせている事実を婉曲的に打ち据えられるのを感じた。動揺と独占欲を抱えて、それでもなおもっと近づきたい、確かに得たい、というむき出しの願望を丸め込むのに必死になる。
「そればっかだな」
「しょうがないだろ。約束したら、守らないといけなくなる」
「じゃあそうしろよ」
「無理だって。おまえも知ってるだろ? 部活始めたから週末も試合あるし、他にもいろいろあるし。オレの予定はな、濃密かつ突発的なんだよ」
リーチの言い草に、俺は奥歯をきしませた。
クソっ。毎度毎度蹴りやがって頑固なやつ!
おまえの言うそれは、優先順位の何番目の話をしてるんだよ。……俺との約束より大事なのか。
心の中にモヤモヤが充満する。目を細め、前方に向かって投げつけるように言った。
「どんだけ忙しんだよ。つき合い悪すぎだぞ」
「そうかあ?」
「そうだよ! そもそも、クソ忙しいおまえが、なんで真面目に部活動してんだよ」
「ちょっこし青春しとこうと思って」
「似合わねえよ!」
あんなにどの部からも勧誘されていたのに、普通ならそろそろ引退を視野に入れるこの時期にバレー部の入部決めたのだって、なにかしらいわれがあるんだろ。なんのために、誰のためにそうしてるんだよ。
「来年俺たち、一応受験生だぞ。いま遊ばないでいつ遊ぶんだよっ」
「オレだって適度に気晴らししてるぞ。それにおまえには、遊び相手ならいくらでもいるだろ」
「いてもいなくても、俺はっ、おまえに言ってんだよ。映画誘っても、遊び誘っても、片っ端から断りやがって。ワーカホリックのサラリーマンかっつーの!」
俺の憤慨を横に、頭をかくリーチが言った。
「そんなにオレをご指名なら、応援来いよ。今週末は、海老原学園高等学校で練習試合だからさ」
「ヤダね」
「うわ。まさかの拒否」
「あたりまえだろ!」
尖るイラだちが沸騰して、俺の髪先までをさかなでる。
「どっかの体育バカじゃないんだ。休みの日に時間かけて、わざわざ学校なんかに来るかよっ」
「誰が『体育バカ』だ?」
「俺の隣にはおまえしかいないだろ!」
鋭い口調でぶつけた。
臆病を理由に掲げてわがままを糧にリーチの心情を量ろうとすれば、闘牛士がヒラリと身をかわすように、一瞬で俺は独りを強いられる。
手を握れたから、コイツの感情まで誘導できると思ったのか、俺は。リーチの隣にいるとして、俺が望むものを得る確証はないのに。
錯覚を繰り返す俺は、健気で懸命に、友情からあらがおうと必死な自分を傷つけていく。失恋の痛みさえも想像に任せて、トゲだらけの風船を膨らませながら、決まったとおりにジダンダを踏んでいるみたいだ。……なにをやっているんだ俺は。
「お」
なんの前触れもなく、リーチが足を止めた。
「なんだよっ」意図せず不機嫌が語尾に出る。
「あの色調が好きなんだよなー」
知れず自己嫌悪にさいなまれる俺を、のんきな声音が刺激する。
「ほれ、見てみろよ。空」
言われた視線の先では、少しのピンクをにじませながら、オレンジのグラデーションが暖かみを空に演出していた。
「夕陽がどうした」
「儚いものほど、繊細で美しい」
すっかりその場に立ち止まったリーチが、穏やかに言った。
「安心するんだ。夕焼け見ると」
「意外すぎ」
「いいんだよ。オレは、ノスタルジックな人間だから」
「自称ってのは恐ろしいな」
俺は、朝陽が好きだ。
ハジマリの光は、夢のような出来事を動かす希望の象徴。それはまるでリーチのようだから、本人も朝陽のほうを好むと思っていた。
「綺麗だな。久々に見たわ」
と、うれし気な声を発しながら、リーチは校庭の方角に向き直り空を仰ぐ。
「夕焼けは、やっぱ秋だよな」
しみじみと発するリーチに俺は思った。
遠くを見つめるその視線を、俺だけに向けてくれる日が来るのだろうか。
「建物の向こうに沈む夕陽より、水平線に沈む夕陽のほうが格段にいいけどな」
嫌みまじりに言うと、ささくれた俺の心がピリッと沁みた。
頭ではわかっている。リーチは、なにも悪くない。願わくは、俺だって解放されたい。……今なら、『友達』を装っていられる今なら、まだ間に合うかもしれない。無難な位置を保っている間、イビツな主張を誇示する細胞が、すべて生まれ変わればいい。そうすれば、ツライ悪循環な妄想から抜け出せるはずだ。……なのに一体なんだって俺は、こんなにも切望するのだろう。リーチといると、自分を偽りたくなくなる。
だからたとえ、それが蜃気楼に似ていると気づいていても、リーチにも俺と同じ気持ちでいてほしいと、俺がそうするように、リーチからも好かれたいと願ってしまう。
「あの太陽。このまま見てたら、あそこの建物にぶつかるな」
「残念。おまえに、じゃないのか」
「相変わらずオレにカラいなぁ、引田伊朔」
「当然だ」
俺は自分に驚く。リーチに対してこんなにも、純粋だということに。
そして同時にこうも思う。
想像上の見えない幸せを得ようとあくせくする俺は、曖昧な地図を逆さにしてさまよう冒険家みたいだ。
やるせない気持ちで、夕陽が民家の屋根にゆったりと沈んでいくさまに目を向ける。夕陽のゆらめきが心の縁と重なり、ほろりと切なくさせた。
ともすれば、リーチが俺を呼ぶ。
「なあ引田」
「……なんだよ」
「音、したか」
「おと?」
「聞いてなかったのか」
「なんのだよ?」
逆光に半分陰らす横顔で、リーチは俺に問いた。
「じゃあさ。夕陽が海に沈む時は、どんな音がするんだ?」
「…………」
詩人にでもなるつもりか、おまえは?
そんな突拍子もないこと、なんでわざわざ俺に訊いたりするんだよ。
リーチの意図を図りかねた俺は、無言で立ち尽くす。
「なんだ、そのアホな間は。おまえ、いつも見てんだろ?」
「そんなの、音までわかるかよ。大抵は、江ノ電ん中だし」
車窓から眺める夕陽は、俺にとっては切ない光景だ。
電車が揺れるたびに俺たちの時間からどんどん離されていく気がして、胸が苦しくなる。エンドロールのような景色を前に思うのは、————「ああ。今日も友達だった」という嘆きだ。
足元に目線を落として自分の靴先を見る。
「うるさいだろ、線路を走る音とか。それに、イヤホンしてる時もあるしな。仮に聞こえてきたとしても、その音は、俺まで届かない」
「……おまえなら、聞こえていると思ったんだけどな」
風に吹かれた校庭の砂がサアっと足をさらい、俺の耳を煩わせた。
「——じゃ、確かめるか」
「なにを?」と、俺は眉間に力を入れた。
「現地調査するしかない!」リーチが右拳を上に突きあげる。
「どうでもいいけど、謎の思いつきを、決定口調で言うな」
「ブウブウうっせえぞぉ」と、拳を下ろすリーチは、「切実な提案なんだから、おまえもつき合え」言ってそのまま、手を腰に添えた。
「なんで俺がっ」
「夕陽見に、今度行くから」
リーチの言葉にがく然とした。
なんだよ突然。
……でも、どうして。
「来るのか。本当に?」
「これよりも綺麗なんだろ?」
「そう、だけど」
「見てみたいじゃん。おまえが絶賛する夕陽ってのを」
「そんな理由で……スケジュールの調整、するのかよ。おまえは」
「あはははは」
「笑ってごまかすな」
口を尖らせて腑に落ちないとぼやいてみるものの、喜びで本心は無邪気にはずんでいた。
悪態をついても無理を要求しても、甘やかすように、リーチの壁を誰に対するよりも低く設定してくれていると感じてしまうのは、俺が自惚れているからだろうか。
今だって、こうして隣にいられるのは、俺だから許されているのだと思ってしまう。これだから、気まぐれなゲーム盤の上で踊る駒の気分に浸ってまでも、俺は懲りずに期待するんだ。
俺はおまえを知ってからずっと、こうして不安定な淡い想いを抱え続けている。いつまで温存すればいいのかコタエを導き出せないまま、宙ぶらりんな俺はおまえと、『友達』をして毎日を過ごしているんだ。
なあリーチ。切なすぎるだろ、こんなの。
こんな俺の、片想いは——。
「まあ変わらず、いつとは言えないけどさ。夕陽が綺麗に見える頃には行くよ」
「そのセリフ、絶っ対に忘れんなよ」
と、半信半疑でリーチにクギを刺す。
「了解しました」
刹那。触れているリーチの指が、俺のを強く引き寄せた。
それを合図に視線を移せば、あかね色に染まったリーチがふわりと笑っていた。
見渡せば、周りの景色同様、穏やかに佇む陽光が包むすべての中に俺たちもすっぽりとおさまっている。
片想いってのは優柔不断の塊だから、同じなにかを刻めるだけで簡単にのぼせてしまうんだ。——そう確信した時、心の真ん中がはじけてやさしい光が生まれた。
今は俺が、おまえの一番近くにいるんだよな。肩を並べた隙間を互いの手で結んで、同じ方向にある美しいものを眺めている。あてのない嫉妬に息切らすよりも、つかの間の幸せに感動したほうがずっといい。だから今は、深く考えるのはやめにしよう。
夕陽に色づく空を見上げながら、ようやく俺は、つないだリーチの手の温かさに気づき……それに惹かれた。
「リーチぃぃぃ!」
無慈悲にも体育館側から、こちらに向かって大声で呼ぶやつが現れた。黄色のビブスを大きく振り回している。
「試合ッ! バスケ! 助っ人頼んだだろおお!」
「やべぇ。そうだった」
さっきリーチが言っていた放課後の用事とは、このことだったのか。
そうして、あっけなく解かれる温もり。
「オレ、行くわ」
無言の俺を置き去りにして、これ幸いといわんばかりに走り出す。こうなると、俺はリーチの行方を目で追うだけだ。
「——で、放置かよ」
いいかげん慣れたぞ、このパターンに。光射したと安堵するとコレだ。
「掴まえたのは俺、だったのにな」
だけど気づいた時には、俺がリーチのペースにドギマギしていて。期待に喜びを錯覚しているうちに、当の本人は俺の前から姿を隠す。
現れては消え、手にしたと思ったら去られ。ぐるくるぐるぐるくるくるぐるぐる、そんなのが巡ってばかりだ。……だから、だろうか。俺のもとに、リーチをつなぎ留めておきたいと願ってしまうのは。こんなにも強い執着心を煩ってしまうのは、みんながリーチを求めているからかもしれない。
遠ざかる背中に想いを馳せる。
ついさっきまで俺と並んでいたのにな。振り返りもせずに、次の場所に一直線かよ。
「糸の切れた風船だな。おまえ」
小さい頃、店先で渡されたそれに、リーチは似ている。ふとした瞬間するりと手のひらから抜け出してしまう、あの、空飛ぶ風船だ。
「俺は、どうすればいい?」
どうしたらいいんだ。俺には、おまえみたいに翔ぶチカラはないんだよ。できないんだ、俺には。俺独りじゃダメなんだ。——なのに、また置いてけぼりにするのかよ。
「足、速いな。相変わらず」
とうとうリーチは、バスケ部員と体育館の中へ入ってしまった。
おまえが見えない。おまえの姿も……気持ちも。独りが不安で、途轍もなくつまらなくなる。おまえが好む夕焼けも、俺独りだと、憂鬱な色にしか映らない。
おまえから憧憬の念を抱いてほしいのに、それは、永遠の空想にすぎないのか。
それでも、待っていられたら、……またおまえに触れてもいいか?
すべてを伝えて、期待どおりのコタエを望めればいいのに。
「おまえとなら、どこまでだって翔べるんだよ。俺は」
まだ感触の残る右手に不平を漏らす。
可能性を見いだせないまま、想い出だけが増えていく。
いちずな俺はこの先も、平静を装っていられるだろうか。
————〝夕陽見に、今度行くから〟
大きなオレンジの下で交わした、指きり代わりの手つなぎ。
「忘れるなよ」
その手をポケットに突っ込んで、俺は、夕映えの校庭をあとにした。
☆★☆