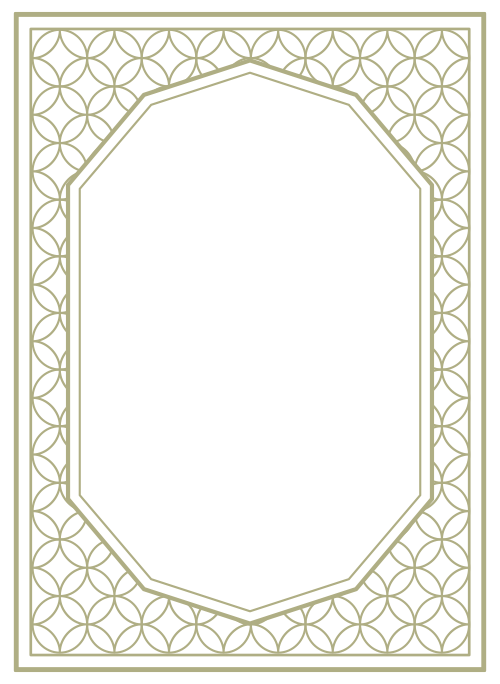千里と再会してから四か月が経ち、僕は中学校を卒業した。
春休み、携帯電話を手に取り、ついに千里に電話をかける決意を固めた。何度もためらっていたので、握る手のひらは汗にまみれている。
僕の犯した罪は頭を下げて済まされるようなものではない。だから、僕にできることは、千里のために人生の時間を差しだすことだ。そうでもしなければ、罪の意識は僕を容赦なく押しつぶしてくるに違いない。
これから始まる贖罪の日々。逃げることなどできっこない。
葛藤を振り払い、両手の親指を重ねて通話ボタンを押下した。話をする前から喉は砂漠の岩山のように乾ききっていた。
しばらく待たされたけれど千里は電話に出た。胸の鼓動が一段と激しくなる。
「もしもし千里? 京本です。お久しぶりです」
後ろめたさを抱えているせいで、無駄にていねい語が混ざってしまう。
「あっ、和也くん? ――驚いた、電話をくれるなんて」
「卒業して進路が決まったから電話したんだ。やっと時間もできたし」
「そんな……わざわざ気を遣わなくてもよかったのに」
――あれ?
最初の会話に僕は妙な違和感を覚えた。やけに他人行儀に感じられたし、敬遠されているような気もした。この前会ったときは無邪気に再会を喜んでいるようだったのに。
「別に気を遣っているわけじゃなくて報告だよ。私立の高校に行くことになったんだ」
「へー、おめでとう。じゃあこれから花の高校生活だね。あたしはエレベーター式っていうのかな? 行くところは決まっているけど。それで、どこの高校? 地元? それとも都会に出るの?」
そこで一度、深呼吸をして自分自身の気持ちを落ち着かせる。
なぜなら、このひとことを千里に伝える瞬間を、何度も脳裏に描いていたのだから。
「城西高等学校。知っているよね」
「……え?」
「千里の街にある高校だよ」
直後、電話の向こうの千里は絶句している、ように思えた。まるで言葉が返ってこなかったからだ。僕はさらに送話口に向かって渾身のひとことを放つ。
「千里にいつでも会えるように、きみのいる街の高校にしたんだ」
城西高等学校は県内でも上位の進学校で、当時の僕の偏差値では合格できるとは思えなかった。けれど千里の住む街にあって、親が納得する高校と言えば城西高等学校しかなかった。
僕は自分でも驚くほどの努力をして受験に挑んだ。けれど勉強のための努力なんてささいなことだった。光を奪われた千里に対してこの僕ができることは、人生をかけて償うことなのだ。だから、結果として高校入学の権利を得たことは、せいぜい贖罪の序章にしか過ぎない。
「そんな……どうしてあたしのために……?」
「僕がそうしたいだけだから。今度、おばさんにも挨拶するから会いに行くよ」
ふたたび沈黙が訪れる。千里がどんな気持ちでいるのか、僕にはよくわからなかった。ただ、僕が期待したほどの喜びを千里は示していなかった。むしろ迷惑だったのだろうかと不安になる。
けれど、たとえそう思われようとも、僕は千里に会いにゆく決心を固めていた。
「だから、もしよかったら明日行ってもいいかな」
「えっ、それは困る!」
即答で断られた。まさか、僕は千里に拒否されているのか? だとしたら僕の努力は意味をなさないのか? おっかなびっくり尋ねる。
「じゃあ、いつか大丈夫なときはある?」
「ちょっ、ちょっと待って、お母さんと相談してくる!」
千里は突然、あわてだした。早足の足音が聞こえ、なにやらおばさんと小声で話しているようだった。目が見えないから携帯電話の送話口を押さえるという発想がないのだろう。
それからまもなく返事があった。
「水曜日っ、水曜日にしてくれない?」
拒否されているわけではなさそうな返事だった。妙に他人行儀な雰囲気だったので心配したけれど、それは杞憂だったと胸を撫でおろす。
だけど、どうして水曜日だけが大丈夫な日なのだろうか。僕は毎日と言われても即、応じるつもりだったのに。ただ、千里にも新しい生活の都合があるのだろうと、訊かずになんとなく納得した。
「わかった。じゃあ今度の水曜日、必ず行くよ」
「あっ、うん、ありがと……待っているからね」
その声は浮かれているようにも、警戒しているようにも聞こえた。けれど僕は努力が報われたと思い気分が高揚していた。だからその疑問はささいなものとしてすぐに頭から消え去った。
――光を失った千里に、光のある世界を見せてあげなくては。
高校生活が始まる直前の、春休み最後の水曜日。単行本を数冊カバンに詰めて千里に会いにゆく。電車に揺られ駅を降りてから、この前とは違う道を進んでゆく。
以前は気づかなかったけれど、千里の家へ向かう上り坂の街路樹は桜の木だったようで、ちょうど桃色の花弁が顔をのぞかせ始めた頃だった。来週、この道を通る頃には満開になるのだろう。
僕はこれから毎年、この桜並木を眺めることになるはずだ。そう思い、立ち並ぶ桜の木に向かって会釈をする。葉のない枝の隙間を通りぬける燦然とした日差しはまぶたを閉じても眩く感じられた。
けれど千里は鮮烈な桜の開花も、眩しい春の陽の光も味わうことができない。それはきっと僕のせいなんだと、いやおうなしに後悔の念が沸き起こる。呵責を振り払うように足を踏みだし、桜の下を全力で駆け抜けた。
春休み、携帯電話を手に取り、ついに千里に電話をかける決意を固めた。何度もためらっていたので、握る手のひらは汗にまみれている。
僕の犯した罪は頭を下げて済まされるようなものではない。だから、僕にできることは、千里のために人生の時間を差しだすことだ。そうでもしなければ、罪の意識は僕を容赦なく押しつぶしてくるに違いない。
これから始まる贖罪の日々。逃げることなどできっこない。
葛藤を振り払い、両手の親指を重ねて通話ボタンを押下した。話をする前から喉は砂漠の岩山のように乾ききっていた。
しばらく待たされたけれど千里は電話に出た。胸の鼓動が一段と激しくなる。
「もしもし千里? 京本です。お久しぶりです」
後ろめたさを抱えているせいで、無駄にていねい語が混ざってしまう。
「あっ、和也くん? ――驚いた、電話をくれるなんて」
「卒業して進路が決まったから電話したんだ。やっと時間もできたし」
「そんな……わざわざ気を遣わなくてもよかったのに」
――あれ?
最初の会話に僕は妙な違和感を覚えた。やけに他人行儀に感じられたし、敬遠されているような気もした。この前会ったときは無邪気に再会を喜んでいるようだったのに。
「別に気を遣っているわけじゃなくて報告だよ。私立の高校に行くことになったんだ」
「へー、おめでとう。じゃあこれから花の高校生活だね。あたしはエレベーター式っていうのかな? 行くところは決まっているけど。それで、どこの高校? 地元? それとも都会に出るの?」
そこで一度、深呼吸をして自分自身の気持ちを落ち着かせる。
なぜなら、このひとことを千里に伝える瞬間を、何度も脳裏に描いていたのだから。
「城西高等学校。知っているよね」
「……え?」
「千里の街にある高校だよ」
直後、電話の向こうの千里は絶句している、ように思えた。まるで言葉が返ってこなかったからだ。僕はさらに送話口に向かって渾身のひとことを放つ。
「千里にいつでも会えるように、きみのいる街の高校にしたんだ」
城西高等学校は県内でも上位の進学校で、当時の僕の偏差値では合格できるとは思えなかった。けれど千里の住む街にあって、親が納得する高校と言えば城西高等学校しかなかった。
僕は自分でも驚くほどの努力をして受験に挑んだ。けれど勉強のための努力なんてささいなことだった。光を奪われた千里に対してこの僕ができることは、人生をかけて償うことなのだ。だから、結果として高校入学の権利を得たことは、せいぜい贖罪の序章にしか過ぎない。
「そんな……どうしてあたしのために……?」
「僕がそうしたいだけだから。今度、おばさんにも挨拶するから会いに行くよ」
ふたたび沈黙が訪れる。千里がどんな気持ちでいるのか、僕にはよくわからなかった。ただ、僕が期待したほどの喜びを千里は示していなかった。むしろ迷惑だったのだろうかと不安になる。
けれど、たとえそう思われようとも、僕は千里に会いにゆく決心を固めていた。
「だから、もしよかったら明日行ってもいいかな」
「えっ、それは困る!」
即答で断られた。まさか、僕は千里に拒否されているのか? だとしたら僕の努力は意味をなさないのか? おっかなびっくり尋ねる。
「じゃあ、いつか大丈夫なときはある?」
「ちょっ、ちょっと待って、お母さんと相談してくる!」
千里は突然、あわてだした。早足の足音が聞こえ、なにやらおばさんと小声で話しているようだった。目が見えないから携帯電話の送話口を押さえるという発想がないのだろう。
それからまもなく返事があった。
「水曜日っ、水曜日にしてくれない?」
拒否されているわけではなさそうな返事だった。妙に他人行儀な雰囲気だったので心配したけれど、それは杞憂だったと胸を撫でおろす。
だけど、どうして水曜日だけが大丈夫な日なのだろうか。僕は毎日と言われても即、応じるつもりだったのに。ただ、千里にも新しい生活の都合があるのだろうと、訊かずになんとなく納得した。
「わかった。じゃあ今度の水曜日、必ず行くよ」
「あっ、うん、ありがと……待っているからね」
その声は浮かれているようにも、警戒しているようにも聞こえた。けれど僕は努力が報われたと思い気分が高揚していた。だからその疑問はささいなものとしてすぐに頭から消え去った。
――光を失った千里に、光のある世界を見せてあげなくては。
高校生活が始まる直前の、春休み最後の水曜日。単行本を数冊カバンに詰めて千里に会いにゆく。電車に揺られ駅を降りてから、この前とは違う道を進んでゆく。
以前は気づかなかったけれど、千里の家へ向かう上り坂の街路樹は桜の木だったようで、ちょうど桃色の花弁が顔をのぞかせ始めた頃だった。来週、この道を通る頃には満開になるのだろう。
僕はこれから毎年、この桜並木を眺めることになるはずだ。そう思い、立ち並ぶ桜の木に向かって会釈をする。葉のない枝の隙間を通りぬける燦然とした日差しはまぶたを閉じても眩く感じられた。
けれど千里は鮮烈な桜の開花も、眩しい春の陽の光も味わうことができない。それはきっと僕のせいなんだと、いやおうなしに後悔の念が沸き起こる。呵責を振り払うように足を踏みだし、桜の下を全力で駆け抜けた。