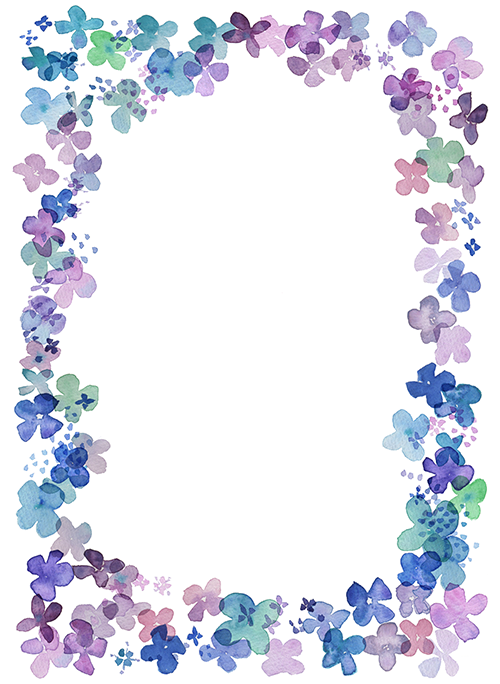どうせ今日もやることはないのだから、日がな一日彼女とくだらない話をするのだと思っていた。君は俺の仕事に強く興味を示していたからテレビとはどんなもので、撮影とはどんな風に進むのか教えてあげるのも良い。17年間も反抗せず素直に小屋に閉じ込められていた彼女は無気力な人間だと想像していたがそうでもないらしい。知らないことを知るたびに落ち着きのある瞳が輝くと年相応の少女と言った感じで、俺はもっと色々なことを教えてあげたくなった。
「後は昨日出来なかった花火を買うだけか」
手にぶら下げられたレジ袋には昼と夜分のおにぎり二人前と、緑茶のペットボトルが入っている。二日前から代わり映えのしないつまらない食事だが、君は文句も言わずいつも美味しそうに頬張っている。単におにぎりが好きなのかもしれないが、彼女が経験した今までの食事はこんな質素なものよりも更に悪質なものだったのかもしれない。想像すると胸が痛んだ。
駄菓子屋に到着すると、店主のおじさんを呼んで線香花火の束を出してもらう。
「見ない顔じゃな。どこから来たんだい」
「少し、用事があって東京から」
「東京からこんな辺境まで来たのかい。好事家もいるものだねぇ」
この人はテレビなどは見ないのだろうか。俺の顔を見ても何とも反応しないし、ここに来た目的も観光だと思っている。よく耳を澄ませばノイズの入った昭和歌謡が流れていて、レジの奥にはレコードが回っていた。なるほど、旧式を好むものもまだいるんだな。彼が俺を好事家というなら、時代の流れに乗らない彼もまた好事家だと思った。
「坊主、若いのにいいのかい?今時はもっと大袋に入った色が鮮やかなやつが人気だと思っとんたんだが」
「いいんです。一緒にする人が花火初心者で、あまり刺激の強いものもどうかと」
俺は苦笑いしながら返す。鳥籠に閉じ込められていた少女には花火の大袋は刺激が強すぎる。線香花火のときの少女の初心な反応を想像すると、安易にねずみ花火や手筒花火を渡す気にはなれなかった。多分、大火事になるか彼女の心臓が止まるかどちらかであろう。
「きみは優しいんじゃなぁ」
腰の曲がった老爺は皺だらけの目元を細めた。
俺はその言葉になんと返せばいいのか分からなかった。何とか小さく笑って誤魔化したが表情筋は弛緩と緊張の間で何とも言えない表情になる。
「わしにも昔花火をしようと約束していた女がいたなぁ」
「そうですか」
「村の祭りの大輪だけでは満足できなかったみたいでな、拗ねた顔をしながらもっと近くで美しいのを見たいと駄々を捏ねたの思い出したよ」
聞き流すつもりだったのにその話にどこか既視感を覚えた。俺は思わずカウンターに小銭入れを揺らす勢いで手を突く。
どうしてか、心臓が痛いくらいに強く、脈を打っていた。
「その、女はどうなったんですか」
老人の眉毛が萎れる。伏せられた睫毛はシミだらけの顔に濃い影を落とした。
「約束した日、彼女は死んだ」
震える声は到底、嘘を吐いているようには見えなかった。正直俺は内臓全部が口から逆流しそうだった。全身に激しい痛みが走る。何もないのに、全身のどこか分からないところが痛くて堪らなかった。それはもしかしたら幻肢痛かもしれないし、ちゃんとした体の不調かもしれない。しかし、俺はこの痛みを表す言葉を知らなかった。
「坊主はこの村の言い伝えを知っているか?」
「神に捧げる少女……」
「なんだ、知っておったのか」
もう何も話さないでくれ。老人が次に喋る言葉を悟ってしまった。ぎゅっと目を閉じる。老人の変わらないトーンは俺の想像通りの言葉をなぞった。
「儂が好いた女は神に捧げる少女だったのだよ」
前後不覚に陥る体が何とかカウンターにしがみつく。萎んだ肺は酸素を求めるが、横隔膜がまるで記憶喪失したように自分の仕事を忘れた。上手く吸えない息は、肺胞を満たすことなく肋骨を不自然に軋ませるだけだった。
目に汗が入った。俺の体には全身から噴き出した冷たい汗が張り付いていた。
「……その話詳しく聞いてもいいですか」
尋常ではない様子の俺に老人は息を呑む。それから咳払いで絡まる淡を胃に落とすと、ゆっくりと話し始めた。
「出会ったきっかけは、儂がいじめでいわくつきと呼ばれているあの神社に忍び込むことを命令されたからなんじゃ。けれど夜になっても何も起こることはなく、下着が汗ばんで気持ちが悪かったから、もう帰ろうとしたその時だった。奥まった場所から声がしたんだよ。それが出会いだったなぁ」
何でもその当時は町が孤児で溢れていたらしい。哀れに思った寺の人間が子供たちを養っていたらしいが、子供たちは例もないのに勝手にカーストを構築し、この老人はその底辺としていじめを受けていたそうだ。
「彼女は全てを諦めたような顔で小さな窓から儂を見つめていた。その姿はさながら鳥籠の扉は開いたままなのに、いつまで経っても外に出ようとはしない小鳥のようだった。儂は最初、幽霊ではと疑ってしまったよ」
それから老人は様々な思い出を語った。名前を聞いたら名前はまだないと返されたこと。その返答から彼女をタマと呼ぶようになったこと。世間知らずの彼女の反応が面白くて、気づけば夜な夜な抜け出しては外の世界の話をしてあげたり、駄菓子屋から駄菓子をくすねては彼女に与えたりしたこと。
いつか寺小屋を出て職に就いたら婚約しようと話したこともあったという。
「彼女の感情のなかった笑顔は段々と喜怒哀楽を含むものに変わっていて、儂はそれが嬉しくて堪らなかった」
彼の穏やかな笑みを見ればわかる。彼らの間には確かに愛が育まれていた。しかし、老人が次の言葉を紡ぐときにはもう、蓄えた微笑みは失われ、操り人形のような目で遠くを見つめていた。
「祭りの日、タマは打ち上げ花火を見つめながら『もっと近くで見たい』と呟いた。儂はいつものように笑って次の日に手持ち花火を持ってくることを約束して帰った。……それが間違いだったのかのぅ」
その横顔には後悔と少しの憎しみが混じっている。どうしてあの時、笑って見過ごしてしまったのだんだろうなとぼやく彼の目尻には涙が滲んでいた。
「もしかして、」
「あぁ、君の予想通り次の日行くと、彼女はもういなかった」
彼が行った時にはもう小屋の中には誰もいなくて、辺りには異臭が漂っていたという。暗がりの中で目を凝らして小屋の中を見ると、葡萄と酒精と酸の匂いが一気に押し寄せて思わず身をのけぞったらしい。
「神に捧げる少女だったタマは最期に葡萄酒と毒が混ぜられたものを飲まされたらしくてね、割れた硝子の破片と食道が爛れるほどの吐瀉物と吐血の痕が残っていたのを目の当たりにした儂はその時生きてきて初めて死んでしまいたいと思ったよ」
つい数分前まで片手に手持ち花火を握りしめ期待で胸を膨らませていた幼い少年が、目を見開き惨状を目の当たりにする。それがどんなに痛々しいことか、想像を絶する思い出話に俺は呼吸一つするのも躊躇われた。
それに、吐瀉物が大量に残されていたということは、毒が全身に回るまで苦しんだということだ。体が必死に生を求めて藻掻いていたということだ。
会ったことのない体の薄い少女の最期を想像する。
何故か、その姿とボタンが重なった。
俺は唐突な嘔気に襲われて、口を押えて必死に胃酸を飲み下す。
「儂は彼女と出会ってからの日々が充実しすぎていて忘れていたよ、彼女がどうしてこんな鳥籠に閉じ込められていたのか」
雲に隠れていた太陽がようやく顔を出したようだ。店に一つしかない窓から木漏れ日が差し込んで、老人の右頬を照らし出す。普通なら光に魅かれるように明るくなった方を見るだろう。しかし、影になっている左半分の暗さに気づいたとき俺は彼の横顔から目を離せなかった。
彼は駄菓子屋の店主として至極普通の人生を歩んできたのだと思う、彼女と出会ったこと以外は。暗がりの彼の表情は当たり前の生活をしてくれば経験しない闇を抱えていた。
「タマは普通の子じゃなく神に捧げる少女、だから祭りの日には殺される。考えればすぐ分かったはずだ、けれどその日に初めて出会ったならすぐ気づくことを、彼女との日々を過ごした儂はタマがいる未来が当たり前だと信じて疑わなかった。儂は実に愚かで、愚鈍で、惰性でしか生きることのできない少年だった」
老人と青年の間に形容しがたい静寂が流れる。呼吸音すら禁忌だと錯覚するほどの静けさなのに、どこかから少女の声が聞こえる。これは俺の空耳なのだろう。脳に直接響く風鈴の端を撫でたような涼やかな声はボタンのものだ。じわりと涙が込み上げた。君が今生きていることは当たり前なんかじゃないのだ。そう思うとつい一時間前まで共に身を寄せ合っていた彼女が急に恋しくなる。
「君が花火を共にする人は想い人なのかい」
「……想い人というか、何というか」
俺が口をもごつかせると、老人は笑う。背中にぬくもりを感じて後ろを振り向くと、シミのある手が優しく背を叩いていた。
「若いというのは素晴らしいことだ。活気に満ち溢れ、恋をして誰かを全身全霊で愛する純粋な心も持っている。けれどそれは同時に愚かさも伴う」
その言葉に俺は押し黙るしかなかった。俺は彼以上に愚かな人間だと思う。幼い頃から優等生な俳優というレッテルを貼られ、その面子を潰さないように必死に自身の仮面を分厚くして、すべて未来への投資の為にいきてきたようなものだ。しかし現在俺は今までの人生を捨てる形でボタンと一緒にいる。若気の至り、痴れ者の何者以外でもない。
俺がしていることは傍から見れば大間違いと言えるだろう。所謂人生負け組というやつだ。
ふと顔をあげると、老人は店の裏から線香花火の束を持ってきた。彼は頼んだ数より随分おまけのされた包みを俺に押し付けてくる。慌てて財布を取り出そうとすると、静かに首を振る老人。その顔は微笑んでいるのに、どこか泣きそうであった。
「ただ愚かであることが必ずしも悪だとは思えないんだ。儂が通う度に、死んだ顔をしていたタマの表情が一つまた一つ増えていった。知らないことを教える度に、何にも染まっていない純粋な瞳が待ち望んでいたように光を取り戻していった。タマが死んで周りは儂を嘲笑した。死ぬことが分かっていた娘に現を抜かすなんて時間の無駄だと嗤った。でも、儂だけは愚者になったのは間違いではなかったと信じている」
愚かであることが必ずしも悪ではない。彼が言うからこそ、それは何十倍にも重くなって俺の心に響く。老人は俺の反応を見ると、にやりと含みのある笑みを浮かべる。その表情は先ほどとは打って変わって晴れやかなものであった。
「君には愚かになる勇気があるかい?」
俺は目を見開いて目の前の人物の瞳を見つめた。嗚呼、この沢山の色を吸収した深い瞳の前では嘘など通用しなさそうだ。俺が答えると、老人は「そうか」とだけ言って煙草をふかし始めた。
「色々とありがとうございました」
「あぁ、いいんだよ。儂の方こそ、もう60年も前のわだかまりからようやく解放された気がするよ」
「それは、よかったです」
白い煙を口から漏らしながら老人は扉の奥に視線を向けた。開けた店の外には小さな山が一つあって、朱色の鳥居が見える。何を考えているのかは分からなかったが、今日見る夢で彼は愛した少女に再び出会うのだろうなと思った。俺が店を去ろうとしたとき、彼は何か思い出したように口にする。
「そういえばどうしてタマは開いた窓から外に出なかったのだろうな」
「監視が厳しくて出れなかったのでは?」
「いいや、それはないと思うよ。儂が通っても一度も警備の人間などいなかったし、抜け出すことをそそのかしても咎めを食らったことはない。窓の大きさも小柄なタマでは十分潜り抜けれたはずなのに、タマは抜け出す素振りを一度も見せないまま生贄となってしまった」
その返答に俺の心拍数は急激に上昇する。
手薄な警備。神に捧げる少女。町に溢れていた孤児。簡単に抜け出すことのできる小屋。
「……まさか」
まさか、そんなこと有り得ない。
荒くなった息を必死に戻す。瞳孔は興奮で大きく開かれたまま震えていた。手汗の滲んだ小包は音をたてて、地面に転がる。
頭を過る最悪の想像に口が痙攣する。乾燥した唇からは言葉を発せられず、意味のない呻きを上げた。
老爺はパニックになる俺の背中を狼狽しながら摩る。しかし何かを思い出したのか「あっ」と声をあげた後、手を止めた。
「そういえば、儂が未来の話をするたびにタマは決まって困ったように同じことを呟いていた」
ふとボタンの笑顔が脳内で弾ける。
「『どうせ結末は皆一緒なのだから』」
毒を飲んで苦しむ少女が脳内でリフレインする。
記憶の中の君が一瞬で朱色に染まった。
俺の予感はいい意味でも悪い意味でも的中することが多い。それに対し気に留めたことはなかった。悪い予感が現実になったとしてもそれが運命なのだと受け入れていた。しかし、今回ばかりは外れてくれと願う。
ボタンが死ぬ
俺の脳内を埋め尽くすのは皮肉にもその言葉だけだった。
俺はなりふり構わず店を飛び出し、陽の光の下を走った。風の噂で俺がこの村にいると聞きつけたファンまがいがと警察が相島透捜索に明け暮れていると聞いたが、そんなのもうどうでもよかった。
手に絡みついたビニール袋も邪魔で道端に投げ捨てる。警察に追われようが、誰かに晒されようが、君が死んでしまうことに比べれば痛くも痒くもない。
「頼む……間に合え……たのむ」
つい一時間前までいた山に戻ってきた。
君はもう、そこにはいなかった。
「後は昨日出来なかった花火を買うだけか」
手にぶら下げられたレジ袋には昼と夜分のおにぎり二人前と、緑茶のペットボトルが入っている。二日前から代わり映えのしないつまらない食事だが、君は文句も言わずいつも美味しそうに頬張っている。単におにぎりが好きなのかもしれないが、彼女が経験した今までの食事はこんな質素なものよりも更に悪質なものだったのかもしれない。想像すると胸が痛んだ。
駄菓子屋に到着すると、店主のおじさんを呼んで線香花火の束を出してもらう。
「見ない顔じゃな。どこから来たんだい」
「少し、用事があって東京から」
「東京からこんな辺境まで来たのかい。好事家もいるものだねぇ」
この人はテレビなどは見ないのだろうか。俺の顔を見ても何とも反応しないし、ここに来た目的も観光だと思っている。よく耳を澄ませばノイズの入った昭和歌謡が流れていて、レジの奥にはレコードが回っていた。なるほど、旧式を好むものもまだいるんだな。彼が俺を好事家というなら、時代の流れに乗らない彼もまた好事家だと思った。
「坊主、若いのにいいのかい?今時はもっと大袋に入った色が鮮やかなやつが人気だと思っとんたんだが」
「いいんです。一緒にする人が花火初心者で、あまり刺激の強いものもどうかと」
俺は苦笑いしながら返す。鳥籠に閉じ込められていた少女には花火の大袋は刺激が強すぎる。線香花火のときの少女の初心な反応を想像すると、安易にねずみ花火や手筒花火を渡す気にはなれなかった。多分、大火事になるか彼女の心臓が止まるかどちらかであろう。
「きみは優しいんじゃなぁ」
腰の曲がった老爺は皺だらけの目元を細めた。
俺はその言葉になんと返せばいいのか分からなかった。何とか小さく笑って誤魔化したが表情筋は弛緩と緊張の間で何とも言えない表情になる。
「わしにも昔花火をしようと約束していた女がいたなぁ」
「そうですか」
「村の祭りの大輪だけでは満足できなかったみたいでな、拗ねた顔をしながらもっと近くで美しいのを見たいと駄々を捏ねたの思い出したよ」
聞き流すつもりだったのにその話にどこか既視感を覚えた。俺は思わずカウンターに小銭入れを揺らす勢いで手を突く。
どうしてか、心臓が痛いくらいに強く、脈を打っていた。
「その、女はどうなったんですか」
老人の眉毛が萎れる。伏せられた睫毛はシミだらけの顔に濃い影を落とした。
「約束した日、彼女は死んだ」
震える声は到底、嘘を吐いているようには見えなかった。正直俺は内臓全部が口から逆流しそうだった。全身に激しい痛みが走る。何もないのに、全身のどこか分からないところが痛くて堪らなかった。それはもしかしたら幻肢痛かもしれないし、ちゃんとした体の不調かもしれない。しかし、俺はこの痛みを表す言葉を知らなかった。
「坊主はこの村の言い伝えを知っているか?」
「神に捧げる少女……」
「なんだ、知っておったのか」
もう何も話さないでくれ。老人が次に喋る言葉を悟ってしまった。ぎゅっと目を閉じる。老人の変わらないトーンは俺の想像通りの言葉をなぞった。
「儂が好いた女は神に捧げる少女だったのだよ」
前後不覚に陥る体が何とかカウンターにしがみつく。萎んだ肺は酸素を求めるが、横隔膜がまるで記憶喪失したように自分の仕事を忘れた。上手く吸えない息は、肺胞を満たすことなく肋骨を不自然に軋ませるだけだった。
目に汗が入った。俺の体には全身から噴き出した冷たい汗が張り付いていた。
「……その話詳しく聞いてもいいですか」
尋常ではない様子の俺に老人は息を呑む。それから咳払いで絡まる淡を胃に落とすと、ゆっくりと話し始めた。
「出会ったきっかけは、儂がいじめでいわくつきと呼ばれているあの神社に忍び込むことを命令されたからなんじゃ。けれど夜になっても何も起こることはなく、下着が汗ばんで気持ちが悪かったから、もう帰ろうとしたその時だった。奥まった場所から声がしたんだよ。それが出会いだったなぁ」
何でもその当時は町が孤児で溢れていたらしい。哀れに思った寺の人間が子供たちを養っていたらしいが、子供たちは例もないのに勝手にカーストを構築し、この老人はその底辺としていじめを受けていたそうだ。
「彼女は全てを諦めたような顔で小さな窓から儂を見つめていた。その姿はさながら鳥籠の扉は開いたままなのに、いつまで経っても外に出ようとはしない小鳥のようだった。儂は最初、幽霊ではと疑ってしまったよ」
それから老人は様々な思い出を語った。名前を聞いたら名前はまだないと返されたこと。その返答から彼女をタマと呼ぶようになったこと。世間知らずの彼女の反応が面白くて、気づけば夜な夜な抜け出しては外の世界の話をしてあげたり、駄菓子屋から駄菓子をくすねては彼女に与えたりしたこと。
いつか寺小屋を出て職に就いたら婚約しようと話したこともあったという。
「彼女の感情のなかった笑顔は段々と喜怒哀楽を含むものに変わっていて、儂はそれが嬉しくて堪らなかった」
彼の穏やかな笑みを見ればわかる。彼らの間には確かに愛が育まれていた。しかし、老人が次の言葉を紡ぐときにはもう、蓄えた微笑みは失われ、操り人形のような目で遠くを見つめていた。
「祭りの日、タマは打ち上げ花火を見つめながら『もっと近くで見たい』と呟いた。儂はいつものように笑って次の日に手持ち花火を持ってくることを約束して帰った。……それが間違いだったのかのぅ」
その横顔には後悔と少しの憎しみが混じっている。どうしてあの時、笑って見過ごしてしまったのだんだろうなとぼやく彼の目尻には涙が滲んでいた。
「もしかして、」
「あぁ、君の予想通り次の日行くと、彼女はもういなかった」
彼が行った時にはもう小屋の中には誰もいなくて、辺りには異臭が漂っていたという。暗がりの中で目を凝らして小屋の中を見ると、葡萄と酒精と酸の匂いが一気に押し寄せて思わず身をのけぞったらしい。
「神に捧げる少女だったタマは最期に葡萄酒と毒が混ぜられたものを飲まされたらしくてね、割れた硝子の破片と食道が爛れるほどの吐瀉物と吐血の痕が残っていたのを目の当たりにした儂はその時生きてきて初めて死んでしまいたいと思ったよ」
つい数分前まで片手に手持ち花火を握りしめ期待で胸を膨らませていた幼い少年が、目を見開き惨状を目の当たりにする。それがどんなに痛々しいことか、想像を絶する思い出話に俺は呼吸一つするのも躊躇われた。
それに、吐瀉物が大量に残されていたということは、毒が全身に回るまで苦しんだということだ。体が必死に生を求めて藻掻いていたということだ。
会ったことのない体の薄い少女の最期を想像する。
何故か、その姿とボタンが重なった。
俺は唐突な嘔気に襲われて、口を押えて必死に胃酸を飲み下す。
「儂は彼女と出会ってからの日々が充実しすぎていて忘れていたよ、彼女がどうしてこんな鳥籠に閉じ込められていたのか」
雲に隠れていた太陽がようやく顔を出したようだ。店に一つしかない窓から木漏れ日が差し込んで、老人の右頬を照らし出す。普通なら光に魅かれるように明るくなった方を見るだろう。しかし、影になっている左半分の暗さに気づいたとき俺は彼の横顔から目を離せなかった。
彼は駄菓子屋の店主として至極普通の人生を歩んできたのだと思う、彼女と出会ったこと以外は。暗がりの彼の表情は当たり前の生活をしてくれば経験しない闇を抱えていた。
「タマは普通の子じゃなく神に捧げる少女、だから祭りの日には殺される。考えればすぐ分かったはずだ、けれどその日に初めて出会ったならすぐ気づくことを、彼女との日々を過ごした儂はタマがいる未来が当たり前だと信じて疑わなかった。儂は実に愚かで、愚鈍で、惰性でしか生きることのできない少年だった」
老人と青年の間に形容しがたい静寂が流れる。呼吸音すら禁忌だと錯覚するほどの静けさなのに、どこかから少女の声が聞こえる。これは俺の空耳なのだろう。脳に直接響く風鈴の端を撫でたような涼やかな声はボタンのものだ。じわりと涙が込み上げた。君が今生きていることは当たり前なんかじゃないのだ。そう思うとつい一時間前まで共に身を寄せ合っていた彼女が急に恋しくなる。
「君が花火を共にする人は想い人なのかい」
「……想い人というか、何というか」
俺が口をもごつかせると、老人は笑う。背中にぬくもりを感じて後ろを振り向くと、シミのある手が優しく背を叩いていた。
「若いというのは素晴らしいことだ。活気に満ち溢れ、恋をして誰かを全身全霊で愛する純粋な心も持っている。けれどそれは同時に愚かさも伴う」
その言葉に俺は押し黙るしかなかった。俺は彼以上に愚かな人間だと思う。幼い頃から優等生な俳優というレッテルを貼られ、その面子を潰さないように必死に自身の仮面を分厚くして、すべて未来への投資の為にいきてきたようなものだ。しかし現在俺は今までの人生を捨てる形でボタンと一緒にいる。若気の至り、痴れ者の何者以外でもない。
俺がしていることは傍から見れば大間違いと言えるだろう。所謂人生負け組というやつだ。
ふと顔をあげると、老人は店の裏から線香花火の束を持ってきた。彼は頼んだ数より随分おまけのされた包みを俺に押し付けてくる。慌てて財布を取り出そうとすると、静かに首を振る老人。その顔は微笑んでいるのに、どこか泣きそうであった。
「ただ愚かであることが必ずしも悪だとは思えないんだ。儂が通う度に、死んだ顔をしていたタマの表情が一つまた一つ増えていった。知らないことを教える度に、何にも染まっていない純粋な瞳が待ち望んでいたように光を取り戻していった。タマが死んで周りは儂を嘲笑した。死ぬことが分かっていた娘に現を抜かすなんて時間の無駄だと嗤った。でも、儂だけは愚者になったのは間違いではなかったと信じている」
愚かであることが必ずしも悪ではない。彼が言うからこそ、それは何十倍にも重くなって俺の心に響く。老人は俺の反応を見ると、にやりと含みのある笑みを浮かべる。その表情は先ほどとは打って変わって晴れやかなものであった。
「君には愚かになる勇気があるかい?」
俺は目を見開いて目の前の人物の瞳を見つめた。嗚呼、この沢山の色を吸収した深い瞳の前では嘘など通用しなさそうだ。俺が答えると、老人は「そうか」とだけ言って煙草をふかし始めた。
「色々とありがとうございました」
「あぁ、いいんだよ。儂の方こそ、もう60年も前のわだかまりからようやく解放された気がするよ」
「それは、よかったです」
白い煙を口から漏らしながら老人は扉の奥に視線を向けた。開けた店の外には小さな山が一つあって、朱色の鳥居が見える。何を考えているのかは分からなかったが、今日見る夢で彼は愛した少女に再び出会うのだろうなと思った。俺が店を去ろうとしたとき、彼は何か思い出したように口にする。
「そういえばどうしてタマは開いた窓から外に出なかったのだろうな」
「監視が厳しくて出れなかったのでは?」
「いいや、それはないと思うよ。儂が通っても一度も警備の人間などいなかったし、抜け出すことをそそのかしても咎めを食らったことはない。窓の大きさも小柄なタマでは十分潜り抜けれたはずなのに、タマは抜け出す素振りを一度も見せないまま生贄となってしまった」
その返答に俺の心拍数は急激に上昇する。
手薄な警備。神に捧げる少女。町に溢れていた孤児。簡単に抜け出すことのできる小屋。
「……まさか」
まさか、そんなこと有り得ない。
荒くなった息を必死に戻す。瞳孔は興奮で大きく開かれたまま震えていた。手汗の滲んだ小包は音をたてて、地面に転がる。
頭を過る最悪の想像に口が痙攣する。乾燥した唇からは言葉を発せられず、意味のない呻きを上げた。
老爺はパニックになる俺の背中を狼狽しながら摩る。しかし何かを思い出したのか「あっ」と声をあげた後、手を止めた。
「そういえば、儂が未来の話をするたびにタマは決まって困ったように同じことを呟いていた」
ふとボタンの笑顔が脳内で弾ける。
「『どうせ結末は皆一緒なのだから』」
毒を飲んで苦しむ少女が脳内でリフレインする。
記憶の中の君が一瞬で朱色に染まった。
俺の予感はいい意味でも悪い意味でも的中することが多い。それに対し気に留めたことはなかった。悪い予感が現実になったとしてもそれが運命なのだと受け入れていた。しかし、今回ばかりは外れてくれと願う。
ボタンが死ぬ
俺の脳内を埋め尽くすのは皮肉にもその言葉だけだった。
俺はなりふり構わず店を飛び出し、陽の光の下を走った。風の噂で俺がこの村にいると聞きつけたファンまがいがと警察が相島透捜索に明け暮れていると聞いたが、そんなのもうどうでもよかった。
手に絡みついたビニール袋も邪魔で道端に投げ捨てる。警察に追われようが、誰かに晒されようが、君が死んでしまうことに比べれば痛くも痒くもない。
「頼む……間に合え……たのむ」
つい一時間前までいた山に戻ってきた。
君はもう、そこにはいなかった。