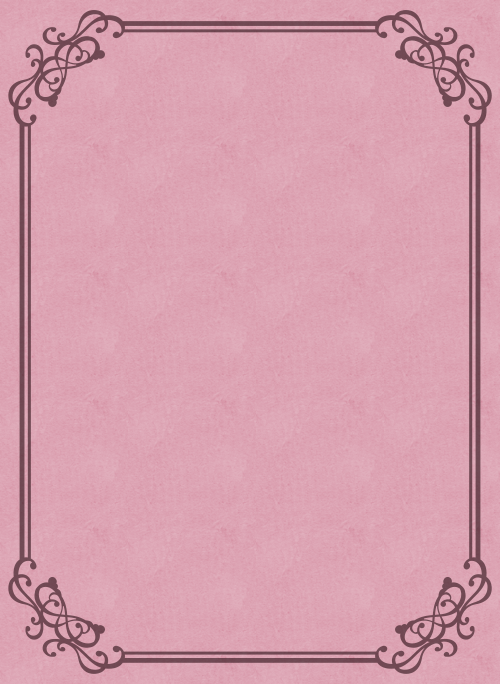ポン、と小気味のいい音を立てて白い煙が体を包み込む。
次の瞬間、私は青いドレス姿になっていた。
「うん。清楚でかわいらしいな。エラにとても似合っている」
アッシュは満足そうに頷いている。
「うーん。さっきのピンクも捨てがたいですね」
イングリードが私を舐めまわすように見ながら言う。
「確かにあれも良かったよなー」
ぽん、と音がして、ドレスが今度はピンクに変わった。
「黄色が案外似合うのでは?」
「あ、確かに」
ぽん。
イングリードの目が輝く。
「ああっ! いいですねえ。明るい野の花って感じで。エラ様は少々お顔が地味ですし、これくらいの方がよさそうです」
「うーん、もう一回青、行ってみるか。あっちはエラの魅力がそのまんま出るからな」
「確かに。もう一度見てみましょうか」
「それにしても……俺ってやっぱセンスの塊だな!」
アッシュは満足そうに呟いた。
もう、こう言うのを何十回となく繰り返されている。
そして私は……。
(どうしよう。違いがさっぱりわからない!!!)
さっきから背中に脂汗が流れている。
全部素敵で全部可愛い。
つまり、どれも同じに見えている。
(付け焼き刃のセンスなんて無理だわ。どうしよう。二人の会話が外国語みたいに聞こえるんですけど! と言うか子守歌?)
くううう。
「エラ様、寝ちゃだめですっ!」
激しい叱責に私は両目をぱちりと開けた。
「ご、ご、ごめんなさい!」
「エラ、君な、やる気あんのか?」
アッシュの眉間には青筋が立っている。
「ありますありますっ! だけど、どれも(同じくらい)素敵に見えて……」
私はしょんぼりと肩を落とす。
「ごめんね。二人とも。なんだか冴えないヒロインで。アッシュと私が交代できたらいいのに……」
イングリードまでが、同意する。
「確かにアッシュ様のファッションショーは見ごたえがありそうですねえ。でもエラ様も十分お可愛いですよ」
「ありがとう……気を使ってくれて……」
そう。
一生懸命な二人のためにも、頑張らなきゃ。
「そういえばアッシュ様はなぜ女装をしているんです? エラ様には素のままで行くべきとおっしゃるのに」
イングリードがアッシュに尋ねている。
「モブキャラとしての矜持だよ。素で行くと王子を食っちゃうからな。俺ってほら、モブの癖にビジュアル良すぎだから」
「でも逆にエラ様を食ってしまうのでは?」
「男は2メートル超えの女には興味を持たない」
「確かに。考えてますねえ。さすがアッシュ様」
二人はまた意味不明な会話で納得しあっている。
私は首をかしげた。
「じょそう……? ここに来る前に除草してきたの? それなのに、全然疲れが顔に出てないわね。お疲れ様」
「君は何を言ってるんだ?」
労いは伝わらなかったらしい。
私は口をつぐんでおくと決めた。
「やっぱり黄色がベストですね」
「だな。決まり」
やっとドレスが決定した。
そして次の瞬間、アクセサリーやヘアスタイルも一気に変わる。
「仕上げだ」
アッシュが杖を一振りすると、透明なハイヒールが現れた。
「ガラスの靴だよ」
これが噂の……。
流石に私でも見惚れてしまう。
キラキラしていて繊細で……とっても綺麗……。
と、アッシュが私を軽々と横抱きにした。
「ちょ、な……」
突然の事に目を白黒させてしまう私を椅子に座らせると、アッシュは足元に跪く。
足首をそっと握られドキっとした。
ガラスの靴が足先に触れる。
そして私の足にフィットした。
「ぴったりだな」
そう言われてふつふつと湧き上がるものがある。
「ありがとう! 二人とも……私、頑張る。立派なシンデレラになって、ハッピーエンドを目指すわ」
私は拳を握りしめ勢いこんで立ち上がる。
しかし慣れないハイヒールにバランスを崩し、よろめいてしまう。
「おっと」
アッシュの胸が私を受け止めた。
彼女の筋肉のついた胸板にドキッとする。そして……。
(ん……何か違和感が……)
私は彼女の胸元にさらに頬を押し付けようとした。
が、すぐに肩を両手で挟まれ遠ざけられる。
そして手を取られ、再び鏡の前に立たされた。
鏡の中にいたのは、黄色いドレスに身を包んだ、どこから見てもプリンセス然とした淑女だった。
「これが私……!」
私は鏡にかぶりつきになった。
「これが君の舞台衣装だ。君の鎧にもなってくれる。絶対に勝てよ。この勝負」
アッシュが言う。
そうか。待ちに待った本番に、今から私は立つんだ。
このドレスとガラスの靴で。
この時を私はずっと待っていた。
みーんみんみん
武者震いとともにセミの鳴き声が、頭の中を駆け巡った。
次の瞬間、私は青いドレス姿になっていた。
「うん。清楚でかわいらしいな。エラにとても似合っている」
アッシュは満足そうに頷いている。
「うーん。さっきのピンクも捨てがたいですね」
イングリードが私を舐めまわすように見ながら言う。
「確かにあれも良かったよなー」
ぽん、と音がして、ドレスが今度はピンクに変わった。
「黄色が案外似合うのでは?」
「あ、確かに」
ぽん。
イングリードの目が輝く。
「ああっ! いいですねえ。明るい野の花って感じで。エラ様は少々お顔が地味ですし、これくらいの方がよさそうです」
「うーん、もう一回青、行ってみるか。あっちはエラの魅力がそのまんま出るからな」
「確かに。もう一度見てみましょうか」
「それにしても……俺ってやっぱセンスの塊だな!」
アッシュは満足そうに呟いた。
もう、こう言うのを何十回となく繰り返されている。
そして私は……。
(どうしよう。違いがさっぱりわからない!!!)
さっきから背中に脂汗が流れている。
全部素敵で全部可愛い。
つまり、どれも同じに見えている。
(付け焼き刃のセンスなんて無理だわ。どうしよう。二人の会話が外国語みたいに聞こえるんですけど! と言うか子守歌?)
くううう。
「エラ様、寝ちゃだめですっ!」
激しい叱責に私は両目をぱちりと開けた。
「ご、ご、ごめんなさい!」
「エラ、君な、やる気あんのか?」
アッシュの眉間には青筋が立っている。
「ありますありますっ! だけど、どれも(同じくらい)素敵に見えて……」
私はしょんぼりと肩を落とす。
「ごめんね。二人とも。なんだか冴えないヒロインで。アッシュと私が交代できたらいいのに……」
イングリードまでが、同意する。
「確かにアッシュ様のファッションショーは見ごたえがありそうですねえ。でもエラ様も十分お可愛いですよ」
「ありがとう……気を使ってくれて……」
そう。
一生懸命な二人のためにも、頑張らなきゃ。
「そういえばアッシュ様はなぜ女装をしているんです? エラ様には素のままで行くべきとおっしゃるのに」
イングリードがアッシュに尋ねている。
「モブキャラとしての矜持だよ。素で行くと王子を食っちゃうからな。俺ってほら、モブの癖にビジュアル良すぎだから」
「でも逆にエラ様を食ってしまうのでは?」
「男は2メートル超えの女には興味を持たない」
「確かに。考えてますねえ。さすがアッシュ様」
二人はまた意味不明な会話で納得しあっている。
私は首をかしげた。
「じょそう……? ここに来る前に除草してきたの? それなのに、全然疲れが顔に出てないわね。お疲れ様」
「君は何を言ってるんだ?」
労いは伝わらなかったらしい。
私は口をつぐんでおくと決めた。
「やっぱり黄色がベストですね」
「だな。決まり」
やっとドレスが決定した。
そして次の瞬間、アクセサリーやヘアスタイルも一気に変わる。
「仕上げだ」
アッシュが杖を一振りすると、透明なハイヒールが現れた。
「ガラスの靴だよ」
これが噂の……。
流石に私でも見惚れてしまう。
キラキラしていて繊細で……とっても綺麗……。
と、アッシュが私を軽々と横抱きにした。
「ちょ、な……」
突然の事に目を白黒させてしまう私を椅子に座らせると、アッシュは足元に跪く。
足首をそっと握られドキっとした。
ガラスの靴が足先に触れる。
そして私の足にフィットした。
「ぴったりだな」
そう言われてふつふつと湧き上がるものがある。
「ありがとう! 二人とも……私、頑張る。立派なシンデレラになって、ハッピーエンドを目指すわ」
私は拳を握りしめ勢いこんで立ち上がる。
しかし慣れないハイヒールにバランスを崩し、よろめいてしまう。
「おっと」
アッシュの胸が私を受け止めた。
彼女の筋肉のついた胸板にドキッとする。そして……。
(ん……何か違和感が……)
私は彼女の胸元にさらに頬を押し付けようとした。
が、すぐに肩を両手で挟まれ遠ざけられる。
そして手を取られ、再び鏡の前に立たされた。
鏡の中にいたのは、黄色いドレスに身を包んだ、どこから見てもプリンセス然とした淑女だった。
「これが私……!」
私は鏡にかぶりつきになった。
「これが君の舞台衣装だ。君の鎧にもなってくれる。絶対に勝てよ。この勝負」
アッシュが言う。
そうか。待ちに待った本番に、今から私は立つんだ。
このドレスとガラスの靴で。
この時を私はずっと待っていた。
みーんみんみん
武者震いとともにセミの鳴き声が、頭の中を駆け巡った。