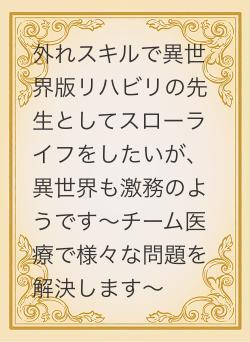「いたたた……痛くない!?」
フェンリルのドロップ品とともに、地面に落ちたはずが痛みを全く感じなかった。痛みを感じるのは、弓が突き刺さってできた怪我と骨折した足だけだ。
「んっ……もふもふするぞ?」
地面に触れるとなぜか床がもふもふとしている。
「これってフェンリルの毛皮?」
僕はフェンリルの毛皮の上に落ちたことで、さらに大きな怪我をせずに済んだようだ。ここでもフェンリルに助けられた。
それにしても最後に"昇天"すると言っていたが、本当に死ぬとは思いもしなかった。
背中を掻くぐらい健康なフェンリルだったらできるはず。だが、あのフェンリルは僕に頼んだ。
きっとあのフェンリルは、背中を掻けないぐらい元々弱っていたのだろう。
僕は体を起こして、フェンリルのドロップ品を確認していく。
目の前にあるのはたくさんのお金と光り輝く液体が入った瓶。
「これってまさかエリクサー!?」
エリクサーとは万能薬とも言われているポーションだ。その特徴は呼ばれている名前の通りで、なんでも怪我や病気を治す効能がある。
ダンジョンの中でしかドロップしないと言われている伝説のポーション。
そのポーションが目の前にあるのだ。
「これでアリアの病気が治るぞ!」
咄嗟に出たのはこれで妹の病気が治る。ただそれだけだ。
だが、現実はそうもいかない。
矢で貫通した足と骨折した足が絡み合う。そんな足でダンジョンから出られるわけない。
そもそも足が治っていても、ダンジョンから一人で脱出できる気がしない。
ただでさえAランク冒険者パーティーが囮を用意して逃げるほどだ。
僕はここで死ぬ運命なんだろう。
再び諦めて寝転んだ瞬間、一際輝きが違うお金を見つける。
金でも銀でもなく、白く輝くコイン。久しぶりに見たやつに僕の興奮が止まらない。
「ガチャコイいいいいたたたたたた!」
勢いよく立ち上がって、そのまま崩れるようにお金の中にダイブする。
僕はガチャコインを手にすると、フェンリルに感謝した。
このガチャ結果で妹の元まで、エリクサーを運ぶことができると思ったからだ。
しかも、明らかに前回見た時よりもガチャコインは大きく、光り輝いている。
きっと強い魔物――。
フェンリルが出てくるに違いない。
そう思った僕はさっそくガチャコインを使用する。
「いでよ、ガチャテイム!」
声に反応してガチャコインが輝き出す。あまりの眩しさに目を閉じる。
前回はこの光にやられて、しばらく目が開けられなかったことを思い出す。
目の前に突如現れた、角張った大きな箱にくるりと回す謎の取手。久しぶりに見るガチャに、足の痛みも忘れてしまう。
「頼む! フェンリル出てこい!」
僕は取っ手を勢いよく回す。隣にある穴から吐き出される玉が魔物を呼び出す魔物玉だ。
コロコロと出てくる白い魔物玉。
いや、白くてもふもふとした塊が出てきたぞ。
『キュー!』
そのまま僕の顔に飛びつく。ゆっくり手を触れると柔らかい毛に覆われているようだ。
この触り心地はまさか――。
「フェンリルか!」
『キュー!』
小さいフェンリルは僕の顔をバタバタと蹴っている。それと同時に風を切る音が聞こえてくる。
僕は顔にしがみつくフェンリルを外すと、そこにはさっきまで見ていたフェンリルとは違うもふもふがいた。
大きな瞳に小さな口。頭には耳のようなものが動いている。
あれ……?
フェンリルって足が六本もあったのか?
あれれ……?
フェンリルって羽が付いていたのか?
明らかにフェンリルと異なる存在に僕は戸惑ってしまう。
――――――――――――――――――――
[ステータス]
【名前】 なし
【種族】 カイコ
【制限】 無制限
【筋力】 23
【耐久】 15
【敏捷】 83
【魔力】 98
【幸運】 95
【スキル】 状態異常付与
――――――――――――――――――――
「お前フェンリルじゃ――」
僕は目の前にいる存在に目を合わせる。大きな瞳がキラキラと輝いている。
ああ、やっぱりこいつはフェンリルだったのか!
――――――――――――――――――――
[ステータス]
【名前】 なし
【種族】 フェンリル亜種(カイコ)
【制限】 無制限
【筋力】 23
【耐久】 15
【敏捷】 83
【魔力】 98
【幸運】 95
【スキル】 状態異常付与
――――――――――――――――――――
さっきのは僕の見間違いなんだろう。こんなにもふもふした存在が、フェンリル以外のはずがない。
ただ、小さなフェンリルだから、多少見た目が違うのだろう。
きっとフェンリルならすぐにダンジョン内を駆け巡るはず。
実際にステータスも高い。ほとんど一桁ばかりの僕とは違い、フェンリルの数値は二桁だ。
僕はエリクサーをポケットに入れると、すぐにフェンリルに掴まる。
「さぁ、フェンリルよ! 僕を家まで送ってくれ!」
これで妹にエリクサーを飲ませることができる。胸の高鳴りを感じながら、フェンリルが走り出すのを待つ。
『キュ?』
だが、フェンリルは全く進まない。むしろ体をピクピクとさせてその場で困り果てている。
「頑張って僕を運ぶんだ!」
『キュ! キュー!』
フェンリルは僕の言ったことを理解したのだろう。ただ、あまりにも僕が重いのか全く進まない。むしろ手足をバタバタとしているだけだ。
僕が手を離すとそのままフェンリルは羽を羽ばたかせて走っていく。どうやら羽はあるものの飛べないようだ。
結局僕はエリクサーを持っていくのは諦めることにした。
目の前にあるお金をどうにか持って帰れば、魔力ポーションを買うことできる。それで妹の寿命が今よりも長くなれば解決策は出てくるだろう。
また、ダンジョンに潜ってエリクサーを探せばいい。
僕にはフェンリルという新しい相棒がいる。
見た目がさっきまでいたフェンリルと違うのは、フェンリルの亜種だからなんだろう。
覚悟ができた僕はエリクサーの蓋を開けて口元に近づける。瓶を逆さまにして、ゆっくりと体の中にエリクサーを流し込んでいく。
「うっ……」
身体中の血が素早く流れているような感覚だ。次第に足の痛みもなくなり、力が湧いてくるような気がした。
それと同時に頭がスッキリする。
「じゃあ、帰ろう……あれあいつフェンリルだったか?」
さっきまでフェンリルだと思い込んでいた魔物が、突然フェンリルではない、なにかかもしれないと思ってしまう。
『キュ? キュキュ!』
それを感じ取ったのかフェンリルは再び僕の顔に飛びついてくる。疑ったことが嫌だったのか、顔の上に乗って、もふもふさをアピールしている。
「君を疑って悪かったよ」
僕の言葉を理解しているのだろう。フェンリルは地面に飛び降りる。
ボス部屋の縁にあるカバンから、中身を取り出して、お金を全て入れていく。鉱石も持っていこうか迷うが、掘るものがないため諦めるしかなかった。
それでもこの大金があれば、数年は生活に困ることはないだろう。
「今から帰るから魔物が出たら助けてくれよ!」
『キュ!』
フェンリルの毛皮を肩からかけると、フェンリルは僕の頭の上によじ登る。どうやら高いとこが好きなようだ。
僕達は高難易度ダンジョンから抜け出すために、ダンジョン部屋を後にした。
フェンリルのドロップ品とともに、地面に落ちたはずが痛みを全く感じなかった。痛みを感じるのは、弓が突き刺さってできた怪我と骨折した足だけだ。
「んっ……もふもふするぞ?」
地面に触れるとなぜか床がもふもふとしている。
「これってフェンリルの毛皮?」
僕はフェンリルの毛皮の上に落ちたことで、さらに大きな怪我をせずに済んだようだ。ここでもフェンリルに助けられた。
それにしても最後に"昇天"すると言っていたが、本当に死ぬとは思いもしなかった。
背中を掻くぐらい健康なフェンリルだったらできるはず。だが、あのフェンリルは僕に頼んだ。
きっとあのフェンリルは、背中を掻けないぐらい元々弱っていたのだろう。
僕は体を起こして、フェンリルのドロップ品を確認していく。
目の前にあるのはたくさんのお金と光り輝く液体が入った瓶。
「これってまさかエリクサー!?」
エリクサーとは万能薬とも言われているポーションだ。その特徴は呼ばれている名前の通りで、なんでも怪我や病気を治す効能がある。
ダンジョンの中でしかドロップしないと言われている伝説のポーション。
そのポーションが目の前にあるのだ。
「これでアリアの病気が治るぞ!」
咄嗟に出たのはこれで妹の病気が治る。ただそれだけだ。
だが、現実はそうもいかない。
矢で貫通した足と骨折した足が絡み合う。そんな足でダンジョンから出られるわけない。
そもそも足が治っていても、ダンジョンから一人で脱出できる気がしない。
ただでさえAランク冒険者パーティーが囮を用意して逃げるほどだ。
僕はここで死ぬ運命なんだろう。
再び諦めて寝転んだ瞬間、一際輝きが違うお金を見つける。
金でも銀でもなく、白く輝くコイン。久しぶりに見たやつに僕の興奮が止まらない。
「ガチャコイいいいいたたたたたた!」
勢いよく立ち上がって、そのまま崩れるようにお金の中にダイブする。
僕はガチャコインを手にすると、フェンリルに感謝した。
このガチャ結果で妹の元まで、エリクサーを運ぶことができると思ったからだ。
しかも、明らかに前回見た時よりもガチャコインは大きく、光り輝いている。
きっと強い魔物――。
フェンリルが出てくるに違いない。
そう思った僕はさっそくガチャコインを使用する。
「いでよ、ガチャテイム!」
声に反応してガチャコインが輝き出す。あまりの眩しさに目を閉じる。
前回はこの光にやられて、しばらく目が開けられなかったことを思い出す。
目の前に突如現れた、角張った大きな箱にくるりと回す謎の取手。久しぶりに見るガチャに、足の痛みも忘れてしまう。
「頼む! フェンリル出てこい!」
僕は取っ手を勢いよく回す。隣にある穴から吐き出される玉が魔物を呼び出す魔物玉だ。
コロコロと出てくる白い魔物玉。
いや、白くてもふもふとした塊が出てきたぞ。
『キュー!』
そのまま僕の顔に飛びつく。ゆっくり手を触れると柔らかい毛に覆われているようだ。
この触り心地はまさか――。
「フェンリルか!」
『キュー!』
小さいフェンリルは僕の顔をバタバタと蹴っている。それと同時に風を切る音が聞こえてくる。
僕は顔にしがみつくフェンリルを外すと、そこにはさっきまで見ていたフェンリルとは違うもふもふがいた。
大きな瞳に小さな口。頭には耳のようなものが動いている。
あれ……?
フェンリルって足が六本もあったのか?
あれれ……?
フェンリルって羽が付いていたのか?
明らかにフェンリルと異なる存在に僕は戸惑ってしまう。
――――――――――――――――――――
[ステータス]
【名前】 なし
【種族】 カイコ
【制限】 無制限
【筋力】 23
【耐久】 15
【敏捷】 83
【魔力】 98
【幸運】 95
【スキル】 状態異常付与
――――――――――――――――――――
「お前フェンリルじゃ――」
僕は目の前にいる存在に目を合わせる。大きな瞳がキラキラと輝いている。
ああ、やっぱりこいつはフェンリルだったのか!
――――――――――――――――――――
[ステータス]
【名前】 なし
【種族】 フェンリル亜種(カイコ)
【制限】 無制限
【筋力】 23
【耐久】 15
【敏捷】 83
【魔力】 98
【幸運】 95
【スキル】 状態異常付与
――――――――――――――――――――
さっきのは僕の見間違いなんだろう。こんなにもふもふした存在が、フェンリル以外のはずがない。
ただ、小さなフェンリルだから、多少見た目が違うのだろう。
きっとフェンリルならすぐにダンジョン内を駆け巡るはず。
実際にステータスも高い。ほとんど一桁ばかりの僕とは違い、フェンリルの数値は二桁だ。
僕はエリクサーをポケットに入れると、すぐにフェンリルに掴まる。
「さぁ、フェンリルよ! 僕を家まで送ってくれ!」
これで妹にエリクサーを飲ませることができる。胸の高鳴りを感じながら、フェンリルが走り出すのを待つ。
『キュ?』
だが、フェンリルは全く進まない。むしろ体をピクピクとさせてその場で困り果てている。
「頑張って僕を運ぶんだ!」
『キュ! キュー!』
フェンリルは僕の言ったことを理解したのだろう。ただ、あまりにも僕が重いのか全く進まない。むしろ手足をバタバタとしているだけだ。
僕が手を離すとそのままフェンリルは羽を羽ばたかせて走っていく。どうやら羽はあるものの飛べないようだ。
結局僕はエリクサーを持っていくのは諦めることにした。
目の前にあるお金をどうにか持って帰れば、魔力ポーションを買うことできる。それで妹の寿命が今よりも長くなれば解決策は出てくるだろう。
また、ダンジョンに潜ってエリクサーを探せばいい。
僕にはフェンリルという新しい相棒がいる。
見た目がさっきまでいたフェンリルと違うのは、フェンリルの亜種だからなんだろう。
覚悟ができた僕はエリクサーの蓋を開けて口元に近づける。瓶を逆さまにして、ゆっくりと体の中にエリクサーを流し込んでいく。
「うっ……」
身体中の血が素早く流れているような感覚だ。次第に足の痛みもなくなり、力が湧いてくるような気がした。
それと同時に頭がスッキリする。
「じゃあ、帰ろう……あれあいつフェンリルだったか?」
さっきまでフェンリルだと思い込んでいた魔物が、突然フェンリルではない、なにかかもしれないと思ってしまう。
『キュ? キュキュ!』
それを感じ取ったのかフェンリルは再び僕の顔に飛びついてくる。疑ったことが嫌だったのか、顔の上に乗って、もふもふさをアピールしている。
「君を疑って悪かったよ」
僕の言葉を理解しているのだろう。フェンリルは地面に飛び降りる。
ボス部屋の縁にあるカバンから、中身を取り出して、お金を全て入れていく。鉱石も持っていこうか迷うが、掘るものがないため諦めるしかなかった。
それでもこの大金があれば、数年は生活に困ることはないだろう。
「今から帰るから魔物が出たら助けてくれよ!」
『キュ!』
フェンリルの毛皮を肩からかけると、フェンリルは僕の頭の上によじ登る。どうやら高いとこが好きなようだ。
僕達は高難易度ダンジョンから抜け出すために、ダンジョン部屋を後にした。