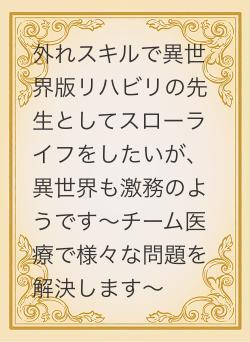あの後プリシラとも話したが、エヴァンは性格と素行の悪さが原因で親から無理やり冒険者をやらされていると言っていた。
プリシラはそんなエヴァンの見張りとプリシラ自身が目標にしている勇者がいるらしい。女性で大賢者と呼ばれており、貴族出身の女性達の憧れの的とも言われている人らしい。
プリシラはその人の教育ノウハウを母親から教え込まれたとか……。
俺は目を覚まし起きるとみんな朝に強いのかすでに起きて準備をしていた。
「よっ、よく寝れたか」
「……お前頭大丈夫か?」
突然エヴァンが声をかけてきた。本当に何かあったのか心配になってくるレベルだ。
「くそ、お前に言われたくないわ」
そう言ってエヴァンはテントを片付けていた。その後ろ姿はどこか楽しそうだった。
「お兄ちゃん達仲直りしたんだね?」
「そうなのか?」
「にいちゃ、たまに抜けてるもんね」
「おおお、そうか」
どうやら俺は2人から見てもどこか抜けているらしい。
その後俺達は野営に使った道具を片付けると隣町のハクダイに向かった。
今日は昨日と違いエヴァンが護衛に参加していた。まぁ、依頼を受けているのに今まで参加してなかったほうがおかしかったんだけどな。
ハクダイまでの道のりは残り半分程度になり今日の夕方ごろには町に着く予定になっている。
「そういえばゴードンさんはなんで商会をやってるんの?」
ロンは馬車の運転をしているゴードンに話しかけていた。
「ああ、私は元々普通に街で商会を開いて働いていたんだよ」
「じゃあなんで今は馬車に乗って色々なところに行ってるの?」
「それは神様にお供えするものを探してるんだよ」
一瞬宗教的な雰囲気を滲み出していたがどうやら違うらしい。詳しく聞いていくと商会の経営が落ち、資金が底を尽きそうになった時に突然朝起きたらお金が落ちてきたらしい。
誰かの落とし物かと思ったけど、定期的に起こるこの現象をゴードンさんは"神様の落とし物"と言っているらしい。
だからその落とし物に見合う物を探して、感謝の気持ちをお返ししたいとゴードンは言っていた。
実際に聖教教会では神様が存在しており、お供え物をした分だけ神様から知恵や神託がもらえると言われているぐらいだから商売の神様でもいるのかもしれない。
そんな話を魔物を狩りながら移動していた。一方エヴァンは昨日よりはしっかりと働いているが動き自体はあまり良いとはいえなかった。
単純な戦力であればポーターであるロンの方が強いのかもしれない。彼の努力次第では今後も変わるがきっと装備があまり良くないのとスキル玉を持っていないからだろう。
俺達は身近な人に助けられたから今の自分達がいるのだろうと思った。
「さぁ、あそこがハクダイだ」
気づいたら俺達は目的の町に着いたようだ。
「報告に行ってきますね」
基本的に町までの護衛依頼は到着した町に冒険者ギルドがあれば報告をする決まりになっている。エヴァンとプリシラがゴードンさんと一緒に宿屋に向かい、俺達は冒険者ギルドに向かった。
俺はいつも通りに冒険者ギルドの扉を開けた。ただ、俺は王都の冒険者ギルドにいて忘れていた。
他の冒険者ギルドではポーターや獣人に対して差別があったことを……。
「おいおい、ポーターと獣人が何しに来たんだ?」
俺は装備を整えたら変わるだろうがロンとニアに関してはどうしようもない。ただ、2人も慣れてきたのかあまり気にしなくなっていた。
俺達はそのまま受け付けに行くとこの職員はまだ差別とかもなく普通の方だった。
ただ、冒険者がタチが悪かったのだ。 俺は無視をしているわけでもなく受け付けと話をしていたが、近づいてきていると気づいた時には隣にいた。
「おい、お前らが無視とはどういう──」
俺に殴りかかろうとした瞬間に男は誰かに邪魔されていた。
「俺のパーティーメンバーに用があるんか?」
なんと男の手を止めたのはエヴァンだった。無駄に放つキラキラ感と助けたタイミングが良かったのが、俺と話していた受け付けの女性は目がうっとりとしていた。
「お前いつもこんな感じなのか?」
「お前本当にエヴァンなのか?」
「どこからどう見ても俺だろ」
どうやら本当にエヴァンだった。急に優しくなるとは俺もびっくりだ。その様子を子供達とプリシラは笑っていた。
「いやいや、やっぱどこかで頭でも打っただろ」
「おい、俺様が優しくしてやったと──」
「おい、お前ら俺を無視──」
「うるせぇな」
俺とエヴァンはうるさいやつがいた方に手を出すと冒険者は倒れていた。
プリシラはそんなエヴァンの見張りとプリシラ自身が目標にしている勇者がいるらしい。女性で大賢者と呼ばれており、貴族出身の女性達の憧れの的とも言われている人らしい。
プリシラはその人の教育ノウハウを母親から教え込まれたとか……。
俺は目を覚まし起きるとみんな朝に強いのかすでに起きて準備をしていた。
「よっ、よく寝れたか」
「……お前頭大丈夫か?」
突然エヴァンが声をかけてきた。本当に何かあったのか心配になってくるレベルだ。
「くそ、お前に言われたくないわ」
そう言ってエヴァンはテントを片付けていた。その後ろ姿はどこか楽しそうだった。
「お兄ちゃん達仲直りしたんだね?」
「そうなのか?」
「にいちゃ、たまに抜けてるもんね」
「おおお、そうか」
どうやら俺は2人から見てもどこか抜けているらしい。
その後俺達は野営に使った道具を片付けると隣町のハクダイに向かった。
今日は昨日と違いエヴァンが護衛に参加していた。まぁ、依頼を受けているのに今まで参加してなかったほうがおかしかったんだけどな。
ハクダイまでの道のりは残り半分程度になり今日の夕方ごろには町に着く予定になっている。
「そういえばゴードンさんはなんで商会をやってるんの?」
ロンは馬車の運転をしているゴードンに話しかけていた。
「ああ、私は元々普通に街で商会を開いて働いていたんだよ」
「じゃあなんで今は馬車に乗って色々なところに行ってるの?」
「それは神様にお供えするものを探してるんだよ」
一瞬宗教的な雰囲気を滲み出していたがどうやら違うらしい。詳しく聞いていくと商会の経営が落ち、資金が底を尽きそうになった時に突然朝起きたらお金が落ちてきたらしい。
誰かの落とし物かと思ったけど、定期的に起こるこの現象をゴードンさんは"神様の落とし物"と言っているらしい。
だからその落とし物に見合う物を探して、感謝の気持ちをお返ししたいとゴードンは言っていた。
実際に聖教教会では神様が存在しており、お供え物をした分だけ神様から知恵や神託がもらえると言われているぐらいだから商売の神様でもいるのかもしれない。
そんな話を魔物を狩りながら移動していた。一方エヴァンは昨日よりはしっかりと働いているが動き自体はあまり良いとはいえなかった。
単純な戦力であればポーターであるロンの方が強いのかもしれない。彼の努力次第では今後も変わるがきっと装備があまり良くないのとスキル玉を持っていないからだろう。
俺達は身近な人に助けられたから今の自分達がいるのだろうと思った。
「さぁ、あそこがハクダイだ」
気づいたら俺達は目的の町に着いたようだ。
「報告に行ってきますね」
基本的に町までの護衛依頼は到着した町に冒険者ギルドがあれば報告をする決まりになっている。エヴァンとプリシラがゴードンさんと一緒に宿屋に向かい、俺達は冒険者ギルドに向かった。
俺はいつも通りに冒険者ギルドの扉を開けた。ただ、俺は王都の冒険者ギルドにいて忘れていた。
他の冒険者ギルドではポーターや獣人に対して差別があったことを……。
「おいおい、ポーターと獣人が何しに来たんだ?」
俺は装備を整えたら変わるだろうがロンとニアに関してはどうしようもない。ただ、2人も慣れてきたのかあまり気にしなくなっていた。
俺達はそのまま受け付けに行くとこの職員はまだ差別とかもなく普通の方だった。
ただ、冒険者がタチが悪かったのだ。 俺は無視をしているわけでもなく受け付けと話をしていたが、近づいてきていると気づいた時には隣にいた。
「おい、お前らが無視とはどういう──」
俺に殴りかかろうとした瞬間に男は誰かに邪魔されていた。
「俺のパーティーメンバーに用があるんか?」
なんと男の手を止めたのはエヴァンだった。無駄に放つキラキラ感と助けたタイミングが良かったのが、俺と話していた受け付けの女性は目がうっとりとしていた。
「お前いつもこんな感じなのか?」
「お前本当にエヴァンなのか?」
「どこからどう見ても俺だろ」
どうやら本当にエヴァンだった。急に優しくなるとは俺もびっくりだ。その様子を子供達とプリシラは笑っていた。
「いやいや、やっぱどこかで頭でも打っただろ」
「おい、俺様が優しくしてやったと──」
「おい、お前ら俺を無視──」
「うるせぇな」
俺とエヴァンはうるさいやつがいた方に手を出すと冒険者は倒れていた。