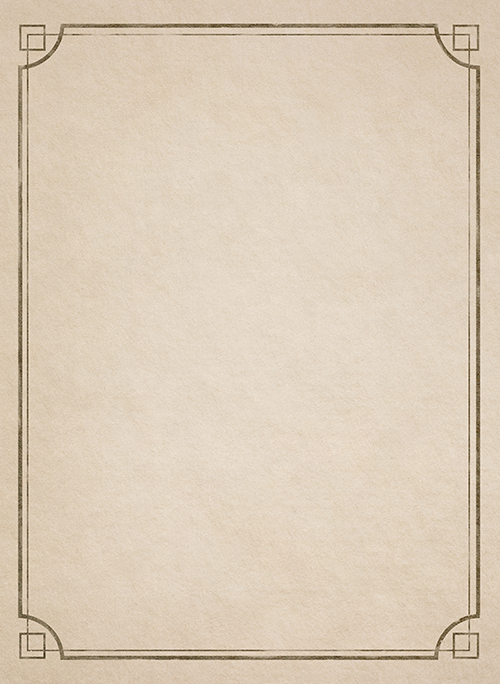あった。
傾斜だけではない。カーブした道を通り抜けた後には、急な階段も待ち構えていた。だが僕はほんの僅かにでも怯んだりはしなかった。ここには何度も訪れているから、今更しんどいとは思わないのだ。
階段や坂を登り続けていると、必然的に汗をかいてくる。ブレザーを脱いだとはいえ、背負ったリュックサックは上着を詰め込んだ分大きくなる。より背中と密着して隙間を無くせば、分泌される汗の量は必然的に多くなる。想像よりもずっと大きい汗の不快感が背中を包み込んでいく。もし誰かとすれ違えば、僕が顔をしかめているのを目撃されるだろう。顔をしかめている場面を見られるのは嫌だが、あまり心配もいらないだろう。何せ公園内には今のところ、人がいない。いつも訪れた際には犬の散歩をしている老人がいるが、今日は彼の姿でさえない。多分、本当に誰もいない日というのがあるのかもしれない。
考えてみれば、卒業式がある日なのだ。あの老人も、自分の孫の卒業式に出席しているのかもしれない。くの字に腰を曲げ、一歩踏み出すのも辛そうにしていた彼だが、大切に思う誰かがいたとしても不思議はない。もし実際に、孫の卒業式に行っているとするなら、あの老人はどんな表情を顔に浮かべるだろうか。無事に卒業してくれたという喜びが元になって、笑顔が現れるのか。それとも感動のあまり拭っても、拭っても止まらない涙を流すのか。
服装はどうしていくのだろう。いつも着ているような古びた作業着ではないはずだが、かといって手入れの行き届いたスーツを着ている姿も想像できない。くたびれた老人が卒業式へ着ていく服とは、一体どんなものなのだろうか。
今日に限って姿を見せない老人の行方をあれこれ思考していると、植物の葉が右の肩を撫でていった。細長い葉をしていて、そこらじゅうに生えている。思考に気を取られていたが、ここは植物に囲まれた公園なのだ。あまり除草作業も行われないので、この辺りの植物は邪魔されずに自らの生息域を拡大している。あと二週間もあれば遊歩道を埋め尽くせそうなほど、緑で溢れかえっているのだ。
初めてここへ来た時、僕はジャングルにでも入り込んだのかと一瞬疑いを持った。幾度となく通う事で忘れかけていたが、そういう場所だ。
僕は足元を見た。案の定、制服のズボンには大量に植物の花粉のようなものが付着していた。いつもは気にかけている事を、この日に限って完全に忘却していた。慌ててズボンを叩いて付いたものを取り除こうと試みるのだが、花粉のようなものはある程度しか落とせなかった。叩いてしまったがために、よりズボンに定着するものが大半だった。まるで潰された蚊が、体液と共に肌の上から動かなくなるみたいに。
いくら叩こうが無駄だ、と判断するのに時間は掛からなかった。僕はズボンと、ズボンをきっかけにして見つけた右肩の花粉を残したまま再び歩き出した。
傾斜だけではない。カーブした道を通り抜けた後には、急な階段も待ち構えていた。だが僕はほんの僅かにでも怯んだりはしなかった。ここには何度も訪れているから、今更しんどいとは思わないのだ。
階段や坂を登り続けていると、必然的に汗をかいてくる。ブレザーを脱いだとはいえ、背負ったリュックサックは上着を詰め込んだ分大きくなる。より背中と密着して隙間を無くせば、分泌される汗の量は必然的に多くなる。想像よりもずっと大きい汗の不快感が背中を包み込んでいく。もし誰かとすれ違えば、僕が顔をしかめているのを目撃されるだろう。顔をしかめている場面を見られるのは嫌だが、あまり心配もいらないだろう。何せ公園内には今のところ、人がいない。いつも訪れた際には犬の散歩をしている老人がいるが、今日は彼の姿でさえない。多分、本当に誰もいない日というのがあるのかもしれない。
考えてみれば、卒業式がある日なのだ。あの老人も、自分の孫の卒業式に出席しているのかもしれない。くの字に腰を曲げ、一歩踏み出すのも辛そうにしていた彼だが、大切に思う誰かがいたとしても不思議はない。もし実際に、孫の卒業式に行っているとするなら、あの老人はどんな表情を顔に浮かべるだろうか。無事に卒業してくれたという喜びが元になって、笑顔が現れるのか。それとも感動のあまり拭っても、拭っても止まらない涙を流すのか。
服装はどうしていくのだろう。いつも着ているような古びた作業着ではないはずだが、かといって手入れの行き届いたスーツを着ている姿も想像できない。くたびれた老人が卒業式へ着ていく服とは、一体どんなものなのだろうか。
今日に限って姿を見せない老人の行方をあれこれ思考していると、植物の葉が右の肩を撫でていった。細長い葉をしていて、そこらじゅうに生えている。思考に気を取られていたが、ここは植物に囲まれた公園なのだ。あまり除草作業も行われないので、この辺りの植物は邪魔されずに自らの生息域を拡大している。あと二週間もあれば遊歩道を埋め尽くせそうなほど、緑で溢れかえっているのだ。
初めてここへ来た時、僕はジャングルにでも入り込んだのかと一瞬疑いを持った。幾度となく通う事で忘れかけていたが、そういう場所だ。
僕は足元を見た。案の定、制服のズボンには大量に植物の花粉のようなものが付着していた。いつもは気にかけている事を、この日に限って完全に忘却していた。慌ててズボンを叩いて付いたものを取り除こうと試みるのだが、花粉のようなものはある程度しか落とせなかった。叩いてしまったがために、よりズボンに定着するものが大半だった。まるで潰された蚊が、体液と共に肌の上から動かなくなるみたいに。
いくら叩こうが無駄だ、と判断するのに時間は掛からなかった。僕はズボンと、ズボンをきっかけにして見つけた右肩の花粉を残したまま再び歩き出した。
僕がどうしてこの公園を目指したのか。理由となるのは、山の頂上にある小さな展望台にある。
展望台からは、付近の畑はもちろん、数キロ離れた所にある住宅街が一望できる。この辺りは畑しかなく、背の高い建物は一つとしてないため、遠くの景色がよく見えるのだ。
住宅街の反対には、青い海だって望める。どこまでも広がる海は、色や形、大きさが様々な建築物と並べてみると驚くほど対照的で、二つの相反する姿は何度眺めても驚嘆する。
小さな山の頂へと続く階段を登ると、屋根と二つのベンチのある展望台が姿を見せた。床は六角形をしていて、屋根はドーム状になっている。それほど広くはない。隙間なく人間を詰め込んで、一〇人が入ればいい方だろう。
手すりに体をもたせかけ、海を見て、次に街を眺める。手前の方は畑があり、奥の方では左右で海と街とに分断されているこの景色は、上手く撮ればネット上で高い評価を得られるかもしれない。一眼レフのような、お金のかかるカメラは必要ない。スマホで撮影して多少加工をすれば十分な仕上がりになる可能性を秘めている。しかし僕は、展望台からの景色を撮影はしなかった。
それどころか、一回たりとも写真に収めてはいない。僕自身、撮影の技術がないというも理由だが、自分の住んでいる地域全てを見渡せる絶好のスポットは誰にも知らせたくないからという気持ちの方が大きい。
この展望台、いやこの公園の存在は誰にも知らせたくない。
海や、畑や、家や、空といった全てを一度に展望するのは自分だけでいい。ある意味では自分だけの特権のようにさえ思っているのだ。自分だけが手にしているものは、秘密として扱って誰にも触れさせない。わざわざ秘密を他人の目に留まるように行動するのは、頼まれたってごめんだ。世の中の大半の人が思っているに違いないはずだ。
それにまた景色を眺めたいと思えば、何度でも訪れればいい。写真より実物の方が、迫力があるに決まっている。だから僕は、あえて景色を撮影はしていない。
小さいとはいえ山の上ではあるので、風は強く吹いている。ワックスもジェルもつけていない、整える気のない髪が、自由気ままに動いて時折視界を塞ごうとする。僕は毛先が目を刺さない程度に最低限手で髪を払った。あとのものは好きに暴れさせた。下へ降りて、ちょっと手を加えればいつもの個性がない頭に戻る事を知っているのだ。
山の上からの風景を、僕は仔細に眺めた。僅かな変化も見逃すまいと、狭い道やアパートのベランダなどにも視線を配った。ここに住んでいる人たちの姿を目の当たりにするのは、ささやかな楽しみになっている。別に、誰かの家を覗き見しようなどとは思っていない。洗濯物を干したり、車を運転したり、軒先で近所の人間同士が会話を弾ませるといったような、生きた人間の生活模様を感じ取るだけで十分だ。どこの誰が、どのように行動しているのかなど、具体的に知る必要もないし、知りたくもない。雰囲気を楽しむ、と表
展望台からは、付近の畑はもちろん、数キロ離れた所にある住宅街が一望できる。この辺りは畑しかなく、背の高い建物は一つとしてないため、遠くの景色がよく見えるのだ。
住宅街の反対には、青い海だって望める。どこまでも広がる海は、色や形、大きさが様々な建築物と並べてみると驚くほど対照的で、二つの相反する姿は何度眺めても驚嘆する。
小さな山の頂へと続く階段を登ると、屋根と二つのベンチのある展望台が姿を見せた。床は六角形をしていて、屋根はドーム状になっている。それほど広くはない。隙間なく人間を詰め込んで、一〇人が入ればいい方だろう。
手すりに体をもたせかけ、海を見て、次に街を眺める。手前の方は畑があり、奥の方では左右で海と街とに分断されているこの景色は、上手く撮ればネット上で高い評価を得られるかもしれない。一眼レフのような、お金のかかるカメラは必要ない。スマホで撮影して多少加工をすれば十分な仕上がりになる可能性を秘めている。しかし僕は、展望台からの景色を撮影はしなかった。
それどころか、一回たりとも写真に収めてはいない。僕自身、撮影の技術がないというも理由だが、自分の住んでいる地域全てを見渡せる絶好のスポットは誰にも知らせたくないからという気持ちの方が大きい。
この展望台、いやこの公園の存在は誰にも知らせたくない。
海や、畑や、家や、空といった全てを一度に展望するのは自分だけでいい。ある意味では自分だけの特権のようにさえ思っているのだ。自分だけが手にしているものは、秘密として扱って誰にも触れさせない。わざわざ秘密を他人の目に留まるように行動するのは、頼まれたってごめんだ。世の中の大半の人が思っているに違いないはずだ。
それにまた景色を眺めたいと思えば、何度でも訪れればいい。写真より実物の方が、迫力があるに決まっている。だから僕は、あえて景色を撮影はしていない。
小さいとはいえ山の上ではあるので、風は強く吹いている。ワックスもジェルもつけていない、整える気のない髪が、自由気ままに動いて時折視界を塞ごうとする。僕は毛先が目を刺さない程度に最低限手で髪を払った。あとのものは好きに暴れさせた。下へ降りて、ちょっと手を加えればいつもの個性がない頭に戻る事を知っているのだ。
山の上からの風景を、僕は仔細に眺めた。僅かな変化も見逃すまいと、狭い道やアパートのベランダなどにも視線を配った。ここに住んでいる人たちの姿を目の当たりにするのは、ささやかな楽しみになっている。別に、誰かの家を覗き見しようなどとは思っていない。洗濯物を干したり、車を運転したり、軒先で近所の人間同士が会話を弾ませるといったような、生きた人間の生活模様を感じ取るだけで十分だ。どこの誰が、どのように行動しているのかなど、具体的に知る必要もないし、知りたくもない。雰囲気を楽しむ、と表
現するのが最適だろう。
僕がついさっき通ってきたあの車道に、一台のバイクが姿を見せた。それも僕の時と同じ方角だった。
運転手の顔は、フルフェイスタイプのヘルメットを被っているので見えない。男性か女性か、年齢がどのくらいなのかも判別がつかなかった。彼、或いは彼女の乗っているマシンは、バイクに詳しくない僕にも高価な事がわかった。手入れがしっかりとされている。緑に塗装されたボディには傷も汚れも付いてはいない。顔を近づけたら、反射して顔が映り込むはずだ。
山の上まで届くほどの走行音を響かせながら、バイクはすぐに視界から消えた。僕と同じように、駐車場にバイクを停め、山を登ってくるのだろうか。もし登ってくるのだとしたら、公園はあまり広くないので展望台にはすぐ気づくはずだ。気づかれて仕舞えば、風景は僕だけのものとは言えなくなる。否応なく風景という財産が見知らぬ他人と共有される事になるだろう。
もちろん、この場所は誰か個人の所有物ではない。公園に立ち入り、ベンチや展望台といった設備を使用する権利は誰にでもある。僕のような子供でも使用できるし、歩行動作がままならない老人が犬の散歩のために利用するのも間違った行為ではない。けれど、叶うのならば、展望台だけは僕に占拠させてほしい。
身勝手な要求であるのは、誰の目にも明らかだ。だから僕は要求を口にだす真似はしないし、同じ道路を辿って入ってきたバイク乗りには、「僕は景色を堪能しました。次はあなたの番です」などと言ってこの場を大人しく開け渡さすべきなのだ。あくまでバイク乗りが公園に入ってきたら、という話だが。
今にヘルメットを脱いで顔を露わにした彼、もしくは彼女が、僕の元へとやってくるのかもしれない。
なんとなく後ろにある階段が気になって、僕は振り返った。そして息を呑んだ。
階段を上り切った場所に、一人の少女が立っていた。
少女は、僕がリュックサックに詰め込んだのと同じブレザーを着ていた。つまり、僕と同じ学校の生徒。肩に届くかどうかという長さに揃えられた黒髪が、僕の髪と同様、風によって荒れ狂っている。だが彼女は、動き回る髪には全く意識を向けていなかった。恐怖とか、怯えと言った感情を内包したまま動けずに立っている。
目は肉食獣に睨まれたウサギのようだし、胸の前で組んだ指が忙しなく動いている様からは落ち着きなど微塵も感じ取れない。だが、僕の顔を見ている。瞳はしっかりと、僕の顔を向いている。何かはわからないが、明確な目的があってこの場にいるのだという気配が感じ取れた。
少女の顔には、見覚えがあった。僕が中学校の頃、一年生の時だけ同じクラスだった生
僕がついさっき通ってきたあの車道に、一台のバイクが姿を見せた。それも僕の時と同じ方角だった。
運転手の顔は、フルフェイスタイプのヘルメットを被っているので見えない。男性か女性か、年齢がどのくらいなのかも判別がつかなかった。彼、或いは彼女の乗っているマシンは、バイクに詳しくない僕にも高価な事がわかった。手入れがしっかりとされている。緑に塗装されたボディには傷も汚れも付いてはいない。顔を近づけたら、反射して顔が映り込むはずだ。
山の上まで届くほどの走行音を響かせながら、バイクはすぐに視界から消えた。僕と同じように、駐車場にバイクを停め、山を登ってくるのだろうか。もし登ってくるのだとしたら、公園はあまり広くないので展望台にはすぐ気づくはずだ。気づかれて仕舞えば、風景は僕だけのものとは言えなくなる。否応なく風景という財産が見知らぬ他人と共有される事になるだろう。
もちろん、この場所は誰か個人の所有物ではない。公園に立ち入り、ベンチや展望台といった設備を使用する権利は誰にでもある。僕のような子供でも使用できるし、歩行動作がままならない老人が犬の散歩のために利用するのも間違った行為ではない。けれど、叶うのならば、展望台だけは僕に占拠させてほしい。
身勝手な要求であるのは、誰の目にも明らかだ。だから僕は要求を口にだす真似はしないし、同じ道路を辿って入ってきたバイク乗りには、「僕は景色を堪能しました。次はあなたの番です」などと言ってこの場を大人しく開け渡さすべきなのだ。あくまでバイク乗りが公園に入ってきたら、という話だが。
今にヘルメットを脱いで顔を露わにした彼、もしくは彼女が、僕の元へとやってくるのかもしれない。
なんとなく後ろにある階段が気になって、僕は振り返った。そして息を呑んだ。
階段を上り切った場所に、一人の少女が立っていた。
少女は、僕がリュックサックに詰め込んだのと同じブレザーを着ていた。つまり、僕と同じ学校の生徒。肩に届くかどうかという長さに揃えられた黒髪が、僕の髪と同様、風によって荒れ狂っている。だが彼女は、動き回る髪には全く意識を向けていなかった。恐怖とか、怯えと言った感情を内包したまま動けずに立っている。
目は肉食獣に睨まれたウサギのようだし、胸の前で組んだ指が忙しなく動いている様からは落ち着きなど微塵も感じ取れない。だが、僕の顔を見ている。瞳はしっかりと、僕の顔を向いている。何かはわからないが、明確な目的があってこの場にいるのだという気配が感じ取れた。
少女の顔には、見覚えがあった。僕が中学校の頃、一年生の時だけ同じクラスだった生
徒だ。名前は、金城瑠夏と言ったはずだ。
聞いた話によれば、瑠夏が中学に上がるタイミングで、両親が引っ越しを決めた。理由は定かではないが、察するに仕事が理由だろう。引っ越しについて瑠夏は、馴染みのある小学校の級友たちに別れを告げなくてはならなかった。
僕の目の前で体現しているように、瑠夏は気が弱く、臆病な性格をしている。当然、両親に引っ越しは嫌だと言い出せなかっただろう。本音を押し隠して、親の言うままに知らない子供達と一緒の中学校に入学した。
だが、中学に上がった瑠夏を待っていたのは、あまり良いとは言えない環境だった。
瑠夏が入学した学校の生徒たちは、殆どが小学校からの持ち上がりだったのだ。六年間を共に過ごした仲間たちと、中学校の三年間も一緒という流れになる。すでに作り上げられたコミュニティに途中から入り、すっかり馴染んでしまうのには時間もかかるし、瑠夏の場合最初の一歩を踏み出すのも難しい。時間をかけさえすれば良いと言う話でもなかった。
実際、瑠夏は最初の一年目で孤立した。一年目、とはいっても、夏休みが始まる頃にはとっくにクラスの輪の中には入れていなかった。夏休み前の一週間の内に、彼女の置かれている実情を僕は察した。
長期休暇に突入する前の、最後の一週間。それまでクラスメイトと仲良くなろうと懸命に話しかけていた瑠夏は、ついに友達作りを諦めていた。授業の合間に設けられた休憩時間では、本を読んで過ごしていた。よく見てみれば、読んでいる本はどれも図書室にはない本ばかりだった。学校の用意した制度すら使わずに孤立して過ごしている様を見て、初めて僕は金城瑠夏という女の子を正しく認識した気がする。
僕も小学校からの持ち上がりで、友達は新しく作るまでもなかった。既に仲の良い彼らと集まって談笑したり、遊んだりしていた。だから正直な所、夏休み前の最後の週に至るまで、瑠夏の存在をほとんど認知していないも同然だったのだ。瑠夏はきっと、女子同士仲良くするのだろうとばかり思うだけだったのだ。結論として、それは間違いだった。
夏休みが刻一刻と迫り、教室内で徐々に浮かれたムードが漂ってくる中、瑠夏だけは黙々と読書に耽っていた。周りの人間など、自分には見えていないかのようだった。
当時の僕からすれば、それはあまりにも残酷な状態に思えた。瑠夏は一日中、誰とも話さず、笑顔も見せず、授業では適当に板書をして、休憩時間には本を読むだけを繰り返すだけだ。移動教室の時以外は、一歩も己の席から動かずに一日をやり過ごす。
一日、二日と経過して、僕も段々それが理解できてきたのだ。だから、思い切って声をかけてみた。このままでいると、きっと彼女は声の出し方すら忘れてしまいそうに思えたから。
具体的に何を言ったのか、もう記憶にはない。「どんな本を読んでいるの?」というよう
聞いた話によれば、瑠夏が中学に上がるタイミングで、両親が引っ越しを決めた。理由は定かではないが、察するに仕事が理由だろう。引っ越しについて瑠夏は、馴染みのある小学校の級友たちに別れを告げなくてはならなかった。
僕の目の前で体現しているように、瑠夏は気が弱く、臆病な性格をしている。当然、両親に引っ越しは嫌だと言い出せなかっただろう。本音を押し隠して、親の言うままに知らない子供達と一緒の中学校に入学した。
だが、中学に上がった瑠夏を待っていたのは、あまり良いとは言えない環境だった。
瑠夏が入学した学校の生徒たちは、殆どが小学校からの持ち上がりだったのだ。六年間を共に過ごした仲間たちと、中学校の三年間も一緒という流れになる。すでに作り上げられたコミュニティに途中から入り、すっかり馴染んでしまうのには時間もかかるし、瑠夏の場合最初の一歩を踏み出すのも難しい。時間をかけさえすれば良いと言う話でもなかった。
実際、瑠夏は最初の一年目で孤立した。一年目、とはいっても、夏休みが始まる頃にはとっくにクラスの輪の中には入れていなかった。夏休み前の一週間の内に、彼女の置かれている実情を僕は察した。
長期休暇に突入する前の、最後の一週間。それまでクラスメイトと仲良くなろうと懸命に話しかけていた瑠夏は、ついに友達作りを諦めていた。授業の合間に設けられた休憩時間では、本を読んで過ごしていた。よく見てみれば、読んでいる本はどれも図書室にはない本ばかりだった。学校の用意した制度すら使わずに孤立して過ごしている様を見て、初めて僕は金城瑠夏という女の子を正しく認識した気がする。
僕も小学校からの持ち上がりで、友達は新しく作るまでもなかった。既に仲の良い彼らと集まって談笑したり、遊んだりしていた。だから正直な所、夏休み前の最後の週に至るまで、瑠夏の存在をほとんど認知していないも同然だったのだ。瑠夏はきっと、女子同士仲良くするのだろうとばかり思うだけだったのだ。結論として、それは間違いだった。
夏休みが刻一刻と迫り、教室内で徐々に浮かれたムードが漂ってくる中、瑠夏だけは黙々と読書に耽っていた。周りの人間など、自分には見えていないかのようだった。
当時の僕からすれば、それはあまりにも残酷な状態に思えた。瑠夏は一日中、誰とも話さず、笑顔も見せず、授業では適当に板書をして、休憩時間には本を読むだけを繰り返すだけだ。移動教室の時以外は、一歩も己の席から動かずに一日をやり過ごす。
一日、二日と経過して、僕も段々それが理解できてきたのだ。だから、思い切って声をかけてみた。このままでいると、きっと彼女は声の出し方すら忘れてしまいそうに思えたから。
具体的に何を言ったのか、もう記憶にはない。「どんな本を読んでいるの?」というよう
な質問だった気がする。瑠夏は僕の問いかけにすぐには気づけず、私ではない誰かなのだと思い込んでいるようだった。
しかし、ほんの僅かに視線を向けてみると、間違いなく自分に話しかけているという事に気づいた。何が起こったのかと、動揺したのがわかりやすく顔に出た。これでもかと目を丸くして、かと思えば目線をあちらこちらに泳がせる。あまりにイレギュラーな事態に対して、彼女自身まったく用意ができていない様子だった。
思い出す限りそれが、瑠夏と交流を持つきっかけだった。以来僕は、友人とある程度話をしたら、勇気を出して瑠夏に声をかけるようになった。殆どが休憩時間に行われた。
きっとこれなら喋ってくれるだろうと、読んでいる本について尋ねた。本のあらすじや、面白いか、面白くないのか。一日にどのくらい本を読んでいるのかなど。会話のとっかかりは、常に瑠夏の手にしている本だった。
初めはしどろもどろになって、話もままならない瑠夏だったが、次第に口から出てくる言葉に落ち着きを見せていった。声量こそ小さいものの、言っている内容は理解できるようになったし、感情がこもるようになって、話している最中に口角を上げたりもした。焦って瞬きが増えるのも、目に見えて緩和されていった。自分で言うのもあれだが、割と仲良くなった方だと当時は感じた。だがそれが、悲劇の始まりとなる。
終業式の日、全校生徒が体育館に集められた。学級ごとに並べられ、これから長期休暇に入る子供達へ、教頭や校長先生たちが注意事項を口にしていった。注意事項とは、異口同音であり、要は校外で面倒を起こすな、というものだった。これに気づかないほど僕たち子供は馬鹿ではないので、途中からは集中力が切れたのもあって、各々小さな声でおしゃべりを開始した。
僕も、一つ前に並んでいた仲の良い友人男子に話しかけられた。彼は僕の方を振り返って、何やら笑顔を浮かべてこちらを眺めた。嫌な顔をしているな、などと思いながら僕も相手の顔をじっと見つめた。目は合わせたくなかったから、主に唇と額とを交互に眺めていた。
一〇秒ほど沈黙が保たれた後に、急にそいつは口を開いた。
「なあ、圭也って、金城瑠夏と付き合ってんの?」
圭也、とは僕の名前だった。僕が、瑠夏と付き合っている。ありえない話だ。だから僕は即座に、首を振って否定した。
「でも、最近仲良いじゃん」
「一人で寂しそうにしてたから、話しかけようと思っただけだよ。付き合いたくてやったわけじゃない」
「聞いた話だと、グループ学習の時女子のグループに金城さんを仲間に加えてほしいって頼み込んでたそうだけど、それは本当?」
しかし、ほんの僅かに視線を向けてみると、間違いなく自分に話しかけているという事に気づいた。何が起こったのかと、動揺したのがわかりやすく顔に出た。これでもかと目を丸くして、かと思えば目線をあちらこちらに泳がせる。あまりにイレギュラーな事態に対して、彼女自身まったく用意ができていない様子だった。
思い出す限りそれが、瑠夏と交流を持つきっかけだった。以来僕は、友人とある程度話をしたら、勇気を出して瑠夏に声をかけるようになった。殆どが休憩時間に行われた。
きっとこれなら喋ってくれるだろうと、読んでいる本について尋ねた。本のあらすじや、面白いか、面白くないのか。一日にどのくらい本を読んでいるのかなど。会話のとっかかりは、常に瑠夏の手にしている本だった。
初めはしどろもどろになって、話もままならない瑠夏だったが、次第に口から出てくる言葉に落ち着きを見せていった。声量こそ小さいものの、言っている内容は理解できるようになったし、感情がこもるようになって、話している最中に口角を上げたりもした。焦って瞬きが増えるのも、目に見えて緩和されていった。自分で言うのもあれだが、割と仲良くなった方だと当時は感じた。だがそれが、悲劇の始まりとなる。
終業式の日、全校生徒が体育館に集められた。学級ごとに並べられ、これから長期休暇に入る子供達へ、教頭や校長先生たちが注意事項を口にしていった。注意事項とは、異口同音であり、要は校外で面倒を起こすな、というものだった。これに気づかないほど僕たち子供は馬鹿ではないので、途中からは集中力が切れたのもあって、各々小さな声でおしゃべりを開始した。
僕も、一つ前に並んでいた仲の良い友人男子に話しかけられた。彼は僕の方を振り返って、何やら笑顔を浮かべてこちらを眺めた。嫌な顔をしているな、などと思いながら僕も相手の顔をじっと見つめた。目は合わせたくなかったから、主に唇と額とを交互に眺めていた。
一〇秒ほど沈黙が保たれた後に、急にそいつは口を開いた。
「なあ、圭也って、金城瑠夏と付き合ってんの?」
圭也、とは僕の名前だった。僕が、瑠夏と付き合っている。ありえない話だ。だから僕は即座に、首を振って否定した。
「でも、最近仲良いじゃん」
「一人で寂しそうにしてたから、話しかけようと思っただけだよ。付き合いたくてやったわけじゃない」
「聞いた話だと、グループ学習の時女子のグループに金城さんを仲間に加えてほしいって頼み込んでたそうだけど、それは本当?」
僕はもう一度、首を振った。終業式に至る日まで、僕がしていたのはただ金城瑠夏に声をかけるだけなのだ。主に休憩時間を使い、適当な話題を口にするだけ。彼女の方も、短く返答をするだけの会話とも呼べないもの。
仲の良い友人と言い切れる関係性でないのは、僕が一番に理解していた。だからこそ、周囲の人間に向かって瑠夏への態度を変えてほしいと懇願するなど、ありえない話だ。
一体誰がそんな話を、と僕は訊いた。だが相手は、答えられなかった。偶然どこかで聞いたのだと。
ため息をついてから、再三噂の内容を否定した。相手も本人が言うのなら、と僕の話を幸いにも信じてくれた。僕はほっと胸を撫で下ろしながらも、噂を流した犯人が誰なのか気になった。同じ教室の中に、根源である奴がいるはずだ。
そうはいっても、その日は終業式であり、詳しい調査などできるはずもない。僕は仕方なく、僅かな引っ掛かりを覚えながら夏休みを過ごす事にした。問題が起こり始めたのは、二学期が開始された後だった。
二学期になれば、噂話など霧散してしまうだろうと考えていたのだが、結果は違うものだった。噂が消えるどころか、寧ろ話がより大きくなっていたのだ。
夏休みの間に、僕と瑠夏が二人で歩いているのを見かけた、とか手を繋いで公園のベンチに座っていたなど、事実を曲解するのではなく、事実そのものを作り上げた噂が流れ始めていた。
当時僕を含め、全員が幼かった。中学校に上がったばかりで、皆一様に恋人を作る事に対して抵抗を感じていた。恋人がいると恥ずかしい。だって周りの友達には、恋人がいないのだから。
僕の居た地域特有の考え方かもしれない。或いは、全国の中学一年生が共通して持っている価値観なのかもしれない。どちらでもいい、とにかく僕は、ありもしない話が生まれたのをきっかけにいじめにも似た扱いを受ける事となった。
噂に気がついたのは、二学期が始まって三日目だった。なんとなく周囲の態度がよそよそしいと感じていた僕は、原因らしきものを発見して、合点がいった。あいつだけ、恋人を作って夏を満喫したんだろうと根拠なく信じられている。真相を直接、本人たちには確かめない。誰かから聞いた話こそが真実であり、当事者の二人は照れ隠しで真相を否定するに違いない。クラスで流れている空気は、大方そんなものだった。
瑠夏に加えて、僕とも距離を取ろうとしている。もはや教室の中で孤独を満喫するのは、僕と瑠夏の二人に増えていた。
裏を返せば、隠していた事が浮き彫りになって二人とも気まずいのだという話も耳に飛び込んできた。僕はあえて、瞬時に噂の否定には入らなかった。慌てて説得を試みても、「それみたことか、圭也はこんなにも慌てているぞ」と言われかねない。自然に噂が消える
仲の良い友人と言い切れる関係性でないのは、僕が一番に理解していた。だからこそ、周囲の人間に向かって瑠夏への態度を変えてほしいと懇願するなど、ありえない話だ。
一体誰がそんな話を、と僕は訊いた。だが相手は、答えられなかった。偶然どこかで聞いたのだと。
ため息をついてから、再三噂の内容を否定した。相手も本人が言うのなら、と僕の話を幸いにも信じてくれた。僕はほっと胸を撫で下ろしながらも、噂を流した犯人が誰なのか気になった。同じ教室の中に、根源である奴がいるはずだ。
そうはいっても、その日は終業式であり、詳しい調査などできるはずもない。僕は仕方なく、僅かな引っ掛かりを覚えながら夏休みを過ごす事にした。問題が起こり始めたのは、二学期が開始された後だった。
二学期になれば、噂話など霧散してしまうだろうと考えていたのだが、結果は違うものだった。噂が消えるどころか、寧ろ話がより大きくなっていたのだ。
夏休みの間に、僕と瑠夏が二人で歩いているのを見かけた、とか手を繋いで公園のベンチに座っていたなど、事実を曲解するのではなく、事実そのものを作り上げた噂が流れ始めていた。
当時僕を含め、全員が幼かった。中学校に上がったばかりで、皆一様に恋人を作る事に対して抵抗を感じていた。恋人がいると恥ずかしい。だって周りの友達には、恋人がいないのだから。
僕の居た地域特有の考え方かもしれない。或いは、全国の中学一年生が共通して持っている価値観なのかもしれない。どちらでもいい、とにかく僕は、ありもしない話が生まれたのをきっかけにいじめにも似た扱いを受ける事となった。
噂に気がついたのは、二学期が始まって三日目だった。なんとなく周囲の態度がよそよそしいと感じていた僕は、原因らしきものを発見して、合点がいった。あいつだけ、恋人を作って夏を満喫したんだろうと根拠なく信じられている。真相を直接、本人たちには確かめない。誰かから聞いた話こそが真実であり、当事者の二人は照れ隠しで真相を否定するに違いない。クラスで流れている空気は、大方そんなものだった。
瑠夏に加えて、僕とも距離を取ろうとしている。もはや教室の中で孤独を満喫するのは、僕と瑠夏の二人に増えていた。
裏を返せば、隠していた事が浮き彫りになって二人とも気まずいのだという話も耳に飛び込んできた。僕はあえて、瞬時に噂の否定には入らなかった。慌てて説得を試みても、「それみたことか、圭也はこんなにも慌てているぞ」と言われかねない。自然に噂が消える
るまで、ただ待つのが懸命な判断だと思えたのだ。
結論から言って、その判断は間違いだった。噂が否定されなかった事で、周囲は言い当てられて黙るしかないのだと考え始めたのだ。『恋人イジり』が、時間経過とともにより多くなった。誰もが、二人は付き合っているのだと言う噂話を真実だと思い込んでいった。
いつしか僕は、噂がなんだと言って気にしないフリを続けるのも難しくなっていった。仲の良かった友人たちも、僕と距離を取るようになったし、僕も彼らから距離を取るようになった。
ある日の放課後、偶然瑠夏と二人きりで教室で当番に割り当てられた清掃をしている時に彼らが教室を覗き見していた。「キスをするのか?」「ハグをするのか?」などと小さな声で呟き、ニヤニヤと笑みを浮かべていた。手にしていた箒で威嚇し、追い払ったが、それきり彼らとの交友は絶たれた。どちらかが宣言したりはせずに、ごく自然に。
二年生と三年生では、それぞれクラス替えがあったが、元々が三クラスしかない小さな学校だったので、かつてのクラスメイトたちの何人かは必ず同じ組に分けられた。金城瑠夏とだけは再び同じクラスにはならなかったが、十分、噂の内容は継続された。
歳を重ねるごとに、ある程度学校内で恋人ができる生徒は増えていったものの、それだけでは僕と瑠夏に向けられる奇異の目は無くならなかった。
だから僕は、学年が上がるごとに誰とも口を聞かないようになっていった。
今、目の前には件の金城瑠夏がいる。僕の特別な場所に足を踏み入れて、しっかり目を合わせている。僕に会いにきたのだと言いたげだ。けれど、彼女は一向に話を切り出そうとはしなかった。固く閉じられた唇が時折動こうとするが、結局元に戻って固く結ばれる。
景色を眺めにきたのではないようだが、ならわざわざここへ来た目的はなんだろうか。
道を歩いていて、知っている人が立ち寄ったから追いかけてみた、と言うような場所ではない。ここは学校から離れているのに加えて、商業施設が一つもないド田舎だ。気分で立ち寄る人など、おそらく一人としていないのではないか。
卒業式が終わって、体育館から僕の後を追ってきたのかとも考えたが、あり得る話ではない。そんな間柄ではない。
僕がありえそうな可能性を頭の中で探っていても、一向に瑠夏は口を開かなかった。彼女が今立っている場所から退いてくれなければ、階段を降りて帰宅できない。僕が帰るためには瑠夏のアクションが必要な訳だが、肝心の本人がどうもしないのでは話にならない。
如何にしてこの事態を突破すべきか、という議題に脳が移りかけた時、ようやく瑠夏が言葉を発した。
「あの、砂川くんの事がすっ、好きなんです。付き合ってください!」
腰を折って頭を下げる瑠夏に対し、僕の方は口を開けて呆然とする他なかった。金城瑠夏は、たった今何を言ったのだろう。好きと言ったか。誰の事を好きと告白したのか。
結論から言って、その判断は間違いだった。噂が否定されなかった事で、周囲は言い当てられて黙るしかないのだと考え始めたのだ。『恋人イジり』が、時間経過とともにより多くなった。誰もが、二人は付き合っているのだと言う噂話を真実だと思い込んでいった。
いつしか僕は、噂がなんだと言って気にしないフリを続けるのも難しくなっていった。仲の良かった友人たちも、僕と距離を取るようになったし、僕も彼らから距離を取るようになった。
ある日の放課後、偶然瑠夏と二人きりで教室で当番に割り当てられた清掃をしている時に彼らが教室を覗き見していた。「キスをするのか?」「ハグをするのか?」などと小さな声で呟き、ニヤニヤと笑みを浮かべていた。手にしていた箒で威嚇し、追い払ったが、それきり彼らとの交友は絶たれた。どちらかが宣言したりはせずに、ごく自然に。
二年生と三年生では、それぞれクラス替えがあったが、元々が三クラスしかない小さな学校だったので、かつてのクラスメイトたちの何人かは必ず同じ組に分けられた。金城瑠夏とだけは再び同じクラスにはならなかったが、十分、噂の内容は継続された。
歳を重ねるごとに、ある程度学校内で恋人ができる生徒は増えていったものの、それだけでは僕と瑠夏に向けられる奇異の目は無くならなかった。
だから僕は、学年が上がるごとに誰とも口を聞かないようになっていった。
今、目の前には件の金城瑠夏がいる。僕の特別な場所に足を踏み入れて、しっかり目を合わせている。僕に会いにきたのだと言いたげだ。けれど、彼女は一向に話を切り出そうとはしなかった。固く閉じられた唇が時折動こうとするが、結局元に戻って固く結ばれる。
景色を眺めにきたのではないようだが、ならわざわざここへ来た目的はなんだろうか。
道を歩いていて、知っている人が立ち寄ったから追いかけてみた、と言うような場所ではない。ここは学校から離れているのに加えて、商業施設が一つもないド田舎だ。気分で立ち寄る人など、おそらく一人としていないのではないか。
卒業式が終わって、体育館から僕の後を追ってきたのかとも考えたが、あり得る話ではない。そんな間柄ではない。
僕がありえそうな可能性を頭の中で探っていても、一向に瑠夏は口を開かなかった。彼女が今立っている場所から退いてくれなければ、階段を降りて帰宅できない。僕が帰るためには瑠夏のアクションが必要な訳だが、肝心の本人がどうもしないのでは話にならない。
如何にしてこの事態を突破すべきか、という議題に脳が移りかけた時、ようやく瑠夏が言葉を発した。
「あの、砂川くんの事がすっ、好きなんです。付き合ってください!」
腰を折って頭を下げる瑠夏に対し、僕の方は口を開けて呆然とする他なかった。金城瑠夏は、たった今何を言ったのだろう。好きと言ったか。誰の事を好きと告白したのか。
僕は咄嗟に左右を見渡した。もしかすると、僕以外に展望台へ立ち寄っていた『砂川くん』がいるのかもしれない。景色に見惚れ、気づいていないだけで別の砂川が存在しているのかもしれないと思った。だがそれはありえない。こんな狭いスペースで他に誰かがいれば、気が付かないはずがないのだ。実際に、展望台には僕と金城瑠夏の他には誰もいない。
瑠夏の言っている砂川くんとは、間違えるはずもなく僕の事だ。状況を飲み込むために、少しだけ時間が必要だった。
僕が目の前で起こった事象の整理に努めていると、急に瑠夏が顔だけを上げた。「返事はまだか」と言っているような気がした。
「あの、へ、返事とか……」
しっかりそう言われてしまった。だが僕には答えようがない。まさか、卒業式の日に昔仲が良かった女の子に告白されるとは、思っても見ないからだ。
「返事と言われても、いまいち状況が飲み込めないんだ。金城さんだよね? 中一の時にクラスが同じだった」
「はい! 覚えててくれたんだね!」
体を起こして、嬉しそうに笑う金城瑠夏。忘れるわけがない。あの出来事を境に、僕の暮らしは大きく変わったのだ。どれだけ忘れようとしても、恐らくは死ぬまで忘れる事はないだろう。
「うん、覚えてるよ。でもどうして、金城さんが僕に告白するの? 何かのイタズラ?」
僕は瑠夏の背後に視線を向けて言った。階段の下に彼女の仲間数人が潜んでいて、飛び出すタイミングを待ち侘びているような気がした。
瑠夏は慌てた様子で両手を振った。
「違う、違うよ。これは、私の本当の気持ちなの。イタズラとかじゃないよ」
「でも、信じられない。僕の事が好きだなんて。一体、いつから?」
僕が訊くと、瑠夏の顔はにわかに紅潮していった。俯いて自分の足元を見つめた。両の手は背中で組まれ、もじもじと体全体を動かす。なんだか、こっちまで気恥ずかしくなってくる。
「中学校の、頃から。一年生の時に、私に話しかけてくれたでしょ?」
「うん、そうだね。確か、読んでる本の事で質問とかしてたんだっけ」
「すごく嬉しかったの。私、人見知りがすごくて誰からも声をかけてもらえなかったんだ。最初だけは、別の場所から引っ越してきたからって話しかけてもらえたんだけど、時間が経ってくると誰も私に興味をもたなくなったの。もちろん、会話に積極的じゃない私が悪いんだけど、でも当時は、どうすることもできなくてすごく苦しかった」
瑠夏は顔をあげて、遠くに見える街の方に視線を向けた。僕とは目を合わせられないか
瑠夏の言っている砂川くんとは、間違えるはずもなく僕の事だ。状況を飲み込むために、少しだけ時間が必要だった。
僕が目の前で起こった事象の整理に努めていると、急に瑠夏が顔だけを上げた。「返事はまだか」と言っているような気がした。
「あの、へ、返事とか……」
しっかりそう言われてしまった。だが僕には答えようがない。まさか、卒業式の日に昔仲が良かった女の子に告白されるとは、思っても見ないからだ。
「返事と言われても、いまいち状況が飲み込めないんだ。金城さんだよね? 中一の時にクラスが同じだった」
「はい! 覚えててくれたんだね!」
体を起こして、嬉しそうに笑う金城瑠夏。忘れるわけがない。あの出来事を境に、僕の暮らしは大きく変わったのだ。どれだけ忘れようとしても、恐らくは死ぬまで忘れる事はないだろう。
「うん、覚えてるよ。でもどうして、金城さんが僕に告白するの? 何かのイタズラ?」
僕は瑠夏の背後に視線を向けて言った。階段の下に彼女の仲間数人が潜んでいて、飛び出すタイミングを待ち侘びているような気がした。
瑠夏は慌てた様子で両手を振った。
「違う、違うよ。これは、私の本当の気持ちなの。イタズラとかじゃないよ」
「でも、信じられない。僕の事が好きだなんて。一体、いつから?」
僕が訊くと、瑠夏の顔はにわかに紅潮していった。俯いて自分の足元を見つめた。両の手は背中で組まれ、もじもじと体全体を動かす。なんだか、こっちまで気恥ずかしくなってくる。
「中学校の、頃から。一年生の時に、私に話しかけてくれたでしょ?」
「うん、そうだね。確か、読んでる本の事で質問とかしてたんだっけ」
「すごく嬉しかったの。私、人見知りがすごくて誰からも声をかけてもらえなかったんだ。最初だけは、別の場所から引っ越してきたからって話しかけてもらえたんだけど、時間が経ってくると誰も私に興味をもたなくなったの。もちろん、会話に積極的じゃない私が悪いんだけど、でも当時は、どうすることもできなくてすごく苦しかった」
瑠夏は顔をあげて、遠くに見える街の方に視線を向けた。僕とは目を合わせられないか
らなのか、景色が綺麗だからなのか、理由はわからない。ただ一つ言えるのは、彼女の目はとてつもなく遠い場所を見つめているように思えた。遠いとは、物理的な距離の話ではない。過ぎ去ってしまった、遥か昔だ。現代の人間には到底辿り着けないほどの遠い場所に、瑠夏の目は向いている。
そして彼女は笑った。笑ったように見えた。
「正直な事を言うと、高校は砂川くんと同じところがいいなって思った。だから先生と砂川くんが話しているのを盗み聞きして、私も同じ学校に入ろうって決めた。砂川くんは頭が良かったから、勉強はとっても大変だった。でも無事に、同じ高校に入学できた」
「それは、本当? 嘘ついてない?」
「ついてない。本当だよ。高校生になったら、砂川くんに告白しようって思ってたの。今よりも立派な大人になって、一緒に隣を歩けるような人になってから、告白しようって思った。付き合ってからの事も考えて、いっぱい話せるようになるために、頑張って友達もたくさん作ったの。中学生の頃と同じなのは、嫌だったから。でも勇気が出せなくて、結局今日になっちゃったんだ」
真剣な顔をして話していた瑠夏だったが、自分の言っている内容を改めて理解したのか、また顔を赤くした。今度は耳まで赤くなるほどだった。一方で僕も、瑠夏に負けないくらいに顔が赤くなっていった。鏡で見ずとも、それくらいわかる。顔面が、とにかく熱くて仕方ないのだ。鼓動も、ものすごく速くなっている。
だが、ただ赤くなっているだけでは駄目だ。瑠夏から突如として持ちかけられた話に、結論を出すのが僕の役目だ。答えがイエスにしろ、ノーにしろ考えて出す。責務から逃れる術はない。
瑠夏は、僕の目を見ていた。気づけば、彼女の目は真っ直ぐと僕の方に向いて、返事を待っていた。
とりあえず返事までの繋ぎのため、僕は言った。
「僕は中学の途中から今まで、金城さんと仲良くしていたような人間じゃなくなってる。人と関わるのはできるだけ避けたいって思うようになってる。昔見たいに友達に恵まれるわけじゃないし、普段から暗い影みたいにして生きてる。それでもいいの?」
「うん。それでもいい。砂川くんが変わったなっていうのは、高校に入る前からなんとなくわかってたし。でも、だからこそ、今度は私が砂川くんの助けになりたい。砂川くんが話しかけてくれた時、学校に行くのがすごく楽しかった。恩返しができるならもちろんしたいし、何より今の砂川くんだって十分かっこいいと思う」
真剣な顔でそう言われたので、僕は真剣に考えてみた。金城瑠夏と付き合えば、どうなるのかを。
高校に入学してから、驚くべき事に瑠夏と同じクラスになった事は一度としてない。廊
そして彼女は笑った。笑ったように見えた。
「正直な事を言うと、高校は砂川くんと同じところがいいなって思った。だから先生と砂川くんが話しているのを盗み聞きして、私も同じ学校に入ろうって決めた。砂川くんは頭が良かったから、勉強はとっても大変だった。でも無事に、同じ高校に入学できた」
「それは、本当? 嘘ついてない?」
「ついてない。本当だよ。高校生になったら、砂川くんに告白しようって思ってたの。今よりも立派な大人になって、一緒に隣を歩けるような人になってから、告白しようって思った。付き合ってからの事も考えて、いっぱい話せるようになるために、頑張って友達もたくさん作ったの。中学生の頃と同じなのは、嫌だったから。でも勇気が出せなくて、結局今日になっちゃったんだ」
真剣な顔をして話していた瑠夏だったが、自分の言っている内容を改めて理解したのか、また顔を赤くした。今度は耳まで赤くなるほどだった。一方で僕も、瑠夏に負けないくらいに顔が赤くなっていった。鏡で見ずとも、それくらいわかる。顔面が、とにかく熱くて仕方ないのだ。鼓動も、ものすごく速くなっている。
だが、ただ赤くなっているだけでは駄目だ。瑠夏から突如として持ちかけられた話に、結論を出すのが僕の役目だ。答えがイエスにしろ、ノーにしろ考えて出す。責務から逃れる術はない。
瑠夏は、僕の目を見ていた。気づけば、彼女の目は真っ直ぐと僕の方に向いて、返事を待っていた。
とりあえず返事までの繋ぎのため、僕は言った。
「僕は中学の途中から今まで、金城さんと仲良くしていたような人間じゃなくなってる。人と関わるのはできるだけ避けたいって思うようになってる。昔見たいに友達に恵まれるわけじゃないし、普段から暗い影みたいにして生きてる。それでもいいの?」
「うん。それでもいい。砂川くんが変わったなっていうのは、高校に入る前からなんとなくわかってたし。でも、だからこそ、今度は私が砂川くんの助けになりたい。砂川くんが話しかけてくれた時、学校に行くのがすごく楽しかった。恩返しができるならもちろんしたいし、何より今の砂川くんだって十分かっこいいと思う」
真剣な顔でそう言われたので、僕は真剣に考えてみた。金城瑠夏と付き合えば、どうなるのかを。
高校に入学してから、驚くべき事に瑠夏と同じクラスになった事は一度としてない。廊
この作家の他の作品
表紙を見る
コメントがいただけると非常に嬉しいです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…