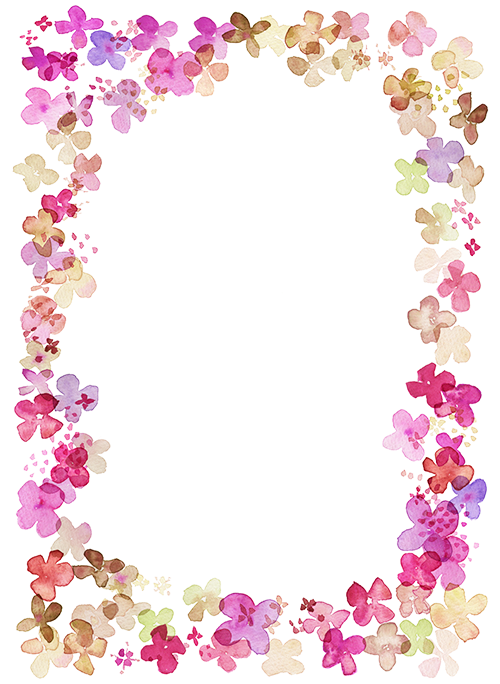落ちるのか、進むのか、自分でもよくわからない上下感覚があった。
やがてリランは自分を包む感触に、まどろみから目覚める。
(毛布、ふわふわ……気持ちいい)
リランは寝返りを打って、柔らかな感触を味わう。
(けど、いつまでも怠けていてはだめね)
リランは心を決めて目を開いた。体力と健康には自信を持っていて、どんな日でも朝からやる気だった。
初めに目に映ったのは、天蓋付きの寝台だった。
「……おや?」
リランは思わず目をまたたかせて声を上げる。
両手を広げても端まで届かない寝台、天蓋から下がる紗。村娘がそんなものの中で目を覚ましたことはなく、リランは自分が見たものを疑っていた。
「夢……ではないみたいね」
とはいえいつまでも自分を疑っているわけにもいかない。リランは声を出してこれが現実だと確かめると、いつも通り元気に起き上がった。
リランが着ているものは白い夜着で、しかも村娘には馴染みがない絹だった。
「あらあら……」
紗の隙間から顔を出すと、そこはリランの家がまるごと入るほどに広い部屋だった。鳥の描かれた衝立に花の模様の彫りこまれた天井、どこかの貴人の部屋のようだった。
リランは夜着姿のまま室内をうろつき、とりあえず着るものを探す。壁際までてくてくと歩いていって、リランはそこに衣装棚を発見した。
ただしリランの家のものとは似ても似つかない見事な棚だった。年を経た分だけくすみ、茶褐色に黄金細工が施されている。
「覗きます……」
誰にともなく断りを入れてから、リランはそっと棚に手をかける。
そこには物語の中で天女がまとうような、絹の衣装が詰まっていた。
「……失礼しました」
やはり断りを入れて、リランはぱたんと棚を閉める。
(やっぱり夢を見ているみたいね。どうしましょう……起きるところからやり直せるかしら)
起きると決意したのに、もう一回眠りたくなるリランだった。
リランはしばらく室内をさ迷っていたが、仕方なく寝室に隣接した居室に足を踏み入れる。
「あ」
そこには部屋の隅にある棚の上に、リランが宴で着ていた服が畳まれて置いてあった。
「そう、これが一番なの」
それは弟のカイがリランの結婚式のために贈ってくれた服だった。
大満足でリランはそれを身につける。甘く熟した秋の木の実で色づけされた赤は、リランの心もほっと温かくしてくれた。
「もしかしてカイがいるのかしら?」
衣服が落ち着いたことで、眠ることは頭の外に追いやった。
リランは期待に胸を熱くして扉へ向かう。
ところが押しても引いても扉は動かず、リランは扉の前で首を傾げる。
(困ったわ。カイに会いたいのに)
閉じ込められているとは微塵も思わないリランだった。
開かないものは仕方がないと、リランはおもむろに窓辺へ歩み寄る。
リランははしたないのを覚悟で、大胆に窓縁に足を掛けた。
「えい!」
リランは自慢の脚力を発揮して、窓を乱暴に開いた。
入り込む涼しい風に目を細めながらリランは外を見つめる。
リランのいる部屋は二階のようで、下には幾重にも花畑が広がっていた。
「まあ、素敵」
花畑の先で弟に会えそうな予感がして、リランは無邪気に微笑んだ。
リランは朝の白い空気を吸い込んでうなずく。
「行きましょう!」
嬉々として、リランはぴょんと窓から飛び降りた。
わんぱくさに自信を持っているリランでもちょっと不安な浮遊感の後、なんとか地面に足がついた。
「あぶないあぶない……」
大した高低差はないと踏んでいたのだが、実際はリランの身長の二倍ほどの高さがあったようだった。
「あ、いけない。お花が」
けれどそれはそれ、リランは足元でつぶれてしまった花を見つめる。
リランがおろおろとして花に触れようとしたときだった。
「そう、いけないわね。わたくしの可愛い子たちをどうしてくれるのかしら?」
突然、花畑から人影が姿を見せる。
長身に淡い緑の衣装を身につけた、柳のような雰囲気の女性だった。湖面のような瞳が知性的で、落ち着いた身のこなしで歩み寄って来る。
リランは慌てて女性に謝る。
「ごめんなさい……」
「これはなかなか育てるのが大変なのよ?」
女性はしょんぼりするリランの顔を覗きこむ。
彼女はふいにリランの顎を取って目を細めた。
「あら、かわいらしい」
彼女は薄い唇を引き上げて、妖しい笑みを浮かべる。
「ちょっと悪戯させてくれるかしら? そうしたら許してあげる」
「え、よろしいのですか?」
弁償方法を考え中だったリランは、その言葉に飛びつく。
「どんな風にすればよろしいでしょう?」
「どんな悪戯かって?」
女性は長い指をリランの唇に押し当てて、リランの耳元で艶やかに囁く。
「こんな明るい所じゃ、話せないわねぇ……」
「そんな……じきに夜明けなのに」
「ふふ」
彼女はリランの耳朶に触れるだけの口付けをすると、体を離してリランを見る。
「まあ冗談はさておき」
「あら?」
リランは不思議そうに首を傾げる。そんなリランに、女性は目を細めて明るく笑った。
「あなた、ここで他の妃の誘いに全部乗っていたら身がもたないに決まっているでしょう? これは先人からのありがたーいお言葉よ」
「あ、そうなのですか」
リランはこくんと幼い仕草で頷く。
「ありがとうございます。これからは気をつけます」
「うんうん、素直でいい子ね。撫で撫でしてあげる」
感触を味わうようにリランのふわふわした髪をなでると、女性はリランの手を取る。
「私の宮にいらっしゃいな。ここは冷えるわ」
「はい」
「……本当に素直ね、あなたは」
ひな鳥のように後を追うリランの手を握って、女性は憂えるように目を伏せた。
辺りには濃く霧が漂って視界は悪いが、手をつないでいるおかげで先を行く女性の姿を見失うことはなかった。
リランは霧の向こうに東屋が立っているのをみつけてほっとしていた。緑色の光が窓辺を照らしていて、ほんのりと明るい。
「さ、お入りなさい」
女性に招かれた東屋は、香草の匂いが漂っていた。深い紺の敷布、優しい目をした猫の置物に囲まれたそこはどこかの貴人の隠れ家のようだった。
歩く途中でも気づいていたが、女性はほとんど足音を立てずに歩く。彼女はその細く長い手足でするりと椅子に掛けると、向かいの席を勧めてリランに言った。
「わたくしはチュンヒ。ここに長く住む者よ」
「あ、私はリランと言います。はじめまして、チュンヒさん」
「んー、しっくりこないわね」
彼女は不満げに口元を歪めると、細い指先を突きつけて言った。
「お姉様とお呼び」
「はい、お姉様」
「ほほ……。それでいいわ」
足を組みかえて、チュンヒは卓の上の茶器を手に取る。
耳に心地よい音を立てて、香り立つ湯気が器へと流れ込む。
「薬草を調合したお茶よ、疲れが癒せるわ」
「はい、頂きます」
リランが茶器に口をつけると、それは仄かな甘みのするお茶だった。
しばらく二人、のんびりとお茶を楽しんで、やがてチュンヒは茶器を置く。
チュンヒは頬に手を当てながらリランを見て言った。
「さぁて、リランちゃん。お探しのひとだけど」
「え、おわかりですか?」
「お姉様は何でも知っているのよ」
チュンヒはリランをみつめかえしながら続ける。
「襲撃を受けた村のひとたちは、弟さんはどうなったか」
「はい……」
呑気に構えながらも心配でたまらなかったことを指摘されて、リランはうなずく。
「そうねぇ。まあ大事なことなのでしょうけど」
チュンヒは思案して顎を引いた。
「信じなくてもいいから聞いて。……それは百年も前のことなの」
リランはきょとんとしてまばたきをする。
「百年前?」
「太陽は百年前に闇に呑まれ、世界は滅んだ。あなたは百年間眠っていたの」
リランは視線を下に落として、それからチュンヒを見返した。
けれどリランから言葉は出てこなかった。どうしたらいいか困っているというリランの表情に、チュンヒも押し黙る。
リランはチュンヒの言葉を信じたわけではなかった。けれど否定するにも、リランは何もかもがわからなかった。
「今私がいるここは?」
落ち着いているようにも聞こえるリランの問いに、チュンヒは答える。
「空中楼閣、皇帝陛下の私庭、いくつか呼び名はあるけど……後宮と言った方がわかりやすいかしら」
リランは一度目を閉じて、何もかもが異質な世界を想った。
チュンヒの言葉を信じるなら、村の人たちも弟も、とっくに亡くなっている。
それは確かに悲惨なこと。けれどただ泣いてそれを惜しむには、まだ実感が一つもなかった。
リランは目を開いて、案外肩の力の抜けた声で言った。
「……新しいことは、いつだって楽しみ」
小さな村で暮らしながら毎日に向き合ってきた信条を口にして、リランはにっこりと笑う。
「まずは暮らしてみないと。お姉様、ここでの暮らし方を教えてください」
「……ふ」
リランの言葉にチュンヒは苦笑してみせた。
「お姉様?」
「あなたはとんでもなく愚かなのか……あるいは、天に選ばれた者なのかと思ったのよ」
リランが首を傾げると、チュンヒは言葉を続ける。
「後宮なのだから、私たちは皇帝陛下の子を産むために集められた。けれど今は皆、その目的を諦めているの。終わった世界の後に皇統の意味があるのかとね。……でも」
チュンヒはいたずらっぽく目配せすると、リランに優しい言葉をかけた。
「いいわ。私の知っている後宮の暮らし方を教えましょう」
チュンヒは湖面のような瞳で空を仰いで、三つの忠告を話してくれた。
一つ目、空中楼閣の外には出ないこと。そこには魔鬼と呼ばれる危険な者たちが行き来している。
二つ目、後宮で絶大な力を持っている「アイシラ」の怒りに触れないこと。
「最後の一つは、皇帝陛下のことだけど」
チュンヒは深く思案してから言葉を続けた。
「皇帝陛下に愛されるのはたやすいことではないわ」
リランはその言葉を考えて問い返す。
「陛下も、皇統をあきらめていらっしゃる?」
チュンヒは苦笑して首を横に振った。
「必ずしもそうではないわ。ただ皇帝陛下はあなたが生まれる前から、魔鬼たちを平定しようと尽力されてきたの。後宮に興味を向ける時間がなかったのよ」
チュンヒはリランを見返しながら言う。
「陛下は魔鬼たちをその身に吸収していって、いくつかの楼閣を築かれた。その結果、永遠の命と冷淡な気性をお持ちになったの」
ため息をついて、チュンヒは憂えるように告げた。
「陛下を理解するのは、妃には難しいのでしょうね。獣と混じったしもべたち……獣僕の方が、陛下には心安いのでしょう」
「獣僕……」
リランはチュンヒの言葉をよく心で繰り返すと、明るい表情で大きくうなずく。
「わかりました! よく心に留めて過ごします」
「ええ」
チュンヒはふいにリランを妖しい目で見た。
髪を手で軽くかき上げて、チュンヒは逆の手でそっとリランの頬に触れる。
「後宮の争いなど放っておいて、ここで私と楽しい時を過ごしてもいいのよ?」
指先をリランの顎に這わせてから、チュンヒは微笑んだ。
チュンヒは慈しみのような、好奇心のような、不思議な感情を浮かべて告げる。
「……でもそれを望むには、あなたは若すぎるのかしら。リラン」
チュンヒはふっと息を吐いた。リランの肩に知らず入っていた力も抜ける。
そのとき、鐘の音が響いた。朝を告げる鐘にしては重々しい音色で、何かの終わりを告げるようにも聞こえた。
チュンヒは立ち上がって袖を広げると、来た道を指し示して言う。
「もう時間よ。帰りなさい」
「お姉様、まだいろいろお話ししたいです」
「私は眠らないといけない時間なの……」
チュンヒは儚く笑って、花が閉じるように自分の身を抱きしめる。
「わたくしはあなたを見ている。はらはらしながら、楽しみに」
強い風が流れてリランは目を閉じる。リランはとっさに一歩後ずさって、風が通り過ぎるままに任せた。
「あなたのその純粋さが……命取りにならないことを祈るわ」
顔を上げた時、そこにチュンヒの姿はなかった。
……代わりに石棺が横たわり、香草の匂いが漂っているだけ。
鐘は鳴り続ける。急かすように、何かの警告のように次第に音を荒らげる。
ふいに足元が揺らいで、リランははっと我に返る。
「え……!」
東屋がまるで土くれのように崩れ始めていた。石で出来た床もひび割れて、後にはぽっかりと空白だけが広がる。
帰りなさいと誰かに言われた気がした。ここにいてはいけないと叫んでいるようにも聞こえた。
「く……っ!」
リランは踵を返して走り出す。
振り向けば東屋はもう霧の中に溶けていた。自らが霧に呑まれるのを想像して、リランは前に走るしかないと決める。
リランは濃霧を走り抜けて、何とか元来た道に合流する。
部屋の下まで戻って来たが、二階の高さにある部屋には手が届かない。
背後に迫って来る霧に、リランが自らの終わりを予感したときだった。
「リラン!」
そのとき、懐かしい声がリランを呼んだ。
「ツタをつかんで! 引き上げますから!」
リランは辺りを見回して、部屋に向かって伸びているツタをみつける。
リランはぐっと拳を握って、ツタへと手をかける。
一生懸命ツタに掴まって部屋までよじ登ったが、窓枠をつかむところで手を滑らせる。
「あ……!」
虚空をかいたリランの手を、誰かがしっかりと掴んだ。
ぐっと引き寄せられて、リランの体はどうにか部屋の中に倒れ込んだ。
リランは息が上がってしばらくうずくまっていると、誰かの声が言う。
「後宮の妃には、死霊もいるんです」
誰かは苦々しい声で告げてから、窓の外を見たようだった。
「春妃……義の妃と呼ばれる最初の妃で、まだよかった。これからは気を付けないと」
「はぁ、は……ありがとう……」
リランは息を収めて顔を上げる。
そこで目にしたものに、リランは目を見開く。
「カイ……!?」
弟に生き写しの少年がそこに立っていて、リランはひととき時を忘れていた。
やがてリランは自分を包む感触に、まどろみから目覚める。
(毛布、ふわふわ……気持ちいい)
リランは寝返りを打って、柔らかな感触を味わう。
(けど、いつまでも怠けていてはだめね)
リランは心を決めて目を開いた。体力と健康には自信を持っていて、どんな日でも朝からやる気だった。
初めに目に映ったのは、天蓋付きの寝台だった。
「……おや?」
リランは思わず目をまたたかせて声を上げる。
両手を広げても端まで届かない寝台、天蓋から下がる紗。村娘がそんなものの中で目を覚ましたことはなく、リランは自分が見たものを疑っていた。
「夢……ではないみたいね」
とはいえいつまでも自分を疑っているわけにもいかない。リランは声を出してこれが現実だと確かめると、いつも通り元気に起き上がった。
リランが着ているものは白い夜着で、しかも村娘には馴染みがない絹だった。
「あらあら……」
紗の隙間から顔を出すと、そこはリランの家がまるごと入るほどに広い部屋だった。鳥の描かれた衝立に花の模様の彫りこまれた天井、どこかの貴人の部屋のようだった。
リランは夜着姿のまま室内をうろつき、とりあえず着るものを探す。壁際までてくてくと歩いていって、リランはそこに衣装棚を発見した。
ただしリランの家のものとは似ても似つかない見事な棚だった。年を経た分だけくすみ、茶褐色に黄金細工が施されている。
「覗きます……」
誰にともなく断りを入れてから、リランはそっと棚に手をかける。
そこには物語の中で天女がまとうような、絹の衣装が詰まっていた。
「……失礼しました」
やはり断りを入れて、リランはぱたんと棚を閉める。
(やっぱり夢を見ているみたいね。どうしましょう……起きるところからやり直せるかしら)
起きると決意したのに、もう一回眠りたくなるリランだった。
リランはしばらく室内をさ迷っていたが、仕方なく寝室に隣接した居室に足を踏み入れる。
「あ」
そこには部屋の隅にある棚の上に、リランが宴で着ていた服が畳まれて置いてあった。
「そう、これが一番なの」
それは弟のカイがリランの結婚式のために贈ってくれた服だった。
大満足でリランはそれを身につける。甘く熟した秋の木の実で色づけされた赤は、リランの心もほっと温かくしてくれた。
「もしかしてカイがいるのかしら?」
衣服が落ち着いたことで、眠ることは頭の外に追いやった。
リランは期待に胸を熱くして扉へ向かう。
ところが押しても引いても扉は動かず、リランは扉の前で首を傾げる。
(困ったわ。カイに会いたいのに)
閉じ込められているとは微塵も思わないリランだった。
開かないものは仕方がないと、リランはおもむろに窓辺へ歩み寄る。
リランははしたないのを覚悟で、大胆に窓縁に足を掛けた。
「えい!」
リランは自慢の脚力を発揮して、窓を乱暴に開いた。
入り込む涼しい風に目を細めながらリランは外を見つめる。
リランのいる部屋は二階のようで、下には幾重にも花畑が広がっていた。
「まあ、素敵」
花畑の先で弟に会えそうな予感がして、リランは無邪気に微笑んだ。
リランは朝の白い空気を吸い込んでうなずく。
「行きましょう!」
嬉々として、リランはぴょんと窓から飛び降りた。
わんぱくさに自信を持っているリランでもちょっと不安な浮遊感の後、なんとか地面に足がついた。
「あぶないあぶない……」
大した高低差はないと踏んでいたのだが、実際はリランの身長の二倍ほどの高さがあったようだった。
「あ、いけない。お花が」
けれどそれはそれ、リランは足元でつぶれてしまった花を見つめる。
リランがおろおろとして花に触れようとしたときだった。
「そう、いけないわね。わたくしの可愛い子たちをどうしてくれるのかしら?」
突然、花畑から人影が姿を見せる。
長身に淡い緑の衣装を身につけた、柳のような雰囲気の女性だった。湖面のような瞳が知性的で、落ち着いた身のこなしで歩み寄って来る。
リランは慌てて女性に謝る。
「ごめんなさい……」
「これはなかなか育てるのが大変なのよ?」
女性はしょんぼりするリランの顔を覗きこむ。
彼女はふいにリランの顎を取って目を細めた。
「あら、かわいらしい」
彼女は薄い唇を引き上げて、妖しい笑みを浮かべる。
「ちょっと悪戯させてくれるかしら? そうしたら許してあげる」
「え、よろしいのですか?」
弁償方法を考え中だったリランは、その言葉に飛びつく。
「どんな風にすればよろしいでしょう?」
「どんな悪戯かって?」
女性は長い指をリランの唇に押し当てて、リランの耳元で艶やかに囁く。
「こんな明るい所じゃ、話せないわねぇ……」
「そんな……じきに夜明けなのに」
「ふふ」
彼女はリランの耳朶に触れるだけの口付けをすると、体を離してリランを見る。
「まあ冗談はさておき」
「あら?」
リランは不思議そうに首を傾げる。そんなリランに、女性は目を細めて明るく笑った。
「あなた、ここで他の妃の誘いに全部乗っていたら身がもたないに決まっているでしょう? これは先人からのありがたーいお言葉よ」
「あ、そうなのですか」
リランはこくんと幼い仕草で頷く。
「ありがとうございます。これからは気をつけます」
「うんうん、素直でいい子ね。撫で撫でしてあげる」
感触を味わうようにリランのふわふわした髪をなでると、女性はリランの手を取る。
「私の宮にいらっしゃいな。ここは冷えるわ」
「はい」
「……本当に素直ね、あなたは」
ひな鳥のように後を追うリランの手を握って、女性は憂えるように目を伏せた。
辺りには濃く霧が漂って視界は悪いが、手をつないでいるおかげで先を行く女性の姿を見失うことはなかった。
リランは霧の向こうに東屋が立っているのをみつけてほっとしていた。緑色の光が窓辺を照らしていて、ほんのりと明るい。
「さ、お入りなさい」
女性に招かれた東屋は、香草の匂いが漂っていた。深い紺の敷布、優しい目をした猫の置物に囲まれたそこはどこかの貴人の隠れ家のようだった。
歩く途中でも気づいていたが、女性はほとんど足音を立てずに歩く。彼女はその細く長い手足でするりと椅子に掛けると、向かいの席を勧めてリランに言った。
「わたくしはチュンヒ。ここに長く住む者よ」
「あ、私はリランと言います。はじめまして、チュンヒさん」
「んー、しっくりこないわね」
彼女は不満げに口元を歪めると、細い指先を突きつけて言った。
「お姉様とお呼び」
「はい、お姉様」
「ほほ……。それでいいわ」
足を組みかえて、チュンヒは卓の上の茶器を手に取る。
耳に心地よい音を立てて、香り立つ湯気が器へと流れ込む。
「薬草を調合したお茶よ、疲れが癒せるわ」
「はい、頂きます」
リランが茶器に口をつけると、それは仄かな甘みのするお茶だった。
しばらく二人、のんびりとお茶を楽しんで、やがてチュンヒは茶器を置く。
チュンヒは頬に手を当てながらリランを見て言った。
「さぁて、リランちゃん。お探しのひとだけど」
「え、おわかりですか?」
「お姉様は何でも知っているのよ」
チュンヒはリランをみつめかえしながら続ける。
「襲撃を受けた村のひとたちは、弟さんはどうなったか」
「はい……」
呑気に構えながらも心配でたまらなかったことを指摘されて、リランはうなずく。
「そうねぇ。まあ大事なことなのでしょうけど」
チュンヒは思案して顎を引いた。
「信じなくてもいいから聞いて。……それは百年も前のことなの」
リランはきょとんとしてまばたきをする。
「百年前?」
「太陽は百年前に闇に呑まれ、世界は滅んだ。あなたは百年間眠っていたの」
リランは視線を下に落として、それからチュンヒを見返した。
けれどリランから言葉は出てこなかった。どうしたらいいか困っているというリランの表情に、チュンヒも押し黙る。
リランはチュンヒの言葉を信じたわけではなかった。けれど否定するにも、リランは何もかもがわからなかった。
「今私がいるここは?」
落ち着いているようにも聞こえるリランの問いに、チュンヒは答える。
「空中楼閣、皇帝陛下の私庭、いくつか呼び名はあるけど……後宮と言った方がわかりやすいかしら」
リランは一度目を閉じて、何もかもが異質な世界を想った。
チュンヒの言葉を信じるなら、村の人たちも弟も、とっくに亡くなっている。
それは確かに悲惨なこと。けれどただ泣いてそれを惜しむには、まだ実感が一つもなかった。
リランは目を開いて、案外肩の力の抜けた声で言った。
「……新しいことは、いつだって楽しみ」
小さな村で暮らしながら毎日に向き合ってきた信条を口にして、リランはにっこりと笑う。
「まずは暮らしてみないと。お姉様、ここでの暮らし方を教えてください」
「……ふ」
リランの言葉にチュンヒは苦笑してみせた。
「お姉様?」
「あなたはとんでもなく愚かなのか……あるいは、天に選ばれた者なのかと思ったのよ」
リランが首を傾げると、チュンヒは言葉を続ける。
「後宮なのだから、私たちは皇帝陛下の子を産むために集められた。けれど今は皆、その目的を諦めているの。終わった世界の後に皇統の意味があるのかとね。……でも」
チュンヒはいたずらっぽく目配せすると、リランに優しい言葉をかけた。
「いいわ。私の知っている後宮の暮らし方を教えましょう」
チュンヒは湖面のような瞳で空を仰いで、三つの忠告を話してくれた。
一つ目、空中楼閣の外には出ないこと。そこには魔鬼と呼ばれる危険な者たちが行き来している。
二つ目、後宮で絶大な力を持っている「アイシラ」の怒りに触れないこと。
「最後の一つは、皇帝陛下のことだけど」
チュンヒは深く思案してから言葉を続けた。
「皇帝陛下に愛されるのはたやすいことではないわ」
リランはその言葉を考えて問い返す。
「陛下も、皇統をあきらめていらっしゃる?」
チュンヒは苦笑して首を横に振った。
「必ずしもそうではないわ。ただ皇帝陛下はあなたが生まれる前から、魔鬼たちを平定しようと尽力されてきたの。後宮に興味を向ける時間がなかったのよ」
チュンヒはリランを見返しながら言う。
「陛下は魔鬼たちをその身に吸収していって、いくつかの楼閣を築かれた。その結果、永遠の命と冷淡な気性をお持ちになったの」
ため息をついて、チュンヒは憂えるように告げた。
「陛下を理解するのは、妃には難しいのでしょうね。獣と混じったしもべたち……獣僕の方が、陛下には心安いのでしょう」
「獣僕……」
リランはチュンヒの言葉をよく心で繰り返すと、明るい表情で大きくうなずく。
「わかりました! よく心に留めて過ごします」
「ええ」
チュンヒはふいにリランを妖しい目で見た。
髪を手で軽くかき上げて、チュンヒは逆の手でそっとリランの頬に触れる。
「後宮の争いなど放っておいて、ここで私と楽しい時を過ごしてもいいのよ?」
指先をリランの顎に這わせてから、チュンヒは微笑んだ。
チュンヒは慈しみのような、好奇心のような、不思議な感情を浮かべて告げる。
「……でもそれを望むには、あなたは若すぎるのかしら。リラン」
チュンヒはふっと息を吐いた。リランの肩に知らず入っていた力も抜ける。
そのとき、鐘の音が響いた。朝を告げる鐘にしては重々しい音色で、何かの終わりを告げるようにも聞こえた。
チュンヒは立ち上がって袖を広げると、来た道を指し示して言う。
「もう時間よ。帰りなさい」
「お姉様、まだいろいろお話ししたいです」
「私は眠らないといけない時間なの……」
チュンヒは儚く笑って、花が閉じるように自分の身を抱きしめる。
「わたくしはあなたを見ている。はらはらしながら、楽しみに」
強い風が流れてリランは目を閉じる。リランはとっさに一歩後ずさって、風が通り過ぎるままに任せた。
「あなたのその純粋さが……命取りにならないことを祈るわ」
顔を上げた時、そこにチュンヒの姿はなかった。
……代わりに石棺が横たわり、香草の匂いが漂っているだけ。
鐘は鳴り続ける。急かすように、何かの警告のように次第に音を荒らげる。
ふいに足元が揺らいで、リランははっと我に返る。
「え……!」
東屋がまるで土くれのように崩れ始めていた。石で出来た床もひび割れて、後にはぽっかりと空白だけが広がる。
帰りなさいと誰かに言われた気がした。ここにいてはいけないと叫んでいるようにも聞こえた。
「く……っ!」
リランは踵を返して走り出す。
振り向けば東屋はもう霧の中に溶けていた。自らが霧に呑まれるのを想像して、リランは前に走るしかないと決める。
リランは濃霧を走り抜けて、何とか元来た道に合流する。
部屋の下まで戻って来たが、二階の高さにある部屋には手が届かない。
背後に迫って来る霧に、リランが自らの終わりを予感したときだった。
「リラン!」
そのとき、懐かしい声がリランを呼んだ。
「ツタをつかんで! 引き上げますから!」
リランは辺りを見回して、部屋に向かって伸びているツタをみつける。
リランはぐっと拳を握って、ツタへと手をかける。
一生懸命ツタに掴まって部屋までよじ登ったが、窓枠をつかむところで手を滑らせる。
「あ……!」
虚空をかいたリランの手を、誰かがしっかりと掴んだ。
ぐっと引き寄せられて、リランの体はどうにか部屋の中に倒れ込んだ。
リランは息が上がってしばらくうずくまっていると、誰かの声が言う。
「後宮の妃には、死霊もいるんです」
誰かは苦々しい声で告げてから、窓の外を見たようだった。
「春妃……義の妃と呼ばれる最初の妃で、まだよかった。これからは気を付けないと」
「はぁ、は……ありがとう……」
リランは息を収めて顔を上げる。
そこで目にしたものに、リランは目を見開く。
「カイ……!?」
弟に生き写しの少年がそこに立っていて、リランはひととき時を忘れていた。