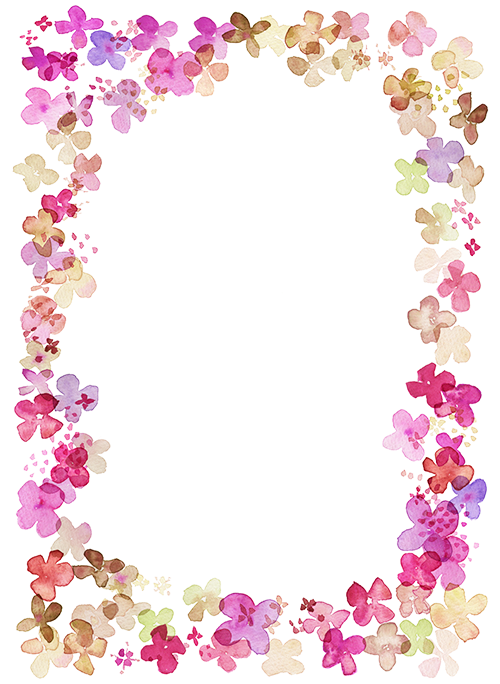うららかな春の日差しが降り注ぐ昼下がり、リランは結婚の日を迎えた。
「おお、リラン。またべっぴんになったな」
「本当にねぇ。こんな田舎にはもったいないよ」
丘の上で開かれたささやかな宴の中、主役自ら酒を注いで回るリランに村人たちが目を細める。
長く癖のない黒髪を結い、はちみつ色の瞳を持つリランは、十六歳になる。
今日はこの地で古くから伝わる、秋の木の実で染めた紅色の婚儀の衣装をまとっていた。それは普段着より少し華やかなくらいだったが、彩るような笑顔がリランを美しく見せていた。
リランははしゃいで村人たちに言う。
「新しいことはいつだって楽しみですね。……あ、踊らないと!」
楽師が弦を弾いて陽気な音楽を奏でると、リランは自ら扇をひらめかせて舞い始める。
今日は山を越えた向こうの村から、リランの婿がやって来る。
リランの伯父たちが今頃馬に乗って婿を迎えに行っているだろう。リランはそれを待っていた。
「あら、減ってきましたね。でもまだたくさんありますよ。ちょっと取ってきます」
リランは酒瓶の残りが少ないことに気づいて、籠を抱えて裏手までやって来た。
「あ」
そこでふいに袖を引かれて、リランは物陰に倒れ込んだ。
「ラン姉」
受け止めたのは二つ年下の弟のカイで、彼は姉を隠すようにして身をひそめる。
カイは陶器のような肌と細工物のような目鼻立ちをした、少女と見まごうほどの繊細な容姿の少年だった。けれど男性には違いなく、とっくにリランの背丈を追い越し、彼女を包む腕の力は既に強い。
「どうしたの、カイ?」
姉を包んだまま動かない弟の胸で、リランはきょとんとして首を傾げた。
カイは空を仰いで一つ息をつくと、リランが驚くようなことを言った。
「……このまま僕と逃げ出して、帝都に行かないか?」
「あらあら。カイ、寂しくなったの?」
唐突な言葉に驚いたのは一瞬で、リランはくすくすと笑う。
両親を亡くしたばかりの姉弟は、少し親子のようなところがあった。リランは手を伸ばして弟の頭を撫でる。
「大丈夫よ。カイがお嫁さんをもらうまでは、私がちゃんとついているんだから」
「そうじゃないんだ」
カイは苛立ったように姉に畳み掛ける。
「こんなちっぽけな村で姉さんが一生を終えるのはあんまりだろう」
「ちっぽけだなんて」
リランは眉をひそめて、弟を仰ぎ見る。
「お父様とお母様が残してくださった土地だもの。小さくとも、私にとっては何より大切なものよ」
「それで、見も知らない男と結婚するのか?」
「カイ、どうして怒っているの?」
声を荒らげた弟にリランは邪気のない微笑みを浮かべて、はちみつ色の瞳でじっと見つめ返す。
「天に定められたことよ。私は村を愛しているし、夫となる人も愛するように努力する」
「姉さん、流されてはいけないよ」
ぴしゃりとはねのけるような弟の言葉に、リランは小首を傾げる。
「なぜ?」
「天が僕らに何をしてくれる。姉さんはおっとりしているけど機転は利くし、美人だ。それを無駄にしてはいけない」
苦しげにみつめてくる弟に、リランは口元を歪める。
弟の言葉を心で繰り返して、リランは目を逸らす。
(そうね、学のあるカイにはこの世界は窮屈でしょう。だけど……)
体は小さくても、リランは姉だった。子どもの頃から弟を守って来たリランには、カイのような野心の代わりに落ち着きがあった。
「私はこの土地を守らなければ」
決意したように言う姉に、カイが露骨に眉を寄せる。
「ラン姉」
「あなたは帝都に行ってらっしゃい。あなたならきっと成功するわ」
リランは胸を張って明るく言う。
「心配しないで。確かに頼りないお姉ちゃんかもしれないけど、丈夫なところは一級品なんだから!」
リランは、ねっと首を傾げて同意を求める。
カイはひとときそんな姉をみつめて考えると、困ったように苦笑を浮かべた。
「……ラン姉には敵わないよ」
カイは先に立ちあがって惜しそうに空を仰ぐ。
「でもラン姉と帝都の月が見たかったな」
「この世のものとは思えないほど綺麗なのだそうね」
リランは元気に弟を見上げて笑う。
「だったらいつか一緒に見ましょう。きっとできるわ!」
「……うん」
カイはくすぐったそうに笑って、リランに手を差し伸べる。
大切な弟と約束を交わして、リランはその手を握り返した。
太陽がもっとも高く昇る時刻、宴も最高潮に達したが、婿はまだ現れなかった。
リランは山の向こうに目をこらして、ふと首を傾げる。
「あら?」
急に空が雲で覆われ始めたのに気づいて、リランは周りに告げる。
「雨かしら。料理を片付けないと」
「リラン、それはあたしたちがやるから」
「ありがとうございます」
リランは年配の女性たちに料理を任せて、老人たちに先に家の中へ入るように勧めた。いつも通りの働きぶりの彼女に、村人たちは苦笑して言った。
「濡れでもしたらいかん。さ、こっちに入りな」
「あ、はい」
壮年の女性にお礼を言って、リランは女性の家に入れてもらう。
料理が引っ込められていく中、リランも部屋の中で敷物の類を片付けて働いていた。
そういった物音とはまったく異質のざわめきが起こったのは、まもなくのことだった。
それはたとえるなら猛獣のうなり声のような、恐ろしげなとどろき。
異変を感じたリランは、そっと扉の隙間から外をのぞき見る。
「……え?」
リランは目を見張って、村人たちのざわめきの正体を知った。
先ほどまでの明るさなど嘘だったかのような、暗黒の空がそこにはあった。太陽だけは白々しいほどに照り輝いているのが、かえって不気味だった。
ゴ……ッと、空を押しつぶすような轟音が響く。
卓を運んでいた男たちもうめいて空を仰ぐ。
「おいおい……!」
誰もが目を見張る中、ゆっくりと空が動いたように見えた。
「太陽が……」
金色の太陽が漆黒の闇に覆われていく。まるで黒い化け物に飲み込まれていくかのようだった。
その光景はリランに一つの古い絵を思い出させた。
消える太陽、静かに受け入れる動植物。
そしてその後に現れるのは、限りなく永い闇だという。
(神話の中の光景が、私の目の前に?)
ごくりと乾いた喉を潤して、リランは息を呑んだ。
(世界の終焉、常闇の到来……!)
リランの耳に痛いほどの耳鳴りが迫ってきた。
同時に突き上げるような激しい地の揺れが襲う。
「きゃっ!」
床に打ち付けられて、リランは悲鳴をもらした。続いて身動きできないほど断続的な揺れが襲う。
地震は長く容赦なく、世界が壊れるように激しさを増すばかりだった。
「……ぁ!」
鼓膜が破けるような轟音と、真っ白な光が空を覆った。
太陽の光は完全に消えうせ、世界は真っ暗に変化する。
「うわぁぁぁ!」
外で悲鳴が上がったとき、リランは目を開いた。
リランは何とか起き上がると、うずくまったまま扉の外を見やる。
「……え」
リランが隙間から見たもの、それは無数の蛇や毒虫が地面から生まれ出て、外の男たちを食い荒らしている光景だった。
獰猛な唸りを上げて襲い掛かる化け物たちから、哀れな人々はただ逃げ回ることしかできない。
家の中の女主人も、へなへなと壁に沿って倒れる。
「な、何が……ひゃぁあ!」
「おばさま、しっかり! こ、こんな、一体……」
地獄絵図にリランもひとときうずくまって頭を抱えた。
けれど彼女には自身の根底に焼きついた使命があった。一度息を吸って自分を落ち着かせると、力を入れて立ち上がる。
「カ、カイを探さなきゃ!」
「あっ、リラン! 駄目だ、外に出るんじゃない!」
制止の声を無視して、リランは外へ走り出す。
「ごめんなさい、どいて、へびさん!」
絡み付く蛇を振り払いながら、必死で闇の中を駆け抜ける。
(カイ! どうしよう、無事でいて……!)
怖くないわけではないが、自分より後に生まれた弟を守るのはリランにとって当然のことだった。
「邪魔しないでください……だめなものはだめですっ!」
襲い掛かる化け物を押し返して、時に踏みつつ、リランは大急ぎで駆けていく。
ふいに何か固いものにぶつかって、リランは反射的に謝った。
「ごめんなさい……ぁ」
言葉が消え失せたのは、それは化け物というにはあまりに人に似ていたからだった。
「ナンダ?」
実際、それは言葉らしいものを口にした。
それは闇の中であるのに淡く輝く黒い体躯をしていて、蝙蝠のような赤い羽根に、短い青髪から羊のように灰色の角が生えている。
男に似た何かは蛇のように長い舌を出しながら、目を月型に細めて言う。
「オンナ?」
リランが後ずさると、あちこちに似たような男がいた。
角が生えている者、体は人間なのに牛の頭を持つ者までいる。
ぽたりと男が手にしている槍先から、赤い血が滴った。
(まさか……まさかこの人たち)
逃げ惑う村の人たちの悲鳴が遠くで聞こえて、リランは時が止まったような感覚に陥った。
男はにたりと笑って言う。
「オイシそう」
「……く」
リランは首を横に振りながら後ずさって……彼女なりの精一杯の力で、男を突き飛ばした。
「待テ!」
リランは息を吸って、踵を返して走り出した。
(あれは、あの方たちはまさか……魔鬼?)
地の底から出でて、すべてを奪うもの。残忍な快楽を求めて、人を食らうもの、それが魔鬼だと神話は語る。
「……カイ!」
遠くにちらりと弟の姿が見えた。
必死でそこへ駆けつけようとしたとき、ズキッと鋭い痛みが足に走る。
目の前がかすみのように揺らいで、リランは平衡感覚を失っていた。
(噛まれた……)
足にからみついた蛇、それには毒があったらしいと気づく。
視界は歪み、黒く覆われていく。地を覆う蛇や、行き交う男たちに飲み込まれてカイの姿も見えなくなっていく。
泥のように生ぬるい毒が体の中を走っていくのを感じた。
(踏んだ蛇に噛まれて死ぬ。これも天の意思なら……仕方ないけれど)
リランはもうろうとした意識の中、地に倒れながら思う。
(カイともう一度、会いたかった……)
世界は反転して、リランの意識は地の底のような深くに沈んでいった。
奇妙な夢を見ていた。
リランは誰か高貴な人の馬車に引っかかって、馬車を止めてしまったらしい。
「馬車の中でお待ちください、陛下。死体を引っかけてしまったようです」
そう言われるほどリランはほとんど虫の息で、目も見えなければ呼吸をしている実感もなかった。
「陛下、何を……あ」
けれどふいにリランに雫が落ちて、それは凍れる炎のようにリランに染みていった。
途端、リランの中を動悸が走って、全身が脈動する。
「陛下の血で息を吹き返すとは……」
ざわめきが辺りを包んで、驚きの声がリランに降り注ぐ。
喉の奥で響かせるような笑い声が聞こえたのはそのときだった。
「良い。……実に、良い」
誰かは興味深そうに言うと、リランを沓の先で転がして告げた。
「……これを後宮に連れて帰る」
突き上げるような、一瞬の激しい振動があった。
地響きがして、リランは今度こそ意識を失っていった。
「おお、リラン。またべっぴんになったな」
「本当にねぇ。こんな田舎にはもったいないよ」
丘の上で開かれたささやかな宴の中、主役自ら酒を注いで回るリランに村人たちが目を細める。
長く癖のない黒髪を結い、はちみつ色の瞳を持つリランは、十六歳になる。
今日はこの地で古くから伝わる、秋の木の実で染めた紅色の婚儀の衣装をまとっていた。それは普段着より少し華やかなくらいだったが、彩るような笑顔がリランを美しく見せていた。
リランははしゃいで村人たちに言う。
「新しいことはいつだって楽しみですね。……あ、踊らないと!」
楽師が弦を弾いて陽気な音楽を奏でると、リランは自ら扇をひらめかせて舞い始める。
今日は山を越えた向こうの村から、リランの婿がやって来る。
リランの伯父たちが今頃馬に乗って婿を迎えに行っているだろう。リランはそれを待っていた。
「あら、減ってきましたね。でもまだたくさんありますよ。ちょっと取ってきます」
リランは酒瓶の残りが少ないことに気づいて、籠を抱えて裏手までやって来た。
「あ」
そこでふいに袖を引かれて、リランは物陰に倒れ込んだ。
「ラン姉」
受け止めたのは二つ年下の弟のカイで、彼は姉を隠すようにして身をひそめる。
カイは陶器のような肌と細工物のような目鼻立ちをした、少女と見まごうほどの繊細な容姿の少年だった。けれど男性には違いなく、とっくにリランの背丈を追い越し、彼女を包む腕の力は既に強い。
「どうしたの、カイ?」
姉を包んだまま動かない弟の胸で、リランはきょとんとして首を傾げた。
カイは空を仰いで一つ息をつくと、リランが驚くようなことを言った。
「……このまま僕と逃げ出して、帝都に行かないか?」
「あらあら。カイ、寂しくなったの?」
唐突な言葉に驚いたのは一瞬で、リランはくすくすと笑う。
両親を亡くしたばかりの姉弟は、少し親子のようなところがあった。リランは手を伸ばして弟の頭を撫でる。
「大丈夫よ。カイがお嫁さんをもらうまでは、私がちゃんとついているんだから」
「そうじゃないんだ」
カイは苛立ったように姉に畳み掛ける。
「こんなちっぽけな村で姉さんが一生を終えるのはあんまりだろう」
「ちっぽけだなんて」
リランは眉をひそめて、弟を仰ぎ見る。
「お父様とお母様が残してくださった土地だもの。小さくとも、私にとっては何より大切なものよ」
「それで、見も知らない男と結婚するのか?」
「カイ、どうして怒っているの?」
声を荒らげた弟にリランは邪気のない微笑みを浮かべて、はちみつ色の瞳でじっと見つめ返す。
「天に定められたことよ。私は村を愛しているし、夫となる人も愛するように努力する」
「姉さん、流されてはいけないよ」
ぴしゃりとはねのけるような弟の言葉に、リランは小首を傾げる。
「なぜ?」
「天が僕らに何をしてくれる。姉さんはおっとりしているけど機転は利くし、美人だ。それを無駄にしてはいけない」
苦しげにみつめてくる弟に、リランは口元を歪める。
弟の言葉を心で繰り返して、リランは目を逸らす。
(そうね、学のあるカイにはこの世界は窮屈でしょう。だけど……)
体は小さくても、リランは姉だった。子どもの頃から弟を守って来たリランには、カイのような野心の代わりに落ち着きがあった。
「私はこの土地を守らなければ」
決意したように言う姉に、カイが露骨に眉を寄せる。
「ラン姉」
「あなたは帝都に行ってらっしゃい。あなたならきっと成功するわ」
リランは胸を張って明るく言う。
「心配しないで。確かに頼りないお姉ちゃんかもしれないけど、丈夫なところは一級品なんだから!」
リランは、ねっと首を傾げて同意を求める。
カイはひとときそんな姉をみつめて考えると、困ったように苦笑を浮かべた。
「……ラン姉には敵わないよ」
カイは先に立ちあがって惜しそうに空を仰ぐ。
「でもラン姉と帝都の月が見たかったな」
「この世のものとは思えないほど綺麗なのだそうね」
リランは元気に弟を見上げて笑う。
「だったらいつか一緒に見ましょう。きっとできるわ!」
「……うん」
カイはくすぐったそうに笑って、リランに手を差し伸べる。
大切な弟と約束を交わして、リランはその手を握り返した。
太陽がもっとも高く昇る時刻、宴も最高潮に達したが、婿はまだ現れなかった。
リランは山の向こうに目をこらして、ふと首を傾げる。
「あら?」
急に空が雲で覆われ始めたのに気づいて、リランは周りに告げる。
「雨かしら。料理を片付けないと」
「リラン、それはあたしたちがやるから」
「ありがとうございます」
リランは年配の女性たちに料理を任せて、老人たちに先に家の中へ入るように勧めた。いつも通りの働きぶりの彼女に、村人たちは苦笑して言った。
「濡れでもしたらいかん。さ、こっちに入りな」
「あ、はい」
壮年の女性にお礼を言って、リランは女性の家に入れてもらう。
料理が引っ込められていく中、リランも部屋の中で敷物の類を片付けて働いていた。
そういった物音とはまったく異質のざわめきが起こったのは、まもなくのことだった。
それはたとえるなら猛獣のうなり声のような、恐ろしげなとどろき。
異変を感じたリランは、そっと扉の隙間から外をのぞき見る。
「……え?」
リランは目を見張って、村人たちのざわめきの正体を知った。
先ほどまでの明るさなど嘘だったかのような、暗黒の空がそこにはあった。太陽だけは白々しいほどに照り輝いているのが、かえって不気味だった。
ゴ……ッと、空を押しつぶすような轟音が響く。
卓を運んでいた男たちもうめいて空を仰ぐ。
「おいおい……!」
誰もが目を見張る中、ゆっくりと空が動いたように見えた。
「太陽が……」
金色の太陽が漆黒の闇に覆われていく。まるで黒い化け物に飲み込まれていくかのようだった。
その光景はリランに一つの古い絵を思い出させた。
消える太陽、静かに受け入れる動植物。
そしてその後に現れるのは、限りなく永い闇だという。
(神話の中の光景が、私の目の前に?)
ごくりと乾いた喉を潤して、リランは息を呑んだ。
(世界の終焉、常闇の到来……!)
リランの耳に痛いほどの耳鳴りが迫ってきた。
同時に突き上げるような激しい地の揺れが襲う。
「きゃっ!」
床に打ち付けられて、リランは悲鳴をもらした。続いて身動きできないほど断続的な揺れが襲う。
地震は長く容赦なく、世界が壊れるように激しさを増すばかりだった。
「……ぁ!」
鼓膜が破けるような轟音と、真っ白な光が空を覆った。
太陽の光は完全に消えうせ、世界は真っ暗に変化する。
「うわぁぁぁ!」
外で悲鳴が上がったとき、リランは目を開いた。
リランは何とか起き上がると、うずくまったまま扉の外を見やる。
「……え」
リランが隙間から見たもの、それは無数の蛇や毒虫が地面から生まれ出て、外の男たちを食い荒らしている光景だった。
獰猛な唸りを上げて襲い掛かる化け物たちから、哀れな人々はただ逃げ回ることしかできない。
家の中の女主人も、へなへなと壁に沿って倒れる。
「な、何が……ひゃぁあ!」
「おばさま、しっかり! こ、こんな、一体……」
地獄絵図にリランもひとときうずくまって頭を抱えた。
けれど彼女には自身の根底に焼きついた使命があった。一度息を吸って自分を落ち着かせると、力を入れて立ち上がる。
「カ、カイを探さなきゃ!」
「あっ、リラン! 駄目だ、外に出るんじゃない!」
制止の声を無視して、リランは外へ走り出す。
「ごめんなさい、どいて、へびさん!」
絡み付く蛇を振り払いながら、必死で闇の中を駆け抜ける。
(カイ! どうしよう、無事でいて……!)
怖くないわけではないが、自分より後に生まれた弟を守るのはリランにとって当然のことだった。
「邪魔しないでください……だめなものはだめですっ!」
襲い掛かる化け物を押し返して、時に踏みつつ、リランは大急ぎで駆けていく。
ふいに何か固いものにぶつかって、リランは反射的に謝った。
「ごめんなさい……ぁ」
言葉が消え失せたのは、それは化け物というにはあまりに人に似ていたからだった。
「ナンダ?」
実際、それは言葉らしいものを口にした。
それは闇の中であるのに淡く輝く黒い体躯をしていて、蝙蝠のような赤い羽根に、短い青髪から羊のように灰色の角が生えている。
男に似た何かは蛇のように長い舌を出しながら、目を月型に細めて言う。
「オンナ?」
リランが後ずさると、あちこちに似たような男がいた。
角が生えている者、体は人間なのに牛の頭を持つ者までいる。
ぽたりと男が手にしている槍先から、赤い血が滴った。
(まさか……まさかこの人たち)
逃げ惑う村の人たちの悲鳴が遠くで聞こえて、リランは時が止まったような感覚に陥った。
男はにたりと笑って言う。
「オイシそう」
「……く」
リランは首を横に振りながら後ずさって……彼女なりの精一杯の力で、男を突き飛ばした。
「待テ!」
リランは息を吸って、踵を返して走り出した。
(あれは、あの方たちはまさか……魔鬼?)
地の底から出でて、すべてを奪うもの。残忍な快楽を求めて、人を食らうもの、それが魔鬼だと神話は語る。
「……カイ!」
遠くにちらりと弟の姿が見えた。
必死でそこへ駆けつけようとしたとき、ズキッと鋭い痛みが足に走る。
目の前がかすみのように揺らいで、リランは平衡感覚を失っていた。
(噛まれた……)
足にからみついた蛇、それには毒があったらしいと気づく。
視界は歪み、黒く覆われていく。地を覆う蛇や、行き交う男たちに飲み込まれてカイの姿も見えなくなっていく。
泥のように生ぬるい毒が体の中を走っていくのを感じた。
(踏んだ蛇に噛まれて死ぬ。これも天の意思なら……仕方ないけれど)
リランはもうろうとした意識の中、地に倒れながら思う。
(カイともう一度、会いたかった……)
世界は反転して、リランの意識は地の底のような深くに沈んでいった。
奇妙な夢を見ていた。
リランは誰か高貴な人の馬車に引っかかって、馬車を止めてしまったらしい。
「馬車の中でお待ちください、陛下。死体を引っかけてしまったようです」
そう言われるほどリランはほとんど虫の息で、目も見えなければ呼吸をしている実感もなかった。
「陛下、何を……あ」
けれどふいにリランに雫が落ちて、それは凍れる炎のようにリランに染みていった。
途端、リランの中を動悸が走って、全身が脈動する。
「陛下の血で息を吹き返すとは……」
ざわめきが辺りを包んで、驚きの声がリランに降り注ぐ。
喉の奥で響かせるような笑い声が聞こえたのはそのときだった。
「良い。……実に、良い」
誰かは興味深そうに言うと、リランを沓の先で転がして告げた。
「……これを後宮に連れて帰る」
突き上げるような、一瞬の激しい振動があった。
地響きがして、リランは今度こそ意識を失っていった。