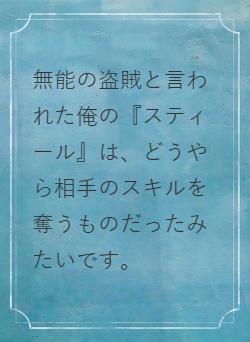それから馬車で揺れること数日。俺たちはその後に盗賊に遭遇することなく、無事にイリスを匿うための隠し別荘へと来ることができた。
ミノラルから少し離れた山の奥。特産物も特色もないただの田舎町であるオリスという町。
そこにイリスの隠れ別荘という物があった。
「……やっぱり、でかいんだな」
「なんか少し神秘的ですね」
大きさで言えば、俺たちが普段住んでいるミノラルの屋敷の二倍ほどの大きさ。壁の色は白く、森にひっそりとある洋館のような雰囲気が出ていた。
いや、実際にそうなのか。
別荘に配置されている騎士団の数は中々のもので、ここに閉じこもっているだけで誘拐されることはないのではないかと思えてしまう。
これだけの数の騎士団を配置しても騒ぎになったりしないのは、この中が山の中だからなのだろう。
聞いた話によると、近隣の家はここからしばらく馬車を走らせないとないらしい。
もしかしたら、誰にも気づかれることなく、ひっそりと隠れることができるから、こんな場所に別荘を構えたのかもしれない。
「それでは、アイクさん、リリさん。別荘の中へご案内いたします」
そんなことを考えながら、リリとポチと別荘を眺めていると、すぐに俺たちの後ろにいたハンスにそう言われて、俺たちは別荘の中へ移動することになった。
「別荘の中で今後の方針について、話し合いをしましょう」
真剣な表情でそう口にしたハンスを見て、これからが依頼の本番であることを再度確認したのだった。
そして、俺たちは別荘の広間で作戦会議を行うことになった。
この場にいるのは『道化師の集い』とイリスとハンス。それと、今回のイリスを護衛する騎士団の隊長のレノンが出席していた。
これ以上の人数を増やすのは、外に情報が漏れる可能性があるため最低限の人数で話し合いが行われていた。
「二回目の盗賊たちの襲撃以降、襲われなかったのが気になりますね」
そんなことを口にしたのは金色の髪を上にあげている好青年、レノンだった。俺よりも少し上くらいの年齢なのに、今回の任務の隊長を任されることになったということもあり、なんとも自信に満ちて堂々としている佇まいだった。
レノンが少し考えるようにしながらそんなことを言うと、その考えに同調するようにハンスが小さく頷いた。
「道中で、我々を襲えなくなった事情があったといった所でしょう」
普通に考えれば、俺たちが屋敷に籠る前に襲った方がイリスを誘拐できる確率は高い。
理由は単純で、移動中の俺たちは人数も多くはなかったし、イリスを守っていた外壁は馬車だけ。
こんな山奥の屋敷に籠られるよりも、もっと早く勝負を駆けたかったはずだ。
つまり、それをしなかった理由が何かあるということだ。
「二回とも返り討ちになったから、戦力をまとめてぶつけようって感じですかね」
「やはり、その可能性が高いかもしれませんね」
どうやら、俺とハンスの意見は同意見のようだった。
つまり、この先の考えていることも同じなのだろう。
俺は一瞬言葉にするかどうかを考えた後、諦めるように小さく息を吐いて言葉を続けた。
「ということは、この場所がバレてる可能性があるってことですか」
「……考えたくはありませんが、おそらくそうではないかと」
考えたくなかったことだが、認めるしかない事実。
一度体制を整えてから攻撃できるということは、俺たちの居場所が分からないとできない判断だ。
そして、それはこれから一気に盗賊たちが、この別荘を襲ってくるかもしれないという可能性を認めざるを得ないということだった。
「待ってください。お二人は騎士団の中に誰か裏切り者がいると仰るんですか?」
俺とハンスが最悪の事態を前に頭を抱えていると、レノンが焦った様子でそんな言葉を口にした。
まっすぐ疑うことを知らないような純粋な瞳は、仲間を疑う行為を知らないように澄んでいた。
「いえ、そういう訳ではないです。騎士団以外にもこの屋敷のことを知る者がいる。内部の誰かしらがリークした、といった所でしょう」
「で、ですが……」
未だに納得いっていない様子のレノンだったが、それでも現状を受け入れられないほど子供ではないようで、悔しそうに視線をこちらから逸らしていた。
そんなレノンをそのままに、ハンスはこちらに視線を向けて言葉を続けた。
「アイクさん、リリさん、ポチさん。あなた達にはイリスの部屋でイリスの警護をお願いします」
「分かりました。何か危険だと思ったら、俺も前線にいつでも出れるようにはしておきます」
ミノラル付近で捕まえた盗賊の話では、今回のイリスの誘拐にはただの盗賊以外に、裏傭兵団なる者も参戦しているかもしれないとのことだった。
もしも、以前にワルド王国に潜入したときのような男がいた場合、例えイリスを守れたとしても、ここにいる騎士団が全滅するという未来もあるかもしれない。
常に気は引き締めえとかねばならないだろう。
「イリスの部屋にベッドを人数分運んでいますので、おやすみの際もそちらをご了承ください」
「分かりましーーえ? イリスとリリとも同部屋ですか?」
「緊急事態なので仕方がありません。アイクさん達以外に頼れる人がいないのです。何卒お願い申し上げます」
ハンスはそう言うと、こちらに深々と頭を下げてきた。
誠心誠意心の籠ったお辞儀。それだというのに、どことなくその言葉が硬いような気もした。
「……くれぐれも、間違いはないようにお願いたします」
王族のイリスを異性と同じ寝床に着かせることへの執事としての葛藤と、イリスを守りたいという忠誠心。それと、依頼を受けてくれた俺たちに失礼な態度は取れない。
そんな感情に板挟みにされていたハンスの口からは、何とも形容しがたい凄みのある声が漏れていた。
深々と頭を下げたのは、見せられない表情を隠すためではないんだよな?
「は、はい」
思い出したのは顔も上げることができなくなった盗賊団の姿。
間違いがあったらどうなるのか。その盗賊団たちの姿を思いだすと、背筋が少しだけぞっとしてしまった。
なんか彼女の家のお父さんと対峙しているようだ。……いや、彼女なんかいたことはないんだけどな。
こうして、俺たちはイリスの部屋でイリスの警護に当たることになったのだった。
ミノラルから少し離れた山の奥。特産物も特色もないただの田舎町であるオリスという町。
そこにイリスの隠れ別荘という物があった。
「……やっぱり、でかいんだな」
「なんか少し神秘的ですね」
大きさで言えば、俺たちが普段住んでいるミノラルの屋敷の二倍ほどの大きさ。壁の色は白く、森にひっそりとある洋館のような雰囲気が出ていた。
いや、実際にそうなのか。
別荘に配置されている騎士団の数は中々のもので、ここに閉じこもっているだけで誘拐されることはないのではないかと思えてしまう。
これだけの数の騎士団を配置しても騒ぎになったりしないのは、この中が山の中だからなのだろう。
聞いた話によると、近隣の家はここからしばらく馬車を走らせないとないらしい。
もしかしたら、誰にも気づかれることなく、ひっそりと隠れることができるから、こんな場所に別荘を構えたのかもしれない。
「それでは、アイクさん、リリさん。別荘の中へご案内いたします」
そんなことを考えながら、リリとポチと別荘を眺めていると、すぐに俺たちの後ろにいたハンスにそう言われて、俺たちは別荘の中へ移動することになった。
「別荘の中で今後の方針について、話し合いをしましょう」
真剣な表情でそう口にしたハンスを見て、これからが依頼の本番であることを再度確認したのだった。
そして、俺たちは別荘の広間で作戦会議を行うことになった。
この場にいるのは『道化師の集い』とイリスとハンス。それと、今回のイリスを護衛する騎士団の隊長のレノンが出席していた。
これ以上の人数を増やすのは、外に情報が漏れる可能性があるため最低限の人数で話し合いが行われていた。
「二回目の盗賊たちの襲撃以降、襲われなかったのが気になりますね」
そんなことを口にしたのは金色の髪を上にあげている好青年、レノンだった。俺よりも少し上くらいの年齢なのに、今回の任務の隊長を任されることになったということもあり、なんとも自信に満ちて堂々としている佇まいだった。
レノンが少し考えるようにしながらそんなことを言うと、その考えに同調するようにハンスが小さく頷いた。
「道中で、我々を襲えなくなった事情があったといった所でしょう」
普通に考えれば、俺たちが屋敷に籠る前に襲った方がイリスを誘拐できる確率は高い。
理由は単純で、移動中の俺たちは人数も多くはなかったし、イリスを守っていた外壁は馬車だけ。
こんな山奥の屋敷に籠られるよりも、もっと早く勝負を駆けたかったはずだ。
つまり、それをしなかった理由が何かあるということだ。
「二回とも返り討ちになったから、戦力をまとめてぶつけようって感じですかね」
「やはり、その可能性が高いかもしれませんね」
どうやら、俺とハンスの意見は同意見のようだった。
つまり、この先の考えていることも同じなのだろう。
俺は一瞬言葉にするかどうかを考えた後、諦めるように小さく息を吐いて言葉を続けた。
「ということは、この場所がバレてる可能性があるってことですか」
「……考えたくはありませんが、おそらくそうではないかと」
考えたくなかったことだが、認めるしかない事実。
一度体制を整えてから攻撃できるということは、俺たちの居場所が分からないとできない判断だ。
そして、それはこれから一気に盗賊たちが、この別荘を襲ってくるかもしれないという可能性を認めざるを得ないということだった。
「待ってください。お二人は騎士団の中に誰か裏切り者がいると仰るんですか?」
俺とハンスが最悪の事態を前に頭を抱えていると、レノンが焦った様子でそんな言葉を口にした。
まっすぐ疑うことを知らないような純粋な瞳は、仲間を疑う行為を知らないように澄んでいた。
「いえ、そういう訳ではないです。騎士団以外にもこの屋敷のことを知る者がいる。内部の誰かしらがリークした、といった所でしょう」
「で、ですが……」
未だに納得いっていない様子のレノンだったが、それでも現状を受け入れられないほど子供ではないようで、悔しそうに視線をこちらから逸らしていた。
そんなレノンをそのままに、ハンスはこちらに視線を向けて言葉を続けた。
「アイクさん、リリさん、ポチさん。あなた達にはイリスの部屋でイリスの警護をお願いします」
「分かりました。何か危険だと思ったら、俺も前線にいつでも出れるようにはしておきます」
ミノラル付近で捕まえた盗賊の話では、今回のイリスの誘拐にはただの盗賊以外に、裏傭兵団なる者も参戦しているかもしれないとのことだった。
もしも、以前にワルド王国に潜入したときのような男がいた場合、例えイリスを守れたとしても、ここにいる騎士団が全滅するという未来もあるかもしれない。
常に気は引き締めえとかねばならないだろう。
「イリスの部屋にベッドを人数分運んでいますので、おやすみの際もそちらをご了承ください」
「分かりましーーえ? イリスとリリとも同部屋ですか?」
「緊急事態なので仕方がありません。アイクさん達以外に頼れる人がいないのです。何卒お願い申し上げます」
ハンスはそう言うと、こちらに深々と頭を下げてきた。
誠心誠意心の籠ったお辞儀。それだというのに、どことなくその言葉が硬いような気もした。
「……くれぐれも、間違いはないようにお願いたします」
王族のイリスを異性と同じ寝床に着かせることへの執事としての葛藤と、イリスを守りたいという忠誠心。それと、依頼を受けてくれた俺たちに失礼な態度は取れない。
そんな感情に板挟みにされていたハンスの口からは、何とも形容しがたい凄みのある声が漏れていた。
深々と頭を下げたのは、見せられない表情を隠すためではないんだよな?
「は、はい」
思い出したのは顔も上げることができなくなった盗賊団の姿。
間違いがあったらどうなるのか。その盗賊団たちの姿を思いだすと、背筋が少しだけぞっとしてしまった。
なんか彼女の家のお父さんと対峙しているようだ。……いや、彼女なんかいたことはないんだけどな。
こうして、俺たちはイリスの部屋でイリスの警護に当たることになったのだった。