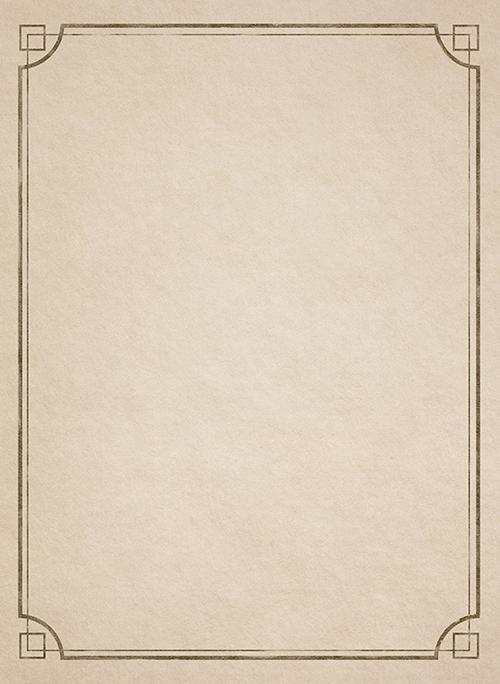一、同じ字を書くが、違う
A市内にある、とある花屋のドアを開ける者がいた。その日は日曜日で、店は定休日だ。ちゃんとドアノブには『本日定休日』と書かれた木の板も掛けられている。だがその者は、一瞬ためらっただけでドアを開ける事をやめはしなかった。
午前中はずっと雨が降り続け、正午を過ぎた今でもアスファルトの地面には空を写す小さな水たまりがいくつもあった。雲は徐々に消えて、青い空が顔を見せ始めている。せっかくの日曜日に降った雨のせいで外出をやめようか迷っていた人々は、次第に可能性を見出し、バスや車を活用して遠くに出かけるかも知れない。季節としては、八月に入ったばかりだ。家族でキャンプをしたり、海へ行ったり何だってできるだろう。
浮かれムードの世間とは対照的に、花屋のドアを開けた人物は恐ろしく静かだった。そっと開いたドアを、そっと閉じる。その動きにはどこか、尾行している何者かを警戒しているようにも感じられた。男で、まだ若い学生のようだが、やろうと思えば犯罪だってできるし、それによって警察か、或いは犯罪に関係する危険なグループから跡をつけられる事も、可能性としてはある。ただでさえ最近は、物騒な事件が多いのだ。
少年の入っていった花屋は、コンクリートで造られた二階建ての建物だった。形は殆ど真四角と言っていい。二階部分の一部が、たんこぶを思わせるようにして突き出ている。そのたんこぶの形も四角いし、他の部分に関しても、屋根が斜めになっていたりというような飾り気はない。随分機能性を重視したように思われる。この家の設計をした人物は、外見を重視した周りの家屋を嫌っているのかもしれない。四角く豆腐を思わせる、機能性重視の建築物にこそ価値を見出しているのかもしれない。
そんな建物の正面入り口が、閉まる。ドアの上部に取り付けてあったベルが小さな音を立てたが、とても小さい音だ。真下に立って、耳をすまさなければまず聞こえないだろう。それほどに小さい。
中に入った少年は、ドアの方を向いていた体を店内に向けた。明かりは点いていないからほんのわずかに薄暗いが、歩いて回る分には支障はない。窓から入る日の光が、十分なほどに中を照らしてくれている。
店内の中央部に、誰かが立っている。少年とは別の人物だ。
「おはよう。やっぱり涼太だった。手を振ったの見えた?」
そう言ったのは少年ではない。彼がここへ入った時既にいた人物の声だ。嬉しそうな感情が読み取れる声色で、女性の声だった。彼女は涼太と呼んだ少年のもとまで歩み寄っていく。灰色の床が靴底に叩かれて軽快な音を立てた。
「うん、外から見えた」
涼太は言った。そして頷いた。
「雨降ってたのに、自転車で来たの?」
「ちがうよ。雨が止んでから家を出た」
「雨が止んだの、ついさっきだよね」
「急いで来たんだ。約束の時間に間に合わせるために」
「真面目だね」
「そうかもしれない。でも、こころさんだって同じだよ」
涼太は、目の前に立っている女性をこころと呼んだ。こころは嬉しそうに笑い、そして手招きをして店の奥へと歩いていった。少し遅れて、涼太がその後ろを歩いた。
この二人の関係は、少し変わっている。少なくとも、街で偶然会って知り合ったという間柄ではない。
沖縄には、宇宙航空研究開発機構、つまりJAXAの施設が一箇所、存在している。沖縄宇宙通信所という施設で、通常は空高く飛んで地球の周りを周回している人工衛星の位置を正確に特定し、コースから逸れていたり何らかの機材トラブルがあった際、必要に応じて人工衛星に指示を与えるという役割を持っている。
そこでは、広報活動の一環として建物内に資料展示室を設けている。個人での見学は予約が要らず、料金も請求されない。団体での見学となると予約が必要という事だが、こちらも料金が発生するわけでもない。誰が、いつでも(勿論閉館までに間に合えばという事だが)気軽に見学を行えるのだ。
そこで、涼太とこころは出会った。初めはただの偶然だった。涼太もこころも、宇宙分野に強く関心を抱く人物であり、何度も施設を訪れる熱心な人間だ。週に一回、とまではいかなくとも、月に平均三回は見学に行っていた。
そこで、たまたま居合わせたのだ。初めて二人がすれ違ったのは、展示室の出入り口だった。涼太が中に入ろうと扉を開けると、同じように中から手を伸ばしていたこころと顔をあわせる。二人は驚いて、「すいません」などと小声で言い合いながらすれ違った。
それからしばらくして、二度目に会ったのも出入り口だ。今度は状況が違っていて、涼太が見学者用の簡単なアンケートに記入をしている最中に、扉を開けてこころが現れた。二人して「あ……」と声を漏らした。そこから見学に入るわけだが、涼太がロケットの模型を眺めているところにこころが話しかけた。涼太にすれば予想だにしない出来事だった。
「宇宙、お好きなんですか?」
緊張のために震える声で背後から言われて、彼は魂が抜け落ちてしまうくらいに驚いた。声こそ発しなかったが、その場で飛び上がりそうになった。すぐにこころが謝り、涼太も驚いてしまっただけですと返した。そこから、二人の交流は始まった。
二人は今後の宇宙開発の流れを予想しあったり、近年問題になっているスペースデブリについてを話しあった。簡単なクイズを出し合ってみたりもした。そうしているうちに、お互い相手がかなりの宇宙好きである事を知った。
共通の話題を持った、友人と呼べる域にまで達しているのかも知れない。涼太が一方的にそう思い始めていた時だ。四回目の会偶の際、こころは言った。
「今度、私の家に来ませんか」
涼太はまず、自分の耳を疑う事をしなくてはならなかった。自分は高校二年で、対するこころは(彼女の言葉を信じるとするならだが)大学一年生なのだ。一体、どういう心境で家に招こうなどと思い至ったのだろうか。
JAXAの資料展示室の中で出し抜けに行われた提案には、『はい』か『いいえ』をすぐに選べなかった。困った様子の涼太を見て、こころは謝った。それから、提案をした理由を説明した。
随分しどろもどろになって話してくれたから、涼太は言葉と言葉を繋げてわかりやすく要約した。
「つまり、最近家で不思議な事が起こっているから、原因を突き止めるのを手伝ってほしいっていう話で合ってる?」
こころは頷いた。涼太は彼女に対して敬語は使わない。それは彼女が望んだ事だった。
「最近、といっても一ヶ月くらい前に絵画を買ったんだけど、それから不思議な事が起こり始めて……。誰もいないはずなのに、家の中で音が鳴るの。足音みたいなのが、聞こえるの。一人で調べるのは怖いから、手伝ってほしいくて……」
お腹の辺りで組んだ指を見つめながら、言いにくそうにこころは言った。そのはずだ。こんな事、本来なら親しい友人や専門家の人にしか話せないはずだ。
何故自分に話したのか。彼には何となく予想できていた。
涼太は宇宙開発や天文学以外にも、興味を示しているものがある。それは所謂オカルト的なものだった。
本来なら、科学とは相反する所に位置する事柄だが、だからこそ彼は心惹かれていた。
日本が宇宙開発を始めてから六〇年以上になるにも関わらず、その科学力を持ってしても解明できない謎。そこに強く魅力を感じた。
涼太はインターネットでは飽き足らず、本屋で数冊のオカルト本を買った。そしてページを捲り、正体が判明していない謎たちと邂逅した。飽きる事はなかった。手元にある本を読み尽くすと、今度は別の本屋で数冊の本を購入した。
そこで手に取ったのは、地元である沖縄の噂話を集めたものだった。ここにある事を、ひょっとしたら自分で確かめたり検証したりできるかも知れないと思った。
試しに幾つかの話を読んで、該当する場所へと向かった。
本では実際の地名は伏せられていたが、話の特徴的な部分からおおよその場所は特定できた。
そのうちの一つに、A市のとある岬にある灯台の話を見つけたのだ。本によれば、灯台を眺めていると何かしら幻が見えるようになるという事らしかった。
理解し難い話だった。だが試してみる価値はあった。A市の灯台といえば、涼太の家から自転車でも行ける距離だったからだ。
そしてよく晴れた日に、涼太は自転車のペダルを漕いで灯台まで向かい、崖を眺め、写真を撮った。すると本当に、その場で幻のようなものが見えた。
ただの立ちくらみとか、そういうものではない。実際に何かが見えたのだ。
言葉表現するのは難しいが、あえてそうするのならあれは青い紐状の何かだった。何かの生き物の触手のようでもあった。周りにいた人達には何も変化が無かったから、見えていたのは涼太一人だけという事になる。あれはただの立ちくらみなどではない。確実に視界に移った幻のはずなのだ。
涼太はこの出来事を、こころに話していた。だからこそ、こころも思い切って家の事を話せたのかも知れない。
「涼太ってきっと、霊感あるんだよ。私に気づけなかった事にも、きっと気づける。だから、ちょっと力を貸してくれないかな」
藁にもすがる思い、という表現が似合う様を、涼太はこれまでに目撃した事はなかった。だからこの話を信じ、彼女を手伝う決心をした。
その一週間後に、涼太はこころの家を訪ねたのだった。連絡先は交換していて、お互いに予定を空けておいた。
「お邪魔します」
そう言って涼太は、会計のためにあるカウンターの奥へと入った。こころの家は花屋を営んでいて、家族の住む場所は店の上、建物の二階にあった。
「ど、どうぞ。汚い所ですけど……」
緊張のためか、こころが年下相手に敬語を使っていた。その事がますます、涼太にある事実を突き出していた。年上の女性の家に入るという事実だ。
二人は一階の玄関から階段を上がり、二階まで来た。居間のソファに座るようにここころに言われて、涼太はその通りにソファに腰を下ろした。それを確認して、こころはどこかへと行ってしまった。「ちょっとだけ待ってて」とだけ言い残して。
座ったソファは、高級感のあるものだった。他に座るためのものは無く、ソファの前には足の短いテーブルがある。さらに向こうには、大きな画面のテレビが置いてあった。何も映していない画面は、反射で涼太のあるがままを見せていた。「これが今のあなたの姿だよ」と無表情に言われているような気がして、思わず視線を逸らした。
逸らした先にあるのもまた、無表情な灰色の壁だった。見渡せば、そんな灰色だけが居間の空間を覆っていた。唯一、彼の背後の壁にはひまわりを描いた絵が飾られていた。教科書ほどの大きさしかないが、しっかり額装されて飾られている。
本来なら、無機質な空間の中その絵に温かみを覚えるはずなのだが、周囲があまりに無表情なためだろうか。絵を見ても、ちっとも気が休まる感じがない。寧ろ、ひまわりすら無表情に自分を監視しているような感覚があって、気味が悪い。
人様の家に上がっておいて失礼だろうが、よくこんな部屋で暮らせるものだと涼太は思った。
そこで、こころがやってきた。盆に載せた二つのグラスには、お茶が入っていた。こころは震える手でその二つをテーブルの上においた。そしてテーブルを挟んで涼太の向かい側に座った。そこには勿論、椅子もソファもない。絨毯すらない。盆を横に置いて、彼女は言った。
「今日は、晴れてくれて助かったよね」
「そうですね」
涼太はそう返した。こころは、目に見えて緊張している様子だった。本人が隠しているつもりなのかはわからないが、少なくとも側から見ればその事実は明白だ。敬語でなくなっている分、少しは和らいでいるのかも知れない。
「まさか、知り合った人と同じ苗字だとは思っても見なかったな。何だか不思議だよね」
「うん、僕もそう思うよ」
涼太は同調した。確かにその通りだった。
涼太の苗字は、キンジョウという。沖縄ではありふれた苗字であり、クラスに二人か三人は見かけるくらいのものだ。本土で言う所の加藤や田中のようなものだ。沖縄県民からしてみれば、そうした苗字の方が珍しく感じる。
そしてこころの苗字は、カネシロといった。
この二つは、発音こそ違うものである。沖縄には『兼城』と書いてカネシロと読む場合も存在する。だが二人の苗字というのは『金城』と書く。読み方は二人して違う。同じ字を書くが、違うのだ。
この事実は、四回目に会って、連絡先を交換する時に発見された。この時初めて二人とも名を名乗り、二人ともが同じ反応を示した。涼太が一瞬動きを止めた後、目を丸くして「へー」と声を漏らし、こころも殆ど同じタイミングで同様のリアクションをとった。こころの方は、何故だか嬉しそうだった。きっと、苗字の一致というのが家へ招く決定的な原動力になったに違いない。
そうして実際に、涼太はこころの家に、『金城家』に訪問している。
「それでね、早速本題に移りたいんだけど」
こころが突然、立ちあがった。合わせるように涼太も立ち上がり、後ろを振り返った。
「もしかして、話にあった絵画ってこれの事?」
そこには、先ほど視界に入ったあのひまわりの絵があった。自分には何の罪もないのだと言いたげに、壁に掛かったまま身動き一つしていない。
当然だ、動き出したら困る。
「そうなの。最近、これを買ったんだけど。あの、元々ある絵のコピーで、指で触っても絵の具がついたりはしないよ。でも、これがおうちにやって来てから、その、誰かの足音みたいなのが聞こえてくるようになって。ちょっと、怖いなって」
「こころさんってその、ご家族とかは……?」
「うん、私が小さい時に両親が離婚して、今はお母さんと二人で暮らしてる。お父さんの事は覚えてるけど、どこにいるのかわからない。ずっと会ってないから、正直生きているのかも……」
そこでこころは言葉を詰まらせた。涼太としては、家族の立てる足音という可能性の有無について尋ねたかっただけなのだが、随分と複雑な家庭事情を耳にしてしまった。絵画とは別件で、少しだけ気になる事が増えてしまった。
「お父さんの事はいいんだ。例えばお母さんが、夜に喉が渇いたり、お手洗いに行ったりする時の足音なんじゃないかって思っただけなんだ」
こころは首を振った。
「ううん、お母さんじゃない。足音は明るい時間にも聞こえる。夕方までお母さんは、下のお店で働くから」
涼太は手を額に当てた。購入した絵画がきっかけで物音がするというのだから、てっきり時間帯は夜を想像していた。こういう現象の相場は夜と決まっているのだ。その先入観というか、想像力不足は改めなくてはならない。
だから涼太が次にしたのは、幾つかの可能性を探り当てる事だった。
「お母さんが、家の方に忘れ物をして、仕事中だけど取りに戻ったとか」
「ないと思う。お母さん、私と違って結構しっかり者だし。今まで忘れ物なんてしたの見た事がない。時間にも正確で、私が中学校の時寝坊した事があったんだけど、その時だって」
「ああうん、わかった。それだけで十分だから。じゃあお母さんの可能性は、ないんだ」
こころは頷いた。
「こころさんって、普段昼間になっても家にいる事が多いの?」
「授業のある時間は、ちゃんと学校に行ってる。でも授業の前と後は、基本家にいる。毎週木曜日は授業がないから、ずっと家に、篭ってます……」
最後の方は、小さくてよく聞き取れなかった。だが知りたい事は把握した。
「なるほどな……」
正直、涼太は霊能力者でも幽霊研究家でもないし、探偵でも警察官でもない。他人の家で起きている謎の足音について、解決するための手立ては何も持ち合わせていない。客観的に状況を見て、当事者の見えていない角度から観察してアドバイスをするのが精一杯だ。
「で、でもね、時々下のお店でお母さんの手伝いはしてるよ? お母さんもちゃんとお駄賃くれるし、けっこういっぱいくれるの。だからアルバイトって無理にする必要もないっていうか……」
首を傾げる涼太の背後で、延々とこころは何かを話し続けていた。
A市内にある、とある花屋のドアを開ける者がいた。その日は日曜日で、店は定休日だ。ちゃんとドアノブには『本日定休日』と書かれた木の板も掛けられている。だがその者は、一瞬ためらっただけでドアを開ける事をやめはしなかった。
午前中はずっと雨が降り続け、正午を過ぎた今でもアスファルトの地面には空を写す小さな水たまりがいくつもあった。雲は徐々に消えて、青い空が顔を見せ始めている。せっかくの日曜日に降った雨のせいで外出をやめようか迷っていた人々は、次第に可能性を見出し、バスや車を活用して遠くに出かけるかも知れない。季節としては、八月に入ったばかりだ。家族でキャンプをしたり、海へ行ったり何だってできるだろう。
浮かれムードの世間とは対照的に、花屋のドアを開けた人物は恐ろしく静かだった。そっと開いたドアを、そっと閉じる。その動きにはどこか、尾行している何者かを警戒しているようにも感じられた。男で、まだ若い学生のようだが、やろうと思えば犯罪だってできるし、それによって警察か、或いは犯罪に関係する危険なグループから跡をつけられる事も、可能性としてはある。ただでさえ最近は、物騒な事件が多いのだ。
少年の入っていった花屋は、コンクリートで造られた二階建ての建物だった。形は殆ど真四角と言っていい。二階部分の一部が、たんこぶを思わせるようにして突き出ている。そのたんこぶの形も四角いし、他の部分に関しても、屋根が斜めになっていたりというような飾り気はない。随分機能性を重視したように思われる。この家の設計をした人物は、外見を重視した周りの家屋を嫌っているのかもしれない。四角く豆腐を思わせる、機能性重視の建築物にこそ価値を見出しているのかもしれない。
そんな建物の正面入り口が、閉まる。ドアの上部に取り付けてあったベルが小さな音を立てたが、とても小さい音だ。真下に立って、耳をすまさなければまず聞こえないだろう。それほどに小さい。
中に入った少年は、ドアの方を向いていた体を店内に向けた。明かりは点いていないからほんのわずかに薄暗いが、歩いて回る分には支障はない。窓から入る日の光が、十分なほどに中を照らしてくれている。
店内の中央部に、誰かが立っている。少年とは別の人物だ。
「おはよう。やっぱり涼太だった。手を振ったの見えた?」
そう言ったのは少年ではない。彼がここへ入った時既にいた人物の声だ。嬉しそうな感情が読み取れる声色で、女性の声だった。彼女は涼太と呼んだ少年のもとまで歩み寄っていく。灰色の床が靴底に叩かれて軽快な音を立てた。
「うん、外から見えた」
涼太は言った。そして頷いた。
「雨降ってたのに、自転車で来たの?」
「ちがうよ。雨が止んでから家を出た」
「雨が止んだの、ついさっきだよね」
「急いで来たんだ。約束の時間に間に合わせるために」
「真面目だね」
「そうかもしれない。でも、こころさんだって同じだよ」
涼太は、目の前に立っている女性をこころと呼んだ。こころは嬉しそうに笑い、そして手招きをして店の奥へと歩いていった。少し遅れて、涼太がその後ろを歩いた。
この二人の関係は、少し変わっている。少なくとも、街で偶然会って知り合ったという間柄ではない。
沖縄には、宇宙航空研究開発機構、つまりJAXAの施設が一箇所、存在している。沖縄宇宙通信所という施設で、通常は空高く飛んで地球の周りを周回している人工衛星の位置を正確に特定し、コースから逸れていたり何らかの機材トラブルがあった際、必要に応じて人工衛星に指示を与えるという役割を持っている。
そこでは、広報活動の一環として建物内に資料展示室を設けている。個人での見学は予約が要らず、料金も請求されない。団体での見学となると予約が必要という事だが、こちらも料金が発生するわけでもない。誰が、いつでも(勿論閉館までに間に合えばという事だが)気軽に見学を行えるのだ。
そこで、涼太とこころは出会った。初めはただの偶然だった。涼太もこころも、宇宙分野に強く関心を抱く人物であり、何度も施設を訪れる熱心な人間だ。週に一回、とまではいかなくとも、月に平均三回は見学に行っていた。
そこで、たまたま居合わせたのだ。初めて二人がすれ違ったのは、展示室の出入り口だった。涼太が中に入ろうと扉を開けると、同じように中から手を伸ばしていたこころと顔をあわせる。二人は驚いて、「すいません」などと小声で言い合いながらすれ違った。
それからしばらくして、二度目に会ったのも出入り口だ。今度は状況が違っていて、涼太が見学者用の簡単なアンケートに記入をしている最中に、扉を開けてこころが現れた。二人して「あ……」と声を漏らした。そこから見学に入るわけだが、涼太がロケットの模型を眺めているところにこころが話しかけた。涼太にすれば予想だにしない出来事だった。
「宇宙、お好きなんですか?」
緊張のために震える声で背後から言われて、彼は魂が抜け落ちてしまうくらいに驚いた。声こそ発しなかったが、その場で飛び上がりそうになった。すぐにこころが謝り、涼太も驚いてしまっただけですと返した。そこから、二人の交流は始まった。
二人は今後の宇宙開発の流れを予想しあったり、近年問題になっているスペースデブリについてを話しあった。簡単なクイズを出し合ってみたりもした。そうしているうちに、お互い相手がかなりの宇宙好きである事を知った。
共通の話題を持った、友人と呼べる域にまで達しているのかも知れない。涼太が一方的にそう思い始めていた時だ。四回目の会偶の際、こころは言った。
「今度、私の家に来ませんか」
涼太はまず、自分の耳を疑う事をしなくてはならなかった。自分は高校二年で、対するこころは(彼女の言葉を信じるとするならだが)大学一年生なのだ。一体、どういう心境で家に招こうなどと思い至ったのだろうか。
JAXAの資料展示室の中で出し抜けに行われた提案には、『はい』か『いいえ』をすぐに選べなかった。困った様子の涼太を見て、こころは謝った。それから、提案をした理由を説明した。
随分しどろもどろになって話してくれたから、涼太は言葉と言葉を繋げてわかりやすく要約した。
「つまり、最近家で不思議な事が起こっているから、原因を突き止めるのを手伝ってほしいっていう話で合ってる?」
こころは頷いた。涼太は彼女に対して敬語は使わない。それは彼女が望んだ事だった。
「最近、といっても一ヶ月くらい前に絵画を買ったんだけど、それから不思議な事が起こり始めて……。誰もいないはずなのに、家の中で音が鳴るの。足音みたいなのが、聞こえるの。一人で調べるのは怖いから、手伝ってほしいくて……」
お腹の辺りで組んだ指を見つめながら、言いにくそうにこころは言った。そのはずだ。こんな事、本来なら親しい友人や専門家の人にしか話せないはずだ。
何故自分に話したのか。彼には何となく予想できていた。
涼太は宇宙開発や天文学以外にも、興味を示しているものがある。それは所謂オカルト的なものだった。
本来なら、科学とは相反する所に位置する事柄だが、だからこそ彼は心惹かれていた。
日本が宇宙開発を始めてから六〇年以上になるにも関わらず、その科学力を持ってしても解明できない謎。そこに強く魅力を感じた。
涼太はインターネットでは飽き足らず、本屋で数冊のオカルト本を買った。そしてページを捲り、正体が判明していない謎たちと邂逅した。飽きる事はなかった。手元にある本を読み尽くすと、今度は別の本屋で数冊の本を購入した。
そこで手に取ったのは、地元である沖縄の噂話を集めたものだった。ここにある事を、ひょっとしたら自分で確かめたり検証したりできるかも知れないと思った。
試しに幾つかの話を読んで、該当する場所へと向かった。
本では実際の地名は伏せられていたが、話の特徴的な部分からおおよその場所は特定できた。
そのうちの一つに、A市のとある岬にある灯台の話を見つけたのだ。本によれば、灯台を眺めていると何かしら幻が見えるようになるという事らしかった。
理解し難い話だった。だが試してみる価値はあった。A市の灯台といえば、涼太の家から自転車でも行ける距離だったからだ。
そしてよく晴れた日に、涼太は自転車のペダルを漕いで灯台まで向かい、崖を眺め、写真を撮った。すると本当に、その場で幻のようなものが見えた。
ただの立ちくらみとか、そういうものではない。実際に何かが見えたのだ。
言葉表現するのは難しいが、あえてそうするのならあれは青い紐状の何かだった。何かの生き物の触手のようでもあった。周りにいた人達には何も変化が無かったから、見えていたのは涼太一人だけという事になる。あれはただの立ちくらみなどではない。確実に視界に移った幻のはずなのだ。
涼太はこの出来事を、こころに話していた。だからこそ、こころも思い切って家の事を話せたのかも知れない。
「涼太ってきっと、霊感あるんだよ。私に気づけなかった事にも、きっと気づける。だから、ちょっと力を貸してくれないかな」
藁にもすがる思い、という表現が似合う様を、涼太はこれまでに目撃した事はなかった。だからこの話を信じ、彼女を手伝う決心をした。
その一週間後に、涼太はこころの家を訪ねたのだった。連絡先は交換していて、お互いに予定を空けておいた。
「お邪魔します」
そう言って涼太は、会計のためにあるカウンターの奥へと入った。こころの家は花屋を営んでいて、家族の住む場所は店の上、建物の二階にあった。
「ど、どうぞ。汚い所ですけど……」
緊張のためか、こころが年下相手に敬語を使っていた。その事がますます、涼太にある事実を突き出していた。年上の女性の家に入るという事実だ。
二人は一階の玄関から階段を上がり、二階まで来た。居間のソファに座るようにここころに言われて、涼太はその通りにソファに腰を下ろした。それを確認して、こころはどこかへと行ってしまった。「ちょっとだけ待ってて」とだけ言い残して。
座ったソファは、高級感のあるものだった。他に座るためのものは無く、ソファの前には足の短いテーブルがある。さらに向こうには、大きな画面のテレビが置いてあった。何も映していない画面は、反射で涼太のあるがままを見せていた。「これが今のあなたの姿だよ」と無表情に言われているような気がして、思わず視線を逸らした。
逸らした先にあるのもまた、無表情な灰色の壁だった。見渡せば、そんな灰色だけが居間の空間を覆っていた。唯一、彼の背後の壁にはひまわりを描いた絵が飾られていた。教科書ほどの大きさしかないが、しっかり額装されて飾られている。
本来なら、無機質な空間の中その絵に温かみを覚えるはずなのだが、周囲があまりに無表情なためだろうか。絵を見ても、ちっとも気が休まる感じがない。寧ろ、ひまわりすら無表情に自分を監視しているような感覚があって、気味が悪い。
人様の家に上がっておいて失礼だろうが、よくこんな部屋で暮らせるものだと涼太は思った。
そこで、こころがやってきた。盆に載せた二つのグラスには、お茶が入っていた。こころは震える手でその二つをテーブルの上においた。そしてテーブルを挟んで涼太の向かい側に座った。そこには勿論、椅子もソファもない。絨毯すらない。盆を横に置いて、彼女は言った。
「今日は、晴れてくれて助かったよね」
「そうですね」
涼太はそう返した。こころは、目に見えて緊張している様子だった。本人が隠しているつもりなのかはわからないが、少なくとも側から見ればその事実は明白だ。敬語でなくなっている分、少しは和らいでいるのかも知れない。
「まさか、知り合った人と同じ苗字だとは思っても見なかったな。何だか不思議だよね」
「うん、僕もそう思うよ」
涼太は同調した。確かにその通りだった。
涼太の苗字は、キンジョウという。沖縄ではありふれた苗字であり、クラスに二人か三人は見かけるくらいのものだ。本土で言う所の加藤や田中のようなものだ。沖縄県民からしてみれば、そうした苗字の方が珍しく感じる。
そしてこころの苗字は、カネシロといった。
この二つは、発音こそ違うものである。沖縄には『兼城』と書いてカネシロと読む場合も存在する。だが二人の苗字というのは『金城』と書く。読み方は二人して違う。同じ字を書くが、違うのだ。
この事実は、四回目に会って、連絡先を交換する時に発見された。この時初めて二人とも名を名乗り、二人ともが同じ反応を示した。涼太が一瞬動きを止めた後、目を丸くして「へー」と声を漏らし、こころも殆ど同じタイミングで同様のリアクションをとった。こころの方は、何故だか嬉しそうだった。きっと、苗字の一致というのが家へ招く決定的な原動力になったに違いない。
そうして実際に、涼太はこころの家に、『金城家』に訪問している。
「それでね、早速本題に移りたいんだけど」
こころが突然、立ちあがった。合わせるように涼太も立ち上がり、後ろを振り返った。
「もしかして、話にあった絵画ってこれの事?」
そこには、先ほど視界に入ったあのひまわりの絵があった。自分には何の罪もないのだと言いたげに、壁に掛かったまま身動き一つしていない。
当然だ、動き出したら困る。
「そうなの。最近、これを買ったんだけど。あの、元々ある絵のコピーで、指で触っても絵の具がついたりはしないよ。でも、これがおうちにやって来てから、その、誰かの足音みたいなのが聞こえてくるようになって。ちょっと、怖いなって」
「こころさんってその、ご家族とかは……?」
「うん、私が小さい時に両親が離婚して、今はお母さんと二人で暮らしてる。お父さんの事は覚えてるけど、どこにいるのかわからない。ずっと会ってないから、正直生きているのかも……」
そこでこころは言葉を詰まらせた。涼太としては、家族の立てる足音という可能性の有無について尋ねたかっただけなのだが、随分と複雑な家庭事情を耳にしてしまった。絵画とは別件で、少しだけ気になる事が増えてしまった。
「お父さんの事はいいんだ。例えばお母さんが、夜に喉が渇いたり、お手洗いに行ったりする時の足音なんじゃないかって思っただけなんだ」
こころは首を振った。
「ううん、お母さんじゃない。足音は明るい時間にも聞こえる。夕方までお母さんは、下のお店で働くから」
涼太は手を額に当てた。購入した絵画がきっかけで物音がするというのだから、てっきり時間帯は夜を想像していた。こういう現象の相場は夜と決まっているのだ。その先入観というか、想像力不足は改めなくてはならない。
だから涼太が次にしたのは、幾つかの可能性を探り当てる事だった。
「お母さんが、家の方に忘れ物をして、仕事中だけど取りに戻ったとか」
「ないと思う。お母さん、私と違って結構しっかり者だし。今まで忘れ物なんてしたの見た事がない。時間にも正確で、私が中学校の時寝坊した事があったんだけど、その時だって」
「ああうん、わかった。それだけで十分だから。じゃあお母さんの可能性は、ないんだ」
こころは頷いた。
「こころさんって、普段昼間になっても家にいる事が多いの?」
「授業のある時間は、ちゃんと学校に行ってる。でも授業の前と後は、基本家にいる。毎週木曜日は授業がないから、ずっと家に、篭ってます……」
最後の方は、小さくてよく聞き取れなかった。だが知りたい事は把握した。
「なるほどな……」
正直、涼太は霊能力者でも幽霊研究家でもないし、探偵でも警察官でもない。他人の家で起きている謎の足音について、解決するための手立ては何も持ち合わせていない。客観的に状況を見て、当事者の見えていない角度から観察してアドバイスをするのが精一杯だ。
「で、でもね、時々下のお店でお母さんの手伝いはしてるよ? お母さんもちゃんとお駄賃くれるし、けっこういっぱいくれるの。だからアルバイトって無理にする必要もないっていうか……」
首を傾げる涼太の背後で、延々とこころは何かを話し続けていた。