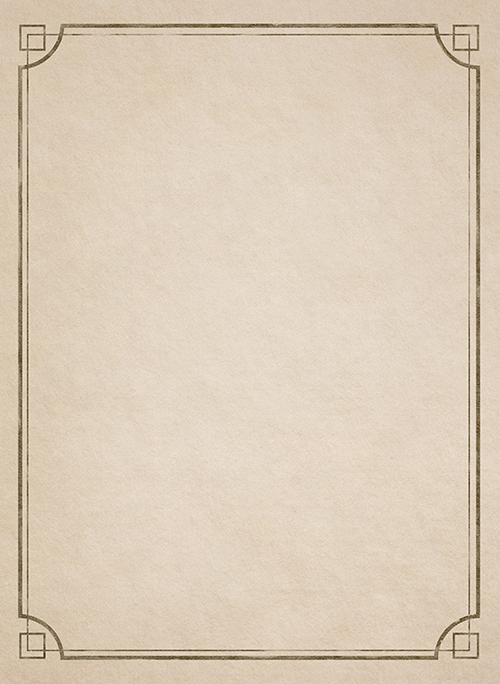一歩、僕が近づくと怯えたように後ろへ下がっていく。
周りのやじ馬は何も言わない。
いや、言わせないように怒気を僕が周囲に放っている。
「彼女の件について、キミに何か関係があったのか?そもそも、今話している相手が違う。別の相手の事と話をすり替える事をしないでくれるかな?」
「雲川、そこまで」
男子生徒にもう一歩、距離を詰めようとしたところで伸びてきた腕が僕を止める。
「何を怒っているのかわからないけれど、流石にやりすぎだって」
「瀬戸さん」
呆れた様子で僕に声をかけてきたのは瀬戸さんだ。
彼女は呆れた様子で周りを指さす。
「アンタ、本気で怒りかけているわよ?周りが怯えている」
「……あぁ」
どうやら僕は自分が思っていた以上に怒気を放っていたらしい。
一部の生徒が涙目になって、距離をとっている。
「そこのクズが何をしたのか知らないけれど」
「だ、誰がクズだ!」
僕が怒気を消した事で余裕が戻ってきたのか男子生徒が瀬戸さんに向かって叫ぶ。
「クズでしょ。雲川をここまで怒らせるなんて、アンタが最低な事をした以外にないし」
「な、なにを根拠に」
「名も知らないアンタよりも、アタシは雲川丈二という男を知っているし、信じているからよ」
「え?」
男子生徒に啖呵をきる瀬戸さん。
突然の事に目を白黒させている男子生徒だけれど、僕はそれだけで。
「プッ」
「ちょっと、なんで笑うのよ!?」
「いや、だって」
とても嬉しい。でも、面と向かって伝えることはできないだろうな。
僕らがわいわい騒いでいる間に男子生徒は逃げ出す。
「あ、逃げた!」
「別にいいよ。追いかける価値もない。最低な男だし」
「アンタ、凍真みたいな事言っているわよ?」
「え、そう?」
「嬉しそうな顔をしているわね。どんだけアイツの事、好きなのよ」
そういう瀬戸さんはどこか不満そうだ。
周りのやじ馬は何も言わない。
いや、言わせないように怒気を僕が周囲に放っている。
「彼女の件について、キミに何か関係があったのか?そもそも、今話している相手が違う。別の相手の事と話をすり替える事をしないでくれるかな?」
「雲川、そこまで」
男子生徒にもう一歩、距離を詰めようとしたところで伸びてきた腕が僕を止める。
「何を怒っているのかわからないけれど、流石にやりすぎだって」
「瀬戸さん」
呆れた様子で僕に声をかけてきたのは瀬戸さんだ。
彼女は呆れた様子で周りを指さす。
「アンタ、本気で怒りかけているわよ?周りが怯えている」
「……あぁ」
どうやら僕は自分が思っていた以上に怒気を放っていたらしい。
一部の生徒が涙目になって、距離をとっている。
「そこのクズが何をしたのか知らないけれど」
「だ、誰がクズだ!」
僕が怒気を消した事で余裕が戻ってきたのか男子生徒が瀬戸さんに向かって叫ぶ。
「クズでしょ。雲川をここまで怒らせるなんて、アンタが最低な事をした以外にないし」
「な、なにを根拠に」
「名も知らないアンタよりも、アタシは雲川丈二という男を知っているし、信じているからよ」
「え?」
男子生徒に啖呵をきる瀬戸さん。
突然の事に目を白黒させている男子生徒だけれど、僕はそれだけで。
「プッ」
「ちょっと、なんで笑うのよ!?」
「いや、だって」
とても嬉しい。でも、面と向かって伝えることはできないだろうな。
僕らがわいわい騒いでいる間に男子生徒は逃げ出す。
「あ、逃げた!」
「別にいいよ。追いかける価値もない。最低な男だし」
「アンタ、凍真みたいな事言っているわよ?」
「え、そう?」
「嬉しそうな顔をしているわね。どんだけアイツの事、好きなのよ」
そういう瀬戸さんはどこか不満そうだ。