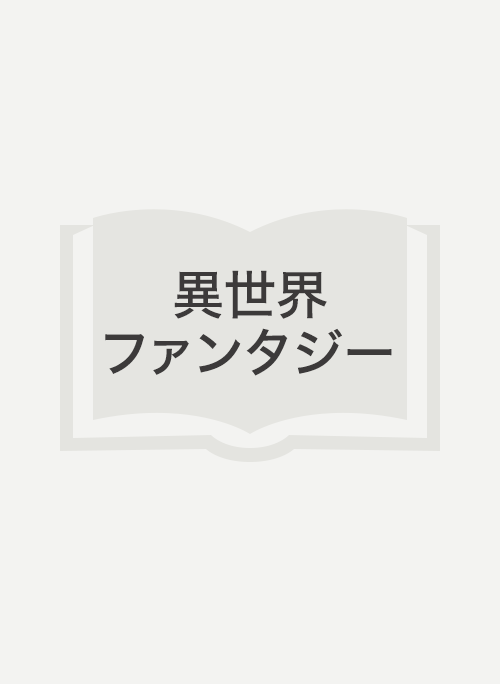前回のあらすじ
思わせぶりに経済の勉強をしておきながらきっと本編に出てこないんだろうなあ。
「お、なんだ経済のお勉強か?」
「世の中ままならねーよなーって話ですよ」
「違いない」
ハキロはちらりとムスコロを見た。ムスコロは一つ頷いた。
この二人に紙月と未来がかかわると、関係は途端に面倒になる。
紙月と未来は、ハキロには下手に出る。世話になったし、先輩冒険屋だからだ。一方でムスコロには対等か上からの目線となる。第一印象が最悪であったし、マウントの取り合いの結果、ムスコロが敗北したからだ。
ところがハキロにとってはムスコロが先輩冒険屋に当たる。極端にへりくだることはないが、それでも一目置いているし、ムスコロもハキロをやや下の後輩冒険屋として見る。
ものの見事に三つ巴の三角関係が発生してしまうのである。
なのでこういう時は、大抵の場合先輩にあたるムスコロが席を外して調整を取ることが多い。粗野なようで何かと機微のわかる男なのだ。今日もそのように、じゃあ俺はここらでとムスコロが席を外し、ハキロは頭をかいた。詫びを入れるのもおかしいし、礼を言うのもなおさらおかしいから、何というにも何も言えないのである。
「邪魔したかな」
「いえ、ちょうど話の切れ目でした」
「保険かなんかだったか。ちょうどそれにも関係する話でな」
退屈してると思って、とハキロが持ってきたのは、やはり依頼の話であった。
「俺達がいるこの辺りは、帝国でも西部という」
帝国は大雑把に言えば、帝都のある中央部、紙月たちのいる平野の多い西部、温暖だが特別なこともない東部、広く海に面し香辛料や交易品も多い南部、険しい寒さに包まれるが魔獣の素材が豊富な北部、そして竜たちのやってくる臥竜山脈を護るもののふたちの住まう辺境の六つに分かれる。
この西部の、さらに西方には、遊牧民たちが住まう平野地帯が広がっており、彼らは帝国民ともいえるし、そうでないともいえる、グレーな存在だ。そのさらに西方には広大な草原が広がる大叢海が横たわっており、そこには帝国とはまた別の勢力である国家が存在する。
遊牧国家アクチピトロである。
西部は長らくこの遊牧民たちに手を焼かされ、大統一時代にようやく和議を結んだとされる。
「その国と諍いでもあったんですか?」
「そう言う血の気の多い話じゃないんだ」
なんでも西部の遊牧民たちとその遊牧国家で、近く大きな部族会議が行われるらしいのだが、そんなおりに平原地帯に家畜を狙う魔獣が跋扈するようになってしまい、準備がなかなか進まないのだという。
「最初は保険が利いたらしいんだが、何度も繰り返されるうちに保険屋が出し渋るようになってきたらしくてな。それに金は帰ってきても、家畜は帰ってこない」
「成程、それで冒険屋の出番ってわけだ」
「そういうことだ」
シンプルな魔獣退治だと思えば、話は早い。しかしシンプルだからこそ疑問でもある。
「言っちゃあなんですけど、俺達ついには山まで殺したことになってるんですけど、そんなやつらを送り込んでいいんですか、この依頼」
「大層な看板だよ、全く。いやな、何しろ平原は広いんで、人手が欲しいんだが、何しろ相手は足の速い大嘴鶏を狙う足の速い魔獣だ。弓や魔法と言った遠距離攻撃の出来る連中が必要なんだが……」
成程、それで分かった。
「うちの事務所、偏ってますからねえ」
「そうなんだよ。俺も人のことは、言えないが」
なにしろ、《巨人の斧冒険屋事務所》である。おかみのアドゾからして斧遣いであり、ハキロもムスコロも、また所属する冒険屋は老いも若きもみな熟練の斧遣いなのである。
「一応少しはいるんだが、数が足りなくてな。シヅキならそのあたりどうとでもなるだろ」
「本音を言えば動きの速いのは得意じゃないんだけど……まあ斧遣いよりは、よほど」
「行ってくれるか」
「勿論。前の仕事の報酬は、暫く入りそうにないし」
「助かる」
それで、どんな魔獣が出るのかと言えば、大嘴鶏ばかりを狙う大嘴鶏食いであるという。人間も襲うは襲うらしいのだが、大きくて、足の速い大嘴鶏に釣られるらしく、積極的に追いかけては捕食してしまう、大型の鱗獣、つまり爬虫類の類であるらしい。
「なんとか食いっての、ついこの間も相手したばっかりだな」
「まあどんな物にでも天敵ってのはいらあな」
石食いの場合、天敵とかそういう問題ではないが。
「それで、難度は?」
「単体なら、まあ、丙種ってとこだな。ただ必ず二頭から三頭で組んでいる賢い連中で、足が速くて追いつきづらいもんだから、まず乙種は見ておいていいだろうな」
「どんな奴なんです」
「狗蜥蜴に似てるな。二足歩行の鱗獣で、もう少し細身だ」
「懐かないんですか?」
「懐かん。完全に肉食で気性が荒いし、群れ以外には気を許さないんだ」
「卵から育てるとか」
「狗蜥蜴と一緒で、卵胎生だ」
「成程」
さっくりとまとめれば、映画で見るような恐竜の相手をして来いと言うことらしい。大型恐竜でないだけましか。だがこの世界の人たち、特に冒険屋というものは結構頻繁にこのようなモンスターをハントしては生計を立てているようだから、決して無理難題ではない訳だ。
「どのくらいかかります?」
「何しろ遊牧してるから多少のずれはあるが、まあ馬車で五日くらいだろう」
早速、出ることになった。
用語解説
・遊牧国家アクチピトロ
大叢海を住処とする天狗たちの遊牧国家。王を頂点に、いくつかの大部族からなる。
その構成人数は帝国とは比べ物にならないほど小さいが、人族が生息不可能な大叢海を住処とすること、またその機動力をもってかなりの広範囲を攻撃範囲内に置けることなど、決して油断できない大勢力である。
・大嘴鶏食い
名前の通り、大嘴鶏をメインとして狙う、平原の狩猟者。
二足歩行の小型~中型の爬虫類で、いうなれば肉食恐竜のようなスタイル。
肉食獣であるし、本来はそこまで増えることはないはずである。
思わせぶりに経済の勉強をしておきながらきっと本編に出てこないんだろうなあ。
「お、なんだ経済のお勉強か?」
「世の中ままならねーよなーって話ですよ」
「違いない」
ハキロはちらりとムスコロを見た。ムスコロは一つ頷いた。
この二人に紙月と未来がかかわると、関係は途端に面倒になる。
紙月と未来は、ハキロには下手に出る。世話になったし、先輩冒険屋だからだ。一方でムスコロには対等か上からの目線となる。第一印象が最悪であったし、マウントの取り合いの結果、ムスコロが敗北したからだ。
ところがハキロにとってはムスコロが先輩冒険屋に当たる。極端にへりくだることはないが、それでも一目置いているし、ムスコロもハキロをやや下の後輩冒険屋として見る。
ものの見事に三つ巴の三角関係が発生してしまうのである。
なのでこういう時は、大抵の場合先輩にあたるムスコロが席を外して調整を取ることが多い。粗野なようで何かと機微のわかる男なのだ。今日もそのように、じゃあ俺はここらでとムスコロが席を外し、ハキロは頭をかいた。詫びを入れるのもおかしいし、礼を言うのもなおさらおかしいから、何というにも何も言えないのである。
「邪魔したかな」
「いえ、ちょうど話の切れ目でした」
「保険かなんかだったか。ちょうどそれにも関係する話でな」
退屈してると思って、とハキロが持ってきたのは、やはり依頼の話であった。
「俺達がいるこの辺りは、帝国でも西部という」
帝国は大雑把に言えば、帝都のある中央部、紙月たちのいる平野の多い西部、温暖だが特別なこともない東部、広く海に面し香辛料や交易品も多い南部、険しい寒さに包まれるが魔獣の素材が豊富な北部、そして竜たちのやってくる臥竜山脈を護るもののふたちの住まう辺境の六つに分かれる。
この西部の、さらに西方には、遊牧民たちが住まう平野地帯が広がっており、彼らは帝国民ともいえるし、そうでないともいえる、グレーな存在だ。そのさらに西方には広大な草原が広がる大叢海が横たわっており、そこには帝国とはまた別の勢力である国家が存在する。
遊牧国家アクチピトロである。
西部は長らくこの遊牧民たちに手を焼かされ、大統一時代にようやく和議を結んだとされる。
「その国と諍いでもあったんですか?」
「そう言う血の気の多い話じゃないんだ」
なんでも西部の遊牧民たちとその遊牧国家で、近く大きな部族会議が行われるらしいのだが、そんなおりに平原地帯に家畜を狙う魔獣が跋扈するようになってしまい、準備がなかなか進まないのだという。
「最初は保険が利いたらしいんだが、何度も繰り返されるうちに保険屋が出し渋るようになってきたらしくてな。それに金は帰ってきても、家畜は帰ってこない」
「成程、それで冒険屋の出番ってわけだ」
「そういうことだ」
シンプルな魔獣退治だと思えば、話は早い。しかしシンプルだからこそ疑問でもある。
「言っちゃあなんですけど、俺達ついには山まで殺したことになってるんですけど、そんなやつらを送り込んでいいんですか、この依頼」
「大層な看板だよ、全く。いやな、何しろ平原は広いんで、人手が欲しいんだが、何しろ相手は足の速い大嘴鶏を狙う足の速い魔獣だ。弓や魔法と言った遠距離攻撃の出来る連中が必要なんだが……」
成程、それで分かった。
「うちの事務所、偏ってますからねえ」
「そうなんだよ。俺も人のことは、言えないが」
なにしろ、《巨人の斧冒険屋事務所》である。おかみのアドゾからして斧遣いであり、ハキロもムスコロも、また所属する冒険屋は老いも若きもみな熟練の斧遣いなのである。
「一応少しはいるんだが、数が足りなくてな。シヅキならそのあたりどうとでもなるだろ」
「本音を言えば動きの速いのは得意じゃないんだけど……まあ斧遣いよりは、よほど」
「行ってくれるか」
「勿論。前の仕事の報酬は、暫く入りそうにないし」
「助かる」
それで、どんな魔獣が出るのかと言えば、大嘴鶏ばかりを狙う大嘴鶏食いであるという。人間も襲うは襲うらしいのだが、大きくて、足の速い大嘴鶏に釣られるらしく、積極的に追いかけては捕食してしまう、大型の鱗獣、つまり爬虫類の類であるらしい。
「なんとか食いっての、ついこの間も相手したばっかりだな」
「まあどんな物にでも天敵ってのはいらあな」
石食いの場合、天敵とかそういう問題ではないが。
「それで、難度は?」
「単体なら、まあ、丙種ってとこだな。ただ必ず二頭から三頭で組んでいる賢い連中で、足が速くて追いつきづらいもんだから、まず乙種は見ておいていいだろうな」
「どんな奴なんです」
「狗蜥蜴に似てるな。二足歩行の鱗獣で、もう少し細身だ」
「懐かないんですか?」
「懐かん。完全に肉食で気性が荒いし、群れ以外には気を許さないんだ」
「卵から育てるとか」
「狗蜥蜴と一緒で、卵胎生だ」
「成程」
さっくりとまとめれば、映画で見るような恐竜の相手をして来いと言うことらしい。大型恐竜でないだけましか。だがこの世界の人たち、特に冒険屋というものは結構頻繁にこのようなモンスターをハントしては生計を立てているようだから、決して無理難題ではない訳だ。
「どのくらいかかります?」
「何しろ遊牧してるから多少のずれはあるが、まあ馬車で五日くらいだろう」
早速、出ることになった。
用語解説
・遊牧国家アクチピトロ
大叢海を住処とする天狗たちの遊牧国家。王を頂点に、いくつかの大部族からなる。
その構成人数は帝国とは比べ物にならないほど小さいが、人族が生息不可能な大叢海を住処とすること、またその機動力をもってかなりの広範囲を攻撃範囲内に置けることなど、決して油断できない大勢力である。
・大嘴鶏食い
名前の通り、大嘴鶏をメインとして狙う、平原の狩猟者。
二足歩行の小型~中型の爬虫類で、いうなれば肉食恐竜のようなスタイル。
肉食獣であるし、本来はそこまで増えることはないはずである。