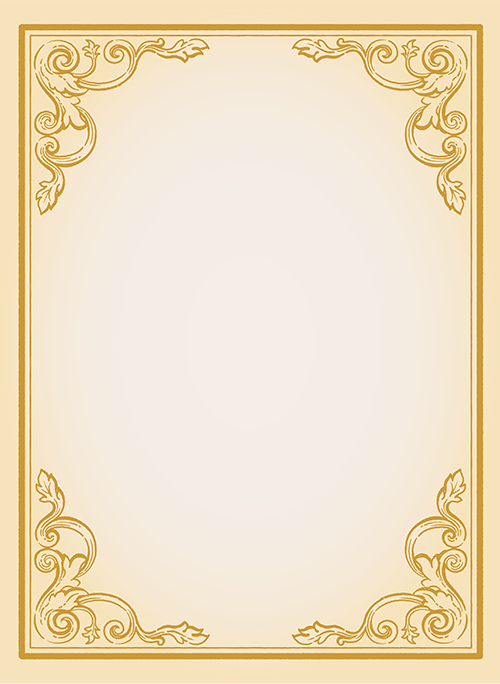家族がいなくなったあの日から、危険を予知することができるようになった。
例えば、角を曲がった先から勢いよく自転車が現れるとき、そのまま歩いているとぶつかり怪我をするだろう。そんなとき、僕の目の前に『!』が現れる。最初はわけがわからなかったが、徐々にそれが危険信号であることを理解した。
視界に突然『!』が現れたとき、僕の身に何かが起きる。雨の日のツルツル滑る鉄板の上で滑ったり、信号無視して突っ込んできた自転車とぶつかりそうになったり、そういったことを未然に防げてしまうのだ。便利な能力だ。
おかげでこの一年間、かすり傷一つもしていない気がする。自分の血の色は本当に真っ赤なのか記憶が定かでない。もしかしたら、青や紫、はたまた黄だったかもしれない。
この能力に目覚めたことは、誰にも言っていない。当然だ。俺は危険がわかるんです、そんなことを言い出して、誰が信じる? きっと俺が当事者ではなく、聞かされる立場であれば、一切信じない。そんなフィクションの世界にありそうな話を本気で信じる奴がいたら、その話を持ち出す奴よりヤバい。
これは俺だけに与えられた能力だろう。
『!』
ほら、出た。
学校に登校中の危険物なんか一切見当たらない歩道。車道と近いけれど、前からも後ろからも車は来ていない。となると、俺自身が原因で怪我をすることになる。
軽く頭を捻らせて考え、俯く。
靴紐が解けていた。きっとこのまま歩くことで、靴紐を踏んで、転けることになり、怪我をする。こういう未来が待っていたのだろう。
本当に便利だと思う。
靴紐をしっかり結び、遅れないように小走りで学校に向かう。
上履きに履き替え、教室に入っても、誰も俺と目を合わそうとしない。俺は誰にも挨拶することなく、自分の席に座る。窓側の席である僕の右隣は誰もいなかった気がするけど、綺麗な机が置かれていた。それ以外は、いつも通り。普段と何ら代わり映えのしない日常だ。
これが日常となったのは、家族が一年前に交通事故にあって死んだときからだ。俺だけを残して、父さん、母さん、そして姉貴。俺はたまたま家にいたから、事故に巻き込まれずに済んだが、果たしてそれが俺にとって良かったのかはわからない。
地元の新聞で取り上げられたからなのか、俺の家族が事故に遭ったことはすぐに広まった。そのこともあって、みんな俺との距離感、接し方がわからなくなって、話しかけられることはなくなった。
別にクラスの全員から無視されているわけではない。いじめとかそういうわけではないのだ。避けられている、と表現した方が適切なのかもしれない。用があって俺から話しかければ応えてくれるし、逆も然りだ。用があって、話しかけられることくらいはある。けれど、プライベートな会話をする人は一人もいなくて、どれも事務的な会話だった。
それでいい。あまり誰かと話す気になれない。誰かと深く関わることで、失うときのより一層深まる。俺はそれを知っているから、関係は希薄であればあるほどいいと思っている。日常生活に支障をきたさない程度の会話で十分だ。深く関わろうとなんかしてはいけない。
教室のざわつきに負けないくらいセミがうるさくさざめく。セミの鳴き声はどうして暑さを掻き立てるのだろう。できれば、合唱をやめて、大人しくして欲しい。そうすればきっと体感温度三度は下がる。
透き通るような青で塗られた空を窓から眺めていると、教室の扉が開き、先生が入ってきた。その瞬間、うるさかった教室は一瞬で静まり返り、セミの鳴き声だけが響いた。
俺も視線を教室内に戻すと、見慣れない女子生徒が一人立っていた。転校生だろうか?
「えー、今日からうちに転校してきた、桜井さんだ」
淡々と喋る担任が、教壇から下りて、転校生に上るように促した。
教卓で半分くらいは見えないが、顔はさっきよりもよく見えた。
身長はそれほど高くなく、小柄。真っ黒な髪は肩下くらいのセミロング。その艶のある真っ黒な髪とは対照的に、日焼けとは無縁そうな白い肌。綺麗や美人とか、そういう言葉よりも、可愛いという言葉が似合う人だった。
きっとすぐに男子から人気が出ることは容易に想像することができた。現に、普段静かに行われるホームルームが少しざわついている。転校生が来たから、というのもあるだろうが、男子のこそこそ話す声は嬉々としているようだった。
「今日からこのクラスでお世話になります、桜井萌笑って言います。一日でも早くクラスに馴染んでいきたいなって思います。よ、よろしくお願いします」
ぺこりと頭を下げた桜井さんは少し緊張しているようだった。笑顔もぎこちない。転校したことがない俺にはわからない感覚だ。
クラスから拍手が起こり、頭を上げた桜井さんは先ほどよりは顔が柔らかくなっていた気がする。少し緊張が和らいだのだろう。
「じゃあ、そこに座ってくれ。長谷部の隣」
担任が指差したのは、俺の隣の席。そんな気はしていた。見慣れない机が隣にあったし、転校生と紹介された段階で納得した。
桜井さんは、はい、と言い、すたすた俺の方に歩いてくる。クラスの全視線が彼女に集まっているようだった。近くにつれて、俺も視界に入るわけで、誰も見ていないことはわかっていても、少し居心地が悪くなった。
彼女はカバンを机にかけて、席に座る前に一度こちらを見た。一瞬、目を見開いた気がしたけど、俺の気のせいだったかもしれない。
クラスの男子からは、長谷部いいなー、という羨ましがる声が聞こえてくる。変わってあげられるのなら、変わってあげるのに。そんなことをこの場で言えば、桜井さんは傷つくだろうし、わざわざ口には出さない。人との関わりを絶ったとしても、それは人を傷つけていい理由にはならないから。
「教科書とかはまだ届いてないと思うから、長谷部。届くまで見せてやれ」
「はい」
俺が少し気怠そうに返事すると、隣の彼女は「ごめんね」と言った。
『!』
彼女がこちらを向いたとき、一瞬だけ見えた。すぐに消えたから気のせいかもしれないけど、いつもの危険予知能力だったと思う。すぐに消えたということは、危険は去ったということだろうか?
まあ、危険が身近にないのなら、それほど気にすることでもないか。そう思い、あまり考えないことにした。
一限目は、現代文。何をしていても怒らない先生だし、当てられることもほとんどない。ぼーっと外を眺めていると、いつの間にか授業が終わっていることが多かった。
だが、今日は隣の転校生に教科書を見せてあげる必要がある。机を近づけて、現代文の教科書を開く。
授業は滞りなく進み、三十分ほどが経過したとき、一枚の紙切れを渡された。
『長谷部くんの下の名前教えて???』
紙切れにはそう書かれていた。渡してきた彼女は、ニコッと笑った。
『長谷部晴翔』
俺はそれだけ書いて、彼女に渡した。それを見た彼女は、なるほど、と言わんばかりに頭を縦に振った。
少ししたら、また紙切れが俺の机に置かれた。
『晴翔くんは、不真面目なの??? 全然ノート取ってないよね』
いきなり下の名前で呼んでくる彼女は、かなりフレンドリーな体質なのかもしれない。要注意だな。
正直、避けたいところだが、きっと彼女は傷つく。人は興味のない相手であったとしても、無視されたら傷つくものだ。
適度な関係を保つことを忘れないようにしよう。
『そういう桜井さんも授業聞かずに俺と会話してる』
『前の学校でこの範囲習ってたから、暇なんだよー。しりとりでもする?』
『しない』
俺はデカデカとそう書き、余白を残さなかった。隣の彼女は、不満げだったけれど、気にせず授業に戻った。なんだか意識を授業に向けると、いつも以上に集中することができた。そこからの内容はしっかりノートを取った。
桜井さんが転校してきた日は、休憩時間になるたびに彼女は囲まれており、少し困っていた。そこで手を差し伸べるほど関係があるわけではないし、そもそもそこまでの関係性にはなりたくない。
昼休憩は校舎の最奥にある屋上につながる階段に逃げた。屋上が開放されていれば、きっとそこで過ごすのだろうけど、しっかり施錠されているので、仕方なく階段に座り、休憩時間を潰す。
とてもじゃないけれど、彼女が来たことでいつも以上に騒がしい教室で過ごすはできなかった。
ここは静かだし、落ち着ける。セミの声もほとんど聞こえない。
俺は自販機で買った紙パックのいちごミルクを飲んでいると、足音が近づいてきた。ここは静かだから、よく響き、すぐにわかる。誰だ?
「いた!」
ひょっこり顔を覗かせて、そう言ったのは、桜井さんだった。口ぶりから俺を探していたみたいだけど、何か用だろうか?
「こんなところに何しに来たの」
「こんなところってわかってるなら、どうしているの?」
悪気なく、無邪気な表情で彼女は訊いた。
「まずは俺の質問に答えてよ」
「そうだなぁ。晴翔くんを探してた」
「どうして」
「だって、仲良くなりたかったから」
仲良く? 俺と? あれだけクラスメイトから囲まれていたのだから、あの中の誰かと仲良くすればいいのに、わざわざ俺を探してまで仲良くしようとする意図はなんなんだろう。
「どうして、俺と」
「なんだか私と似てる気がしたから」
「はぁ……」
彼女と俺のどこが似ているのだろう。明るい彼女とは違い、陰鬱な雰囲気を纏っている俺とでは、似ている要素が一ミリ足りともない。
どういう思考回路をしているのか心配になる。
「君と仲良くなりたいの!」
「お好きにどうぞ」
「やったねっ」
きっとすぐに愛想を尽かして、俺に話しかけて来なくなるだろう。こんな無愛想にしていたら楽しくもないはずだ。
彼女はぐいぐい距離感を詰めてこようとする。やっぱり、危ない存在かもしれない。
『桜井萌笑さん、桜井萌笑さん。職員室まで来てください。繰り返します──』
校内放送だ。転校初日で、色々配布物とかあるのだろう。
彼女の方に目をやると、嫌そうな顔をしている。喋らなくても何を考えているのか大体わかりそうだ。
「はぁ……、じゃあね」
遥々校舎の最奥まで来たというのに、ものの数分で引き返すことになったら、確かに俺もこうなるかもしれない。彼女の背中は幾分老けたように感じられた。
『!』
まただ。一瞬見えて、一瞬で消える。
彼女の後ろ姿が見えなくなった頃には消えていて、俺の頭には『?』しか浮かばなかった。なんなんだろう。
例えば、角を曲がった先から勢いよく自転車が現れるとき、そのまま歩いているとぶつかり怪我をするだろう。そんなとき、僕の目の前に『!』が現れる。最初はわけがわからなかったが、徐々にそれが危険信号であることを理解した。
視界に突然『!』が現れたとき、僕の身に何かが起きる。雨の日のツルツル滑る鉄板の上で滑ったり、信号無視して突っ込んできた自転車とぶつかりそうになったり、そういったことを未然に防げてしまうのだ。便利な能力だ。
おかげでこの一年間、かすり傷一つもしていない気がする。自分の血の色は本当に真っ赤なのか記憶が定かでない。もしかしたら、青や紫、はたまた黄だったかもしれない。
この能力に目覚めたことは、誰にも言っていない。当然だ。俺は危険がわかるんです、そんなことを言い出して、誰が信じる? きっと俺が当事者ではなく、聞かされる立場であれば、一切信じない。そんなフィクションの世界にありそうな話を本気で信じる奴がいたら、その話を持ち出す奴よりヤバい。
これは俺だけに与えられた能力だろう。
『!』
ほら、出た。
学校に登校中の危険物なんか一切見当たらない歩道。車道と近いけれど、前からも後ろからも車は来ていない。となると、俺自身が原因で怪我をすることになる。
軽く頭を捻らせて考え、俯く。
靴紐が解けていた。きっとこのまま歩くことで、靴紐を踏んで、転けることになり、怪我をする。こういう未来が待っていたのだろう。
本当に便利だと思う。
靴紐をしっかり結び、遅れないように小走りで学校に向かう。
上履きに履き替え、教室に入っても、誰も俺と目を合わそうとしない。俺は誰にも挨拶することなく、自分の席に座る。窓側の席である僕の右隣は誰もいなかった気がするけど、綺麗な机が置かれていた。それ以外は、いつも通り。普段と何ら代わり映えのしない日常だ。
これが日常となったのは、家族が一年前に交通事故にあって死んだときからだ。俺だけを残して、父さん、母さん、そして姉貴。俺はたまたま家にいたから、事故に巻き込まれずに済んだが、果たしてそれが俺にとって良かったのかはわからない。
地元の新聞で取り上げられたからなのか、俺の家族が事故に遭ったことはすぐに広まった。そのこともあって、みんな俺との距離感、接し方がわからなくなって、話しかけられることはなくなった。
別にクラスの全員から無視されているわけではない。いじめとかそういうわけではないのだ。避けられている、と表現した方が適切なのかもしれない。用があって俺から話しかければ応えてくれるし、逆も然りだ。用があって、話しかけられることくらいはある。けれど、プライベートな会話をする人は一人もいなくて、どれも事務的な会話だった。
それでいい。あまり誰かと話す気になれない。誰かと深く関わることで、失うときのより一層深まる。俺はそれを知っているから、関係は希薄であればあるほどいいと思っている。日常生活に支障をきたさない程度の会話で十分だ。深く関わろうとなんかしてはいけない。
教室のざわつきに負けないくらいセミがうるさくさざめく。セミの鳴き声はどうして暑さを掻き立てるのだろう。できれば、合唱をやめて、大人しくして欲しい。そうすればきっと体感温度三度は下がる。
透き通るような青で塗られた空を窓から眺めていると、教室の扉が開き、先生が入ってきた。その瞬間、うるさかった教室は一瞬で静まり返り、セミの鳴き声だけが響いた。
俺も視線を教室内に戻すと、見慣れない女子生徒が一人立っていた。転校生だろうか?
「えー、今日からうちに転校してきた、桜井さんだ」
淡々と喋る担任が、教壇から下りて、転校生に上るように促した。
教卓で半分くらいは見えないが、顔はさっきよりもよく見えた。
身長はそれほど高くなく、小柄。真っ黒な髪は肩下くらいのセミロング。その艶のある真っ黒な髪とは対照的に、日焼けとは無縁そうな白い肌。綺麗や美人とか、そういう言葉よりも、可愛いという言葉が似合う人だった。
きっとすぐに男子から人気が出ることは容易に想像することができた。現に、普段静かに行われるホームルームが少しざわついている。転校生が来たから、というのもあるだろうが、男子のこそこそ話す声は嬉々としているようだった。
「今日からこのクラスでお世話になります、桜井萌笑って言います。一日でも早くクラスに馴染んでいきたいなって思います。よ、よろしくお願いします」
ぺこりと頭を下げた桜井さんは少し緊張しているようだった。笑顔もぎこちない。転校したことがない俺にはわからない感覚だ。
クラスから拍手が起こり、頭を上げた桜井さんは先ほどよりは顔が柔らかくなっていた気がする。少し緊張が和らいだのだろう。
「じゃあ、そこに座ってくれ。長谷部の隣」
担任が指差したのは、俺の隣の席。そんな気はしていた。見慣れない机が隣にあったし、転校生と紹介された段階で納得した。
桜井さんは、はい、と言い、すたすた俺の方に歩いてくる。クラスの全視線が彼女に集まっているようだった。近くにつれて、俺も視界に入るわけで、誰も見ていないことはわかっていても、少し居心地が悪くなった。
彼女はカバンを机にかけて、席に座る前に一度こちらを見た。一瞬、目を見開いた気がしたけど、俺の気のせいだったかもしれない。
クラスの男子からは、長谷部いいなー、という羨ましがる声が聞こえてくる。変わってあげられるのなら、変わってあげるのに。そんなことをこの場で言えば、桜井さんは傷つくだろうし、わざわざ口には出さない。人との関わりを絶ったとしても、それは人を傷つけていい理由にはならないから。
「教科書とかはまだ届いてないと思うから、長谷部。届くまで見せてやれ」
「はい」
俺が少し気怠そうに返事すると、隣の彼女は「ごめんね」と言った。
『!』
彼女がこちらを向いたとき、一瞬だけ見えた。すぐに消えたから気のせいかもしれないけど、いつもの危険予知能力だったと思う。すぐに消えたということは、危険は去ったということだろうか?
まあ、危険が身近にないのなら、それほど気にすることでもないか。そう思い、あまり考えないことにした。
一限目は、現代文。何をしていても怒らない先生だし、当てられることもほとんどない。ぼーっと外を眺めていると、いつの間にか授業が終わっていることが多かった。
だが、今日は隣の転校生に教科書を見せてあげる必要がある。机を近づけて、現代文の教科書を開く。
授業は滞りなく進み、三十分ほどが経過したとき、一枚の紙切れを渡された。
『長谷部くんの下の名前教えて???』
紙切れにはそう書かれていた。渡してきた彼女は、ニコッと笑った。
『長谷部晴翔』
俺はそれだけ書いて、彼女に渡した。それを見た彼女は、なるほど、と言わんばかりに頭を縦に振った。
少ししたら、また紙切れが俺の机に置かれた。
『晴翔くんは、不真面目なの??? 全然ノート取ってないよね』
いきなり下の名前で呼んでくる彼女は、かなりフレンドリーな体質なのかもしれない。要注意だな。
正直、避けたいところだが、きっと彼女は傷つく。人は興味のない相手であったとしても、無視されたら傷つくものだ。
適度な関係を保つことを忘れないようにしよう。
『そういう桜井さんも授業聞かずに俺と会話してる』
『前の学校でこの範囲習ってたから、暇なんだよー。しりとりでもする?』
『しない』
俺はデカデカとそう書き、余白を残さなかった。隣の彼女は、不満げだったけれど、気にせず授業に戻った。なんだか意識を授業に向けると、いつも以上に集中することができた。そこからの内容はしっかりノートを取った。
桜井さんが転校してきた日は、休憩時間になるたびに彼女は囲まれており、少し困っていた。そこで手を差し伸べるほど関係があるわけではないし、そもそもそこまでの関係性にはなりたくない。
昼休憩は校舎の最奥にある屋上につながる階段に逃げた。屋上が開放されていれば、きっとそこで過ごすのだろうけど、しっかり施錠されているので、仕方なく階段に座り、休憩時間を潰す。
とてもじゃないけれど、彼女が来たことでいつも以上に騒がしい教室で過ごすはできなかった。
ここは静かだし、落ち着ける。セミの声もほとんど聞こえない。
俺は自販機で買った紙パックのいちごミルクを飲んでいると、足音が近づいてきた。ここは静かだから、よく響き、すぐにわかる。誰だ?
「いた!」
ひょっこり顔を覗かせて、そう言ったのは、桜井さんだった。口ぶりから俺を探していたみたいだけど、何か用だろうか?
「こんなところに何しに来たの」
「こんなところってわかってるなら、どうしているの?」
悪気なく、無邪気な表情で彼女は訊いた。
「まずは俺の質問に答えてよ」
「そうだなぁ。晴翔くんを探してた」
「どうして」
「だって、仲良くなりたかったから」
仲良く? 俺と? あれだけクラスメイトから囲まれていたのだから、あの中の誰かと仲良くすればいいのに、わざわざ俺を探してまで仲良くしようとする意図はなんなんだろう。
「どうして、俺と」
「なんだか私と似てる気がしたから」
「はぁ……」
彼女と俺のどこが似ているのだろう。明るい彼女とは違い、陰鬱な雰囲気を纏っている俺とでは、似ている要素が一ミリ足りともない。
どういう思考回路をしているのか心配になる。
「君と仲良くなりたいの!」
「お好きにどうぞ」
「やったねっ」
きっとすぐに愛想を尽かして、俺に話しかけて来なくなるだろう。こんな無愛想にしていたら楽しくもないはずだ。
彼女はぐいぐい距離感を詰めてこようとする。やっぱり、危ない存在かもしれない。
『桜井萌笑さん、桜井萌笑さん。職員室まで来てください。繰り返します──』
校内放送だ。転校初日で、色々配布物とかあるのだろう。
彼女の方に目をやると、嫌そうな顔をしている。喋らなくても何を考えているのか大体わかりそうだ。
「はぁ……、じゃあね」
遥々校舎の最奥まで来たというのに、ものの数分で引き返すことになったら、確かに俺もこうなるかもしれない。彼女の背中は幾分老けたように感じられた。
『!』
まただ。一瞬見えて、一瞬で消える。
彼女の後ろ姿が見えなくなった頃には消えていて、俺の頭には『?』しか浮かばなかった。なんなんだろう。