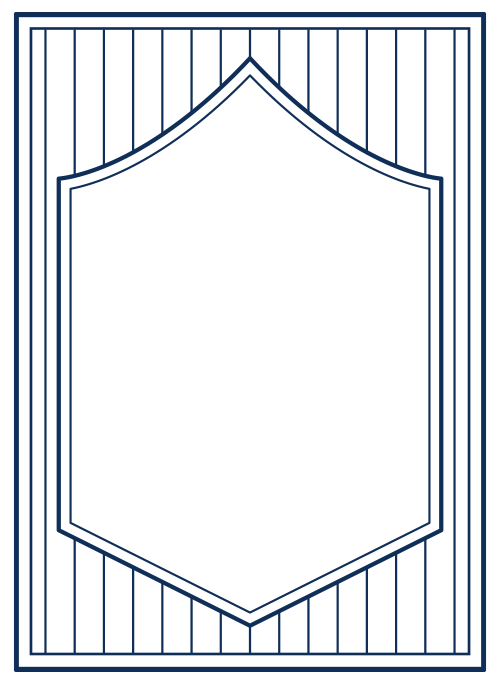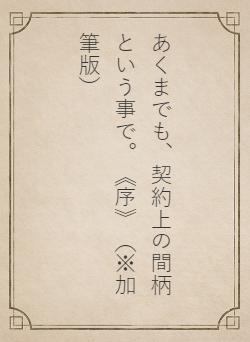「この離れともお別れだね」
自分の荷物を手に、彼女は離れを振り返った。
「『住めば都』とは言うし、都の元を作って下さったのは大お祖母様だけど、住んで都としてくれたのは、全部お母さんの努力と工夫のお陰だったね」
子供達が心地よく過ごせるように、母が心を砕いて住まいを整えてくれた事を思い返しながら、彼女は言った。頷く瑤太の目は、心なしか潤んでいるように見える。
「なら、次の所も、住んで都にすればいいよ」
同じく潤んだ目で、瑠子は子供達に笑顔を見せた。彼女達は「そうだね」と頷く。
瑠子の両隣に双子は並び、離れに頭を下げた。また屋敷の門の前でも、屋敷自体に頭を下げる事も忘れなかった。
自分の荷物を手に、彼女は離れを振り返った。
「『住めば都』とは言うし、都の元を作って下さったのは大お祖母様だけど、住んで都としてくれたのは、全部お母さんの努力と工夫のお陰だったね」
子供達が心地よく過ごせるように、母が心を砕いて住まいを整えてくれた事を思い返しながら、彼女は言った。頷く瑤太の目は、心なしか潤んでいるように見える。
「なら、次の所も、住んで都にすればいいよ」
同じく潤んだ目で、瑠子は子供達に笑顔を見せた。彼女達は「そうだね」と頷く。
瑠子の両隣に双子は並び、離れに頭を下げた。また屋敷の門の前でも、屋敷自体に頭を下げる事も忘れなかった。