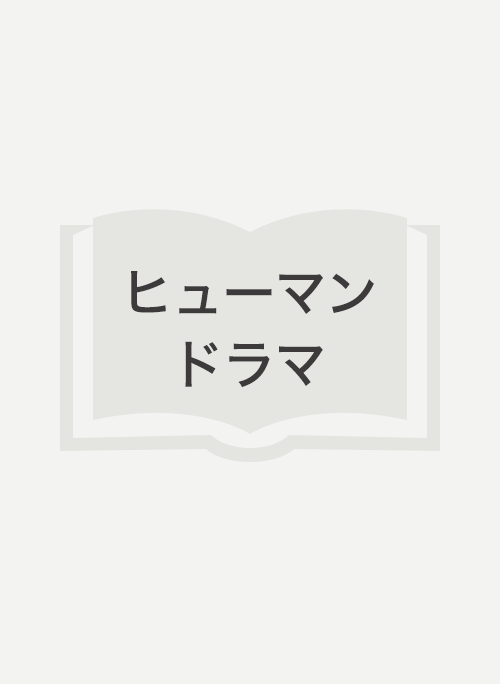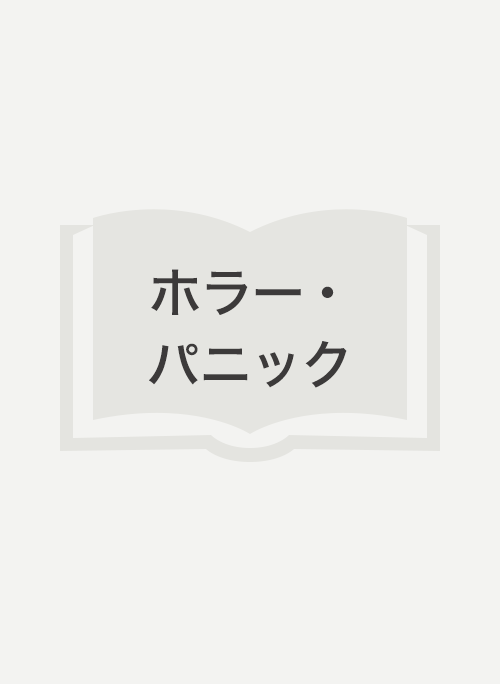ようするに、当主が代替わりしないうちに『役職』の人間が変わる事はなく、席が空いたとしても埋め直されるのはないという事だろう。とはいえ、蒼緋蔵家内で独自に続いている制度でもあるので、雪弥としてはいまいち実感はなかった。
「過去の役職が記録された本というのは、わざわざ隠し扉の向こうに隠すほど重要な物なんですかね?」
「歴史が古い一族ほど、その歴史や記録の重要性は上がりますよ。いくつもの時代を過ごしてきた三大大家や、表十三家や裏二十一家は、家系図や『役職記録』だけではない、門外不出の歴史書も存在しているといいます」
雪弥を室内へ促しながら、宵月は淡々と口にした。
「あなた様にも分かりやすいよう申しますと、蒼慶様が今夜手にしなければならないその本は、時代を超えて受け継がれている博物館級の貴重な本というわけです。それが狙われている可能性が非常に高い、ということでございます」
蒼緋蔵家以外にも『役職』といった制度があり、同じように記録された書物が残されているらしい。経ている年月からすれば、貴重な記録には違いないだろうけれど、一族内の事というだけなのに何故そこまで重要視されているのか?
「過去の役職が記録された本というのは、わざわざ隠し扉の向こうに隠すほど重要な物なんですかね?」
「歴史が古い一族ほど、その歴史や記録の重要性は上がりますよ。いくつもの時代を過ごしてきた三大大家や、表十三家や裏二十一家は、家系図や『役職記録』だけではない、門外不出の歴史書も存在しているといいます」
雪弥を室内へ促しながら、宵月は淡々と口にした。
「あなた様にも分かりやすいよう申しますと、蒼慶様が今夜手にしなければならないその本は、時代を超えて受け継がれている博物館級の貴重な本というわけです。それが狙われている可能性が非常に高い、ということでございます」
蒼緋蔵家以外にも『役職』といった制度があり、同じように記録された書物が残されているらしい。経ている年月からすれば、貴重な記録には違いないだろうけれど、一族内の事というだけなのに何故そこまで重要視されているのか?