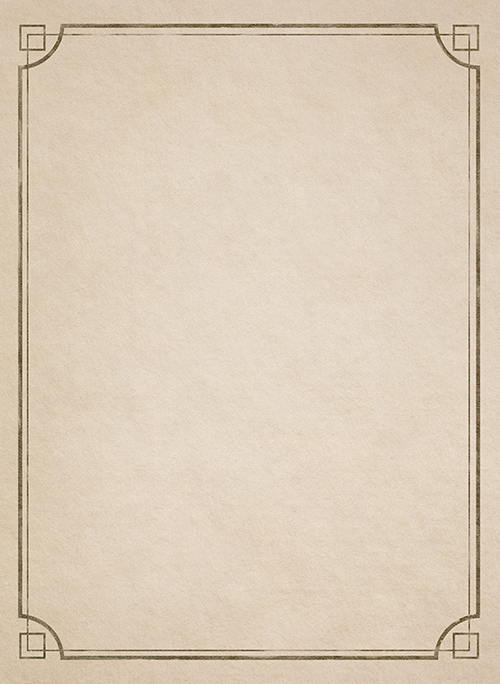いつもの大学、いつものバイト、いつもの帰り道。人類史が辿ってきた争いの歴史を顧みればこの普遍に続く平和がいかに大切なものか理解できるが、普遍な平和はいわば平凡だ。平々凡々だと何度も繰り返して言いたくもなる。
たいして取り柄もない、才能もない私が過ごす日常は退屈で何の彩もない。まるで戦後の白黒写真のようなものだ。どうせ色が付けられないなら意味がないと、私の服装も黒っぽい地味なコーデになってしまっている。化粧だって時間とお金のかからない簡単なものしか使っていない。
私自身の過去を顧みても、甦ってくる思い出はどれもモノクロの写真だけ。でもアニメや漫画だけは今なお光り輝いていた。漫画は常に私に理想を見せてくれて、アニメでは憧れを見つけられる。それが同時に現実の私を暗くしているのはわかっている。
だがこれが私だ。今さら変わろうとは思わない。
宣誓! 私はこれまでの自分をすべて肯定し、それに反する陽キャ・リア充を一切否定することを、ここに誓います!
日課である最低な陰キャ宣誓をしたところで、今日も今日とてバイトの帰りに近くのスーパーへと足を運んだ。
スーパーの陽気なオリジナルソングを口ずさみながらカゴを持って惣菜コーナーへと真っ直ぐ向かっていく。2割り引きの惣菜を選んでカゴに入れると、他の陳列棚には見向きもせずにまっすぐレジに並ぶ。私は昔からスイーツやお菓子といったものに興味がなかったことが幸いして、大学に入ってからの一人暮らしでは食費が浮いて助かっている。
「1272円になります。カードはお持ちですか?」
「あ、大丈夫です」
何度も通ってるのだからカードはないとわかってほしいものだが、レジのお姉さんからすれば何度も通うんだったらカードを作れよって気持ちなんだろう。それといい加減に「あ」を付けるのは止めろって思ってるのだろう。
私はパッパと手早く食材をレジ袋に入れて駅チカのアパートへと帰る。駅だけでなく大学へ行くにも徒歩7分と立地が良いため、このアパートには一人暮らしの大学生が多く住んでいる。
エントランスホールの自動扉を解錠しようとポケットからカギを取り出していると、ちょうど扉の向こう側から同じく大学生のカップルがやって来た。
私がカギを使うまでもなく自動扉は開く。
「でね、またネックレス貰ってるんよ。ちょっとさすがに早すぎん?」
「まあ確かに。三か月でネックレスなら一年目には指輪になる勢いだろうな」
「いやいや、あの二人は一年も続かんよ。前の彼氏だってなんだかんだ半年も持たんかったし」
聞きたくもないのに大声で話されると会話が聞こえてきてしまう。
私にはまるで気づいていないかのように、ジェルの香りが強い彼氏と関西弁を隠す気のない茶髪の彼女はエントランスホールを抜けていく。そうですかそうですか。陽の者は陰には見向きもしませんか。
僻みと分かっていながらリアルを充実させているカップルの幸せそうな後ろ姿を恨めしく睨みつけたあと、自分の部屋へと帰った。
「あぁ~」
だらしのない声を出しながら荷物を下ろすと、流れるように部屋の電気をつけてそのままベッドにダイブイン。柔らかなベッドはスプリングの音をたてながら私を迎え入れてくれた。
まったくさっきの若者たちと来たら……。
枕に顔を埋め、泡のように浮かんでくる先ほどすれ違ったカップルへの恨みを発散する。
対象はさっきのカップルだけではない。季節は秋になりしばらく経過したが、現実でもSNS上でもクリスマスに合わせて付き合い始める、もしくは当日に告白するために相手の外堀を埋めてポイントを稼ぐ輩が目立ちだした。お前たちは冬眠する前に食糧を貯め込むクマか。だがクマとは違ってクリスマスの夜に寝ることはないのだろうと想像すると、余計にはらわたが煮え繰り返る。
とはいえ奴らリア充は1人でクリスマスも越せないような人類でも最弱の存在。私なら1人でも某ランドを一日中楽しめることができるのだ。フハハハハ。
虚しい高笑いが秋空に響き渡る。
いいもん。私には彼氏がいなくても推しがいるんだもん。寂しくなんてないんだもん。
寂しくなんてないもん、略してサビモンが出たところで私は身体をゆっくりと起こして大学の生協で購入したラップトップパソコンをカバンから取り出した。電源を付けてカタカタと操作すると、画面にダウンロードした推しのシチュエーションボイスのファイルが現れる。
このためだけにネットで買った高性能のヘッドフォンを付けると、再生ボタンをクリックした。
『おかえり。ずっと待ってたよ』
優しい低音ボイスが鼓膜を震わせる。それに合わせて私の身体も疼くように身体をよじった。やはり帰宅第一声はこの声に限る。
この声は私が推している騎士系Vtuberの黒岸ナイトという、雑談・実況配信をしている男性ライバーだ。多くのVtuberを擁している大きな事務所に所属しており、配信歴は二年弱だがチャンネル登録者数は50万人を突破している。
多くの女性ファンはナイト様と呼んでおり、私は初回配信を偶然見てから一瞬にしてナイト様の虜になってしまった。シチュエーションボイスはもちろんのこと、グッズも欠かさず買いそろえている。さらにスーパーチャットと呼ばれる配信者に送る投げ銭は定期的にナイト様へ送っている。
そんな古参のファンである私が選ぶ最もお気に入りのシチュエーションボイスを再生する。リア充の光によって傷ついてしまった私をナイト様に癒やして貰うのだ。
『もう大丈夫ですよ。私が助けに来ました』
それは囚われの姫を騎士であるナイト様が助けに来るというシチュエーションで、リスナーは命がけで助けに来たナイト様と甘々な会話をすることができる。
より愉しむために目を閉じてナイト様とのシチュエーションを想像する。
----私は姫。敵国の地下に幽閉されており、もう助かることはないと諦めて大粒の涙を流す。そのとき、地下室の扉を開けられる。そこに私の幼馴染で国家騎士のナイト様……もといナイトが私を助けに来た。
「ナイト? あなた、どうしてこんなところに?」
次のボイスに合わせて予定調和されたセリフを述べる。
『どうして助けたのか、ですか? そんなの私が騎士だからに決まって……いや、それだけでないことなど、とっくにお見通しですよね……』
地下室ではっきりとナイトの顔は見えないが、その頬は紅潮しているようだった。凛々しい眉も困ったように垂れている。
吐息の混じった悩ましげな声に頭も心も壊されてしまう。普段は強気で話すだけにこうして困惑したり下手に回っていると私の中で嗜虐心というか好きな子に対する乙女心のようなものが生まれてくる。
「ナイト……。言いたいことがあるなら、はっきりと言ってちょうだい」
心を鬼にしてナイトに意地悪をする。ナイトは覚悟を決め、逞しい手で私の両手を握った。
『一生あなたを守らせてください。騎士ではなく、一人の男として』
キャー!
雄叫びならぬ雌叫びをあげてベッドの上でもだえ苦しむ。妄想から現実に帰ってきても耳にはナイト様の言葉が反芻してトキメキが止まらない。セリフを覚えるほど何度も繰り返し聞いたボイスだが、いつ聞いても新鮮な気持ちで聞くことができる。
私は行き場のない叫びを子供のころから持っている某ランドのぬいぐるみを力いっぱい抱きしめることで代替する。ぬいぐるみは身体が「く」の字に曲がり、魂が宿っていたなら苦痛の叫びをあげていただろう。もちろんぬいぐるみだから黙って私の胸で抱かれてくれているのだが。
そのまま悶絶してぬいぐるみとじゃれ続け、遂には力尽きてベッドの上の干物となった。だるい身体でゴロゴロと転がって眠気とも無気力とも違う、なんとも言えない退屈に苛まれる。
最近は暇つぶし異世界転生もののアニメを多く見ていたが、それももう見飽きた。漫画を読もうにももう何十回と繰り返し読んで無いようも覚えてしまった作品ばかり。かといって大学の課題をやる気力はない。
「ナイト様……」
物憂げに推しの名前を叫ぶ。
私はそのままパソコンを操作してインターネットを開いた。カタカタとタイピングをして開いたサイトはVtuber好きが集まる掲示板サイトで、大手事務所に所属するVtuberから個人で活動をしているVtuberまで網羅してある。ここを利用する人たちはグッズやイベントの情報を共有したり、最近勢いのあるVtuberをまとめたりしている。
暇な時間はここでサーフィンをするのが日課になっており、今日はナイト様の配信について書いてあるスレを開いた。
【朗報】 黒岸ナイト、実写配信
2021/11/4(木)12:30:54.19
今日の7時から料理配信。
最近は他の人たちも実写の手元配信多いから助かる
2021/11/4(木)12:46:42.09
ただ料理配信だと調理器具で顔が反射しそうで怖いっていうのはある
2021/11/4(木)12:48:39.46
なんならナイトは多少の顔バレはウェルカムっていう感じはする。「え?顔映ってた?イケメンだったでしょww」とかいってそう
2021/11/4(木)13:05:48.01
めっちゃ想像できたわw
2021/11/4(木)13:17:40.89
というか男で料理配信とかめずらしいよね。しかもお菓子作りって難易度高そう
2021/11/4(木)13:34:19.21
ナイト様はSNSでもお菓子の画像あげてるから簡単そう
2021/11/4(木)13:36:29.06
視聴者層が女性多いのはわかるけどもう少し男性向けのコンテンツをやって欲しい気もする。雑談とかは見てるけど料理配信はさすがにみないわ
などと様々なコメントが見受けられる。このサイトではアンチコメントがあまり流れないため、安心して読み進めることができるのだ
ダラダラと他のVtuberについて書いているスレも開いて時間を潰していく。そして遂に、ポケットのスマホがブルブルと震えた。
キタ!
隣人迷惑になるから心の中で大声を出し、急いでスマホのロックを外す。画面を横にして準備は万端。通知が来てからこの間僅かに2秒! 流れるように私はナイト様の配信を開いた。
ちなみに私が通知をオンにしているのはナイト様の配信だけのため、携帯がブルっとするときはナイト様が私を呼んでいる時だけなのだ。
スマホからはいつ聞いても耳馴染みのよいオリジナルソングが流れ、デフォルメされた甲冑の騎士が白馬に乗って画面の端から端をずっと往復している。これは配信が始まるまでの待機画面で、これがあるため通知が来ても私のように急いで配信を開ける必要はないのだ。
とはいえ、私のような上級者になれば通知が来ればすぐに向かうし待機画面でもすることはある。
スマホを縦にすると流れるようにコメントを打ち込む。
「待ってました!」
待機画面のコメントはライバーも見ていることが多いため、こういったコメントは積極的に打ち込んでいくべきなのだ。現に同志たちの「こんばんは!」や「楽しみ!」といったコメントが流れていく。
『皆さん、こんばんは』
待機画面が終わるとともに画面の端に黒髪をなびかせた甲冑姿のキャラクターの立ち絵が登場した。
『王族護衛騎士VTuberの黒岸ナイトです。さっそくだけど今日は、久々の料理配信でもしていこうかと思います』
はぁぁ……ナイト様ぁ……。
いつもと同じ低音ボイスに思わずため息が漏れてしまう。どこか威圧的な雰囲気を醸し出しながらふと見せる甘く優しい声。さらに中性的な見た目は私の心を完全に掌握している。
ナイト様は今でこそ登録者数が50万人を突破しているが、二年前の初配信はもはや伝説となっている。
全身甲冑姿の立ち絵で登場し、そのまま20分近く自己紹介を続けていたのだ。私は偶然その初配信を見ていたのだが、その時点でナイト様の声には心を奪われるものがあった。
そしてナイト様の『暑くなったな』の一言で甲冑のヘルメットを脱いだ瞬間、紅顔の美少年が現れ私を含めた視聴者たちは一瞬にしてナイト様の虜になってしまった。どうしてもナイト様の見た目から女性ファンの方が多いが、ワードセンスやオープンな性格から男性ファンも少なくない。さきほど掲示板でもあったようなプロレスと呼ばれるような雑談配信は男女共に人気がある。
今はデビュー当時と同じヘルメットだけを脱いだ甲冑姿だが、私の一番の推し衣装は訓練服と呼ばれるラフな薄着だ。鎖骨が見えるほど胸元が緩く、豪壮な甲冑に隠れた細くたおやかな身体を見た私は歓喜のあまり隣人に怒られるほど叫び声をあげてしまうほどだった。
『前にもちょっと言ったけど、今日はチョコクッキーを作っていきます。今はチョコレートを湯煎する準備をしているので、もうちょっとだけここで雑談しておきます。……湯煎してから配信しろって? いやいや、ちょっとでも早くみんなと会いたかったんだよ』
コメントと会話しながらナイト様は楽しそうに笑っている。それだけで耳が幸せだ。
私も参加しなくては、とスマホでコメントを打ち込む。
「私も、会いたかったよ」
コメントの流れが速すぎてナイト様は私のコメントを拾ってくれなかったが、それでも私は十分満ち足りた気分になっていた。読まれるか読まれないかは関係なく、ただ形でもナイト様に思いを告げられただけで万々歳なのだ。……とはいえ心のどこかに承認欲求というものがあって定期的にその鬱憤を晴らさなければいけないのも事実。
月例の金額分はまだ使っていないので、日ごろの感謝の思いも込めてナイト様にスーパーチャット、略してスパチャを送る。しかも12000円で赤スパと呼ばれる高級なスパチャだ。
「いつも応援しています」
シンプルな文言ではあるが愛を伝えるにはこれだけで十分なのだ。スパチャは値段に応じて打ち込める文字数が変わり、赤スパの場合は270文字以上打ち込むことが可能なのだが、文字が多くてもナイト様が読み上げるのが大変なため数時間にわたる雑談配信でもない限り長文スパチャは私の中で送らないように心掛けている。
『お、”一応仮名”さん。赤スパありがとうございます! いつもありがとうございます!』
何度も赤スパを投げることでナイト様に名前を覚えてもらえるにまで至った私の努力! 学生の身分だと月に一回くらいしか赤スパを投げることはできないが、自分の私腹を肥やすくらいならナイト様に献上した方が100倍マシだ。
『じゃあそろそろいい感じみたいだし、料理配信の方へ移っていこうかな』
そして画面が切り替わり、ナイト様の台所の映像に切り替わる。まな板を俯瞰した映像に、ゴム手袋をつけたナイト様の手が現れた。
ナイト様の手は画面に向かって手を振っている。
『みんな見えてる?』
ナイト様の問いかけにコメント欄では「みえてるよ」「みえてる!」と統率されたコメントが流れていく。
『見えてる……っぽいね。それじゃあ早速だけど始めていきます!』
ナイト様は慣れた手つきで 食材や食器を紹介していく。
『とりあえずさっきも言った通り、今日はチョコレートクッキーを作っていきます。型はハートとダイヤの二つにしようかな。それともう一つ、大きな型のクッキーを作ってやってみたいことがあるんだよね』
小さな三角形のビニールに入った色とりどりなクリームがお皿に乗って登場した。
『えー、これを使ってね、今日はアイシングに挑戦していこうと思います!』
「アイ……シング……?」
聞き覚えのない単語に頭を捻る。しかしコメント欄では「ホントに?!」や「アイシングできるの?」といったアイシングを知る視聴者のコメントが流れていた。
『知らない人のために教えると、このいろんな色のクリームを使ってクッキーの上とかにキャラやデコレーションをしていくことです」
なんとも女子力の高い言葉の羅列に絶句してしまう。私は身体を起こして部屋を見渡し、レジ袋に入ったお惣菜や脱ぎ捨てられた部屋着の有様に絶句する。
嘘、私の女子力低すぎ……!
コメント欄でも私と同じようにナイト様の女子力に圧倒された人たちがコメントをしていた。どうして世の中には女子よりも女子力に優れた男子がいるのか。これならいっそのこと可愛いモノを作れる力とか呼んでほしいものだ。
『それじゃあ早速作っていこうかな』
ナイト様はバターや卵、薄力粉を入れて混ぜていく。その間もずっとコメント欄と話を続けており、楽しそうに笑っている。
『お菓子作りだけでなく料理するときは定期的にボウルや調理道具の水気は取らないといけないんだよ。結構手間がかかるけど、ちょっとした水滴でお菓子ってボロボロになっちゃったりするからね』
豆知識を話しながらもお菓子を作る手は止まらない。コメントを見ているであろう時も手は食材を混ぜる手を止めておらず、ナイト様の女子力というか主婦力がいかに高いのかということが伺える。それに対して私は……。
食べようと思って買ってきたお惣菜にも手を付けず、私は「すごすぎ……」とコメントで打ち込んだ。
『えっと……”アイシングでどんな絵を描くんですか”。あれ、まだ言ってなかったっけ?』
ナイト様はコメント欄からアイシングについての質問を拾った。
『普段からアイシングは練習しているから、ちょっと難易度高めのものにチャレンジしようかなって思ってて。それでいつも言ってるようにピンクタイガーが好きだからさ、全身は無理でもピンクタイガーの顔を作るつもりです』
ピンクタイガーというのは千葉にある某ランドのキャラクターの一人で、他のマウスやクマさんと比べるとマイナーキャラである。しかしどういうわけかナイト様は異常にそのピンクタイガーに嵌っており、事あるごとに配信で話している。ナイト様曰く、クマさんに雑に扱われている時のリアクションがツボらしい。
私もナイト様がピンクタイガーが好きと聞いて、ネットでキーホルダーを買いカバンに付けている。
『よし、じゃあ型をとっていくか』
作業はつつがなく進んでクッキーの型をとる段階まで来る。ナイト様は用意した型を持ち、蛇口の下まで移動させて水を出した。
勢いよく飛び出た水が型に当たり、その水滴がカメラのレンズにまで飛び散った。画面の殆どが水滴で覆われてナイト様の手元が見えなくなってしまう。
『これ型抜きが結構難しくて、割と今でも失敗することが多いんだよね』
ナイト様はカメラの水滴には気づかずに雑談と作業を続ける。
私はコメントで「水滴!」と打ち込んで送信する。他の人たちも私と同じように送っており、コメント欄が「水滴」や「見えないよ〜」といった内容で埋め尽くされた。
『水滴?』
コメントに気づいたナイト様はしばらく黙ったのち、
『ああ、カメラに飛び散ったのか。ごめんごめん、今すぐ拭くね』
とティッシュでカメラのレンズを拭き始めた。手とティシュが覆いかぶさってカメラは真っ暗になる。
『これで大丈夫かな?』
レンズはすっかり綺麗になっており、はっきりと手元が見れる。私は「大丈夫だよ」と答えようとスマホの画面をタッチした瞬間、画面の端に映るあるものに気づいた。
「―――!」
私は思わず息をのんだ。
そこにはレンズを拭くときに使ったであろうポケットティッシュが置かれていた。一見すると何の変哲もないポケットティッシュだが、中にはどこかの国の民族衣装のように色鮮やかな変わった柄のカードが入っていた。
「これって……」
スマホを手放すと急いで洗面所へと走った。洗面所の戸棚を開け、化粧水やカミソリといった美容品群の中にあるポケットティッシュを取り上げる。
その中にはナイト様と似たような色鮮やかな奇妙な柄のカードが入っている。
私はそのカードを取り出し、裏面を見た。そこには私が通っている大学の名前と、今年度の学園祭の文字が入っている。
私はそのカードを持ったままスマホの元へと戻り、ナイト様の画面を見る。
『それじゃあ型を取っていくよ』
ナイト様はクッキーの生地をハート型にくりぬいており、さっきのポケットティッシュはもう写っていなかった。
私は動画のアーカイブ機能を使って時間を巻き戻し、カメラのレンズに水滴がついたところまで戻った。
『これで大丈夫かな?』
ナイト様の手がカメラから離れ、画面の端に色鮮やかな奇妙な柄のポケットティッシュが現れた。私はすぐに一時停止を押し、持っている自分のポケットティッシュと見比べる。
「やっぱりそうだ……」
画像が微妙にブレているためナイト様のポケットティッシュのカードの柄を鮮明に見ることはできないが、私のカードとよく似ている。
これは先月行われた私の通う大学での学園祭で貰ったものだ。私の大学の学園祭では、学生にのみ特別なポケットティッシュが渡される。ポケットティッシュには色鮮やかな柄のカードが入っており、その柄は一つ一つ似てはいるものの微妙に違っている。自分と同じ柄のカードは自分ともう一つだけあり、同じカードを持っている人を探して運営に行けば豪華賞品が貰えるという企画が行われていた。
「どうしてナイト様が……?」
このカードを持っているということは、ナイト様が大学の関係者という可能性が高い。いや、このポケットティッシュは学生証を提示しないと貰えなかったため、ナイト様は私と同じ大学の学生なのでは……?
そのとき、私の心の中で何かが芽生えた。
たいして取り柄もない、才能もない私が過ごす日常は退屈で何の彩もない。まるで戦後の白黒写真のようなものだ。どうせ色が付けられないなら意味がないと、私の服装も黒っぽい地味なコーデになってしまっている。化粧だって時間とお金のかからない簡単なものしか使っていない。
私自身の過去を顧みても、甦ってくる思い出はどれもモノクロの写真だけ。でもアニメや漫画だけは今なお光り輝いていた。漫画は常に私に理想を見せてくれて、アニメでは憧れを見つけられる。それが同時に現実の私を暗くしているのはわかっている。
だがこれが私だ。今さら変わろうとは思わない。
宣誓! 私はこれまでの自分をすべて肯定し、それに反する陽キャ・リア充を一切否定することを、ここに誓います!
日課である最低な陰キャ宣誓をしたところで、今日も今日とてバイトの帰りに近くのスーパーへと足を運んだ。
スーパーの陽気なオリジナルソングを口ずさみながらカゴを持って惣菜コーナーへと真っ直ぐ向かっていく。2割り引きの惣菜を選んでカゴに入れると、他の陳列棚には見向きもせずにまっすぐレジに並ぶ。私は昔からスイーツやお菓子といったものに興味がなかったことが幸いして、大学に入ってからの一人暮らしでは食費が浮いて助かっている。
「1272円になります。カードはお持ちですか?」
「あ、大丈夫です」
何度も通ってるのだからカードはないとわかってほしいものだが、レジのお姉さんからすれば何度も通うんだったらカードを作れよって気持ちなんだろう。それといい加減に「あ」を付けるのは止めろって思ってるのだろう。
私はパッパと手早く食材をレジ袋に入れて駅チカのアパートへと帰る。駅だけでなく大学へ行くにも徒歩7分と立地が良いため、このアパートには一人暮らしの大学生が多く住んでいる。
エントランスホールの自動扉を解錠しようとポケットからカギを取り出していると、ちょうど扉の向こう側から同じく大学生のカップルがやって来た。
私がカギを使うまでもなく自動扉は開く。
「でね、またネックレス貰ってるんよ。ちょっとさすがに早すぎん?」
「まあ確かに。三か月でネックレスなら一年目には指輪になる勢いだろうな」
「いやいや、あの二人は一年も続かんよ。前の彼氏だってなんだかんだ半年も持たんかったし」
聞きたくもないのに大声で話されると会話が聞こえてきてしまう。
私にはまるで気づいていないかのように、ジェルの香りが強い彼氏と関西弁を隠す気のない茶髪の彼女はエントランスホールを抜けていく。そうですかそうですか。陽の者は陰には見向きもしませんか。
僻みと分かっていながらリアルを充実させているカップルの幸せそうな後ろ姿を恨めしく睨みつけたあと、自分の部屋へと帰った。
「あぁ~」
だらしのない声を出しながら荷物を下ろすと、流れるように部屋の電気をつけてそのままベッドにダイブイン。柔らかなベッドはスプリングの音をたてながら私を迎え入れてくれた。
まったくさっきの若者たちと来たら……。
枕に顔を埋め、泡のように浮かんでくる先ほどすれ違ったカップルへの恨みを発散する。
対象はさっきのカップルだけではない。季節は秋になりしばらく経過したが、現実でもSNS上でもクリスマスに合わせて付き合い始める、もしくは当日に告白するために相手の外堀を埋めてポイントを稼ぐ輩が目立ちだした。お前たちは冬眠する前に食糧を貯め込むクマか。だがクマとは違ってクリスマスの夜に寝ることはないのだろうと想像すると、余計にはらわたが煮え繰り返る。
とはいえ奴らリア充は1人でクリスマスも越せないような人類でも最弱の存在。私なら1人でも某ランドを一日中楽しめることができるのだ。フハハハハ。
虚しい高笑いが秋空に響き渡る。
いいもん。私には彼氏がいなくても推しがいるんだもん。寂しくなんてないんだもん。
寂しくなんてないもん、略してサビモンが出たところで私は身体をゆっくりと起こして大学の生協で購入したラップトップパソコンをカバンから取り出した。電源を付けてカタカタと操作すると、画面にダウンロードした推しのシチュエーションボイスのファイルが現れる。
このためだけにネットで買った高性能のヘッドフォンを付けると、再生ボタンをクリックした。
『おかえり。ずっと待ってたよ』
優しい低音ボイスが鼓膜を震わせる。それに合わせて私の身体も疼くように身体をよじった。やはり帰宅第一声はこの声に限る。
この声は私が推している騎士系Vtuberの黒岸ナイトという、雑談・実況配信をしている男性ライバーだ。多くのVtuberを擁している大きな事務所に所属しており、配信歴は二年弱だがチャンネル登録者数は50万人を突破している。
多くの女性ファンはナイト様と呼んでおり、私は初回配信を偶然見てから一瞬にしてナイト様の虜になってしまった。シチュエーションボイスはもちろんのこと、グッズも欠かさず買いそろえている。さらにスーパーチャットと呼ばれる配信者に送る投げ銭は定期的にナイト様へ送っている。
そんな古参のファンである私が選ぶ最もお気に入りのシチュエーションボイスを再生する。リア充の光によって傷ついてしまった私をナイト様に癒やして貰うのだ。
『もう大丈夫ですよ。私が助けに来ました』
それは囚われの姫を騎士であるナイト様が助けに来るというシチュエーションで、リスナーは命がけで助けに来たナイト様と甘々な会話をすることができる。
より愉しむために目を閉じてナイト様とのシチュエーションを想像する。
----私は姫。敵国の地下に幽閉されており、もう助かることはないと諦めて大粒の涙を流す。そのとき、地下室の扉を開けられる。そこに私の幼馴染で国家騎士のナイト様……もといナイトが私を助けに来た。
「ナイト? あなた、どうしてこんなところに?」
次のボイスに合わせて予定調和されたセリフを述べる。
『どうして助けたのか、ですか? そんなの私が騎士だからに決まって……いや、それだけでないことなど、とっくにお見通しですよね……』
地下室ではっきりとナイトの顔は見えないが、その頬は紅潮しているようだった。凛々しい眉も困ったように垂れている。
吐息の混じった悩ましげな声に頭も心も壊されてしまう。普段は強気で話すだけにこうして困惑したり下手に回っていると私の中で嗜虐心というか好きな子に対する乙女心のようなものが生まれてくる。
「ナイト……。言いたいことがあるなら、はっきりと言ってちょうだい」
心を鬼にしてナイトに意地悪をする。ナイトは覚悟を決め、逞しい手で私の両手を握った。
『一生あなたを守らせてください。騎士ではなく、一人の男として』
キャー!
雄叫びならぬ雌叫びをあげてベッドの上でもだえ苦しむ。妄想から現実に帰ってきても耳にはナイト様の言葉が反芻してトキメキが止まらない。セリフを覚えるほど何度も繰り返し聞いたボイスだが、いつ聞いても新鮮な気持ちで聞くことができる。
私は行き場のない叫びを子供のころから持っている某ランドのぬいぐるみを力いっぱい抱きしめることで代替する。ぬいぐるみは身体が「く」の字に曲がり、魂が宿っていたなら苦痛の叫びをあげていただろう。もちろんぬいぐるみだから黙って私の胸で抱かれてくれているのだが。
そのまま悶絶してぬいぐるみとじゃれ続け、遂には力尽きてベッドの上の干物となった。だるい身体でゴロゴロと転がって眠気とも無気力とも違う、なんとも言えない退屈に苛まれる。
最近は暇つぶし異世界転生もののアニメを多く見ていたが、それももう見飽きた。漫画を読もうにももう何十回と繰り返し読んで無いようも覚えてしまった作品ばかり。かといって大学の課題をやる気力はない。
「ナイト様……」
物憂げに推しの名前を叫ぶ。
私はそのままパソコンを操作してインターネットを開いた。カタカタとタイピングをして開いたサイトはVtuber好きが集まる掲示板サイトで、大手事務所に所属するVtuberから個人で活動をしているVtuberまで網羅してある。ここを利用する人たちはグッズやイベントの情報を共有したり、最近勢いのあるVtuberをまとめたりしている。
暇な時間はここでサーフィンをするのが日課になっており、今日はナイト様の配信について書いてあるスレを開いた。
【朗報】 黒岸ナイト、実写配信
2021/11/4(木)12:30:54.19
今日の7時から料理配信。
最近は他の人たちも実写の手元配信多いから助かる
2021/11/4(木)12:46:42.09
ただ料理配信だと調理器具で顔が反射しそうで怖いっていうのはある
2021/11/4(木)12:48:39.46
なんならナイトは多少の顔バレはウェルカムっていう感じはする。「え?顔映ってた?イケメンだったでしょww」とかいってそう
2021/11/4(木)13:05:48.01
めっちゃ想像できたわw
2021/11/4(木)13:17:40.89
というか男で料理配信とかめずらしいよね。しかもお菓子作りって難易度高そう
2021/11/4(木)13:34:19.21
ナイト様はSNSでもお菓子の画像あげてるから簡単そう
2021/11/4(木)13:36:29.06
視聴者層が女性多いのはわかるけどもう少し男性向けのコンテンツをやって欲しい気もする。雑談とかは見てるけど料理配信はさすがにみないわ
などと様々なコメントが見受けられる。このサイトではアンチコメントがあまり流れないため、安心して読み進めることができるのだ
ダラダラと他のVtuberについて書いているスレも開いて時間を潰していく。そして遂に、ポケットのスマホがブルブルと震えた。
キタ!
隣人迷惑になるから心の中で大声を出し、急いでスマホのロックを外す。画面を横にして準備は万端。通知が来てからこの間僅かに2秒! 流れるように私はナイト様の配信を開いた。
ちなみに私が通知をオンにしているのはナイト様の配信だけのため、携帯がブルっとするときはナイト様が私を呼んでいる時だけなのだ。
スマホからはいつ聞いても耳馴染みのよいオリジナルソングが流れ、デフォルメされた甲冑の騎士が白馬に乗って画面の端から端をずっと往復している。これは配信が始まるまでの待機画面で、これがあるため通知が来ても私のように急いで配信を開ける必要はないのだ。
とはいえ、私のような上級者になれば通知が来ればすぐに向かうし待機画面でもすることはある。
スマホを縦にすると流れるようにコメントを打ち込む。
「待ってました!」
待機画面のコメントはライバーも見ていることが多いため、こういったコメントは積極的に打ち込んでいくべきなのだ。現に同志たちの「こんばんは!」や「楽しみ!」といったコメントが流れていく。
『皆さん、こんばんは』
待機画面が終わるとともに画面の端に黒髪をなびかせた甲冑姿のキャラクターの立ち絵が登場した。
『王族護衛騎士VTuberの黒岸ナイトです。さっそくだけど今日は、久々の料理配信でもしていこうかと思います』
はぁぁ……ナイト様ぁ……。
いつもと同じ低音ボイスに思わずため息が漏れてしまう。どこか威圧的な雰囲気を醸し出しながらふと見せる甘く優しい声。さらに中性的な見た目は私の心を完全に掌握している。
ナイト様は今でこそ登録者数が50万人を突破しているが、二年前の初配信はもはや伝説となっている。
全身甲冑姿の立ち絵で登場し、そのまま20分近く自己紹介を続けていたのだ。私は偶然その初配信を見ていたのだが、その時点でナイト様の声には心を奪われるものがあった。
そしてナイト様の『暑くなったな』の一言で甲冑のヘルメットを脱いだ瞬間、紅顔の美少年が現れ私を含めた視聴者たちは一瞬にしてナイト様の虜になってしまった。どうしてもナイト様の見た目から女性ファンの方が多いが、ワードセンスやオープンな性格から男性ファンも少なくない。さきほど掲示板でもあったようなプロレスと呼ばれるような雑談配信は男女共に人気がある。
今はデビュー当時と同じヘルメットだけを脱いだ甲冑姿だが、私の一番の推し衣装は訓練服と呼ばれるラフな薄着だ。鎖骨が見えるほど胸元が緩く、豪壮な甲冑に隠れた細くたおやかな身体を見た私は歓喜のあまり隣人に怒られるほど叫び声をあげてしまうほどだった。
『前にもちょっと言ったけど、今日はチョコクッキーを作っていきます。今はチョコレートを湯煎する準備をしているので、もうちょっとだけここで雑談しておきます。……湯煎してから配信しろって? いやいや、ちょっとでも早くみんなと会いたかったんだよ』
コメントと会話しながらナイト様は楽しそうに笑っている。それだけで耳が幸せだ。
私も参加しなくては、とスマホでコメントを打ち込む。
「私も、会いたかったよ」
コメントの流れが速すぎてナイト様は私のコメントを拾ってくれなかったが、それでも私は十分満ち足りた気分になっていた。読まれるか読まれないかは関係なく、ただ形でもナイト様に思いを告げられただけで万々歳なのだ。……とはいえ心のどこかに承認欲求というものがあって定期的にその鬱憤を晴らさなければいけないのも事実。
月例の金額分はまだ使っていないので、日ごろの感謝の思いも込めてナイト様にスーパーチャット、略してスパチャを送る。しかも12000円で赤スパと呼ばれる高級なスパチャだ。
「いつも応援しています」
シンプルな文言ではあるが愛を伝えるにはこれだけで十分なのだ。スパチャは値段に応じて打ち込める文字数が変わり、赤スパの場合は270文字以上打ち込むことが可能なのだが、文字が多くてもナイト様が読み上げるのが大変なため数時間にわたる雑談配信でもない限り長文スパチャは私の中で送らないように心掛けている。
『お、”一応仮名”さん。赤スパありがとうございます! いつもありがとうございます!』
何度も赤スパを投げることでナイト様に名前を覚えてもらえるにまで至った私の努力! 学生の身分だと月に一回くらいしか赤スパを投げることはできないが、自分の私腹を肥やすくらいならナイト様に献上した方が100倍マシだ。
『じゃあそろそろいい感じみたいだし、料理配信の方へ移っていこうかな』
そして画面が切り替わり、ナイト様の台所の映像に切り替わる。まな板を俯瞰した映像に、ゴム手袋をつけたナイト様の手が現れた。
ナイト様の手は画面に向かって手を振っている。
『みんな見えてる?』
ナイト様の問いかけにコメント欄では「みえてるよ」「みえてる!」と統率されたコメントが流れていく。
『見えてる……っぽいね。それじゃあ早速だけど始めていきます!』
ナイト様は慣れた手つきで 食材や食器を紹介していく。
『とりあえずさっきも言った通り、今日はチョコレートクッキーを作っていきます。型はハートとダイヤの二つにしようかな。それともう一つ、大きな型のクッキーを作ってやってみたいことがあるんだよね』
小さな三角形のビニールに入った色とりどりなクリームがお皿に乗って登場した。
『えー、これを使ってね、今日はアイシングに挑戦していこうと思います!』
「アイ……シング……?」
聞き覚えのない単語に頭を捻る。しかしコメント欄では「ホントに?!」や「アイシングできるの?」といったアイシングを知る視聴者のコメントが流れていた。
『知らない人のために教えると、このいろんな色のクリームを使ってクッキーの上とかにキャラやデコレーションをしていくことです」
なんとも女子力の高い言葉の羅列に絶句してしまう。私は身体を起こして部屋を見渡し、レジ袋に入ったお惣菜や脱ぎ捨てられた部屋着の有様に絶句する。
嘘、私の女子力低すぎ……!
コメント欄でも私と同じようにナイト様の女子力に圧倒された人たちがコメントをしていた。どうして世の中には女子よりも女子力に優れた男子がいるのか。これならいっそのこと可愛いモノを作れる力とか呼んでほしいものだ。
『それじゃあ早速作っていこうかな』
ナイト様はバターや卵、薄力粉を入れて混ぜていく。その間もずっとコメント欄と話を続けており、楽しそうに笑っている。
『お菓子作りだけでなく料理するときは定期的にボウルや調理道具の水気は取らないといけないんだよ。結構手間がかかるけど、ちょっとした水滴でお菓子ってボロボロになっちゃったりするからね』
豆知識を話しながらもお菓子を作る手は止まらない。コメントを見ているであろう時も手は食材を混ぜる手を止めておらず、ナイト様の女子力というか主婦力がいかに高いのかということが伺える。それに対して私は……。
食べようと思って買ってきたお惣菜にも手を付けず、私は「すごすぎ……」とコメントで打ち込んだ。
『えっと……”アイシングでどんな絵を描くんですか”。あれ、まだ言ってなかったっけ?』
ナイト様はコメント欄からアイシングについての質問を拾った。
『普段からアイシングは練習しているから、ちょっと難易度高めのものにチャレンジしようかなって思ってて。それでいつも言ってるようにピンクタイガーが好きだからさ、全身は無理でもピンクタイガーの顔を作るつもりです』
ピンクタイガーというのは千葉にある某ランドのキャラクターの一人で、他のマウスやクマさんと比べるとマイナーキャラである。しかしどういうわけかナイト様は異常にそのピンクタイガーに嵌っており、事あるごとに配信で話している。ナイト様曰く、クマさんに雑に扱われている時のリアクションがツボらしい。
私もナイト様がピンクタイガーが好きと聞いて、ネットでキーホルダーを買いカバンに付けている。
『よし、じゃあ型をとっていくか』
作業はつつがなく進んでクッキーの型をとる段階まで来る。ナイト様は用意した型を持ち、蛇口の下まで移動させて水を出した。
勢いよく飛び出た水が型に当たり、その水滴がカメラのレンズにまで飛び散った。画面の殆どが水滴で覆われてナイト様の手元が見えなくなってしまう。
『これ型抜きが結構難しくて、割と今でも失敗することが多いんだよね』
ナイト様はカメラの水滴には気づかずに雑談と作業を続ける。
私はコメントで「水滴!」と打ち込んで送信する。他の人たちも私と同じように送っており、コメント欄が「水滴」や「見えないよ〜」といった内容で埋め尽くされた。
『水滴?』
コメントに気づいたナイト様はしばらく黙ったのち、
『ああ、カメラに飛び散ったのか。ごめんごめん、今すぐ拭くね』
とティッシュでカメラのレンズを拭き始めた。手とティシュが覆いかぶさってカメラは真っ暗になる。
『これで大丈夫かな?』
レンズはすっかり綺麗になっており、はっきりと手元が見れる。私は「大丈夫だよ」と答えようとスマホの画面をタッチした瞬間、画面の端に映るあるものに気づいた。
「―――!」
私は思わず息をのんだ。
そこにはレンズを拭くときに使ったであろうポケットティッシュが置かれていた。一見すると何の変哲もないポケットティッシュだが、中にはどこかの国の民族衣装のように色鮮やかな変わった柄のカードが入っていた。
「これって……」
スマホを手放すと急いで洗面所へと走った。洗面所の戸棚を開け、化粧水やカミソリといった美容品群の中にあるポケットティッシュを取り上げる。
その中にはナイト様と似たような色鮮やかな奇妙な柄のカードが入っている。
私はそのカードを取り出し、裏面を見た。そこには私が通っている大学の名前と、今年度の学園祭の文字が入っている。
私はそのカードを持ったままスマホの元へと戻り、ナイト様の画面を見る。
『それじゃあ型を取っていくよ』
ナイト様はクッキーの生地をハート型にくりぬいており、さっきのポケットティッシュはもう写っていなかった。
私は動画のアーカイブ機能を使って時間を巻き戻し、カメラのレンズに水滴がついたところまで戻った。
『これで大丈夫かな?』
ナイト様の手がカメラから離れ、画面の端に色鮮やかな奇妙な柄のポケットティッシュが現れた。私はすぐに一時停止を押し、持っている自分のポケットティッシュと見比べる。
「やっぱりそうだ……」
画像が微妙にブレているためナイト様のポケットティッシュのカードの柄を鮮明に見ることはできないが、私のカードとよく似ている。
これは先月行われた私の通う大学での学園祭で貰ったものだ。私の大学の学園祭では、学生にのみ特別なポケットティッシュが渡される。ポケットティッシュには色鮮やかな柄のカードが入っており、その柄は一つ一つ似てはいるものの微妙に違っている。自分と同じ柄のカードは自分ともう一つだけあり、同じカードを持っている人を探して運営に行けば豪華賞品が貰えるという企画が行われていた。
「どうしてナイト様が……?」
このカードを持っているということは、ナイト様が大学の関係者という可能性が高い。いや、このポケットティッシュは学生証を提示しないと貰えなかったため、ナイト様は私と同じ大学の学生なのでは……?
そのとき、私の心の中で何かが芽生えた。