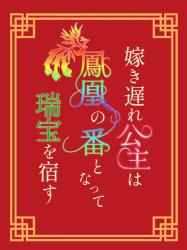一戦目の余韻もそこそこに、勝負は続く。
帝と斎は頭弁に促されるまま西の端にあった壇を下り、次の舞台である庭の中心へ移った。
「二番勝負は剣競べです。使用するのは木太刀。いずれかの剣が使用不能となる、あるいはどちらかが降参するまで打ち込み合っていただきます」
向かい合うふたりの元へ頭中将がやって来て、それぞれへ剣を渡す。どちらも同じ形のやや短めの木太刀だった。木製なので刃はないが、それなりに重量がある。打ち所によっては人を殺せる武器だ。
当初公卿会議では「そんな物騒なものを帝に向けてよいのか」というのが議論になったが、花琉帝自身が「構わない」と答えたので今回に限りお咎めなしとされている。
西の斎は剣を両手に握ると、一度深く呼吸する。それからまっすぐ正眼に構えた。一方東の帝は、感触を確かめるように一度だけ軽く振る。右手の中でもてあそぶように握り直して、左足を引き半身に構えた。片手一本に納まった剣先は、地を向いている。
「(蔵人少将どのはああ見えて、剣の腕は右近衛府でも一二を争うという噂だ)」
「(ああ、同期の武官を軒並み負かしたというのを聞いたことがある。だが帝の剣の腕についてはわからないな……)」
ひそひそと後輩の蔵人達が噂し合う。
斎は小柄な体躯と身軽さを活かした独特の剣術で、見た目以上の手練れとして知られている。今回の勝負で剣競べを指定したのも、彼女の自信の表れだ。一方の帝は、そもそも剣を取るべき立場ではないのでその実力はまったくの未知数である。
帝と斎の合い間に横たわる一丈(約三メートル)ほどの間に、静かに風が吹き抜ける。場に緊張の糸が張り詰めた。
「はじめ!」
静寂を断ち切る頭弁の合図。その瞬間、斎は飛び出していた。目にも留まらぬ早さで距離を詰め、玉砂利の地面を蹴って宙に飛ぶ。中天の太陽を背に、帝の頭上へ剣を振り下ろした。
「はぁああああああ!」
一打目で帝の脳天を狙うとはなんたる畏れ知らず。相手が誰であろうと決してひるまない斎の気迫に、観客は息を呑んだ。
しかし渾身の一撃は上段で真っ向受け止められる。そのまま帝が剣ごと押しのけると、斎の小さな身体は反動でくるりと回転、後方に着地した。だが膝をついたと思ったのも束の間、しゃがみ姿勢のまま飛び出して素早く足下を薙ぐ。
「おっと」
帝は冷静に、後ろ足を軸に半歩下がった。畳みかける斎の攻撃は止まず、すぐに下から伸び上がるような一撃。帝はすれすれで上背を反らして剣先をかわし、同時に剣身を滑らせることで斎の剣の軌道を変える。左へ受け流されて、しかし斎はすぐさま踏み込み斬り返す。
「まだまだっ!」
「そうこなくては」
斎は片時も攻撃の手を休めない。俊敏さを活かして反撃の隙を与えず、果敢に懐に飛び込んでは何度も何度も打ちかかる。その懸命な姿は、思わず声援を送りたくなるような熱狂を人々へもたらした。
一撃、二撃、素早い打撃を加えるたびに観衆の注目が斎へ傾く。だがその中に、ひとりだけ冷静な者がいた。
「帝の動き……まるで舞でも舞っているようだわ……」
帝と斎は頭弁に促されるまま西の端にあった壇を下り、次の舞台である庭の中心へ移った。
「二番勝負は剣競べです。使用するのは木太刀。いずれかの剣が使用不能となる、あるいはどちらかが降参するまで打ち込み合っていただきます」
向かい合うふたりの元へ頭中将がやって来て、それぞれへ剣を渡す。どちらも同じ形のやや短めの木太刀だった。木製なので刃はないが、それなりに重量がある。打ち所によっては人を殺せる武器だ。
当初公卿会議では「そんな物騒なものを帝に向けてよいのか」というのが議論になったが、花琉帝自身が「構わない」と答えたので今回に限りお咎めなしとされている。
西の斎は剣を両手に握ると、一度深く呼吸する。それからまっすぐ正眼に構えた。一方東の帝は、感触を確かめるように一度だけ軽く振る。右手の中でもてあそぶように握り直して、左足を引き半身に構えた。片手一本に納まった剣先は、地を向いている。
「(蔵人少将どのはああ見えて、剣の腕は右近衛府でも一二を争うという噂だ)」
「(ああ、同期の武官を軒並み負かしたというのを聞いたことがある。だが帝の剣の腕についてはわからないな……)」
ひそひそと後輩の蔵人達が噂し合う。
斎は小柄な体躯と身軽さを活かした独特の剣術で、見た目以上の手練れとして知られている。今回の勝負で剣競べを指定したのも、彼女の自信の表れだ。一方の帝は、そもそも剣を取るべき立場ではないのでその実力はまったくの未知数である。
帝と斎の合い間に横たわる一丈(約三メートル)ほどの間に、静かに風が吹き抜ける。場に緊張の糸が張り詰めた。
「はじめ!」
静寂を断ち切る頭弁の合図。その瞬間、斎は飛び出していた。目にも留まらぬ早さで距離を詰め、玉砂利の地面を蹴って宙に飛ぶ。中天の太陽を背に、帝の頭上へ剣を振り下ろした。
「はぁああああああ!」
一打目で帝の脳天を狙うとはなんたる畏れ知らず。相手が誰であろうと決してひるまない斎の気迫に、観客は息を呑んだ。
しかし渾身の一撃は上段で真っ向受け止められる。そのまま帝が剣ごと押しのけると、斎の小さな身体は反動でくるりと回転、後方に着地した。だが膝をついたと思ったのも束の間、しゃがみ姿勢のまま飛び出して素早く足下を薙ぐ。
「おっと」
帝は冷静に、後ろ足を軸に半歩下がった。畳みかける斎の攻撃は止まず、すぐに下から伸び上がるような一撃。帝はすれすれで上背を反らして剣先をかわし、同時に剣身を滑らせることで斎の剣の軌道を変える。左へ受け流されて、しかし斎はすぐさま踏み込み斬り返す。
「まだまだっ!」
「そうこなくては」
斎は片時も攻撃の手を休めない。俊敏さを活かして反撃の隙を与えず、果敢に懐に飛び込んでは何度も何度も打ちかかる。その懸命な姿は、思わず声援を送りたくなるような熱狂を人々へもたらした。
一撃、二撃、素早い打撃を加えるたびに観衆の注目が斎へ傾く。だがその中に、ひとりだけ冷静な者がいた。
「帝の動き……まるで舞でも舞っているようだわ……」