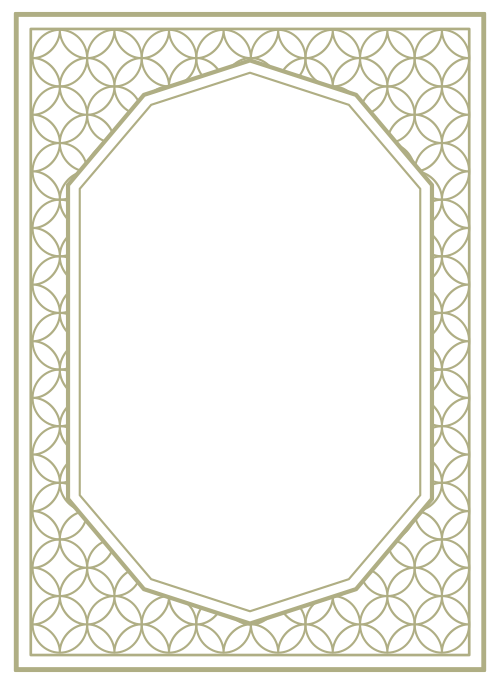思い返すのは子供の頃。裕福だったあの頃、年頭ともなれば祖父と父が経営する会社の取引企業や子会社の社長たちが、祖父や父に頭をぺこぺこ下げて、祖父や父のご機嫌を窺っていた。
岬(みさき)はそんなパーティーで社長子息としてパーティーにデビューし、岬の周りには祖父たちに頭を下げる大人たちの子供があてがわれていた。どの子供も、岬の機嫌を損ねるようなことはしない。岬くん、岬くん、と言ってあとをついて回ってきていて、それが気分良かった。
野球グラウンドが二つくらい取れそうな庭で鬼ごっこをしていた時、庭の隅にある物置小屋に一人の子供を見つけた。さっき、皆で鬼ごっこをするぞ、と宣言したにもかかわらず、その子供は物置小屋の隅っこで隠れることもしないで何かを見ている。
(……僕の言うことを聞かない、変な奴)
ずり、ずり、と膝で歩くその後ろ姿に、おい、と話し掛けると、その子供はくるっと岬の方を向き直ると、しっ! と口に指を立てた。庭掃除に使っていた道具にまみれて其処にうずくまっていた子供――女の子だった――は、視線を小屋の奥に戻す。まるで岬に興味を持たないその女の子に、岬は憤慨した。
「おい、お前。僕は偉いんだぞ。僕の言うことを聞かないお前なんか要らないんだぞ」
「しっ! お母さん猫がおびえちゃう!」
岬の気分を損ねたと知ったら、子供たちはみんな即座に謝って来た。ところがこの女の子はそんな素振りを全く見せない。なんて立場の分かってない子供だろうと思ったら、女の子が見つめる視線の先に、黒い猫と、それから子猫が三匹、蹲っていた。
「……赤ちゃん、生まれたてなのね……。ちっちゃい……、かわいい……」
ぽうっと猫の母子を見る女の子は全く岬に興味を示さない。腹立たしいことこの上なかった。岬はこの女の子の父親も頭を下げる王様なのに。
「おい、お前。僕のことを知らんふりするとはいい度胸だな」
岬が女の子を脅しても、女の子には響かなかった。
「ねえ! この子たち、岬くんのおうちで飼ってもらえる? 本当は私が連れて帰りたいけどおじいちゃんが猫アレルギーなの……」
女の子はそう言ってしょんぼりと眉を寄せた。
なんだって、王様の岬がこんな言うことを聞かない子供の言うことを聞かなきゃならないのか。しかし、小屋の奥でひと固まりに丸まっている猫たちはとてもかわいかった。岬は自分付きの執事である長谷川を呼ぶと、彼に猫たちの寝床を作るよう命じた。
「旦那様たちには、私から話しておきます。寝床は坊ちゃまのお部屋で宜しゅうございますか?」
「ああ、頼む」
即座に行動する大人を見て、漸く女の子の目つきが変わった。
「岬くん、今の人はだあれ?」
「うん? 今のは僕の執事で、長谷川。この屋敷で一番信頼してるやつだ。お父さまやおじいさまは、たまに僕が嫌だと思うことも言うけど、長谷川は僕のことが一番だと言って嫌なことは何一つ言わない。だから僕も長谷川の事は好きだ」
女の子はやっと目を輝かせて岬の言葉を聞いた。
「岬くん、すごいのねえ!」
女の子から称賛の声を聞けて、漸く岬の気分も良くなった。
「執事って、そう言うもんだからな。……ところでお前。猫が気になるなら、何時でも屋敷に見に来ていいぞ。僕は心が広いんだ」
えへん、と胸を張ると、女の子がぱっと明るい顔になった。
「ありがとう、岬くん! 大好き!」
そう言って、岬にぴょんと抱き付いてくる。ふわっと香る、甘いバニラアイスクリームの匂い。岬は驚いて、カッコ悪いことに体を硬直させてしまった。
これが、宮田彩乃(みやたあやの)との出会いだった――。
岬(みさき)はそんなパーティーで社長子息としてパーティーにデビューし、岬の周りには祖父たちに頭を下げる大人たちの子供があてがわれていた。どの子供も、岬の機嫌を損ねるようなことはしない。岬くん、岬くん、と言ってあとをついて回ってきていて、それが気分良かった。
野球グラウンドが二つくらい取れそうな庭で鬼ごっこをしていた時、庭の隅にある物置小屋に一人の子供を見つけた。さっき、皆で鬼ごっこをするぞ、と宣言したにもかかわらず、その子供は物置小屋の隅っこで隠れることもしないで何かを見ている。
(……僕の言うことを聞かない、変な奴)
ずり、ずり、と膝で歩くその後ろ姿に、おい、と話し掛けると、その子供はくるっと岬の方を向き直ると、しっ! と口に指を立てた。庭掃除に使っていた道具にまみれて其処にうずくまっていた子供――女の子だった――は、視線を小屋の奥に戻す。まるで岬に興味を持たないその女の子に、岬は憤慨した。
「おい、お前。僕は偉いんだぞ。僕の言うことを聞かないお前なんか要らないんだぞ」
「しっ! お母さん猫がおびえちゃう!」
岬の気分を損ねたと知ったら、子供たちはみんな即座に謝って来た。ところがこの女の子はそんな素振りを全く見せない。なんて立場の分かってない子供だろうと思ったら、女の子が見つめる視線の先に、黒い猫と、それから子猫が三匹、蹲っていた。
「……赤ちゃん、生まれたてなのね……。ちっちゃい……、かわいい……」
ぽうっと猫の母子を見る女の子は全く岬に興味を示さない。腹立たしいことこの上なかった。岬はこの女の子の父親も頭を下げる王様なのに。
「おい、お前。僕のことを知らんふりするとはいい度胸だな」
岬が女の子を脅しても、女の子には響かなかった。
「ねえ! この子たち、岬くんのおうちで飼ってもらえる? 本当は私が連れて帰りたいけどおじいちゃんが猫アレルギーなの……」
女の子はそう言ってしょんぼりと眉を寄せた。
なんだって、王様の岬がこんな言うことを聞かない子供の言うことを聞かなきゃならないのか。しかし、小屋の奥でひと固まりに丸まっている猫たちはとてもかわいかった。岬は自分付きの執事である長谷川を呼ぶと、彼に猫たちの寝床を作るよう命じた。
「旦那様たちには、私から話しておきます。寝床は坊ちゃまのお部屋で宜しゅうございますか?」
「ああ、頼む」
即座に行動する大人を見て、漸く女の子の目つきが変わった。
「岬くん、今の人はだあれ?」
「うん? 今のは僕の執事で、長谷川。この屋敷で一番信頼してるやつだ。お父さまやおじいさまは、たまに僕が嫌だと思うことも言うけど、長谷川は僕のことが一番だと言って嫌なことは何一つ言わない。だから僕も長谷川の事は好きだ」
女の子はやっと目を輝かせて岬の言葉を聞いた。
「岬くん、すごいのねえ!」
女の子から称賛の声を聞けて、漸く岬の気分も良くなった。
「執事って、そう言うもんだからな。……ところでお前。猫が気になるなら、何時でも屋敷に見に来ていいぞ。僕は心が広いんだ」
えへん、と胸を張ると、女の子がぱっと明るい顔になった。
「ありがとう、岬くん! 大好き!」
そう言って、岬にぴょんと抱き付いてくる。ふわっと香る、甘いバニラアイスクリームの匂い。岬は驚いて、カッコ悪いことに体を硬直させてしまった。
これが、宮田彩乃(みやたあやの)との出会いだった――。