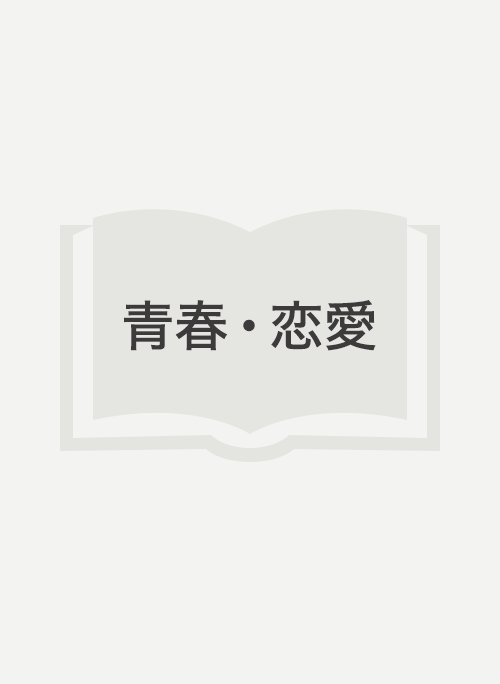「先生と私の?」
「うん。先生は、日本を離れようと思ってるんだ。学びたいんだよ。そしたら、次に君に会ったとき、どうなってると思う?」
「うんと。先生が頭良くなってる?」
くすりと笑うと
「それもあるかもしれないね。次に会ったら、もっとお互いが素敵なひとになっているだろうから、一緒にいる時間がとても楽しくなると思うよ」
少女はしゅんとした顔をする。
「嫌だよ。一緒にいて、お互い素敵なひとになって、楽しいのがいい」
「大丈夫。またすぐに会えるから」
「本当に?」
「うん」
「絶対に?」
はははと声に出して、彼は笑った。
「うん」
「じゃあ、待ってるからね! 宗明先生のこと!」
「うん。待っててね。そうだ。あげたいものがあるんだ」
彼は立ち上がり、壁にかけていた額縁を手に取った。腰を落とすと「はい」と手渡した。
「風」と少女は呟いた。 胸の中に草原にいるようなやわらぎを感じた。
「葉凪は風みたいな子だからね」
その言葉に少女は瞳を潤ませた。それから我慢できないというように、涙が溢れてくる。とても可憐に見えて、彼は優しく抱きとめる。 先生の右肩が、そっと涙で湿った。