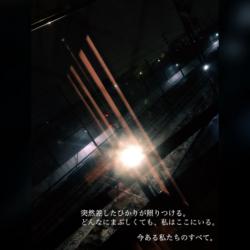バスがいっぱいに詰め込んだ生徒たちを一気に解放した。昨日のスーツ姿とはうって変わって私服のういういしい大学生が正門を通り抜けていく。
宏紀はメインストリートを行くと、大きくそびえたつ時計に時刻を知らせてもらった。一時限目の講義までまだ三十分ぐらいある。最初の講義だということもあって、余裕を持たせたからこの時間になった。七海に講義に遅れそうになってあたふたしているさまは見せたくないだろうから。
時計を通り過ぎて、宏紀は学生食堂や国際関係学部、教育学部の建物を眺めながら歩く。
宏紀が口元を動かして自分自身の耳に向けてささやいている。表情はどこか晴れ晴れとしていて曇りはどこにも見られない。七海の存在があるからだろう。人はたった一つのことでも、前向きな表情を見せられるんだ。私も、のちに経験することなんだろう。
生活環境学部の建物が見えてくると、宏紀は少しだけ自分に力を与えて駆け足になった。
この学部は創設されてまだ間もないから、足を踏み入れることでさえ躊躇してしまいそうなぐらいきれいだ。宏紀は中に入るのに勇気が必要だった。昨日はみんな入学式の緊張でそんなことを気にする余裕なんて皆無だったと思うけど。
講義室がある三階に上がると、宏紀はゆっくりと引き戸を開けた。
講義の三十分前だから、集まってきている学生たちはそんなにいなかった。いるのは、大学の近くで一人暮らしをしている生徒か、電車の時刻表の関係で早く来ることを選択した学生たちだ。
宏紀は七海を射程圏内にとらえようとしたけど、まだ来ていないみたいだった。
変な緊張は一気に抜け落ちて、軽い足取りで教室の床を踏んだ。
無意識に宏紀は前方の中央に並ぶ席に着いた。わざわざ聞こえにくい後ろの方に行くことはないと思ったんだろう。
最初の講義だけあってどんな風に進んでいくか未知数だから、宏紀は胸を押さえて鼓動の揺れを知る。とりあえずノートとこの講義で使用する参考書を取り出して目の前に置いた。それらが宏紀の動悸を丸く収めてくれるとは思わないけど、とりあえずの行動だった。
引き戸が再び動き出した。宏紀が後ろを振り返ると、七海がゆっくりと入ってきた。少し焦りを顔に七海は添えていた。
宏紀の姿を見つけると、七海は小さく手を振って近づいて行った。
「おはよう! 講義室間違えて入っちゃった」
焦りを振り払うように七海は体を揺らしている。
「そうなんだ。気付いて良かったね。別の講義受けるところだったじゃん」
私服の七海をほとんど見たことがなかったから、宏紀は新しい七海の一面を見るようで笑みがこぼれる。七海も宏紀の私服は初めてかもしれない。
「本当だよ! マジで焦った!」と七海は胸に手を当てて、「ここ、座っていい?」と宏紀に尋ねた。
「もちろん」
宏紀は隣においていたリュックサックを退けて、七海の席を作った。隣に置いていたのは七海の席を確保していたんだと思う。
「ありがとう。今日、早く起きたんじゃない?」
宏紀の住む横浜市港南台区は私が住んでいる磯子よりももっと距離があるからかなりの長旅になる。約二時間かけて来るから、朝は相当早いだろう。
「うん。これから通学できるかなって心配なった」
そう漏らす宏紀を見てクスッと笑った七海は、「この辺で一人暮らししたらいいよ。思い切って親に言ってみたら?」
「したいけど、金銭的に無理かな」
苦笑しながらも、七海にそう言ってもらえたのは嬉しかっただろう。宏紀って、本当に分かりやすい子だ。
「そうか……今じゃなくても、もう少しお金が貯まったらしたらいいんじゃない?」
「うん……」
したくてもできない状況がもどかしい。宏紀はそう言いたいけど、できない。
「宏紀、その筆箱、まだ使っているんだね」
教科書の寝ころぶ筆箱を見つめて七海は言った。
「よく覚えてるね」
「うん。そのチェックの筆箱かわいかったから覚えているよ」
「すごい!」
細かいことでもすぐに伝える七海が微笑ましい。宏紀はそう思っているだろう。
講義の開始時間が迫ると同時に、総勢百名ほどいる食品栄養学科の生徒たちの顔ぶれが揃いつつある。席も埋まってきて人の威圧感が宏紀たちを包んだ。
この講義の担当教授が入室してきた。頭に白い髪の毛を乗せて、老眼鏡を首からかけ、大きめの紙袋を持っている。ホワイトボードの前に立つと、生徒たちを眺めて微笑んだ。
最初の講義だからみんなが声を一斉に抑えた。
「おはようございます。みんな最初の講義だから、緊張しているかと思いますが始めていきますね」
そう言って学生たちのカチカチに凍った緊張のアイスを溶かすために、中央の最前列に座っている学生たち四人を例に、五分間、隣同士で話をするように指示を出した。
教室全体のあちこちから沈黙を優しくなだめて活気を呼び込む学生たちの声が上がった。
宏紀の隣には黒の短髪に、色白の肌が輝く中学生のような幼い微笑みが印象的な男の子が座っていた。
「おはよう」
宏紀も教室に活気を入れるために、ペコっと頭を下げて言った。
「おはよう」
男の子は緊張の笑顔かと思ったら、自然な笑みを見せたから宏紀も安堵した。
勇気を絞って声をかけた宏紀を七海はその様子を見守っている。
「深沢宏紀って言います。名前はなんて言うんですか?」
「園田真也です。よろしくお願いします」
宏紀は笑みを見せたけど、次の質問を模索していると次の言葉が出てこなくなった。
「宏紀、それだけ?」
七海が鋭く突っ込みを入れた。
「ちょっと待って。今何を聞こうか考えてるから」
正直に宏紀は今の胸の内を明かした。宏紀はどこか嘘がつけない性格なのかなって、私は思った。真也もそれを見て質問を頭の中で考え出した。
「園田君っていうんですか?」
次が見つからなかった宏紀と真也を見かねて七海が助け船を出した。
『先を越された』、と言わんばかりの表情で宏紀は七海を見た。対人関係が慣れていない感じが見透かされたと思って、少し気まずそうにしている。
「はい」
真也は手を膝の上に乗せたまま頷いた。
「私は、北川七海です」
軽く手を振って七海は挨拶した。
真也は恥ずかしそうに顔を赤く塗って頭を軽く縦に振った。
「二人はもう、友達なんですか?」
確かに講義の初日から一部だけさわやかな空気が漂ってきているのは真也も感じたのだろう。もしかしたら、真也から見たら、宏紀はチャラい感じの印象を持たれているかもしれない。
「中学の同級生なんです、私たち」
どこか恥ずかしそうにしている宏紀。
「えっ? そうなんだ」
真也は目を丸く描いてそう言った。
「マジでビックリしました」
昨日の出来事をもう一度噛みしめながら宏紀は言った。十分すぎるほど味が残っているようだ。
「そうだね。大学が同じならまだしも、学部と学科まで同じなんてすごいね」
「本当にそうだよ」
今ある現実に直視する宏紀。これは夢ではない。いいところで現実世界に引き戻される都合のいい夢ではないはずだ。
隣には七海がいる。確かに七海がいる。
そしてこれから、みんなと人間関係を作っていくんだ。
二時限目の講義が終了する時刻が来た。
これからみんなはランチタイムで、生活環境学部の学生たちは、生活環境学部の建物の一階にある第四食堂でランチを取る子たちがほとんどで、学生食堂のほかに、ベーカリー、イタリアンのお店、コンビニがある。すぐに飽きてしまうことはないだろう。飽きてしまったら、他にも食堂があるからそこを覗いてみればいい。
宏紀は真也を誘って学生たちがひしめき合う第四食堂に降りた。まるで大人気アーティストのコンサート会場のグッズ売り場にいるようだ。
本当は七海も一緒に行きたかったけど、七海はアルバイトの面接があると言って、一足先に大学を後にした。残念そうな顔をしていた宏紀だったけど、でも『また明日から七海に会える』と宏紀は胸をゴムマリのように弾ませていた。表情は初日の対人関係が苦手な男の子が見せる表情には思えない。それぐらい宏紀にとって、七海の存在は大きなものなんだろう。
数多くのテーブルが用意されているけど、すべてがお腹をすかせた学生たちで埋もれていてその場を動くことができない宏紀と真也。二人のように席が空くのを待っている学生たちもいる。
「すごく混んでるね」
真也がそう宏紀に言った。
「本当だね。仕方ないから待ってようか」
「うん、そうだな。次の講義って何時からだっけ?」
宏紀が履修申告をした際にプリントアウトした紙を取り出して、「一時半から」
「それまでに食べられるかな」
「ダメだったらあそこのベーカリーに行こうよ」
「それいいな」
「真也って、どこの人なの?」
初対面でいきなり下の名前で、しかも呼び捨てで呼ぶなんてかなり抵抗があったけど、宏紀は勇気をふり絞って言った。ぎこちなくて少しだけ俯いてしまった。
「長野県だよ。まだこっちの生活に慣れてなくて、だから一人や二人でも話せる人ができて良かった」
真也はまっすぐにピンと立つ髪の毛をかいてそう言った。宏紀の感じたぎこちなさは、慣れない環境が気にも留めさせなかったようだ。宏紀もさぞや安堵しているだろう。
「そうなんだ。じゃあ、こっちで一人暮らしだよね?」
「さすがに長野県から通おうと思えなかった」
真也はおどけてそう言った。宏紀でも今の通学時間に圧倒される勢いなのに。
「そうだよね。僕もここから二時間ぐらいかかるから気が遠くなるよ。横浜の人だから」
「いいな、横浜。都会の人って感じだね」
「東京には近いけど、僕が住んでいるのは田舎の方だよ」
「そうなんだ。七海ちゃんも同じってことだよね?」
七海も宏紀と同じ港南台出身だ。
「そうだよ。でも七海は大学の近くに住んでるよ」
「七海って、なんかドキッとするな」
真也はどこか恥ずかしそうに言った。
「何が?」
「いや、呼び捨てで呼べるっていいなって。そんな深い意味はないよ」
「そうか。同級生だから、いつもの癖が出ちゃったよ」
言い訳がましい自分を隠しつつも、喜びは隠せない様子だった。
「そっか。前から知っている子ならそうなるよね」
宏紀の気まずさを体の一部から感じ取ったのか、真也は事態を収束させようとした。
「真也は、彼女いるの?」
突っ込んだ質問だったと思って、宏紀はまた少し気まずくなった。
「いるわけないよ。こんなにシャイでサッカーしかしてこなかった僕が。田舎だからかわいい子もいなかったから」
意外にもサラリと答えたくれた真也に感謝した。真也みたいに、人前で言いにくいことも変にかっこつけずに言える感じが宏紀は羨ましかった。
「そうなんだ。ここで見つければいいよね」
「そうだな。それが東京の近くに出てきたのもあるから」
そう言って真也は笑っておどけた。それを見ていたら宏紀も真也の笑顔を分けてもらった。
「宏紀はいないの?」
「いないよ」
顔を背けて宏紀は言った。宏紀はこういう話は苦手みたいだ。
「そっか。できたら教えてくれよ。どちら先にできるか楽しみだね」
「競争な」
競争はしたくないけど、宏紀は笑ってそう答えた。
その相手が、七海だったらいいと思っているだろう。宏紀の瞳の中に七海が映っているのは、私じゃなくても分かることかもしれない。
人々が電車という密閉空間から解放されて、東京駅のホームに流れ出る。
私もその群れに紛れて電車を降りた。初日の講義は少し緊張したけど、持ち前の明るさと元気で乗り切った。オリエンテーションの時に話した沙織と、講義も昼食も一緒に共にした。沙織も壁を感じさせない笑顔で手を振ってくれたからすんなりまた会話を交わすことができた。沙織が今日の私服がかわいいって言うから気分が良かった。お気に入りの白のニットワンピを着て、買ったばかりのブラウンのリュックサックを背負ってきた。
それに助けられて、私は自分自身を表現できている。
人の流れに便乗してJR京浜東北線の乗り場に向かう。私が歩くのが遅いのか、人々は私をどんどん追い抜いていく。徒競走なら確実に焦って速度を上げるけど、私はそんなこと気にせずマイペースに足跡をつける。長い通学時間と、初日の講義で疲れているからゆっくりしたい。
私の住む磯子方面行の電車はあと六分後に到着する。
階段を登ると狭いホームにいくつもの人々の行列が目に入る。またここから約一時間、電車に揺られないといけない。少し溜め息をついて列を眺めると、一人の男の子だけがクローズアップされた。見覚えの横顔だった。それは自然と頬が緩んでしまうぐらいきれいで、ずっと眺めていたくなるような表情だった。人生、充実しているってことなのかな。
「あの子……」
私はやめておいた方が良いと分かっていたけど、カタカタとパンプスという楽器で音を奏でながら男の子に近づいて行く。相手に変な目で見られるだけだ。
「すいません」
「はい……」
声をかけられた宏紀は、横を向いてキョトンとしている。警戒心というよりかはビックリしていると今の宏紀を表現した方が良いだろう。
「食品栄養の人ですよね?」
私の言葉をよく噛み砕いてから宏紀は軽く頷いた。
「やっぱり! 私もなんです」
私は思わず自分の記憶力の良さに脱帽した。
「同じ大学なんだね……」
次の言葉が見つからない宏紀。唐突すぎてどうしたらいいか分からない感じだった。こうなることは分かっていたはずだ。
「いきなり声かけてごめんなさい」
不穏な空気を察知して私はそう言った。
「いえ、大丈夫ですよ……」
宏紀は口調はまるで機械のようだった。これはかなり困惑している。このままでは宏紀が自ら終了ボタンを押しかねない。私は咄嗟に「名前は、何て言うんですか?」
「あ、名前……」
だんだん警戒心が増してきた感じが私の顔を顰めさせる。
「ちなみに私は、永井未砂って言います」
まずは自分が名乗るべきだと思って私はそう言った。せめてこの嫌な雰囲気を払拭してからここを去るべきだろう。
「永井さんって言うんだね。僕は深沢宏紀です」
「こうき君って言うんだ。かっこいい名前だね」
「ありがとう……」
警戒しながらも私との会話のレールに乗ってくれた宏紀に感謝した。こういう時はたいてい相手に無視されるか、私が諦めてコミュニケーションの終了ボタンを押すことが多い。
「たくさん並んでるね。次の電車に乗るんですか?」
「うん、乗るよ」
「私は磯子まで行くんですけど、宏紀君はどこまで行くんですか?」
「港南台です」
「近いね!」
大学の学部学科が同じで、地元が同じだとテンションが上がる。他にもいるだろうけど、私にとっては宏紀が記念すべき一人目だったからテンションを上げた。
「そうだね。磯子から三つ先が港南台だからね」
会話らしい会話になってきた。それが嬉しくて私はうなずいて笑顔を送った。
「磯子まで、一緒に帰ってもいいですか?」
「はい、いいですよ」
「やったぁ!」
宏紀は慣れない間でも少しだけ笑ってくれた。
そう話しているうちに電車が来た。ただでさえ人が多い場所に、そこに到着した電車がさらに人を加える。私は宏紀に近づいてエスカレーターに引き込まれないようにした。
ほぼ空っぽになった電車に人々が押し寄せる。みんなの目当ては座席だ。どう考えても座れないだろうと諦めている私たちはゆっくりと足を運ぶ。
宏紀は吊革につかまって、ドア付近にスペースを作って、私を壁にもたれさせてくれた。
私は宏紀と目を合わすと、頬をキュッと上げて笑顔を作った。宏紀はすぐに目を少しだけ動かして、私の鼻と口元のあたりを見つめている。
「何かついてますか?」
宏紀の視線の真相を追いかけるように私は聞いた。ジッと見つめられるのは恥ずかしかったのもある。
「あっ、ごめん。笑窪が、なんていうか」
軽く私は笑窪を触れて、「笑窪がなんですか?」
「なんかいい感じっていうか……」
ストレートに言うのもおかしくてごまかすように宏紀は言った。普通に言うと、印象に残るとかかわいいって言うことなんだと、私はいい風に解釈しておいた。失礼なことを言う子にも見えないから。
「ありがとう。みんなに言われます」
「そうなんだ。同じ学科なんだよね?」
「はい」
「昨日のオリエンテーションの時に、隣にいた女の子に話しかけてなかった?」
自分の行動を振り返ってオリエンテーションの記憶を抽出する。その時に話しかけたのは沙織ぐらいしかいなかったから沙織だろう。
「後ろから、それを見ていたから……変な意味じゃなくてね」
見ていたという言葉に違和感を覚えたのか、宏紀はそう付け足した。
「分かってますよ。笑窪を見て、私だと思ったんですね」
私は顔を覆って赤く染まらせた表情を隠した。
「そういうこと」
言いにくかった宏紀は私がまとめあげた文章に笑顔を見せた。
「その子ともう友達になって、今日も一緒にご飯食べました」
「そうなんだ。早く人と仲良くなれる感じなんだね」
そう捉えてもらえると、冷たいカーペットに毛布を引いてくれたような感覚で、私の居心地はすごくよくなる。
「はい」
カーペットの温かみを肌で感じた私は笑顔で言った。
電車が田町に到着してドアが開いた。街へ解き放つ人、車内に迎え入れる人を見極めて扉が閉まった。
「あの……」
「はい!」
私が威勢の良い声で返事をすると、宏紀は「どうして、僕のこと、知っているというか、声をかけてくれたの?」
「ああ、それは……今日さぁ、講義室で女の子と話してたよね?」
女の子は七海のことだってすぐに分かって宏紀はコクリと頷いた。恥ずかしいのか、一瞬だけ目を逸らしてまた私の口許に目を移す。
「宏紀君の横顔が印象に残って」
宏紀の横顔を再現するために、私は少しだけ移動して今朝見た景色を思い出す。
「それが目印になって!」
「ああ、そうなんだ……」
宏紀から聞いておいて、その後の言葉が続かなくなった。
私の予測だと、そんな理由で話しかけたのかって、思っているんだろう。
「ごめんなさい。ビックリしたよね?」
「いやいや。そうじゃなくて、なんていうか……」
「これから四年間、一緒に勉強する人だし、声かけた方がいいなって」
言い訳のように、宏紀の耳では咀嚼されているかもしれない。でもこれが、私の真実だから素直にそう言った。
「なるほど」
その場では頷いている宏紀だけど、不思議な感覚に包まれたままだった。
「それで、さっきホームで見かけたから、声をかけようって」
笑顔で私は宏紀を見つめた。変なのは分かっている。
「そっか」
宏紀は理解に努めようとしているが、うまくできない感じだった。
「私、そんなに親しくない人でも、一度も話したことない人でも、見たことある人なら声をかけちゃうっていうか。ビックリされるけどね……」
言い訳っぽくてぎこちないけど、私はそう言った。
「どうして? それって、結構勇気のいることだなって思うけど……」
宏紀はそう疑問を投げかけた。宏紀にはもしかしたら考えられないことなのかもしれない。今理解に苦しむ宏紀は、理解への突破口を開こうとしている。
「知っている人だから。知っているのに素通りって、なんか失礼な感じがするから」
「へぇーすごいね」
物珍しいものを見るようではなく、宏紀は小さな笑みを見せた。その表情が私のカーペットに温かみをさらに与えてくれた。言葉では言えないけど、変に思われずに受け止めてくれたようだ。
「なるほどね。永井さんにとっては、普通の行動だったんだね」
「はい! そういうことです」
「声かけてくれてありがとう」
「はい……」
目を丸くして私は言った。どうしてお礼を言われたのか、すぐに宏紀の言葉を飲み込めなかった。私が話しかけたことでぎこちない中で会話をさせられたのにお礼を言ってくれた。
しばらく話していると、目的地に近づいてきていた。磯子のホームにゆっくりと電車が止まった。朝は長く感じた乗車時間があっという間だったような気がする。
「じゃあ、私、降りるね。話してくれてありがとう」
「こちらこそ。気を付けて帰ってね」
私は軽く首を縦に振って、「また一緒に帰ろうね」
「うん」
私は電車を降りてドアが閉まるのを見届けると、宏紀に小さく手を振った。
人と話せるなら、この通学時間も悪くない。
今日の第四時限目の講義が始まって三十分あまり。複数の受講生はホワイトボードではなくて無意味に開かれた参考書に至近距離に視線を落として、講義の内容が入ってこない。宏紀もその中のひとりで、睡魔の餌食になるのを必死に抵抗しながら目を見開こうとしている。
気持ちは分かる。私も今同じような状況で宏紀と同じ講義室にいる。若さで乗り切れると思ったけど、睡魔に手を引っ張られたまま抜け出せない。
宏紀の隣に座っている真也は、宏紀の膝をポンと叩いた。睡魔の執拗な勧誘から宏紀を救い出して現実世界に引き戻した。
「宏紀、もう少しだから頑張れよ」
ゆっくりと顔を上げた宏紀は、手から滑り落ちそうだったシャーペンを握り直して、ライオンのような髪の毛をなびかせながら流暢に講義内容を話していく非常勤教師を見た。
「うん……」
真也が書いているノートと宏紀のノートを見比べると、書き取った文量に大きく差があった。
大きな欠伸を小さくして宏紀は、ノートの上でペンを滑らせた。
私はというと、沙織の隣で睡魔と戯れていた。沙織に後でノートを見せてもらえばいいって、私は割り切っている。眠たい時は、寝た方がいいって。
宏紀はメインストリートを行くと、大きくそびえたつ時計に時刻を知らせてもらった。一時限目の講義までまだ三十分ぐらいある。最初の講義だということもあって、余裕を持たせたからこの時間になった。七海に講義に遅れそうになってあたふたしているさまは見せたくないだろうから。
時計を通り過ぎて、宏紀は学生食堂や国際関係学部、教育学部の建物を眺めながら歩く。
宏紀が口元を動かして自分自身の耳に向けてささやいている。表情はどこか晴れ晴れとしていて曇りはどこにも見られない。七海の存在があるからだろう。人はたった一つのことでも、前向きな表情を見せられるんだ。私も、のちに経験することなんだろう。
生活環境学部の建物が見えてくると、宏紀は少しだけ自分に力を与えて駆け足になった。
この学部は創設されてまだ間もないから、足を踏み入れることでさえ躊躇してしまいそうなぐらいきれいだ。宏紀は中に入るのに勇気が必要だった。昨日はみんな入学式の緊張でそんなことを気にする余裕なんて皆無だったと思うけど。
講義室がある三階に上がると、宏紀はゆっくりと引き戸を開けた。
講義の三十分前だから、集まってきている学生たちはそんなにいなかった。いるのは、大学の近くで一人暮らしをしている生徒か、電車の時刻表の関係で早く来ることを選択した学生たちだ。
宏紀は七海を射程圏内にとらえようとしたけど、まだ来ていないみたいだった。
変な緊張は一気に抜け落ちて、軽い足取りで教室の床を踏んだ。
無意識に宏紀は前方の中央に並ぶ席に着いた。わざわざ聞こえにくい後ろの方に行くことはないと思ったんだろう。
最初の講義だけあってどんな風に進んでいくか未知数だから、宏紀は胸を押さえて鼓動の揺れを知る。とりあえずノートとこの講義で使用する参考書を取り出して目の前に置いた。それらが宏紀の動悸を丸く収めてくれるとは思わないけど、とりあえずの行動だった。
引き戸が再び動き出した。宏紀が後ろを振り返ると、七海がゆっくりと入ってきた。少し焦りを顔に七海は添えていた。
宏紀の姿を見つけると、七海は小さく手を振って近づいて行った。
「おはよう! 講義室間違えて入っちゃった」
焦りを振り払うように七海は体を揺らしている。
「そうなんだ。気付いて良かったね。別の講義受けるところだったじゃん」
私服の七海をほとんど見たことがなかったから、宏紀は新しい七海の一面を見るようで笑みがこぼれる。七海も宏紀の私服は初めてかもしれない。
「本当だよ! マジで焦った!」と七海は胸に手を当てて、「ここ、座っていい?」と宏紀に尋ねた。
「もちろん」
宏紀は隣においていたリュックサックを退けて、七海の席を作った。隣に置いていたのは七海の席を確保していたんだと思う。
「ありがとう。今日、早く起きたんじゃない?」
宏紀の住む横浜市港南台区は私が住んでいる磯子よりももっと距離があるからかなりの長旅になる。約二時間かけて来るから、朝は相当早いだろう。
「うん。これから通学できるかなって心配なった」
そう漏らす宏紀を見てクスッと笑った七海は、「この辺で一人暮らししたらいいよ。思い切って親に言ってみたら?」
「したいけど、金銭的に無理かな」
苦笑しながらも、七海にそう言ってもらえたのは嬉しかっただろう。宏紀って、本当に分かりやすい子だ。
「そうか……今じゃなくても、もう少しお金が貯まったらしたらいいんじゃない?」
「うん……」
したくてもできない状況がもどかしい。宏紀はそう言いたいけど、できない。
「宏紀、その筆箱、まだ使っているんだね」
教科書の寝ころぶ筆箱を見つめて七海は言った。
「よく覚えてるね」
「うん。そのチェックの筆箱かわいかったから覚えているよ」
「すごい!」
細かいことでもすぐに伝える七海が微笑ましい。宏紀はそう思っているだろう。
講義の開始時間が迫ると同時に、総勢百名ほどいる食品栄養学科の生徒たちの顔ぶれが揃いつつある。席も埋まってきて人の威圧感が宏紀たちを包んだ。
この講義の担当教授が入室してきた。頭に白い髪の毛を乗せて、老眼鏡を首からかけ、大きめの紙袋を持っている。ホワイトボードの前に立つと、生徒たちを眺めて微笑んだ。
最初の講義だからみんなが声を一斉に抑えた。
「おはようございます。みんな最初の講義だから、緊張しているかと思いますが始めていきますね」
そう言って学生たちのカチカチに凍った緊張のアイスを溶かすために、中央の最前列に座っている学生たち四人を例に、五分間、隣同士で話をするように指示を出した。
教室全体のあちこちから沈黙を優しくなだめて活気を呼び込む学生たちの声が上がった。
宏紀の隣には黒の短髪に、色白の肌が輝く中学生のような幼い微笑みが印象的な男の子が座っていた。
「おはよう」
宏紀も教室に活気を入れるために、ペコっと頭を下げて言った。
「おはよう」
男の子は緊張の笑顔かと思ったら、自然な笑みを見せたから宏紀も安堵した。
勇気を絞って声をかけた宏紀を七海はその様子を見守っている。
「深沢宏紀って言います。名前はなんて言うんですか?」
「園田真也です。よろしくお願いします」
宏紀は笑みを見せたけど、次の質問を模索していると次の言葉が出てこなくなった。
「宏紀、それだけ?」
七海が鋭く突っ込みを入れた。
「ちょっと待って。今何を聞こうか考えてるから」
正直に宏紀は今の胸の内を明かした。宏紀はどこか嘘がつけない性格なのかなって、私は思った。真也もそれを見て質問を頭の中で考え出した。
「園田君っていうんですか?」
次が見つからなかった宏紀と真也を見かねて七海が助け船を出した。
『先を越された』、と言わんばかりの表情で宏紀は七海を見た。対人関係が慣れていない感じが見透かされたと思って、少し気まずそうにしている。
「はい」
真也は手を膝の上に乗せたまま頷いた。
「私は、北川七海です」
軽く手を振って七海は挨拶した。
真也は恥ずかしそうに顔を赤く塗って頭を軽く縦に振った。
「二人はもう、友達なんですか?」
確かに講義の初日から一部だけさわやかな空気が漂ってきているのは真也も感じたのだろう。もしかしたら、真也から見たら、宏紀はチャラい感じの印象を持たれているかもしれない。
「中学の同級生なんです、私たち」
どこか恥ずかしそうにしている宏紀。
「えっ? そうなんだ」
真也は目を丸く描いてそう言った。
「マジでビックリしました」
昨日の出来事をもう一度噛みしめながら宏紀は言った。十分すぎるほど味が残っているようだ。
「そうだね。大学が同じならまだしも、学部と学科まで同じなんてすごいね」
「本当にそうだよ」
今ある現実に直視する宏紀。これは夢ではない。いいところで現実世界に引き戻される都合のいい夢ではないはずだ。
隣には七海がいる。確かに七海がいる。
そしてこれから、みんなと人間関係を作っていくんだ。
二時限目の講義が終了する時刻が来た。
これからみんなはランチタイムで、生活環境学部の学生たちは、生活環境学部の建物の一階にある第四食堂でランチを取る子たちがほとんどで、学生食堂のほかに、ベーカリー、イタリアンのお店、コンビニがある。すぐに飽きてしまうことはないだろう。飽きてしまったら、他にも食堂があるからそこを覗いてみればいい。
宏紀は真也を誘って学生たちがひしめき合う第四食堂に降りた。まるで大人気アーティストのコンサート会場のグッズ売り場にいるようだ。
本当は七海も一緒に行きたかったけど、七海はアルバイトの面接があると言って、一足先に大学を後にした。残念そうな顔をしていた宏紀だったけど、でも『また明日から七海に会える』と宏紀は胸をゴムマリのように弾ませていた。表情は初日の対人関係が苦手な男の子が見せる表情には思えない。それぐらい宏紀にとって、七海の存在は大きなものなんだろう。
数多くのテーブルが用意されているけど、すべてがお腹をすかせた学生たちで埋もれていてその場を動くことができない宏紀と真也。二人のように席が空くのを待っている学生たちもいる。
「すごく混んでるね」
真也がそう宏紀に言った。
「本当だね。仕方ないから待ってようか」
「うん、そうだな。次の講義って何時からだっけ?」
宏紀が履修申告をした際にプリントアウトした紙を取り出して、「一時半から」
「それまでに食べられるかな」
「ダメだったらあそこのベーカリーに行こうよ」
「それいいな」
「真也って、どこの人なの?」
初対面でいきなり下の名前で、しかも呼び捨てで呼ぶなんてかなり抵抗があったけど、宏紀は勇気をふり絞って言った。ぎこちなくて少しだけ俯いてしまった。
「長野県だよ。まだこっちの生活に慣れてなくて、だから一人や二人でも話せる人ができて良かった」
真也はまっすぐにピンと立つ髪の毛をかいてそう言った。宏紀の感じたぎこちなさは、慣れない環境が気にも留めさせなかったようだ。宏紀もさぞや安堵しているだろう。
「そうなんだ。じゃあ、こっちで一人暮らしだよね?」
「さすがに長野県から通おうと思えなかった」
真也はおどけてそう言った。宏紀でも今の通学時間に圧倒される勢いなのに。
「そうだよね。僕もここから二時間ぐらいかかるから気が遠くなるよ。横浜の人だから」
「いいな、横浜。都会の人って感じだね」
「東京には近いけど、僕が住んでいるのは田舎の方だよ」
「そうなんだ。七海ちゃんも同じってことだよね?」
七海も宏紀と同じ港南台出身だ。
「そうだよ。でも七海は大学の近くに住んでるよ」
「七海って、なんかドキッとするな」
真也はどこか恥ずかしそうに言った。
「何が?」
「いや、呼び捨てで呼べるっていいなって。そんな深い意味はないよ」
「そうか。同級生だから、いつもの癖が出ちゃったよ」
言い訳がましい自分を隠しつつも、喜びは隠せない様子だった。
「そっか。前から知っている子ならそうなるよね」
宏紀の気まずさを体の一部から感じ取ったのか、真也は事態を収束させようとした。
「真也は、彼女いるの?」
突っ込んだ質問だったと思って、宏紀はまた少し気まずくなった。
「いるわけないよ。こんなにシャイでサッカーしかしてこなかった僕が。田舎だからかわいい子もいなかったから」
意外にもサラリと答えたくれた真也に感謝した。真也みたいに、人前で言いにくいことも変にかっこつけずに言える感じが宏紀は羨ましかった。
「そうなんだ。ここで見つければいいよね」
「そうだな。それが東京の近くに出てきたのもあるから」
そう言って真也は笑っておどけた。それを見ていたら宏紀も真也の笑顔を分けてもらった。
「宏紀はいないの?」
「いないよ」
顔を背けて宏紀は言った。宏紀はこういう話は苦手みたいだ。
「そっか。できたら教えてくれよ。どちら先にできるか楽しみだね」
「競争な」
競争はしたくないけど、宏紀は笑ってそう答えた。
その相手が、七海だったらいいと思っているだろう。宏紀の瞳の中に七海が映っているのは、私じゃなくても分かることかもしれない。
人々が電車という密閉空間から解放されて、東京駅のホームに流れ出る。
私もその群れに紛れて電車を降りた。初日の講義は少し緊張したけど、持ち前の明るさと元気で乗り切った。オリエンテーションの時に話した沙織と、講義も昼食も一緒に共にした。沙織も壁を感じさせない笑顔で手を振ってくれたからすんなりまた会話を交わすことができた。沙織が今日の私服がかわいいって言うから気分が良かった。お気に入りの白のニットワンピを着て、買ったばかりのブラウンのリュックサックを背負ってきた。
それに助けられて、私は自分自身を表現できている。
人の流れに便乗してJR京浜東北線の乗り場に向かう。私が歩くのが遅いのか、人々は私をどんどん追い抜いていく。徒競走なら確実に焦って速度を上げるけど、私はそんなこと気にせずマイペースに足跡をつける。長い通学時間と、初日の講義で疲れているからゆっくりしたい。
私の住む磯子方面行の電車はあと六分後に到着する。
階段を登ると狭いホームにいくつもの人々の行列が目に入る。またここから約一時間、電車に揺られないといけない。少し溜め息をついて列を眺めると、一人の男の子だけがクローズアップされた。見覚えの横顔だった。それは自然と頬が緩んでしまうぐらいきれいで、ずっと眺めていたくなるような表情だった。人生、充実しているってことなのかな。
「あの子……」
私はやめておいた方が良いと分かっていたけど、カタカタとパンプスという楽器で音を奏でながら男の子に近づいて行く。相手に変な目で見られるだけだ。
「すいません」
「はい……」
声をかけられた宏紀は、横を向いてキョトンとしている。警戒心というよりかはビックリしていると今の宏紀を表現した方が良いだろう。
「食品栄養の人ですよね?」
私の言葉をよく噛み砕いてから宏紀は軽く頷いた。
「やっぱり! 私もなんです」
私は思わず自分の記憶力の良さに脱帽した。
「同じ大学なんだね……」
次の言葉が見つからない宏紀。唐突すぎてどうしたらいいか分からない感じだった。こうなることは分かっていたはずだ。
「いきなり声かけてごめんなさい」
不穏な空気を察知して私はそう言った。
「いえ、大丈夫ですよ……」
宏紀は口調はまるで機械のようだった。これはかなり困惑している。このままでは宏紀が自ら終了ボタンを押しかねない。私は咄嗟に「名前は、何て言うんですか?」
「あ、名前……」
だんだん警戒心が増してきた感じが私の顔を顰めさせる。
「ちなみに私は、永井未砂って言います」
まずは自分が名乗るべきだと思って私はそう言った。せめてこの嫌な雰囲気を払拭してからここを去るべきだろう。
「永井さんって言うんだね。僕は深沢宏紀です」
「こうき君って言うんだ。かっこいい名前だね」
「ありがとう……」
警戒しながらも私との会話のレールに乗ってくれた宏紀に感謝した。こういう時はたいてい相手に無視されるか、私が諦めてコミュニケーションの終了ボタンを押すことが多い。
「たくさん並んでるね。次の電車に乗るんですか?」
「うん、乗るよ」
「私は磯子まで行くんですけど、宏紀君はどこまで行くんですか?」
「港南台です」
「近いね!」
大学の学部学科が同じで、地元が同じだとテンションが上がる。他にもいるだろうけど、私にとっては宏紀が記念すべき一人目だったからテンションを上げた。
「そうだね。磯子から三つ先が港南台だからね」
会話らしい会話になってきた。それが嬉しくて私はうなずいて笑顔を送った。
「磯子まで、一緒に帰ってもいいですか?」
「はい、いいですよ」
「やったぁ!」
宏紀は慣れない間でも少しだけ笑ってくれた。
そう話しているうちに電車が来た。ただでさえ人が多い場所に、そこに到着した電車がさらに人を加える。私は宏紀に近づいてエスカレーターに引き込まれないようにした。
ほぼ空っぽになった電車に人々が押し寄せる。みんなの目当ては座席だ。どう考えても座れないだろうと諦めている私たちはゆっくりと足を運ぶ。
宏紀は吊革につかまって、ドア付近にスペースを作って、私を壁にもたれさせてくれた。
私は宏紀と目を合わすと、頬をキュッと上げて笑顔を作った。宏紀はすぐに目を少しだけ動かして、私の鼻と口元のあたりを見つめている。
「何かついてますか?」
宏紀の視線の真相を追いかけるように私は聞いた。ジッと見つめられるのは恥ずかしかったのもある。
「あっ、ごめん。笑窪が、なんていうか」
軽く私は笑窪を触れて、「笑窪がなんですか?」
「なんかいい感じっていうか……」
ストレートに言うのもおかしくてごまかすように宏紀は言った。普通に言うと、印象に残るとかかわいいって言うことなんだと、私はいい風に解釈しておいた。失礼なことを言う子にも見えないから。
「ありがとう。みんなに言われます」
「そうなんだ。同じ学科なんだよね?」
「はい」
「昨日のオリエンテーションの時に、隣にいた女の子に話しかけてなかった?」
自分の行動を振り返ってオリエンテーションの記憶を抽出する。その時に話しかけたのは沙織ぐらいしかいなかったから沙織だろう。
「後ろから、それを見ていたから……変な意味じゃなくてね」
見ていたという言葉に違和感を覚えたのか、宏紀はそう付け足した。
「分かってますよ。笑窪を見て、私だと思ったんですね」
私は顔を覆って赤く染まらせた表情を隠した。
「そういうこと」
言いにくかった宏紀は私がまとめあげた文章に笑顔を見せた。
「その子ともう友達になって、今日も一緒にご飯食べました」
「そうなんだ。早く人と仲良くなれる感じなんだね」
そう捉えてもらえると、冷たいカーペットに毛布を引いてくれたような感覚で、私の居心地はすごくよくなる。
「はい」
カーペットの温かみを肌で感じた私は笑顔で言った。
電車が田町に到着してドアが開いた。街へ解き放つ人、車内に迎え入れる人を見極めて扉が閉まった。
「あの……」
「はい!」
私が威勢の良い声で返事をすると、宏紀は「どうして、僕のこと、知っているというか、声をかけてくれたの?」
「ああ、それは……今日さぁ、講義室で女の子と話してたよね?」
女の子は七海のことだってすぐに分かって宏紀はコクリと頷いた。恥ずかしいのか、一瞬だけ目を逸らしてまた私の口許に目を移す。
「宏紀君の横顔が印象に残って」
宏紀の横顔を再現するために、私は少しだけ移動して今朝見た景色を思い出す。
「それが目印になって!」
「ああ、そうなんだ……」
宏紀から聞いておいて、その後の言葉が続かなくなった。
私の予測だと、そんな理由で話しかけたのかって、思っているんだろう。
「ごめんなさい。ビックリしたよね?」
「いやいや。そうじゃなくて、なんていうか……」
「これから四年間、一緒に勉強する人だし、声かけた方がいいなって」
言い訳のように、宏紀の耳では咀嚼されているかもしれない。でもこれが、私の真実だから素直にそう言った。
「なるほど」
その場では頷いている宏紀だけど、不思議な感覚に包まれたままだった。
「それで、さっきホームで見かけたから、声をかけようって」
笑顔で私は宏紀を見つめた。変なのは分かっている。
「そっか」
宏紀は理解に努めようとしているが、うまくできない感じだった。
「私、そんなに親しくない人でも、一度も話したことない人でも、見たことある人なら声をかけちゃうっていうか。ビックリされるけどね……」
言い訳っぽくてぎこちないけど、私はそう言った。
「どうして? それって、結構勇気のいることだなって思うけど……」
宏紀はそう疑問を投げかけた。宏紀にはもしかしたら考えられないことなのかもしれない。今理解に苦しむ宏紀は、理解への突破口を開こうとしている。
「知っている人だから。知っているのに素通りって、なんか失礼な感じがするから」
「へぇーすごいね」
物珍しいものを見るようではなく、宏紀は小さな笑みを見せた。その表情が私のカーペットに温かみをさらに与えてくれた。言葉では言えないけど、変に思われずに受け止めてくれたようだ。
「なるほどね。永井さんにとっては、普通の行動だったんだね」
「はい! そういうことです」
「声かけてくれてありがとう」
「はい……」
目を丸くして私は言った。どうしてお礼を言われたのか、すぐに宏紀の言葉を飲み込めなかった。私が話しかけたことでぎこちない中で会話をさせられたのにお礼を言ってくれた。
しばらく話していると、目的地に近づいてきていた。磯子のホームにゆっくりと電車が止まった。朝は長く感じた乗車時間があっという間だったような気がする。
「じゃあ、私、降りるね。話してくれてありがとう」
「こちらこそ。気を付けて帰ってね」
私は軽く首を縦に振って、「また一緒に帰ろうね」
「うん」
私は電車を降りてドアが閉まるのを見届けると、宏紀に小さく手を振った。
人と話せるなら、この通学時間も悪くない。
今日の第四時限目の講義が始まって三十分あまり。複数の受講生はホワイトボードではなくて無意味に開かれた参考書に至近距離に視線を落として、講義の内容が入ってこない。宏紀もその中のひとりで、睡魔の餌食になるのを必死に抵抗しながら目を見開こうとしている。
気持ちは分かる。私も今同じような状況で宏紀と同じ講義室にいる。若さで乗り切れると思ったけど、睡魔に手を引っ張られたまま抜け出せない。
宏紀の隣に座っている真也は、宏紀の膝をポンと叩いた。睡魔の執拗な勧誘から宏紀を救い出して現実世界に引き戻した。
「宏紀、もう少しだから頑張れよ」
ゆっくりと顔を上げた宏紀は、手から滑り落ちそうだったシャーペンを握り直して、ライオンのような髪の毛をなびかせながら流暢に講義内容を話していく非常勤教師を見た。
「うん……」
真也が書いているノートと宏紀のノートを見比べると、書き取った文量に大きく差があった。
大きな欠伸を小さくして宏紀は、ノートの上でペンを滑らせた。
私はというと、沙織の隣で睡魔と戯れていた。沙織に後でノートを見せてもらえばいいって、私は割り切っている。眠たい時は、寝た方がいいって。