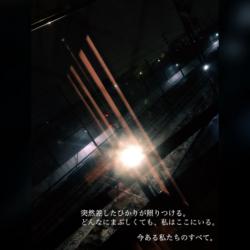みなさん、こんにちは! 大学四年の永井未砂と言います。
スーツを着て大学にいるなんて、なんか変な感じ。そう、大学生を名乗るのももうすぐ終わってしまう。社会人として新しいステージに行くのは楽しみだけど、学科の子や後輩たちと会えなくなるのは寂しいな。
この物語は、私が大学一年生の時に経験した恋のはなしです。
私、なんでか分からないけどナレーションもすることになって(笑)。一人二役は結構な負担なんですけど、物語の私と、ナレーションの私で混乱することのないよう、みなさんついてきてくださいね!
それでは、第一章「心にひかりを灯す人」へご案内します!
苦しいあの日々はもうしまっておこう。それでみんなで同じ方向を見られれば。
それに宏紀の笑顔を添えよう。小さな笑顔ではあるけど、それを見ると私は嬉しくなる。
期待と不安が入り混じる。
周囲にバレないように見渡す。キョロキョロしていると変人扱いされる。男子が三割、女子が七割の割合でスーツに身にまとった集団が緊張の面持ちで、緑ヶ丘大学・生活環境学部・食品栄養学科の学生として最初を飾る。もうすぐ、学科別のオリエンテーションの幕が切って落とされる。ちらほら話し声は聞こえてくるけど、みんな小さな声ばかり。威勢の良い声をあげるには勇気がいるだろう。
そんな重くのしかかる空気を切り裂くために、私、永井未砂(みさ)は隣にいる女の子に声をかけようと思った。その子がアイドル並みに可愛くてずっと眺めていたくなった。
自分で容姿を描写するのは難しい。高校の友達から、顔のラインに張り付いてくる黒髪のボブヘアーがチャームポイントで、笑うと現れる笑窪が印象的だって言われた。高校の時に、『目が合うと笑ってくれるから安心する』と言われたのが、すごく嬉しかった。
小さいころから人と話すのが大好きで、何振りかまわず人に話しかけるから、お母さんに、「あんまり失礼なこと聞かないでね」と、念を押されたこともあった。
そんなつもりはなかったからとても心外だった。ただ人と楽しく話をしたいだけだ。今のオリエンテーションの重たい空気を切り裂きたいって思ったのも、私のこの性格が影響している。
それでも、最近は人と距離を置くって言うことも覚えてきた。犯罪に巻き込まれることもあるから。
さりげなく女の子を見ると、相手もこの重苦しい空気に耐えかねたのか目を合わせてくれた。
「私、永井未砂って言います。名前、何て言うんですか?」
体を少しだけ女の子の方に向けて私は笑窪を光らせた。
「丹羽沙織です」
まともな返事が返ってきたから胸を撫で下ろした。
私は来る人は誰でも大歓迎だからいいけど、相手によってはただの八方美人に思われて陰で悪口まではいかないけど噂をされることも多々あった。だから普通に会話をしてくれた沙織に感謝した。
「千葉の人ですか?」
私たちが通う緑ヶ丘大学は千葉県にある。
「私、愛知県から来たんです。千葉の人ですか?」
「神奈川の磯子っていうところです……分からないよね?」
沙織の戸惑った表情を見せた。
「……分からない」
困った表情がまたかわいい。もっと困らせてみたいって思ったけど、やらない。出会いから人をいじっていてはダメだと思い直す。
笑窪をここぞの時の武器のように再び光らせて「じゃあ、今度、案内しますね」と言った。
「お願いします」
素直なだけで好きになってしまいそうだった。
オリエンテーションが終わると、生活環境学部の建物から出てきた新入生が、先輩たちにクラブやサークルのビラの嵐に出迎えられた。
「ラクロス部、よろしくお願いします!」
「バレーボール、私たちと一緒にやりませんか?」
「写真で、私たちの世界を変えましょう!」
そんなうたい文句を掲げて、先輩たちの熱のこもった声が響き渡る。
私だったら喜んですべてのビラを受け取ってあげたいけど、積極的に部活動に入る気になれなかった。緑ヶ丘大学から私の自宅がある磯子まで約一時間半かかる。往復すると三時間だ。この時間が私のクラブやサークルへの思いを削いだ。両サイドから熱烈な歓迎を受けても無視しないといけないのが辛い。うっすら笑みを浮かべながら先輩の間をすり抜けた。
一方で、何事もなかったかのように建物から出てくる一人の男の子がいた。彼もスーツを着ているから新入生だろう。背は高くもなく低くもないちょうどいい身長に、長い前髪を七三で分けている。パッチリした大きな目が印象的でどこか影を持っているイケメンっていう感じ。彼の名前は、深沢宏紀(こうき)。
宏紀は多くの生徒たちが先輩たちに捕まっているさまを見てどこか寂しそうにしている。もしかしたら、私と同じようにクラブやサークルに入られない事情でもあるのだろうか。そんな雰囲気を携えて、宏紀は多くの新入生に紛れてメインストリートに出た。
宏紀は春風に吹かれてスーツのズボンに手を突っ込んで歩き始めた。
「ねぇ!」
宏紀は振り返った。
呼んだのは私じゃない。
目の前には背丈があって長い黒髪の女の子がいた。きれいな顔立ちで薄っすらと笑みを浮かべて立っている。
宏紀は自分が呼ばれたのでないと判断して、また前を向いて歩いて行ってしまった。新入生だからここに知り合いはいないはず。だから宏紀の行動は自然かもしれない。私なら、「私ですか?」って笑顔で聞いていただろう。
女の子は宏紀を追いかけて、優しくポンポンと、まるで買ったばかりの可愛い人形を扱うように、宏紀の肩を叩いた。
また宏紀は振り返って、女の子を見つめた。
「こうき……だよね?」
「はい……」
宏紀は反射的にそう答えた。状況が把握できなくて困惑している感じだ。目の前で名前を呼んだ女の子を記憶の中で探している。薄暗い場所をさまようかのように記憶の中を歩いていくと、一つのメッセージが返ってきた。記憶の出所は中学生のころだった。
「ななみ?」
「うん!」
トランポリンで跳ねるように七海は体を弾ませて言った。
「北川七海?」
「そうそう! やっぱり宏紀だ」
再び七海は興奮して体一杯に喜びを表現した。
「久しぶり! 元気だった?」
「うん! 良かったぁ。間違えちゃったかと思って心臓バクバクしたよ!」
七海は胸のあたりを抑えて、静まりつつある鼓動を聞きながら安堵した。
こうして二人は、久しぶりの再会に声を弾ませた。
スーツを着て大学にいるなんて、なんか変な感じ。そう、大学生を名乗るのももうすぐ終わってしまう。社会人として新しいステージに行くのは楽しみだけど、学科の子や後輩たちと会えなくなるのは寂しいな。
この物語は、私が大学一年生の時に経験した恋のはなしです。
私、なんでか分からないけどナレーションもすることになって(笑)。一人二役は結構な負担なんですけど、物語の私と、ナレーションの私で混乱することのないよう、みなさんついてきてくださいね!
それでは、第一章「心にひかりを灯す人」へご案内します!
苦しいあの日々はもうしまっておこう。それでみんなで同じ方向を見られれば。
それに宏紀の笑顔を添えよう。小さな笑顔ではあるけど、それを見ると私は嬉しくなる。
期待と不安が入り混じる。
周囲にバレないように見渡す。キョロキョロしていると変人扱いされる。男子が三割、女子が七割の割合でスーツに身にまとった集団が緊張の面持ちで、緑ヶ丘大学・生活環境学部・食品栄養学科の学生として最初を飾る。もうすぐ、学科別のオリエンテーションの幕が切って落とされる。ちらほら話し声は聞こえてくるけど、みんな小さな声ばかり。威勢の良い声をあげるには勇気がいるだろう。
そんな重くのしかかる空気を切り裂くために、私、永井未砂(みさ)は隣にいる女の子に声をかけようと思った。その子がアイドル並みに可愛くてずっと眺めていたくなった。
自分で容姿を描写するのは難しい。高校の友達から、顔のラインに張り付いてくる黒髪のボブヘアーがチャームポイントで、笑うと現れる笑窪が印象的だって言われた。高校の時に、『目が合うと笑ってくれるから安心する』と言われたのが、すごく嬉しかった。
小さいころから人と話すのが大好きで、何振りかまわず人に話しかけるから、お母さんに、「あんまり失礼なこと聞かないでね」と、念を押されたこともあった。
そんなつもりはなかったからとても心外だった。ただ人と楽しく話をしたいだけだ。今のオリエンテーションの重たい空気を切り裂きたいって思ったのも、私のこの性格が影響している。
それでも、最近は人と距離を置くって言うことも覚えてきた。犯罪に巻き込まれることもあるから。
さりげなく女の子を見ると、相手もこの重苦しい空気に耐えかねたのか目を合わせてくれた。
「私、永井未砂って言います。名前、何て言うんですか?」
体を少しだけ女の子の方に向けて私は笑窪を光らせた。
「丹羽沙織です」
まともな返事が返ってきたから胸を撫で下ろした。
私は来る人は誰でも大歓迎だからいいけど、相手によってはただの八方美人に思われて陰で悪口まではいかないけど噂をされることも多々あった。だから普通に会話をしてくれた沙織に感謝した。
「千葉の人ですか?」
私たちが通う緑ヶ丘大学は千葉県にある。
「私、愛知県から来たんです。千葉の人ですか?」
「神奈川の磯子っていうところです……分からないよね?」
沙織の戸惑った表情を見せた。
「……分からない」
困った表情がまたかわいい。もっと困らせてみたいって思ったけど、やらない。出会いから人をいじっていてはダメだと思い直す。
笑窪をここぞの時の武器のように再び光らせて「じゃあ、今度、案内しますね」と言った。
「お願いします」
素直なだけで好きになってしまいそうだった。
オリエンテーションが終わると、生活環境学部の建物から出てきた新入生が、先輩たちにクラブやサークルのビラの嵐に出迎えられた。
「ラクロス部、よろしくお願いします!」
「バレーボール、私たちと一緒にやりませんか?」
「写真で、私たちの世界を変えましょう!」
そんなうたい文句を掲げて、先輩たちの熱のこもった声が響き渡る。
私だったら喜んですべてのビラを受け取ってあげたいけど、積極的に部活動に入る気になれなかった。緑ヶ丘大学から私の自宅がある磯子まで約一時間半かかる。往復すると三時間だ。この時間が私のクラブやサークルへの思いを削いだ。両サイドから熱烈な歓迎を受けても無視しないといけないのが辛い。うっすら笑みを浮かべながら先輩の間をすり抜けた。
一方で、何事もなかったかのように建物から出てくる一人の男の子がいた。彼もスーツを着ているから新入生だろう。背は高くもなく低くもないちょうどいい身長に、長い前髪を七三で分けている。パッチリした大きな目が印象的でどこか影を持っているイケメンっていう感じ。彼の名前は、深沢宏紀(こうき)。
宏紀は多くの生徒たちが先輩たちに捕まっているさまを見てどこか寂しそうにしている。もしかしたら、私と同じようにクラブやサークルに入られない事情でもあるのだろうか。そんな雰囲気を携えて、宏紀は多くの新入生に紛れてメインストリートに出た。
宏紀は春風に吹かれてスーツのズボンに手を突っ込んで歩き始めた。
「ねぇ!」
宏紀は振り返った。
呼んだのは私じゃない。
目の前には背丈があって長い黒髪の女の子がいた。きれいな顔立ちで薄っすらと笑みを浮かべて立っている。
宏紀は自分が呼ばれたのでないと判断して、また前を向いて歩いて行ってしまった。新入生だからここに知り合いはいないはず。だから宏紀の行動は自然かもしれない。私なら、「私ですか?」って笑顔で聞いていただろう。
女の子は宏紀を追いかけて、優しくポンポンと、まるで買ったばかりの可愛い人形を扱うように、宏紀の肩を叩いた。
また宏紀は振り返って、女の子を見つめた。
「こうき……だよね?」
「はい……」
宏紀は反射的にそう答えた。状況が把握できなくて困惑している感じだ。目の前で名前を呼んだ女の子を記憶の中で探している。薄暗い場所をさまようかのように記憶の中を歩いていくと、一つのメッセージが返ってきた。記憶の出所は中学生のころだった。
「ななみ?」
「うん!」
トランポリンで跳ねるように七海は体を弾ませて言った。
「北川七海?」
「そうそう! やっぱり宏紀だ」
再び七海は興奮して体一杯に喜びを表現した。
「久しぶり! 元気だった?」
「うん! 良かったぁ。間違えちゃったかと思って心臓バクバクしたよ!」
七海は胸のあたりを抑えて、静まりつつある鼓動を聞きながら安堵した。
こうして二人は、久しぶりの再会に声を弾ませた。