庭仕事に勤しむ祖母に声を掛けてから家を出ると、期待と不安を一緒くたに背負い、約束の場所を目指して赤土の耕作地を進む。
幼少の頃より何回この道を通って海まで足を運んだことだろう。
そのすべてで夏の日差しは容赦なく俺の肌を灼いた。
ただ、今日に限っては少しだけ時期が早く、また時間も遅いせいだろうか。
涼しいかと言われればそんなことはなかったが、少なくとも今夜風呂に入った時に、湯が肌に染みるといったことにはならずに済みそうだった。
やがて突き当たった竹藪のトンネルを潜り抜けた途端、じきに訪れるであろう黄昏をわずかに匂わせる瑠璃色の空と、それを反映して青藍の深みを増した海とが目の前に広がる。
足元に咲き乱れるハマゴウの花たちを踏みつけないように気をつけながら、その中ほどに居場所を見つけて腰を降ろす。
遥か水平線の上に浮かぶ入道雲に目を向けると、綿菓子のようなその表面に白い稲光が走るのが見えた。
だが、遠く離れたこの場所にまで雷鳴が届くことはなく、打ち寄せては崩れ去る波の音だけが聞こえてくる。
そうして三十分も経っただろうか。
気づかないうちに少しだけ風が出てきていた。
ともに海を見下ろしていたハマゴウたちが、その可憐で小さな花をサラサラと小さく揺さぶる音が、さざ波の音に混じりかすかに聞こえてくる。
すぐ近くにあった一輪のそれを手のひらでそっと包む。
本当はすべてをそうしてやりたかったが、この世界にはいくら望んだところで叶えられぬ願いがあることを、十七歳になった俺は知ってしまっていた。
「おまたせしました」
唐突に鈴の音ような涼し気な声が耳に届き、その方向に顔を向ける。
「俺もいま来たところだよ」
この形式張ったやり取りをするのは何度目だったか。
彼女は俺と目が合うと、両手を身体の前で重ねて小さく頭を下げた。
その他人行儀な姿に再び胸が痛み、昨日の夜から用意しておいた言葉が喉の奥へと引っ込んでしまう。
俺は無言のままで立ち上がり、彼女の方に歩み寄った。
そこでようやくひとつだけ取り出すことに成功した台詞を、浜風にかき消されぬギリギリの声量で投げかける。
「少しだけ歩かない?」
彼女の方を向くことはできず、かといって真っ直ぐ顔を上げる気にもなれなかった。
足元から一メートルほどの地面を見下ろしながら、波打ち際から少しだけ離れた砂浜の上をゆっくりと歩く。
すぐ後ろからは彼女が踏んだ砂の乾いた音が、ラジオのノイズにも似た波の音に紛れて聞こえてくる。
たまに足元を過る黒く小さな影は、塒へと帰ってゆく海鳥たちのものだろうか?
その姿を捉えようと見上げた空は、東の端から徐々に消炭色のコントラストを強めつつあった。
「夏生さん」
後ろから呼び掛けられて足を止める。
いつの間にか立ち止まっていた彼女は、肩に掛けた小さなポシェットから何かを取り出すと、二歩三歩とこちらに歩み寄ってくる。
そして、無言でそれを俺の胸の前に差し出した。
それは水色の小さな封筒だった。
「これは?」
ほとんど反射的に受け取りながら尋ねると、彼女はその小さく薄い唇を静かに開いた。
幼少の頃より何回この道を通って海まで足を運んだことだろう。
そのすべてで夏の日差しは容赦なく俺の肌を灼いた。
ただ、今日に限っては少しだけ時期が早く、また時間も遅いせいだろうか。
涼しいかと言われればそんなことはなかったが、少なくとも今夜風呂に入った時に、湯が肌に染みるといったことにはならずに済みそうだった。
やがて突き当たった竹藪のトンネルを潜り抜けた途端、じきに訪れるであろう黄昏をわずかに匂わせる瑠璃色の空と、それを反映して青藍の深みを増した海とが目の前に広がる。
足元に咲き乱れるハマゴウの花たちを踏みつけないように気をつけながら、その中ほどに居場所を見つけて腰を降ろす。
遥か水平線の上に浮かぶ入道雲に目を向けると、綿菓子のようなその表面に白い稲光が走るのが見えた。
だが、遠く離れたこの場所にまで雷鳴が届くことはなく、打ち寄せては崩れ去る波の音だけが聞こえてくる。
そうして三十分も経っただろうか。
気づかないうちに少しだけ風が出てきていた。
ともに海を見下ろしていたハマゴウたちが、その可憐で小さな花をサラサラと小さく揺さぶる音が、さざ波の音に混じりかすかに聞こえてくる。
すぐ近くにあった一輪のそれを手のひらでそっと包む。
本当はすべてをそうしてやりたかったが、この世界にはいくら望んだところで叶えられぬ願いがあることを、十七歳になった俺は知ってしまっていた。
「おまたせしました」
唐突に鈴の音ような涼し気な声が耳に届き、その方向に顔を向ける。
「俺もいま来たところだよ」
この形式張ったやり取りをするのは何度目だったか。
彼女は俺と目が合うと、両手を身体の前で重ねて小さく頭を下げた。
その他人行儀な姿に再び胸が痛み、昨日の夜から用意しておいた言葉が喉の奥へと引っ込んでしまう。
俺は無言のままで立ち上がり、彼女の方に歩み寄った。
そこでようやくひとつだけ取り出すことに成功した台詞を、浜風にかき消されぬギリギリの声量で投げかける。
「少しだけ歩かない?」
彼女の方を向くことはできず、かといって真っ直ぐ顔を上げる気にもなれなかった。
足元から一メートルほどの地面を見下ろしながら、波打ち際から少しだけ離れた砂浜の上をゆっくりと歩く。
すぐ後ろからは彼女が踏んだ砂の乾いた音が、ラジオのノイズにも似た波の音に紛れて聞こえてくる。
たまに足元を過る黒く小さな影は、塒へと帰ってゆく海鳥たちのものだろうか?
その姿を捉えようと見上げた空は、東の端から徐々に消炭色のコントラストを強めつつあった。
「夏生さん」
後ろから呼び掛けられて足を止める。
いつの間にか立ち止まっていた彼女は、肩に掛けた小さなポシェットから何かを取り出すと、二歩三歩とこちらに歩み寄ってくる。
そして、無言でそれを俺の胸の前に差し出した。
それは水色の小さな封筒だった。
「これは?」
ほとんど反射的に受け取りながら尋ねると、彼女はその小さく薄い唇を静かに開いた。
「それはお姉ちゃんが夏生さんに書いた手紙です」
手にした封筒に目を落としたまま、彼女がいま何を言ったのかを理解しようとした。
お姉ちゃん?
なぜ彼女の姉が俺に手紙を?
手元から視線を上げて彼女の顔を見ると、ふたたびその小さな唇がゆっくりと動き、言葉の続きを発した。
それは今しがた抱いた疑問に対する明確な回答だったのだが、それでも尚、彼女が一体何を言っているのかまったく理解できなかった。
「お姉ちゃんは二年前に亡くなりました。私は志帆の妹で美帆といいます」
「え」
彼女は何を言っているんだろう?
「あ」
もしかして、この子が志帆ちゃんの妹だと?
「ああ」
だから容姿があの夏とまったく変わって――。
「え」
亡くなったって?
「……」
亡くなった? 誰が?
「……あ」
あ。
「……志帆ちゃんが」
ああ。
ようやく俺は、理解してしまった。
その瞬間、後頭部をバットで殴られたかのような強い衝撃を受け、温かな砂の上に膝から崩れ落ちた。
そのまま土下座でもするような格好で額を強く砂に擦りつける。
息ができない。
声がでない。
涙もでない。
「あの……」
すぐ近くから聞き慣れた声が聞こえた。
顔を上げれば見慣れた姿もそこにあるはずだ。
しかし、その聞き慣れた声と見慣れた姿の少女は、彼女の妹であって彼女ではない。
鼻先にある砂の上に大きな雫がポタポタと落ち、みるみるうちに砂の色を白から黒へと変えていく。
やっと涙が出てくれた。
「……あああ……あああああ!」
やっと声が出てくれた。
あの夏の日に出会った少女は。
会ってすぐに惹かれ合った少女は。
夕暮れの砂浜で口づけを交わした少女は。
俺の大好きだった少女は、志帆ちゃんは。
志帆ちゃんはこの世界から、永遠に失われてしまったのだ。
どのくらいの時間が経っただろう。
ようやく顔を上げた俺の目に飛び込んできたのは、志帆ちゃんの妹――美帆ちゃんが肩を激しく上下させ、瞳から溢れ続ける涙を両手の甲で懸命に拭っている姿だった。
よろよろと立ち上がって彼女に歩み寄り、その白い肩にそっと手を置く。
途端に彼女は膝から崩れ落ち、砂の上に突っ伏してしまう。
すぐ横に腰を降ろして背中を擦ると、彼女は俺の膝の上に顔を埋め、その小さな身体を大きく震わせる。
彼女の涙を吸った俺のジーンズは、麦わら帽子を追いかけて海に落ちたあの夏の日のように、その青色をみるみるうちに深く濃くしていった。
しばらくのあと、ゆっくりと顔を上げた彼女の目はウサギのように真っ赤に充血しており、涙の伝った頬には沢山の砂が貼り付いていた。
白磁の肌を傷付けぬよう細心の注意を払い、親指の腹でそっと砂の粒を落とす。
「……ありがとうございます」
乱れた髪を手櫛で整えた彼女は俺の横で膝を曲げると、おもむろにその顔をこちらに向け、そして口を開いた。
「夏生さんのことは、お姉ちゃんから何度も聞いていたんです」
彼女はそれだけ言うと、今度は水平線の方向に顔を向けた。
その横顔は本当に姉の志帆ちゃんにそっくりで、またしても俺はあの日の夏に戻ったかのような錯覚を起こす。
「あの年の夏は私たち家族にとって、すごく特別な夏でした」
当時小学五年生だった私は、突然決まったお母さんの再婚と、やはり急な転校の予定に胸を痛めていた。
お父さんが亡くなってから心を弱らせていたお母さんに代わり、甲斐甲斐しく家事をしたり私の世話を焼いてくれていたお姉ちゃんも、どうやらそれは同じだったようだ。
家族の会話は日に日に減っていき、やがて家の中には常に冷たい空気が漂うようになっていた。
お盆初日の、八月十三日の夕方。
自室で机に向かい、夏休みの宿題をしていた時だった。
何やら玄関の方からバタバタと大きな足音が聞こえてくる。
その大きな足音の主は、次の瞬間にはもう私の部屋の前までやってくると、そのままの勢いでドアをバタンと開けて入ってきた。
そこに居たのはお姉ちゃんで、その顔は久しく見ていなかった笑顔で満たされていた。
「美帆ちゃん聞いて! お姉ちゃん今日ね、すっごい面白い人とお友達になったよ!」
お姉ちゃんが息を弾ませて語ったのは、風に飛ばされた帽子をびしょ濡れになりながら取ってくれた、同い年の男の子の話だった。
その日からお姉ちゃんは毎日のように出掛けていき、帰ってくる度に『彼』の話をしてくれた。
会ったこともない『彼』の話を聞くと、私も自然と笑顔になることが出来た。
引っ越しを翌日に控えたお盆の終わりの日も、いつものように出掛けていったお姉ちゃんが帰って来たことに気がついて、今日も『彼』の話を聞かせてもらおうと部屋のドアの前に立った。
ノックをしようとしたその時、ドアの向こう側から泣き声が聞こえた。
結局その日お姉ちゃんは、一度も部屋から出てこなかった。
引っ越し当日の朝。
お姉ちゃんは昨日の昼までそうだったように、笑顔で「おはよう」と言ってくれた。
でも、それ以降お姉ちゃんの口から『彼』の話を聞くことはなかった。
引っ越し先は全く知らない土地だった。
気候も方言も前に住んでいたところとはだいぶ違ったが、それでも友達はすぐに出来たし、クラスに馴染むこともできた。
新しいお父さんもとても優しくて、何より嬉しかったのは、お母さんが前より笑顔をみせてくれる機会が多くなったことだった。
引っ越してから一年が過ぎた、ある日。
学校から戻り、部屋でランドセルの中から教科書やノートを取り出していた時だった。
隣のお姉ちゃんの部屋で大きな物音がした。
お姉ちゃんは朝から体調が悪く、今日は学校を休んでいたはずだった。
ノックをしてからドアを開けると、お姉ちゃんはベッドの上で膝を抱え込むようにして体を丸めていた。
苦痛に歪ませた顔は深い海のように真っ青で、私が部屋に入ってきたことにすら気付いていないようだった。
すぐにお母さんの職場に電話を掛けると、お母さんが帰ってくるよりも早く到着した救急車で、お姉ちゃんは病院へと運ばれていった。
そして、次の日の夜。
顔に白い布を掛けられ戻ってきたお姉ちゃんは、もう二度と話してくれることも、もう二度と笑顔を見せてくれることもなかった。
詳しい病名は教えてもらっていないが、心臓の筋肉に異常が起きたのが原因だということだけは、お通夜の席で大人たちが話しているのを聞いて知った。
手にした封筒に目を落としたまま、彼女がいま何を言ったのかを理解しようとした。
お姉ちゃん?
なぜ彼女の姉が俺に手紙を?
手元から視線を上げて彼女の顔を見ると、ふたたびその小さな唇がゆっくりと動き、言葉の続きを発した。
それは今しがた抱いた疑問に対する明確な回答だったのだが、それでも尚、彼女が一体何を言っているのかまったく理解できなかった。
「お姉ちゃんは二年前に亡くなりました。私は志帆の妹で美帆といいます」
「え」
彼女は何を言っているんだろう?
「あ」
もしかして、この子が志帆ちゃんの妹だと?
「ああ」
だから容姿があの夏とまったく変わって――。
「え」
亡くなったって?
「……」
亡くなった? 誰が?
「……あ」
あ。
「……志帆ちゃんが」
ああ。
ようやく俺は、理解してしまった。
その瞬間、後頭部をバットで殴られたかのような強い衝撃を受け、温かな砂の上に膝から崩れ落ちた。
そのまま土下座でもするような格好で額を強く砂に擦りつける。
息ができない。
声がでない。
涙もでない。
「あの……」
すぐ近くから聞き慣れた声が聞こえた。
顔を上げれば見慣れた姿もそこにあるはずだ。
しかし、その聞き慣れた声と見慣れた姿の少女は、彼女の妹であって彼女ではない。
鼻先にある砂の上に大きな雫がポタポタと落ち、みるみるうちに砂の色を白から黒へと変えていく。
やっと涙が出てくれた。
「……あああ……あああああ!」
やっと声が出てくれた。
あの夏の日に出会った少女は。
会ってすぐに惹かれ合った少女は。
夕暮れの砂浜で口づけを交わした少女は。
俺の大好きだった少女は、志帆ちゃんは。
志帆ちゃんはこの世界から、永遠に失われてしまったのだ。
どのくらいの時間が経っただろう。
ようやく顔を上げた俺の目に飛び込んできたのは、志帆ちゃんの妹――美帆ちゃんが肩を激しく上下させ、瞳から溢れ続ける涙を両手の甲で懸命に拭っている姿だった。
よろよろと立ち上がって彼女に歩み寄り、その白い肩にそっと手を置く。
途端に彼女は膝から崩れ落ち、砂の上に突っ伏してしまう。
すぐ横に腰を降ろして背中を擦ると、彼女は俺の膝の上に顔を埋め、その小さな身体を大きく震わせる。
彼女の涙を吸った俺のジーンズは、麦わら帽子を追いかけて海に落ちたあの夏の日のように、その青色をみるみるうちに深く濃くしていった。
しばらくのあと、ゆっくりと顔を上げた彼女の目はウサギのように真っ赤に充血しており、涙の伝った頬には沢山の砂が貼り付いていた。
白磁の肌を傷付けぬよう細心の注意を払い、親指の腹でそっと砂の粒を落とす。
「……ありがとうございます」
乱れた髪を手櫛で整えた彼女は俺の横で膝を曲げると、おもむろにその顔をこちらに向け、そして口を開いた。
「夏生さんのことは、お姉ちゃんから何度も聞いていたんです」
彼女はそれだけ言うと、今度は水平線の方向に顔を向けた。
その横顔は本当に姉の志帆ちゃんにそっくりで、またしても俺はあの日の夏に戻ったかのような錯覚を起こす。
「あの年の夏は私たち家族にとって、すごく特別な夏でした」
当時小学五年生だった私は、突然決まったお母さんの再婚と、やはり急な転校の予定に胸を痛めていた。
お父さんが亡くなってから心を弱らせていたお母さんに代わり、甲斐甲斐しく家事をしたり私の世話を焼いてくれていたお姉ちゃんも、どうやらそれは同じだったようだ。
家族の会話は日に日に減っていき、やがて家の中には常に冷たい空気が漂うようになっていた。
お盆初日の、八月十三日の夕方。
自室で机に向かい、夏休みの宿題をしていた時だった。
何やら玄関の方からバタバタと大きな足音が聞こえてくる。
その大きな足音の主は、次の瞬間にはもう私の部屋の前までやってくると、そのままの勢いでドアをバタンと開けて入ってきた。
そこに居たのはお姉ちゃんで、その顔は久しく見ていなかった笑顔で満たされていた。
「美帆ちゃん聞いて! お姉ちゃん今日ね、すっごい面白い人とお友達になったよ!」
お姉ちゃんが息を弾ませて語ったのは、風に飛ばされた帽子をびしょ濡れになりながら取ってくれた、同い年の男の子の話だった。
その日からお姉ちゃんは毎日のように出掛けていき、帰ってくる度に『彼』の話をしてくれた。
会ったこともない『彼』の話を聞くと、私も自然と笑顔になることが出来た。
引っ越しを翌日に控えたお盆の終わりの日も、いつものように出掛けていったお姉ちゃんが帰って来たことに気がついて、今日も『彼』の話を聞かせてもらおうと部屋のドアの前に立った。
ノックをしようとしたその時、ドアの向こう側から泣き声が聞こえた。
結局その日お姉ちゃんは、一度も部屋から出てこなかった。
引っ越し当日の朝。
お姉ちゃんは昨日の昼までそうだったように、笑顔で「おはよう」と言ってくれた。
でも、それ以降お姉ちゃんの口から『彼』の話を聞くことはなかった。
引っ越し先は全く知らない土地だった。
気候も方言も前に住んでいたところとはだいぶ違ったが、それでも友達はすぐに出来たし、クラスに馴染むこともできた。
新しいお父さんもとても優しくて、何より嬉しかったのは、お母さんが前より笑顔をみせてくれる機会が多くなったことだった。
引っ越してから一年が過ぎた、ある日。
学校から戻り、部屋でランドセルの中から教科書やノートを取り出していた時だった。
隣のお姉ちゃんの部屋で大きな物音がした。
お姉ちゃんは朝から体調が悪く、今日は学校を休んでいたはずだった。
ノックをしてからドアを開けると、お姉ちゃんはベッドの上で膝を抱え込むようにして体を丸めていた。
苦痛に歪ませた顔は深い海のように真っ青で、私が部屋に入ってきたことにすら気付いていないようだった。
すぐにお母さんの職場に電話を掛けると、お母さんが帰ってくるよりも早く到着した救急車で、お姉ちゃんは病院へと運ばれていった。
そして、次の日の夜。
顔に白い布を掛けられ戻ってきたお姉ちゃんは、もう二度と話してくれることも、もう二度と笑顔を見せてくれることもなかった。
詳しい病名は教えてもらっていないが、心臓の筋肉に異常が起きたのが原因だということだけは、お通夜の席で大人たちが話しているのを聞いて知った。
「この春にやっと、ずっとそのままだったお姉ちゃんのお部屋をお母さんと一緒に片付けたんです。その手紙はその時に机の引き出しから見つけたものです」
いつの間にかまた溢れ出していた涙で濡らしてしまわないよう、細心の注意を払いながら封筒に手を掛ける。
丸く可愛らしい字で『夏生くんへ』と書かれたその中には、手紙と一枚の写真が入っていた。
二度、三度と深く呼吸をしてから覚悟を決め、彼女が残してくれたその内容に目を通す。
夏生くんへ
ごめんなさい。
夏生くんと初めて会った日にはもう、私はあの町からいなくなることが決まっていました。
でも、あなたにそのことを言えませんでした。
それはきっと話してしまったら、笑顔であなたと会うことが出来なくなってしまうような、そんな気がしていたからだと思います。
風に飛んだぼうしをびしょぬれになって取ってくれた時、私はすぐにあなたのことを好きになっていました。
夏休みの小学校でデートをして、盆おどりを一緒におどって、山みたいなかき氷を一緒に食べて、それに灯台にも一緒に行きましたね。
私はその一日一日で…ううん、一秒ごとにあなたのことをどんどん好きになっていきました。
夕方の海であなたと別れたあと、私は家に帰ってからいっぱい泣きました。
でも、もう悲しくはありません。
家族にはナイショですが、今おこずかいを貯めてあなたに会いに行く計画を立てています。
来年の夏にはあの海でまた、あなたと一緒に灯台まで歩いて新しい思い出を作りたいです。
そして、高校を卒業するまでにはもっといっぱいお金を貯めて、あなたと同じ大学に通うのが私の夢です。
だから、それまでは絶対に彼女を作らないでください。
絶対に!
あなたと過ごした夏の日々は、私にとって一生の宝物です。
次に会った時には、あの時に言えなかった言葉を伝えたいです。
P.S.
もうひとつだけ、ごめんなさい。
ハマゴウの花言葉を知らないって言ったのはウソです。
でも、はずかしいのでここには書きません。
図書館に行く機会があったら調べてほしいです。
志帆
手紙を封筒に仕舞い、次に一緒に入っていた写真を取り出す。
そこには、海を背景にして真顔でカメラに目を向ける俺と、海風に髪を靡かせながら笑みを浮かべる彼女が写っていた。
「お姉ちゃんが夏生さんのお話をしてくれる時、いつもこんな顔で笑ってました」
俺たちは涙を拭うことすらせずに、写真の中で幸せそうな笑みを浮かべている彼女のことをずっと見ていた。
しばらくそうしたあとに顔を上げると、いつの間にか夏の夜空に一番星が瞬いていた。
彼女が行ってしまった遠い場所と比べれば、あの星など少し手を伸ばせば簡単に届いてしまうことだろう。
「俺は君のお姉さんの……志帆ちゃんのことが大好きだった」
「お姉ちゃんもです。夏生さんのおかげでお姉ちゃんは幸せでした」
彼女はそう言うと、先ほどとは逆にその白く細い指で俺の頬の雫を拭ってくれた。
茜色に支配されつつある空の下、赤土の畑の間を真っ直ぐに伸びる道を並んで歩く。
言葉も交わさずに足を動かし続けているこの状況は、あの日の海で彼女の姉と過ごした時とよく似ていた。
だが、目指しているゴールはとても対照的に思えた。
「……お姉ちゃんに聞いていた夏生さんと、実際に会って話してみた夏生さんって、なんだか少しだけイメージが違いました」
ふいに彼女がそんなことを言い出す。
発言の意図を問うために、ちょうど頭ひとつ分だけ低い位置に目を向ける。
その場所にあった小さな顔が、あまりにも初恋の人のそれと瓜二つで、止まったばかりの涙がまた溢れてきてしまう。
そのことを悟られないよう、わざとらしく咳払いをして空を見上げると、改めて言葉の意味を彼女にたずねる。
「違ったって、どんなふうに?」
「夏生さんはヘンな人だって。お姉ちゃん、そう言ってました」
『夏生くんって、ちょっと変わってる』
確かに彼女の姉には幾度となくそう言われたことがあった。
しかし、変わってると変な人だと、後者の方が随分と印象が悪い気がしてならない。
「ちょっと変わってるだけだよ」
自分でそう言ってから、どちらにせよ変であることには違いないことに気づく。
「……でも、夏生さんはお姉ちゃんが好きだった人です。だからもしヘンな人だったとしても、それはきっと……」
頬を赤らめながらそう言った彼女は、まるでスキップでもするかのように軽い足取りで俺の前に躍り出ると、長い黒髪を手で押さえながら勢いよく振り向く。
そして、はにかんだような笑顔を見せながら、さらに短く言葉を続けた。
「夏生さんは私が想像していた通りで、とってもとっても素敵な人でした」
そのあと俺たちは言葉を交わすようなこともなく、ゆっくりでも急ぐでもなく歩みを進めた。
やがて景色はさみしげな耕作地から、人の営みの気配がする小規模な集落へと変わっていった。
窓に明かりを灯す家々が目に入ると、久しぶりに人の住む世界に戻ってきたような気分になる。
それと同時に、長かった少年時代が今まさに終わってしまうような、そんな不確かな予感が胸をよぎった。
「夏生さん。うち、もうすぐそこなので。送ってくれてありがとうございました」
「……こちらこそ、今日は本当にありがとう」
「いえ。……あ、そうだ」
彼女はポシェットから取り出した何かを手のひらの上に載せ、俺のすぐ目の前に差し出した。
それは夏の空と同じ色の小さなシーグラスで、今日という日の残滓であるわずかな自然光を受け、宝石のようにキラキラと輝いていた。
「今日、夏生さんに会う少し前にみつけたんです。これ、もらってください」
「いいの?」
「はい。私とお姉ちゃんからのプレゼントです」
「……ありがとう」
俺たちは最後に数秒だけ見つめ合い、申し合わせていたかのように同時に頷く。
彼女はそのまま何も言わずに背を向けると、わずかに歩幅を広げて歩き出す。
幼い後ろ姿がやがて夕闇に紛れて見えなくなる、その寸前。
突如として振り返った彼女は口の横に両手を当て、驚いてしまうほどの大きな声で、こう叫んだのだった。
「夏生さんにお願いがあります! これからもずっと! ず~っとヘンな人でいてくださいね!」
いつの間にかまた溢れ出していた涙で濡らしてしまわないよう、細心の注意を払いながら封筒に手を掛ける。
丸く可愛らしい字で『夏生くんへ』と書かれたその中には、手紙と一枚の写真が入っていた。
二度、三度と深く呼吸をしてから覚悟を決め、彼女が残してくれたその内容に目を通す。
夏生くんへ
ごめんなさい。
夏生くんと初めて会った日にはもう、私はあの町からいなくなることが決まっていました。
でも、あなたにそのことを言えませんでした。
それはきっと話してしまったら、笑顔であなたと会うことが出来なくなってしまうような、そんな気がしていたからだと思います。
風に飛んだぼうしをびしょぬれになって取ってくれた時、私はすぐにあなたのことを好きになっていました。
夏休みの小学校でデートをして、盆おどりを一緒におどって、山みたいなかき氷を一緒に食べて、それに灯台にも一緒に行きましたね。
私はその一日一日で…ううん、一秒ごとにあなたのことをどんどん好きになっていきました。
夕方の海であなたと別れたあと、私は家に帰ってからいっぱい泣きました。
でも、もう悲しくはありません。
家族にはナイショですが、今おこずかいを貯めてあなたに会いに行く計画を立てています。
来年の夏にはあの海でまた、あなたと一緒に灯台まで歩いて新しい思い出を作りたいです。
そして、高校を卒業するまでにはもっといっぱいお金を貯めて、あなたと同じ大学に通うのが私の夢です。
だから、それまでは絶対に彼女を作らないでください。
絶対に!
あなたと過ごした夏の日々は、私にとって一生の宝物です。
次に会った時には、あの時に言えなかった言葉を伝えたいです。
P.S.
もうひとつだけ、ごめんなさい。
ハマゴウの花言葉を知らないって言ったのはウソです。
でも、はずかしいのでここには書きません。
図書館に行く機会があったら調べてほしいです。
志帆
手紙を封筒に仕舞い、次に一緒に入っていた写真を取り出す。
そこには、海を背景にして真顔でカメラに目を向ける俺と、海風に髪を靡かせながら笑みを浮かべる彼女が写っていた。
「お姉ちゃんが夏生さんのお話をしてくれる時、いつもこんな顔で笑ってました」
俺たちは涙を拭うことすらせずに、写真の中で幸せそうな笑みを浮かべている彼女のことをずっと見ていた。
しばらくそうしたあとに顔を上げると、いつの間にか夏の夜空に一番星が瞬いていた。
彼女が行ってしまった遠い場所と比べれば、あの星など少し手を伸ばせば簡単に届いてしまうことだろう。
「俺は君のお姉さんの……志帆ちゃんのことが大好きだった」
「お姉ちゃんもです。夏生さんのおかげでお姉ちゃんは幸せでした」
彼女はそう言うと、先ほどとは逆にその白く細い指で俺の頬の雫を拭ってくれた。
茜色に支配されつつある空の下、赤土の畑の間を真っ直ぐに伸びる道を並んで歩く。
言葉も交わさずに足を動かし続けているこの状況は、あの日の海で彼女の姉と過ごした時とよく似ていた。
だが、目指しているゴールはとても対照的に思えた。
「……お姉ちゃんに聞いていた夏生さんと、実際に会って話してみた夏生さんって、なんだか少しだけイメージが違いました」
ふいに彼女がそんなことを言い出す。
発言の意図を問うために、ちょうど頭ひとつ分だけ低い位置に目を向ける。
その場所にあった小さな顔が、あまりにも初恋の人のそれと瓜二つで、止まったばかりの涙がまた溢れてきてしまう。
そのことを悟られないよう、わざとらしく咳払いをして空を見上げると、改めて言葉の意味を彼女にたずねる。
「違ったって、どんなふうに?」
「夏生さんはヘンな人だって。お姉ちゃん、そう言ってました」
『夏生くんって、ちょっと変わってる』
確かに彼女の姉には幾度となくそう言われたことがあった。
しかし、変わってると変な人だと、後者の方が随分と印象が悪い気がしてならない。
「ちょっと変わってるだけだよ」
自分でそう言ってから、どちらにせよ変であることには違いないことに気づく。
「……でも、夏生さんはお姉ちゃんが好きだった人です。だからもしヘンな人だったとしても、それはきっと……」
頬を赤らめながらそう言った彼女は、まるでスキップでもするかのように軽い足取りで俺の前に躍り出ると、長い黒髪を手で押さえながら勢いよく振り向く。
そして、はにかんだような笑顔を見せながら、さらに短く言葉を続けた。
「夏生さんは私が想像していた通りで、とってもとっても素敵な人でした」
そのあと俺たちは言葉を交わすようなこともなく、ゆっくりでも急ぐでもなく歩みを進めた。
やがて景色はさみしげな耕作地から、人の営みの気配がする小規模な集落へと変わっていった。
窓に明かりを灯す家々が目に入ると、久しぶりに人の住む世界に戻ってきたような気分になる。
それと同時に、長かった少年時代が今まさに終わってしまうような、そんな不確かな予感が胸をよぎった。
「夏生さん。うち、もうすぐそこなので。送ってくれてありがとうございました」
「……こちらこそ、今日は本当にありがとう」
「いえ。……あ、そうだ」
彼女はポシェットから取り出した何かを手のひらの上に載せ、俺のすぐ目の前に差し出した。
それは夏の空と同じ色の小さなシーグラスで、今日という日の残滓であるわずかな自然光を受け、宝石のようにキラキラと輝いていた。
「今日、夏生さんに会う少し前にみつけたんです。これ、もらってください」
「いいの?」
「はい。私とお姉ちゃんからのプレゼントです」
「……ありがとう」
俺たちは最後に数秒だけ見つめ合い、申し合わせていたかのように同時に頷く。
彼女はそのまま何も言わずに背を向けると、わずかに歩幅を広げて歩き出す。
幼い後ろ姿がやがて夕闇に紛れて見えなくなる、その寸前。
突如として振り返った彼女は口の横に両手を当て、驚いてしまうほどの大きな声で、こう叫んだのだった。
「夏生さんにお願いがあります! これからもずっと! ず~っとヘンな人でいてくださいね!」
勤め先で在宅勤務が常態化して早二年。
日の出とともに起床しては満員電車にすし詰めにされ、自宅から三〇キロも離れた都心のオフィスに通勤していたのが、遥か昔の出来事のように感じられた。
十数人からが出席する会議に、下半身は寝間着のままで何食わぬ顔をし参加できる時代が、まさか生きているうちにやって来ようとは。
飽くなき進化の末に人類がたどり着いた終着点とは、まさに今いるこの場所のことなのではないか?
もっとも、それにより新たに生み出された弊害もあった。
例えば今日のように休日であっても、時間があればパソコンの画面を開き、もしそこに簡単なタスクを見つけでもしようものなら、給金が支払われるわけでもないのにやっつけてしまう。
そんな昭和時代を彷彿とさせる悪しき働き方が、いつの間にやら身についてしまっていた。
それは決して私が仕事人間だからというわけではなく、むしろ家族と過ごす大切な時間を捻出するための手段だった。
……が、当の妻と娘の理解はまったく得られていない。
無念である。
「あーパパ! またお休みの日なのにお仕事してたでしょ! ママに言いつけてもいい?」
今もこうして、その悪癖を娘に見咎められてしまった上に、ちょっとした恫喝――しかも急所攻撃である――までされてしまう。
「今日、あっちに行ったら好きなもの買ってあげるから。だからママに言うのだけは、ね?」
娘はその言葉を聞くや否や、への字に結んでいた口を俄に弛ませる。
「ホントに? じゃあねじゃあね! わたし、新しいお帽子がほしい!」
身から出た錆とはいえ、随分と高い代償を支払う羽目になってしまった。
「ところでその洋服、君にすごく似合っていて素敵だね」
それは茶を濁すために咄嗟に発した言葉だったが、その評価は至って正当なものであった。
私は今までの人生で、彼女ほど白色のワンピースがよく似合う女性を、たったの二人しか知らない。
「……まえから思ってたんだけど、パパってちょっとヘンだと思う」
赤らめた頬に手をあてそう言った彼女は、スリッパの音をパタパタと立てながら廊下を走り去って行ってしまった。
きりのいいところまで仕事を片付けたかったのだが、それを今度は妻に見られでもしたら、せっかくの買収工作が無駄になってしまう。
それに今日はこのあと、親子三人で外出する予定が控えている。
なんだかんだで丁度いい頃合いだったかもしれない。
パソコンの画面が消えるのを見届けたあと、デスク脇に置かれたワゴンから草臥れた封筒を取り出す。
毎年たったの一度だけ、八月の今の時期に行うこの儀式は、妻と娘にはずっと秘密にしている。
封筒から取り出した写真をデスクの上に置き、椅子の背もたれに体重を預けて目を閉じる。
すると、まぶたの裏のスクリーンにあの日の光景が、まるで昨日のことのように鮮明に浮かび上がる。
柔らかな潮風に揺れる浜栲の花畑と、その只中で微笑みを浮かべて佇む、麦わら帽子を被った白いワンピースの少女の姿が。
「今年も会いに行くよ。君と出会った、あの夏の日の海に」
儀式を終えてから壁の時計に目を向けると、ちょうど出発を予定していた時刻になるところだった。
特段に急ぐ旅ではないのだが、うちの女性たちは時間という概念の外側で生きているふしがあった。
彼女らの自主性に任せるがまま放っておきでもしようものなら、短い夏季休暇などあっという間に終わってしまうこと請け合いだ。
「おーい夏帆! あと三十分で支度しないと、さっきのナシだからね!」
椅子に座ったまま振り返りそう叫んだ私だったが、自身も荷造りがまだ終わっていなかったことを思い出す。
「ごめん美帆! 僕の靴下の買い置きって、どこに仕舞ってあったんだっけ?」
おそらくはリビング辺りに居るであろう妻子の名を呼びながら、愛する家族と下ろしたての靴下を求め、自室をあとにした。
誰も居なくなった部屋。
開け放たれた窓から吹き込む八月の風が、デスクに置かれたままだった写真を軽やかに舞い上がらせた。
それはまるであの夏の日の麦わら帽子のようにしばらくのあいだ空中を漂うと、やがてその高度を徐々に落としながらくるりと裏返しになり、ついには白いフローリングの床の上に落ちる。
年月の経過からか、それとも夏生があの日流した涙のせいか。
色褪せた写真の裏側には滲んだボールペンの文字で、以下のような数行からの文字が刻まれていた。
親愛なる彼と彼女へ
この写真は お二人への感謝の気持ちで撮らせていただいたものだったのですが 現像をしてみたところ あまりのできの良さに お二人への許可も取らずに 勝手にコンクールに出させて頂きました
本当に申し訳ありません
いつか必ず このお詫びとお礼に伺わせて頂きますので 何卒お許しください
末筆ではございますが あなた方お二人の永遠の愛を心よりお祈り申し上げます
第9回中日本フォトコンテスト入選作品
『海の青より、空の青』
完
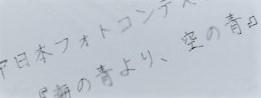
日の出とともに起床しては満員電車にすし詰めにされ、自宅から三〇キロも離れた都心のオフィスに通勤していたのが、遥か昔の出来事のように感じられた。
十数人からが出席する会議に、下半身は寝間着のままで何食わぬ顔をし参加できる時代が、まさか生きているうちにやって来ようとは。
飽くなき進化の末に人類がたどり着いた終着点とは、まさに今いるこの場所のことなのではないか?
もっとも、それにより新たに生み出された弊害もあった。
例えば今日のように休日であっても、時間があればパソコンの画面を開き、もしそこに簡単なタスクを見つけでもしようものなら、給金が支払われるわけでもないのにやっつけてしまう。
そんな昭和時代を彷彿とさせる悪しき働き方が、いつの間にやら身についてしまっていた。
それは決して私が仕事人間だからというわけではなく、むしろ家族と過ごす大切な時間を捻出するための手段だった。
……が、当の妻と娘の理解はまったく得られていない。
無念である。
「あーパパ! またお休みの日なのにお仕事してたでしょ! ママに言いつけてもいい?」
今もこうして、その悪癖を娘に見咎められてしまった上に、ちょっとした恫喝――しかも急所攻撃である――までされてしまう。
「今日、あっちに行ったら好きなもの買ってあげるから。だからママに言うのだけは、ね?」
娘はその言葉を聞くや否や、への字に結んでいた口を俄に弛ませる。
「ホントに? じゃあねじゃあね! わたし、新しいお帽子がほしい!」
身から出た錆とはいえ、随分と高い代償を支払う羽目になってしまった。
「ところでその洋服、君にすごく似合っていて素敵だね」
それは茶を濁すために咄嗟に発した言葉だったが、その評価は至って正当なものであった。
私は今までの人生で、彼女ほど白色のワンピースがよく似合う女性を、たったの二人しか知らない。
「……まえから思ってたんだけど、パパってちょっとヘンだと思う」
赤らめた頬に手をあてそう言った彼女は、スリッパの音をパタパタと立てながら廊下を走り去って行ってしまった。
きりのいいところまで仕事を片付けたかったのだが、それを今度は妻に見られでもしたら、せっかくの買収工作が無駄になってしまう。
それに今日はこのあと、親子三人で外出する予定が控えている。
なんだかんだで丁度いい頃合いだったかもしれない。
パソコンの画面が消えるのを見届けたあと、デスク脇に置かれたワゴンから草臥れた封筒を取り出す。
毎年たったの一度だけ、八月の今の時期に行うこの儀式は、妻と娘にはずっと秘密にしている。
封筒から取り出した写真をデスクの上に置き、椅子の背もたれに体重を預けて目を閉じる。
すると、まぶたの裏のスクリーンにあの日の光景が、まるで昨日のことのように鮮明に浮かび上がる。
柔らかな潮風に揺れる浜栲の花畑と、その只中で微笑みを浮かべて佇む、麦わら帽子を被った白いワンピースの少女の姿が。
「今年も会いに行くよ。君と出会った、あの夏の日の海に」
儀式を終えてから壁の時計に目を向けると、ちょうど出発を予定していた時刻になるところだった。
特段に急ぐ旅ではないのだが、うちの女性たちは時間という概念の外側で生きているふしがあった。
彼女らの自主性に任せるがまま放っておきでもしようものなら、短い夏季休暇などあっという間に終わってしまうこと請け合いだ。
「おーい夏帆! あと三十分で支度しないと、さっきのナシだからね!」
椅子に座ったまま振り返りそう叫んだ私だったが、自身も荷造りがまだ終わっていなかったことを思い出す。
「ごめん美帆! 僕の靴下の買い置きって、どこに仕舞ってあったんだっけ?」
おそらくはリビング辺りに居るであろう妻子の名を呼びながら、愛する家族と下ろしたての靴下を求め、自室をあとにした。
誰も居なくなった部屋。
開け放たれた窓から吹き込む八月の風が、デスクに置かれたままだった写真を軽やかに舞い上がらせた。
それはまるであの夏の日の麦わら帽子のようにしばらくのあいだ空中を漂うと、やがてその高度を徐々に落としながらくるりと裏返しになり、ついには白いフローリングの床の上に落ちる。
年月の経過からか、それとも夏生があの日流した涙のせいか。
色褪せた写真の裏側には滲んだボールペンの文字で、以下のような数行からの文字が刻まれていた。
親愛なる彼と彼女へ
この写真は お二人への感謝の気持ちで撮らせていただいたものだったのですが 現像をしてみたところ あまりのできの良さに お二人への許可も取らずに 勝手にコンクールに出させて頂きました
本当に申し訳ありません
いつか必ず このお詫びとお礼に伺わせて頂きますので 何卒お許しください
末筆ではございますが あなた方お二人の永遠の愛を心よりお祈り申し上げます
第9回中日本フォトコンテスト入選作品
『海の青より、空の青』
完
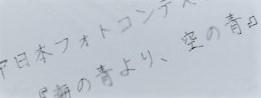
この作家の他の作品
表紙を見る
本作は拙作短編小説『海の青より、空の青』の前日譚です。
本編もお読みいただければ幸いです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…



