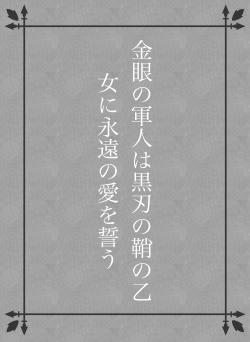「おはよう、魚谷さん」
「おはようございます」
瑞希はマンションの前まで迎えに来てくれた木綿子に、楚々と頭を下げた。
「今日はよろしくお願いします」
そう言って頭を上げれば、にゃおんと決めポーズをとる猫ちゃんと目が合う。
(あ。藤峰さん、猫Tシャツ着てる……)
今日の木綿子はギュルンギュルンのマスカラも、大ぶりのイアリングも派手なネイルもなし。
Tシャツにキュロットスカート、スポーツタイプのスパッツという、典型的な山ガールスタイルだ。
対する瑞希もチンアナゴTシャツにトレッキングパンツと格好だけ見れば、ほぼ同類である。
「行きましょうか。龍河谷までは三時間ぐらいよ」
バックパックを後部座席に置き、助手席に身体を滑り込ませたら車はすぐに発進した。
「龍河谷も晴れみたい。登山日和でよかったね」
木綿子の運転する車は、早朝の高速道路を爽快に駆け抜ける。
瑞希はカーラジオから聞こえる天気予報と渋滞情報にぼうっと耳を傾けていた。
(真剣さが足りないか……)
ひと晩経ち、怒りのピークが通り過ぎると彼女の言いたいことも、わかる気がしてくる。
本気で結婚したいのか聞かれたら、力強く「はい」とは答えられない。
性格の合う人がいたら。
条件の釣り合う人がいたら。
結婚したいと思えるような人がいたら。
そうやって、いつも心のどこかで逃げ道を用意していたのかもしれない。
断られるたびに傷ついていたのはたしかだけれど、心のどこかでホッとしていたのもまた事実だ。
(もう、自分で自分がよくわからないよ)
結婚したいのか、したくないのか。
三十歳になってもなお、自分で自分がわからないなんて情けない。
「どうしたの? 寝不足?」
浮かない表情で物思いに耽る瑞希の様子に、なにかを感じ取ったのだろうか。
木綿子が話しかけてくれる。
「いえ、大丈夫です!」
瑞希は先ほどとは打って変わり明るく答えた。
(いけない、いけない)
これから楽しみにしていた登山に向かうというのに、暗い顔ばかりしていては木綿子に心配をかけてしまう。
「ほら、あれが龍河谷だよ」
木綿子に言われてフロントガラスに視線を向ければ、堂々とした稜線が見える。
瑞希が昨日の出来事を反芻しているうちに、目的地はすぐそこまで迫っていた。
車はそのまま走り続け、やがて登山口に到着した。
「うわあ――」
荷物を下ろし車から降り立つと、湿り気を帯びた風が通り過ぎ、思わず身震いする。
四月も終わろうとしているのに、山の気温はまだ下がらない。
標高千メートルともなれば、気温は平地より五度は低い。風が吹けば体感温度はもっと低くなる。
瑞希はウィンドブレーカーを羽織りながら、他の登山者の様子に目を向けた。
登山口には大勢の人が立っている。
皆、瑞希と同じようにバックパックを背負い、登山ウェアに身を包んでいた。
(さあ歩くぞ)
瑞希が意気揚々と登山道へ足を踏み入れようとしたそのときだ。
「あ、ちょっと待って!」
「へ?」
木綿子は先を行こうとする瑞希を引き留め、ポストに似た木製の箱に、ふたつ折りにした紙を差し入れた。
木綿子だけではなく、他にも同じような人が何人も現れ、次々とポストに紙を投函していく。
「お待たせ。行きましょうか」
「あの箱、なんなんですか?」
「ああ。あれはクライミングプランの投函箱よ」
「クライミングプラン?」
聞きなれない単語で、瑞希は思わず聞き返した。
「えーっと。登山するときは登山口でその日の行程と予想到着時間、同行者の名前や連絡先をあらかじめ紙に書いて提出するのがマナーなの」
「え!? そうなんですか?」
「いざっていうときに誰が入山しているのか、わからないと困るでしょう?」
(たしかに……)
どれだけ安全に気を配ろうと、遭難や自然災害の可能性はゼロにはならない。
瑞希たちが登るのはあくまでも自然の山々。
相手が誰だろうと手加減してくれない。
無事にクライミングプランを提出したふたりは、ようやく登山道を歩き始めた。
木綿子によると、しばらくはなだらかな上り坂が続くらしい。
初心者にはちょうどいい肩慣らしだ。
歩くリズムとペースを掴みながら、ひたすら足を前後に動かす。
木綿子は瑞希に歩調を合わせ、ゆっくり進んでくれる。
「そういえば、さっきから鈴をつけている人が多いですね」
歩き始めたばかりでまだ余裕があった瑞希は、なんとはなしに話しかけた。
ベテラン風の何人かは、カウベルのような大きな鈴をカランカランと派手に鳴らしながら瑞希達を追い抜いていった。
風の音や、鳥が鳴く声しかしない山の中に、甲高い人工音だけがやたら大きく響く。
お洒落のひとつかと思ったけれど、あまりにもつけている人が多くて不思議に思う。
「ああ、熊鈴ね。熊が寄ってこないようにするためにつけておくの」
「熊!?」
「龍河谷の周辺は熊の出没情報は少ないけど、熊が出てくる山って結構多いのよ」
瑞希は唖然とした。
野生の熊と遭遇するなんて、ニュースの中の出来事でしかない。
口をあんぐり開けた瑞希を見て、木綿子があははと笑いながら情報を足していく。
「熊だけで驚いてたら大変よ。山の中には野生の鹿も猪だっているからね」
「鹿!?」
熊だけではなく、鹿まで生息しているのか。
(私、今日無事に帰れる?)
瑞希は大自然の生態系を直に感じて圧倒されていた。
ひょっとして、とんでもない世界に足を踏み入れてしまった?
にわかに心配になっていると、ふいに真横から視線を感じる。
「あーう?」
かわいらしいくりくりとふたつの丸い瞳と目が合い、ぎょっとする。
一歳ぐらいの赤ちゃんが瑞希に向かって、にぱ~と微笑む。
「ふ、ふふ藤峰さん! あれ見てください! 赤ちゃんがいます!」
「あら、本当! かわいいわねえ!」
赤ちゃんはベビーキャリアを背中に装備した父親と思しき男性に背負われ、大人しく親指をしゃぶっていた。
見慣れた光景なのか木綿子はさほど驚きもせず、赤ちゃんに軽く手を振った。
(子連れで登山ってどういうこと!?)
ただでさえ水やら着替えやらで重いのに、子どもを背負って歩こうなんて狂気の沙汰だ。
「すごい……」
瑞希は感心するしかなかった。
――山って不思議だ。
さまざまな価値観がひとつの場所に集まっている。
ここでは瑞希の常識は通用しない。
瑞希はゴクンと唾を飲み込んだ。
予想通り、物見遊山ではしゃいでいられたのも最初のうちだけだった。
「魚谷さん、大丈夫?」
「だ、だいじょうぶ、で、す……」
登り始めて二時間ほど経つと、瑞希の呼吸が明らかに乱れ始めた。
ふくらはぎが疲労でパンパンになり、膝がガクガクと震えている。
足を上げるのも億劫で、何度もつまずく。
「休憩しましょう」
「へ、平気です。さっきも休憩したばかりですし……」
「いいから!」
見るに見かねた木綿子はそう言うと、強引に瑞希の腕を引き、登山道の端に連れて行った。
バックパックからレジャーシートを出し、地面の上に広げる。
「ここに座って靴と靴下を脱いで」
「はい……」
瑞希は言われるがまま腰を下ろし、トレッキングシューズと靴下を脱いだ。
長い時間、足首を固く拘束されたいた分、開放感は格別だったが、左足の小指から三センチほどの辺りからうっすら血が滲んでいる。
「靴擦れしてるね。なんで言わなかったの?」
「ペースを落としたくなくて……」
瑞希は口を濁らせ、もごもごと言い訳を始めた。
最初のうちはすべてがもの珍しく、足に感じた違和感が気にならなかったのだ。
痛みに気づいたのは、歩き始めてからしばらくしてから。
靴擦れを起こした右足を庇ううちに、今度は左足までおかしな具合になった。
「藤峰さん、私のことはいいので先に進んでください」
足は痛いし、寝不足だし、身体はクタクタで、メンタルもボロボロだ。
つい弱音を吐いてしまう。
「最初から無理だったんです。碌に運動もしないのに、山に登るなんて。婚活が上手くいかないからって、どこかに行ってみたいなんて馬鹿みたいですよね」
(思い出した)
婚活を始めたのだって、いい加減な動機だ。
二十五歳を過ぎた頃から、友人知人が結婚し始め、自分もそろそろ結婚を考え始める年齢になったかと何も考えずに周りに倣った。
恋人はいないから、結婚相談所に入会して。
アドバイザーに勧められたから、見合いを繰り返した。
大学を卒業し、就職して、結婚して、出産する。
誰もが考える普通の人生というレールに乗らなきゃいけないとせき立てられていた。
でも、結婚相談所に登録しても、なにも変わらなかった。
瑞希は今でも変わらずひとりだ。
ウジウジと膝を抱え出した瑞希に木綿子がそっと声をかける。
「私と一緒だね」
「え?」
地面の一点を見つめていた瑞希は木綿子を仰ぎ見た。
目が合うと木綿子はニコリと微笑んでくれた。
「私、実はバツイチなの」
「バツイチ!?」
木綿子がバツイチだなんて、初耳だった。
会社でもそんな話は聞いたことがない。
「結婚して二年後ぐらいにね、子どもが出来ない身体だってわかったの。元夫はそれでもいいって言ってくれたんだけど、彼に人並みの幸せを与えられないことに私が耐えきれなくなって……」
木綿子はどこか遠い目をしていた。
昔を懐かしんでいるのか、離婚を後悔しているのか、うまく読み取れない。
「離婚した後、たまたま旅行雑誌でトレッキング特集を見たの。あまりに綺麗な写真で、ここに行ってみたいって離婚してから初めて思えた。それから、なんとなーく登山が趣味になって緩く続いている感じ?」
木綿子はそうして自分の話を締めくくった。
(知らなかった)
あっけらかんとしている木綿子の知られざる一面に、瑞希はなにも言えなくなった。
「人生って山あり谷ありって言うけど、実際歩いてみるときついよね。どっちに歩いたらいいか誰も教えてくれないもの」
――そう言えるまでに、木綿子はどれぐらい山に登ったのだろう。
登って、登って、登り続けて。
ようやく辿り着いた先にしか、紡ぎ出せない言葉がこの世にはある。
「とりあえず大きめの絆創膏と包帯で保護するね。手当てが終わったら、おやつを食べましょう。魚谷さんと食べようと思って、とっておきの栗羊羹を持ってきたの。甘いものを食べれば元気が出てくるはずよ」
木綿子はバックパックからファーストエイドキットを取り出し、手早く処置を始めた。
手当てが終わると、ふたりでレジャーシートに座り、ひと口サイズの栗羊羹を食べる。
(美味しい)
甘い栗羊羹は疲れた身体に効果覿面だった。
「どう? 歩けそう?」
「はい」
手当してもらったおかげで、靴擦れの痛みもだいぶ和らいだ。
「じゃあ、行こうか」
ふたりは立ち上がると、再び登山道を歩き出した。
太陽が空のてっぺんに差し掛かり、木々の隙間からキラキラと光が漏れてくる。
ポツポツと登山道を照らす光はまるで道標のようだった。
(静かだ)
ざっざっと土を蹴る音だけが耳に心地よい。
山の中には車のクラクションの音も、エアコンの排気音も一切響かない。
自分の呼吸音と、地面を踏みしめる足音に支配されている。
歩いている最中は、無心になって自分自身を見つめ直すしかない。
(そもそも普通ってなんだろう?)
成長したらキチンとした大人になれると思っていた。
大人になったら結婚して、子供を産むのが普通だと思っていた。
けれど、今の自分は子どもの頃に思い描いていた大人像とはかけ離れている。
今でもピーマンが苦手だし、掃除も洗濯も面倒臭い。休みの日は二度寝が当たり前。
(そうだよね)
普通なんてひとによって違う。
大多数の人が選んでいる道が、普通だとは限らない。
別のルートを歩んでいると思えばいい。
人生という山の楽しみ方は人それぞれだ。
「ほら、見えてきたよ」
木綿子に声をかけられ山頂を見上げれば、木々がひらけ、空が徐々に見え始める。
瑞希は最後の力を振り絞り足を上げた。
目的地はすぐそこだった。