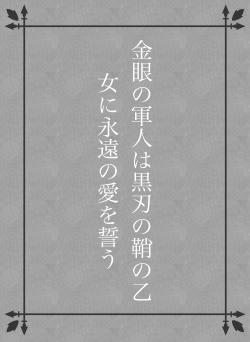木綿子からメッセージが届いたのは、帰宅後のことだ。
風呂上がりの瑞希は髪をタオルで拭きながら、スマホを手に取った。
【買い物なんだけど、次の土曜はどう? お店の前で待ち合わせしましょう】
なにを買えばいいのかわからないと泣きつくと、木綿子は買い物への同行を快く引き受けてきた。
ひとりで怖気づいた身としては、やはり木綿子の存在は大変ありがたい。
(なるほど。上級者は登山用品をギアって呼ぶのか)
早速、ひとつ発見をした瑞希は【よろしくお願いします】とメッセージを返信した。
◇
「おはようございます」
「おはよう、魚谷さん」
木綿子はビジネス用のセットアップではなく、タイトジーンズにロングカーディガンという、いくらかカジュアルな出立ちで登場した。
「さ、行きましょう」
登山用品店に入るなり、魔窟のような店内を先陣を切って歩いていく。
頼もしい背中は会社で見かけるものと、まったく同じである。
「魚谷さん、登山は初めてなのよね?」
「はい」
「それならまずは靴ね。トレッキングシューズは普通の靴と違って生地も厚くて重たいの。メーカーによって履き心地が全然違うからきちんと試着しましょう」
木綿子は慣れた足取りで瑞希をトレッキングシューズ売り場に案内した。
「魚谷さん、靴のサイズは?」
「二十五センチです」
木綿子は棚に置かれている靴をいくつか見繕い、瑞希に渡した。
(なにこれっ! 本当に重いっ!)
木綿子の言う通り、トレッキングシューズは手に取るとズシリと重たかった。
「なんでこんなに重いんですか?」
「怪我をしないように足先とか足裏が丈夫にできているの。ハイキング用の軽いタイプもあるけど、龍河谷は岩も多いし滑って危ないからハイカットがおすすめ」
「な、なるほど……」
木綿子に言われるがままに、トレッキングシューズを履いた。
「履けた?」
「はい、なんとか……」
紐を何度もクロスさせる必要があり手間取ったが、どうにか履けた。
瑞希はその場で立ち上がった。
それにしても、足首ががっちり固定されていて歩きにくい。
足を持ち上げるのも一苦労だ。
ローヒールのパンプスや、スニーカーを履き慣れていると違和感しかない。
「じゃあ早速歩いてみましょう」
木綿子は小石や砂利、急傾斜が作られた模擬コースを指さした。
まるで小さめのアスレチックのようだ。
「ここを歩くんですか?」
「登山って平坦な道だけを歩くわけじゃないでしょう? だから、こうやって山道を模したコースで履き心地を色々と試すの」
「あ、なるほど」
瑞希はポンと手で鼓を打った。
舗装された道路を歩くわけではないのだ。
怪我防止だと思えば、ゴツい作りも納得だ。
瑞希は何回か試着を行い、一番履きやすかったワインレッドのトレッキングシューズをカゴに入れた。
「靴が決まったら、次はバックパックね。日帰りだし、おすすめは大体このあたりかな」
靴が決まると今度はバックパック売り場に連れてかれる。
他にも帽子や、レインウェアを次々物色していく。
日頃から経営陣を相手にプレゼンを行っているだけあって、木綿子の提案力はそれは素晴らしかった。
アドバイスのひとつひとつが実体験に基づいていて的確だ。
瑞希は迷うことなく勧められたギアを次々とカゴに入れていった。
(この人、本物のガチ勢なんだな)
登山が趣味と聞いたときは半信半疑だったが、嬉々として山登りのノウハウを語る木綿子を見た今となっては認めざるをえない。
(藤峰さんはどうして登山を始めたんだろう?)
他人の趣味に口を出すつもりはないが、いつか機会があれば尋ねてみたい。
「ところで、藤峰さんはなにを買ったんですか?」
瑞希が小物を見ている間に、木綿子は既に己の買い物を済ませ、店名がプリントされた紙袋を腕に下げていた。
「新しいカラビナでしょ。あと、プロテイバーの新しい味がでてたからそれを五本。あとはこれ!」
木綿子はホクホク顔で紙袋を開け放ち、猫のイラストがプリントされたTシャツを広げてみせた。
それも、色違いで三種類も。
「全部同じ柄ですけど……」
たまらず指摘すれば、木綿子はあっけらかんと言い放った。
「いいのいいの! Tシャツなんて何枚あってもいいんだから! ね、かわいいでしょ?」
Tシャツの中央には猫が前脚で顔を撫でている様子が描かれている。
たしかにかわいいけれど――。
「猫、お好きなんですか?」
「好きなんだけど、マンションがペット禁止で飼えないのよねー」
なるほど、猫への愛情を猫グッズを集めることで昇華させているようだ。
「ほら! 長い時間をかけて山に登るんだから、自分の好きな服を着ていた方が気分が上がるでしょう?」
無難な無地のグレーやネイビーのTシャツを選ぶつもりだった瑞希はある意味衝撃を受けた。
(なるほど。そういう考え方もあるのか)
ちらりと棚の上のマネキンを仰ぎ見れば、着こなしもさまざまだ。
シンプルなボトムスの他にも、キュロットスカートにレギンスを合わせたり、巻きスカートなんてものもある。
自分の好みに合うものが見つかれば、登山をより一層楽しめる違いない。
しかし、登山初心者、所詮付け焼き刃の瑞希には無理な話だ。
(まあ、私は普通のTシャツでいいな)
瑞希はそう思い、手近にあったネイビーのTシャツを手に取った。
「うわあ可愛い! 魚谷さん、そういうのが好きなんだ!」
「え?」
瑞希は手元にあるTシャツに視線を落とした。
無地だと思って手に取ったTシャツには三匹のチンアナゴが左胸にプリントされている。
「チンアナゴのプリントTシャツなんて珍しいわね」
「あ、いや、私は……」
棚に戻そうとしたが、チンアナゴと目があってしまう。
デフォルメされたクリクリと大きな瞳が「買ってよ〜!」と妙な同情を誘う。
タグをよく見れば、売れ残りなのか定価の半額の値段に値下げされている。
棚の中には他に仲間はいないようだ。
つまり、この子達は売れ残った最後の一枚というわけだ。
(なんか、かわいそう……)
婚活十連敗中の身として、親近感を覚えてしまったのか、どうしてもTシャツを棚に戻せない。
(半額だし!)
瑞希は言い訳しながら、カゴの中にチンアナゴを放り投げた。
「登山用品って毎月のように便利なものが発売されるから、散財しないようにするのが本当に大変よねー」
「ぐふっ!」
瑞希は思わず口もとを押さえ、こみあげてくる笑いを我慢した。
猫Tシャツを三枚も購入しておいて、言える台詞ではない。
(藤峰さんって案外かわいい人だったんだ)
瑞希はテイクアウトしたコーヒー片手に廊下をヒールで闊歩する木綿子の姿しか知らない。
完璧美人の木綿子のイメージがガラリと変わっていく。
瑞希は茶目っ気溢れる木綿子に不思議と親近感を覚えるようになっていた。
◇
「えーと。水とレインウェアとファーストエイドキットでしょ……」
木綿子と龍河谷に行く前日。
瑞希は床の上に荷物を並べ、パッキングを行っていた。
日帰りとはいえ、荷物は多い。
登山道の途中には、自販機もコンビニもない。
必要なものはすべて自分で持っていかなければいけない。
荷物をすべて入れ終わると、大きいと思っていたバックパックが隙間なくパンパンになった。
明日は朝五時に木綿子が車で迎えに来てくれる。
渋滞に巻き込まれなければ、九時には登山が開始できるはずだ。
明日に備え今日は早めに風呂と食事を済ませ、たっぷり睡眠をとらなければ。
瑞希が布団の中に潜り込もうとしたそのとき、スマホが着信を知らせた。
電話は結婚相談所からだった。
「もしもし?」
『魚谷さん? この間は残念だったわね。あの方、とっても素敵な男性だったのに』
そう早口で捲し立てるのは、瑞希を担当する婚活アドバイザーの女性だ。
五十代前半の小太りで、やや上から目線だがアドバイザーとしての腕はたしかで、彼女のおかげでこれまで何人もの男女が結婚にこぎつけているらしい。
(なんで今日なのよ……)
なんというタイミングだろう。
瑞希はうげっとうめきそうになった。
一刻も早く眠りたいのに、彼女の話はいつも長いのだ。
瑞希は軽く相槌を打ちながら、壁掛け時計を仰ぎ見た。
「あの男性ね、『あなたが本気がどうかわからなかった』っておっしゃっていたの。どうもあなたには真剣さが足りないみたい」
「はあ……」
彼女から先日御破算になった男性からのフィードバックが伝えられ、瑞希は辟易した。
あのメガネ野郎のことなんて、思い出したくもない。
(やっぱりメガネを叩き割っておけばよかったな)
苛立ちのあまり、つい過激な思考に走る。
どうやら彼女は瑞希がどうしてお断りされたのか理由を知らないみたいだ。
矢継ぎ早にアドバイスと称したお説教が続く。
「他の女性はね、本当に努力されているの。エステに通ったり、マナー講座を受講されたり、男性から選ばれるために必死で自分を磨いているの。あなたも自分をよく見せようという努力をしましょうよ」
そう言われた瞬間、瑞希の中でなにかが音を立てて崩れていった。
「次の男性を紹介する前に少しお勉強したらどうかしら? 女性らしい所作や、温かみのある会話を――」
「もういいです」
瑞希はヤケクソ気味に言い捨てると、通話終了マークをタップした。
「なにそれ」
悔しさで涙が滲みそうになり、思わず天井を見上げる。
真剣さが足りないなんてよく言える。
瑞希だって自分なりに努力したつもりだった。
デートの前の日は相手のプロフィールを熱心に読み込み、服だって新調した。
今まで二年も婚活に費やしてきたのに、そんな言い方されるなんてあんまりだ。
(私が結婚できないのはアドバイザーに問題があるんじゃないの!?)
そう真っ向から文句を言ってやればよかった。
男性から断られるたびに自分自身の生き方を否定され、メンタルがゴリゴリ削られる。
この気持ちがアドバイザーの彼女にわかるものか。
瑞希は頭から布団を被り瞼を閉じたが、目は冴えるばかりでちっとも眠れなかった。