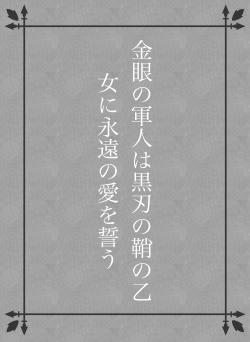(また遅れてる)
瑞希は電光掲示板に映し出された遅延情報を見て、うんざりとため息をついた。
電車が遅れるのは今月に入ってこれで五回目だ。
新学期が始まったばかりの四月上旬とあって、毎日のように混雑による遅延や事故が発生している。
各駅停車しか停まらないこの駅は急行電車の通過待ちのあおりを食うばかり。
(もう今日は遅刻でいいか)
いつもなら代替手段として二十分かけて地下鉄の駅まで歩くが、今日はなんとなくそんな気分にもなれない。
瑞希はベンチに座ると、肩にずしりと食い込む重たいトートバッグをかたわらにそっと置いた。
そのまま電車が停まる気配のない線路をぼんやり眺める。
気まぐれに吹く春風が肩までのびた漆黒のボブヘアをふわりと揺らしていく。若々しい青葉の香りが混じる生温い風に春の息吹を感じた。
プラットホームには人の姿はまばらだ。皆、早々に見切りをつけて地下鉄へ移動したのだろう。
瑞希のように呑気にベンチに腰を下ろしている者はひとりもいない。
「休もうかな……」
頭の中に棲みつく小狡い悪魔が甘い誘惑を囁く。ズル休みをしたい誘惑に駆られる。毎日あくせくと働いているのだから、たまにはそんな日があってもいいじゃないか。
そうだそうだと、悪魔が囃したててくる。
ひとりになると先日の出来事をつい思い出してしまう。
(そもそも、複数の女性と同時にやりとりするなんてマナー違反でしょ!)
時間は有限だ。
ひとりずつ相手をするより、同時にやりとりした方が効率的なのは認める。
しかし、生涯の伴侶を探している立場としては、誠実さが足りないのではないか。
瑞希は、はあっとため息をついた。
(これで十人目かあ……)
自分に至らない点があったのは認めよう。
可愛らしい仕草や笑顔が魅力的でもない。
容姿に華やかさがあればいいのだろうけれど、母譲りのストレートの黒髪と、凹凸の少ないのっぺりした目鼻立ちは、メイクをしても実力以上の効力を発揮できない。
一緒にいて楽しい気分になるような会話術を会得しているわけでもない。
瑞希には瑞希なりの美点があるはず。
そうわかっていても心には、ぽっかりと大きな穴が開いている。
「どこか遠くに行きたいな……」
なんとはなしに呟いた言の葉が風に乗り、すうっとかき消されていく。
瑞希はふっと自嘲気味な笑みをこぼした。
「やだ、学生じゃあるまいし」
瑞希は今年三十歳になった。アラサーなんて薄いオブラートに包むまでもない、正真正銘本物の三十歳。
モラトリアムはとうの昔に終わらせていたはず。
いい歳した社会人が自由気ままに振る舞ったら給料泥棒と後ろ指をさされかねない。
そもそも、どこに行けばいいのかわからないのに、どこかに行きたいなんて変な話だ。
(さて、そろそろ会社に行きますか)
いつまでもベンチに座っているわけにもいかない。
瑞希は勝利を確信し陽気にコサックダンスを踊っていた悪魔を無理やり頭の中から追い出した。
八年かけて培われた社会人としての性が許さない。なんと悲しき社畜のさだめだろう。
婚活十連敗を決めたとしても、容易くルーティンは変えられない。
瑞希が重い腰を上げたその刹那、エメラルドブルーのなにかに目を奪われる。
瑞希は吸い寄せられるようにベンチから立ち上がり、そろそろと壁に貼られていたポスターに近づいていった。
「龍河谷……?」
瑞希の心を捕らえたのは、龍河谷という国立公園にある蓬莱湖という湖の写真だ。
いつから掲示されていたのかわからないそのポスターは大きく色褪せている。
しかし、青空を逆さに映したエメラルドブルーは強烈な輝きを放っていた。
◇
「おはようございます」
「おはよう、魚谷さん。今日は遅かったんだね」
「はい。電車が遅れておりまして」
「ああ、四月だもんね〜」
瑞希は遅刻を上司に報告してから、自席に腰を下ろした。
サボっちゃおうかなと思っていたのは、チラとでも気取られてはいけない。
パソコンの電源を入れ、今日のタスクをチェックしていく。
瑞希は大学を卒業してから、リビングケア、ボディケア、衛生用品を扱う総合企業である『清和堂』で働いている。
瑞希の所属する部材調達では、清和堂の主力商品である、洗濯洗剤やシャンプーに使う原材料や香料、ディスペンサーやパウチといった容器を仲介業者から仕入れ、管理している。
調達部の棚にはサンプル用の容器と原料が所狭しと並べられている。
(またか……)
瑞希はため息をつきながら椅子から立ち上がった。サンプル容器の入った段ボールが箱が乱雑に床に置かれているのを発見したからだ。
犯人はわかっている。
瑞希は、仕事はしないくせに口だけは達者の課長代理のデスクに直談判しに行った。
「課長代理、持ち出したサンプルはキチンと棚に返却してください」
「えー。いいじゃんどうせすぐ誰かが持ってくんだしー。置いといたって困らないじゃん?」
四十をとうに過ぎた中年男性の若者ぶった言葉遣いはどうも聞くに耐えない。
端的に言えば、イラっとさせられる。
「規則ですから」
「怖い顔しないでよ。今からやるからさあ〜」
課長代理は渋々、段ボールを片付け始めた。
瑞希とて怒りたくて怒っているわけではない。
他に指摘する人がいないから、憎まれ役を買って出ているだけだ。
黙って傍観している社員と同じ給料が支払われると思うと、本当に割に合わない。
真面目な性格が損をすることもあると知ったのは社会に出てから。
真面目にやっている人間より、要領よく適度に手を抜いた人間が出世するのは、課長代理の例を見る限り明らかだ。
――婚活でも同じことが言える。
(あー、疲れた)
遅刻による遅れを取り戻し、午前中の仕事をマキで終わらせた瑞希は社員食堂に足を運んだ。
同僚達が連れ立ってランチに出かける中、瑞希はいつもひとりで持参した弁当を食べている。
昔は一緒に出かけたけれど、なんやかんや最近はひとりの方が気が楽だった。
(ふーん。龍河谷って隣の県にあるんだ……)
ハムとレタスを挟んだだけのサンドウィッチを食べながら、スマホ片手に調べものを始める。
今朝見たあのポスターの場所がどうしても気になったのだ。
蓬莱湖は火山の噴火によってできた窪地に雨が溜まってできるカルデラ湖らしい。
どんな秘境にあるのかと思ったら、まあまあ近い。
特急列車で二時間。駅からは登山口までバスで三十分。
しかし、蓬莱湖を臨める展望台広場まで行くには三時間以上山に登らなければならないようだ。
片道二時間半かけたあとに、さらに三時間の登山が必要らしい。
(いやいや、無理でしょ)
出来ることなら行ってみたいなと思ったのがそもそもの間違いだった。
ひとりでもふらっと入れるチェーンの居酒屋じゃあるまいし、敷居は高くて当然だ。
もっぱらインドア派の瑞希は社会人になってからロクな運動をしていない。
三時間の登山なんて想像すらできない。
蓬莱湖をこの目で見るなんて、到底無理な話だ。
(でも……)
婚活十連敗を喫していた瑞希はなんだか疲れていた。
何でもいいからこの鬱々とした気持ちを発散させたい。
(あの風景を見たら、絶対に元気が出てくるはずなのに!)
心はすでに龍河谷に旅立っている。柔らかな風を全身に受け、湖を眺めている自分を想像していたそのときだ。
「魚谷さん」
春の日差しの穏やかな空気を纏う女性から、鈴の音色のような軽やかな声で話しかけられる。
瑞希は慌ててサンドウィッチを飲み込み、後ろを振り返った。
「藤峰さん、何でしょうか?」
「先週頼んでおいたフェイスミストの新しいサンプルボトルってもう届いてる? 来週のプレゼンで使いたいの」
「あ、はい。もう届いてます。のちほど企画部までお持ちしますよ」
「あら、いいの? ありがとう」
チキンサラダをのせたトレーを手に持った彼女はツカツカとヒールをかき鳴らし、流れるような動作で瑞希と同じおひとり様専用のカウンター席に座る。
小綺麗なネイビーのセットアップ。背筋がピンと伸びた美しい姿勢。
まるで、目に見えないビロードの絨毯でも敷かれているように、誰もが彼女を振り返っていた。
藤峰木綿子は、清和堂の中でも異色の存在だ。
二年前に地方支社から本社に異動になってからというもの、彼女の話題には事欠かない。
彼女が所属する営業企画部は清和堂の花形部門だ。
有望な若手や、古参のエースがひしめきあう中、彼女が企画から販売まで担当したルームフレグランス『スノウフレーク』は爆発的な人気を博し、販売以来右肩上がりの売上を誇る。
三十五歳を過ぎてなお結婚せず、バリバリ仕事をこなす美人キャリアウーマンの木綿子は社内でも一目置かれている。
もちろん、上層部からの覚えもめでたく、女性初の営業企画部長の座も夢ではないと噂されている。
(世の中にはあんな人もいるんだよなあ)
木綿子は瑞希のような地味な一般社員の顔を覚え、わざわざ気さくに声をかけてくれる。
たとえば瑞希が木綿子のように華のある女性だったら、婚活に成功していただろうか。
思わず考えずにはいられなかった。
◇
(見るだけ。ほんのちょっと覗くだけだから)
退社後、瑞希は自分で自分に言い訳しながら、 大型ファッションビルの七階にある登山用品店にやって来ていた。
(こんなところに登山用品店があるなんて知らなかった)
このビルには何度も来たことがあるが上層階に登山店があるなんて調べるまで知らなかった。
入口をおっかなびっくり抜けていけば、いかにも登山用品店という風景が広がっている。
壁際にはトレッキングシューズに、バックパック。
最も目立つ入口前のスペースにはテントやバーベキュー用のコンロといったアウトドアグッズが所狭しと展示されている。
春先のバーベキューと花見の需要を見越しているのか、焚き火の体験セットなんかが手頃な値段で売られている。
(へー。おもしろい)
もちろん、目当ての登山グッズも豊富に販売されている。
レディースコーナーも充実していて、瑞希はホッと胸を撫で下ろした。
なにせ登山用品店を訪れるのは初めてだ。
登山といえば男性のイメージが強いが、ちゃんと女性物のサイズも取り揃えられているようだ。
ところが、安心したのも束の間。
どんなものがあるのか店内を練り歩いていた瑞希の足取りが次第に重くなる。
(どうしよう)
清水の舞台から飛び降りるような気持ちでここまでやってきたわけだが、初心者の瑞希には何を買えばいいのか見当がつかない。
例えば、バックパック。
全てがリットルで表記されている。
数字が大きければ大きいほど中身がたくさん入るのはわかるが、龍河谷に行くには一体どの程度の大きさと荷物が必要なのか瑞希にはわからない。
しかも形も種類も様々で瑞希はフックにかかっているバックパックを手に取っては、首を傾げながら戻していった。
大きく弾んでいた気持ちが、徐々に萎んでいく。
(すっかりその気になってたけど、本当に龍河谷に行くつもり?)
道具を揃えればなんとかなるかもと思っていたが、気持ちが揺らいでいく。
行く、行かないのルーレットが頭の中で、ぐるぐると回り続ける。
そうして店内をあてもなく彷徨っていた瑞希の目が、ふいに”龍河谷”という三文字を捉えた。
店内に設置されていたラックに、『春にオススメ、龍河谷トレッキングツアー』と題されたフライヤーが置かれていたのだ。
瑞希はパアッと顔を輝かせた。
(ひとりで行くつもりだったけど、複数人で行くのも全然アリだ!)
喜び勇んでラックからフライヤーを抜き出し手に取ったその刹那。
「魚谷さん」
瑞希の肩にポンと誰かの手が置かれた。
「ひっ!」
瑞希は小さく悲鳴を上げ、思わず肩をすくませた。手からスルリとフライヤーが滑り落ちる。
「驚かせてごめんね。知っている人がいたから、つい話しかけちゃった」
「ふ、藤峰さん?」
突然、声をかけてきたのは瑞希と同じ仕事帰りと思しき木綿子だった。
(な、なんで藤峰さんが登山用品店に!?)
「ん? なにか落としたよ」
木綿子は瑞希が床に落としたフライヤーを拾い上げたかと思えば、まじまじと眺め始めた。
「魚谷さん、龍河谷に行くの?」
――しまった。
ポスターに心惹かれて興味本位で登山を始めようとしているのをまだ誰にも知られたくなかった。
しかし、フライヤーを眺めている現場を押さえられては、誤魔化しようがない。
瑞希は仕方なく白状した。
「ほ、蓬莱湖に行ってみたくて……」
瑞希がそう言うと、木綿子はもう一度フライヤーに視線を落とした。
「このツアーだと蓬莱湖には行かないわよ? その手前で折り返すルートだもの」
「え!?」
木綿子いわく、龍河谷には複数の登山ルートが存在し、このツアーでは蓬莱湖までは行かないらしい。
(そんなあ……)
期待を膨らませていたこともあり、瑞希はすっかり肩を落とした。
落胆する様子を見かねたのか、木綿子が口を開く。
「えーっと、魚谷さんさえよければなんだけど……」
「はい?」
「私と一緒に登らない?」
「藤峰さんとですか?」
「ええ。私も龍河谷には何回か登ったことがあるし、知らない人同士で登るよりずっと気楽でしょう? 車で行くつもりだから家まで送り迎えもできるわ」
瑞希は思わず目をパチクリさせた。
この口ぶりからすると、もしかして……。
「藤峰さん、登山がご趣味なんですか?」
「ええ」
キャリアを極める木綿子と山登りがいまいちイコールで繋がらない。
たしかに同行者がいれば、初心者ひとりで行くよりもずっとハードルが下がる。
そのうえ、家まで送り迎えもしてくれるなんて、至れり尽くせりだ。
なにごとも先達がいてほしいものだと、詠んだのは徒然草の兼好法師だったか。
旅は道連れだとよく言ったものだ。
瑞希はしばし考えた末にもう一度清水の舞台から飛び降りる覚悟を決めた。
「お願いしてもいいでしょうか?」
「決まりね」
こうして瑞希は清和堂のマドンナである木綿子とプライベートの連絡先を交換したのだった。