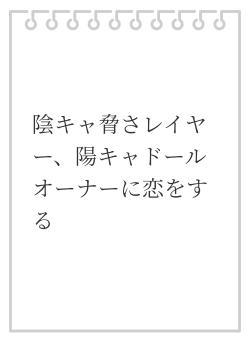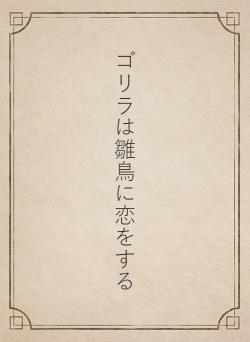金井は夏休みの間、バイトと課題の合間に、自宅でミシンに向かった。その間も小沢からは、まめに連絡が入った。
時間に余裕があれば、音声通話やビデオ通話をした。ミシンをかけているときは音がうるさくてできないが。
手縫いの時、何もしゃべらなくても、彼がそばにいる気がして、何だか楽しい。
無言で作業する金井に、小沢は時々からかってくることもある。
「おーい。居眠りしているのか?」
「今細かい作業しているの!」
「うん、知ってる。ははは」
時々、通話中に母親が入ってくることもあった。
「陽、晩御飯冷めちゃうわよ?」
「か、母さん! いつもノックしてから入ってって言ってるのに……ごめん。小沢くん」
「あ、金井くんのお母さん? どうもー、いつも仲良くしてもらってます!」
丁度その時、ビデオ通話だったため、お互いの顔が丸見えだった。
「あらー! 最近、陽が楽しそうだと思ったら、こんなイケメンのお友だちがいたなんて!」
「金井くんのお母さんなだけあって、とても可愛いですね! いつもお世話になっています!」
「まー! 可愛いだなんて言われるの何年ぶりかしら! 今度うちに遊びにいらっしゃいな!」
母親は自身の頬を押さえ、興奮気味に体を揺らした。よほど可愛いと言われたのが嬉かったようだ。
陽キャ同士の会話、しゅごい。
「陽、キリのいいところで下に降りていらっしゃいね!」
母親はスキップするんじゃないかという勢いで部屋を出ていった。その後の静けさはまるで嵐がさったようだ。
「な、なんかごめんね。うるさくて」
「いいよ。さ、ごはん食べてきなよ」
「うん。またね」
数日後、そんな騒がしかったりした衣裳作りの日々は終わりをむかえた。
ドール服は借りたボディにぴったりだった。
金井が着る衣裳もどこから見ても、小沢の推しだ。
普段衣裳が完成した時は、イベントに間に合った気持ちと、達成感で飛び上がるほど喜ばしいことだが、何かが引っかかる。
もやもやした気持ち。これは何だろうと考えた末、気付いた。
あぁ、これは、不安な気持ちだ。
学校でまたひとりぼっちに戻ってしまう?
近いが違う。
ひとりぼっちじゃなければ、誰とでもいい?
違う。今気づいた。あの時きっと誰とでもよかったから、つるんでいたオタク友達と、クラスが離れて疎遠になってしまったのだろう。
撮影が終わったら小沢と関われなくなってしまう?
そうだ。
小沢と関わっている間は、自分がひとりぼっちだということをすっかり忘れていた。
学校でも、端から見ればひとりぼっちだったが、水面下でメッセージをやりとりしており、孤独を忘れていた。
小沢くんと離れたくない!
だけど、自分は小沢にとって願いを叶えられるだけの存在だけでしかない。
用が済めば、全て終わりなのだ。
作り終わったよと完成した衣裳の画像を送ろうと、メッセージアプリを立ち上げるが、もう一息のタップが出来ない。
ドールボディが服を着ている画像と、金井が試着している画像の二枚を送れない。
『出来たよ、ウィッグはこれから整えるね。ドールのウィッグは用意出来ているの? よかったら、俺がセットしようか?』
ダラダラと先延ばしにしても、いつかはしびれを切らして嫌われてしまうだろう。
深呼吸を一つ、思いきってタップした。
直ぐに既読がつき、返事が来た。
『凄いな。推しそのものだ。ドールウィッグの件は似たようなもの見つけたから大丈夫。ありがとう』
メッセージアプリの通知がまるで、終わりのカウントダウンをしているようだった。
時間に余裕があれば、音声通話やビデオ通話をした。ミシンをかけているときは音がうるさくてできないが。
手縫いの時、何もしゃべらなくても、彼がそばにいる気がして、何だか楽しい。
無言で作業する金井に、小沢は時々からかってくることもある。
「おーい。居眠りしているのか?」
「今細かい作業しているの!」
「うん、知ってる。ははは」
時々、通話中に母親が入ってくることもあった。
「陽、晩御飯冷めちゃうわよ?」
「か、母さん! いつもノックしてから入ってって言ってるのに……ごめん。小沢くん」
「あ、金井くんのお母さん? どうもー、いつも仲良くしてもらってます!」
丁度その時、ビデオ通話だったため、お互いの顔が丸見えだった。
「あらー! 最近、陽が楽しそうだと思ったら、こんなイケメンのお友だちがいたなんて!」
「金井くんのお母さんなだけあって、とても可愛いですね! いつもお世話になっています!」
「まー! 可愛いだなんて言われるの何年ぶりかしら! 今度うちに遊びにいらっしゃいな!」
母親は自身の頬を押さえ、興奮気味に体を揺らした。よほど可愛いと言われたのが嬉かったようだ。
陽キャ同士の会話、しゅごい。
「陽、キリのいいところで下に降りていらっしゃいね!」
母親はスキップするんじゃないかという勢いで部屋を出ていった。その後の静けさはまるで嵐がさったようだ。
「な、なんかごめんね。うるさくて」
「いいよ。さ、ごはん食べてきなよ」
「うん。またね」
数日後、そんな騒がしかったりした衣裳作りの日々は終わりをむかえた。
ドール服は借りたボディにぴったりだった。
金井が着る衣裳もどこから見ても、小沢の推しだ。
普段衣裳が完成した時は、イベントに間に合った気持ちと、達成感で飛び上がるほど喜ばしいことだが、何かが引っかかる。
もやもやした気持ち。これは何だろうと考えた末、気付いた。
あぁ、これは、不安な気持ちだ。
学校でまたひとりぼっちに戻ってしまう?
近いが違う。
ひとりぼっちじゃなければ、誰とでもいい?
違う。今気づいた。あの時きっと誰とでもよかったから、つるんでいたオタク友達と、クラスが離れて疎遠になってしまったのだろう。
撮影が終わったら小沢と関われなくなってしまう?
そうだ。
小沢と関わっている間は、自分がひとりぼっちだということをすっかり忘れていた。
学校でも、端から見ればひとりぼっちだったが、水面下でメッセージをやりとりしており、孤独を忘れていた。
小沢くんと離れたくない!
だけど、自分は小沢にとって願いを叶えられるだけの存在だけでしかない。
用が済めば、全て終わりなのだ。
作り終わったよと完成した衣裳の画像を送ろうと、メッセージアプリを立ち上げるが、もう一息のタップが出来ない。
ドールボディが服を着ている画像と、金井が試着している画像の二枚を送れない。
『出来たよ、ウィッグはこれから整えるね。ドールのウィッグは用意出来ているの? よかったら、俺がセットしようか?』
ダラダラと先延ばしにしても、いつかはしびれを切らして嫌われてしまうだろう。
深呼吸を一つ、思いきってタップした。
直ぐに既読がつき、返事が来た。
『凄いな。推しそのものだ。ドールウィッグの件は似たようなもの見つけたから大丈夫。ありがとう』
メッセージアプリの通知がまるで、終わりのカウントダウンをしているようだった。