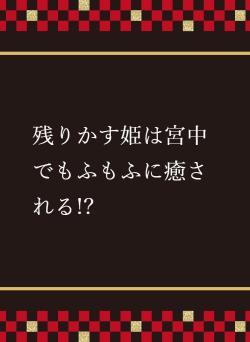俺は矢田吹に「先、飯食ってて」と言い置いて、伊月と一緒に教室を出た。
先生に呼ばれてるって、マジかよ。ヤバすぎだろ。用件は何だ?
……ってなことを漫然と考えていたのが間違いだった。角を曲がったところで、誰かと正面衝突しちまった。
「……痛って、うわっ、ヤベっ」
なんとか転ばずに済み、軽い痛みに耐えていた俺は、ぶつかった相手を見た瞬間ギョッとした。
「うぅぅ……」
俺とは対照的に廊下に転がり、白衣に包まれた身体をくねらせて呻く長身の男は、この学校の教師だ。名前は確か……。
「浦辻先生、大丈夫ですか」
伊月が長身を抱え起こしながら名前を呼んでくれたお陰で、思い出した。
浦辻は化学の担当で、今日もトレードマークの白衣を身に着けている。確かまだ三十歳そこそこで、狸穴高校の教員の中じゃ若い方だが、眼鏡と長めの前髪が顔の大半を覆っているせいか、いまいち見た目が冴えない。
無口でぬぼーっとしているのも相まって、存在感がまるでなかった。俺も名前がすぐ出てこなかったくらいだしな。
「あの、すいませんでした」
伊月に掴まってようやく立ち上がった浦辻に、俺はぺこっと頭を下げた。
「君、怪我は?」
「あ……大丈夫っす」
浦辻と俺がそんなやりとりをしているうちに、伊月が地面に転がっていた薄っぺらいものをそっと拾い上げた。
「先生、ぶつかったとき、これを落としましたよ」
「あ、それは僕のタブレット!」
浦辻は伊月の手からタブレットをもぎ取った。動作確認をして異常がないことを確かめると、安堵の表情を浮かべる。
「よかった、無事だ。これが壊れていたら、次の授業ができなくなるところだったよ」
理系科目の担当だからだろうか、浦辻はあらゆるものをデジタル化していた。
授業では自ら作った動画をスクリーンに投影して説明をするし、テストの結果をデータとして取り込み、生徒の弱点をソフトで分析して答案返却時に渡してきたりする。
俺は一年のとき浦辻の授業を受けたが、教科書より動画を見る方が分かりやすかったし、テスト結果の分析も参考になった。……まぁ、毎回赤点スレスレだったけどな。
他の教師は教科書やファイルや筆記用具なんかを持ち歩くことが多いが、浦辻が手にしているのはいつも薄いタブレットのみだ。俺たち生徒の間では、浦辻の本体はそのタブレットなんじゃないかと密かに囁かれていたりいなかったり。
まぁとにかく、浦辻の持ち物が少なくてよかった。他の教師みたいにいろいろ持ち歩いてたら、ぶつかったときに散乱して大変だっただろう。
「じゃあ、僕はこれで失礼する」
浦辻は白衣の裾を翻し、タブレットを大事そうに抱えて立ち去った。俺と伊月も、再び歩き始める。
ずんずん進む背中を素直に追いかけていた俺は、しばらくして「はて」と首を傾げた。
「おい、伊月。職員室ならあっちじゃねー?」
職員室は、今いるメイン校舎の二階にある。
だが伊月は一番下の階まで降り、そのまま渡り廊下を通って、音楽室や視聴覚室が並ぶ別校舎に入っていった。
「なぁ、どこ行くんだよ、伊月」
いい加減わけが分からなくて、俺は前を行く伊月の肩を叩いた。伊月はそこでようやく足を止め、古ぼけた木の引き戸を指さす。
「ここだよ」
先生に呼ばれてるって、マジかよ。ヤバすぎだろ。用件は何だ?
……ってなことを漫然と考えていたのが間違いだった。角を曲がったところで、誰かと正面衝突しちまった。
「……痛って、うわっ、ヤベっ」
なんとか転ばずに済み、軽い痛みに耐えていた俺は、ぶつかった相手を見た瞬間ギョッとした。
「うぅぅ……」
俺とは対照的に廊下に転がり、白衣に包まれた身体をくねらせて呻く長身の男は、この学校の教師だ。名前は確か……。
「浦辻先生、大丈夫ですか」
伊月が長身を抱え起こしながら名前を呼んでくれたお陰で、思い出した。
浦辻は化学の担当で、今日もトレードマークの白衣を身に着けている。確かまだ三十歳そこそこで、狸穴高校の教員の中じゃ若い方だが、眼鏡と長めの前髪が顔の大半を覆っているせいか、いまいち見た目が冴えない。
無口でぬぼーっとしているのも相まって、存在感がまるでなかった。俺も名前がすぐ出てこなかったくらいだしな。
「あの、すいませんでした」
伊月に掴まってようやく立ち上がった浦辻に、俺はぺこっと頭を下げた。
「君、怪我は?」
「あ……大丈夫っす」
浦辻と俺がそんなやりとりをしているうちに、伊月が地面に転がっていた薄っぺらいものをそっと拾い上げた。
「先生、ぶつかったとき、これを落としましたよ」
「あ、それは僕のタブレット!」
浦辻は伊月の手からタブレットをもぎ取った。動作確認をして異常がないことを確かめると、安堵の表情を浮かべる。
「よかった、無事だ。これが壊れていたら、次の授業ができなくなるところだったよ」
理系科目の担当だからだろうか、浦辻はあらゆるものをデジタル化していた。
授業では自ら作った動画をスクリーンに投影して説明をするし、テストの結果をデータとして取り込み、生徒の弱点をソフトで分析して答案返却時に渡してきたりする。
俺は一年のとき浦辻の授業を受けたが、教科書より動画を見る方が分かりやすかったし、テスト結果の分析も参考になった。……まぁ、毎回赤点スレスレだったけどな。
他の教師は教科書やファイルや筆記用具なんかを持ち歩くことが多いが、浦辻が手にしているのはいつも薄いタブレットのみだ。俺たち生徒の間では、浦辻の本体はそのタブレットなんじゃないかと密かに囁かれていたりいなかったり。
まぁとにかく、浦辻の持ち物が少なくてよかった。他の教師みたいにいろいろ持ち歩いてたら、ぶつかったときに散乱して大変だっただろう。
「じゃあ、僕はこれで失礼する」
浦辻は白衣の裾を翻し、タブレットを大事そうに抱えて立ち去った。俺と伊月も、再び歩き始める。
ずんずん進む背中を素直に追いかけていた俺は、しばらくして「はて」と首を傾げた。
「おい、伊月。職員室ならあっちじゃねー?」
職員室は、今いるメイン校舎の二階にある。
だが伊月は一番下の階まで降り、そのまま渡り廊下を通って、音楽室や視聴覚室が並ぶ別校舎に入っていった。
「なぁ、どこ行くんだよ、伊月」
いい加減わけが分からなくて、俺は前を行く伊月の肩を叩いた。伊月はそこでようやく足を止め、古ぼけた木の引き戸を指さす。
「ここだよ」