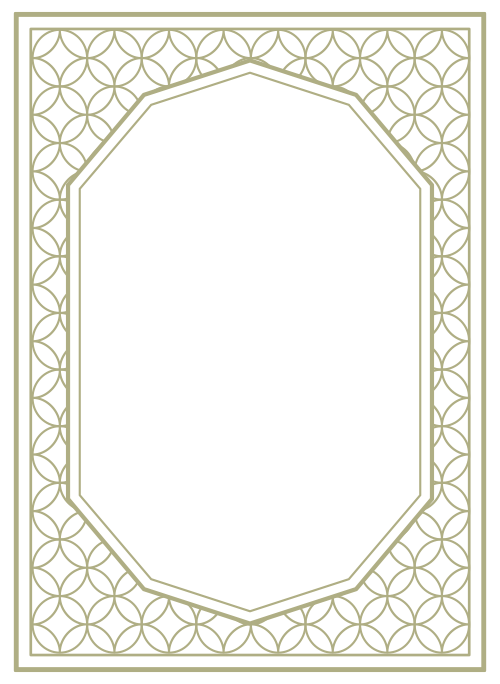その日、僕の背負った十字架の重さが、ふと軽くなった。
僕だけではできなかった、千里の新しい挑戦を、ふたりがもたらしてくれたからだ。
葉山は興味本位で千里に会いにきただけと思ったが、その行動力には驚かされた。
『マインド・コネクト・ゲーム』にはまんまと嵌められた。調べても見つけられないゲームだったから、きっと彼の作戦だったのだろう。けれど、まさか僕らだけで千里を屋外に連れだそうなんて。
無計画で能天気なやつかと思っていたけれど、彼は彼なりの苦悩を抱えていた。それが彼の外向的な性格の裏に隠されていたなんて意外だったし、知って不思議な気持ちが湧いていた。
不遜な侵入者と思っていた高円寺さんは、意外にも僕にしっかりと向き合い、千里と僕の大切な時間を尊重してくれた。千里の友達にもなってくれたし、ふたりは音楽でも気が合いそうだった。ミーハーなお嬢様かと思いきや、根は驚くほど真面目だった。
ふたりは不自由を抱える千里に対しても分け隔てなく気軽な友達として接してくれたし、楽しみを与える工夫も凝らしてくれた。千里の笑顔が増えたのは、彼らのおかげだと、今は素直に認められる。
僕の十字架は、ひとりで背負うにはあまりにも重すぎた。ふたりはそんな十字架を知らず知らずのうちに支えてくれていた。ふたりがもたらす千里の笑顔が、僕の十字架を軽くしてくれたのだ。
だからだろうか、僕はいつの間にか、ごく自然に笑えるようになっていた。
けれど、どうしても千里のことでは引っかかっていた。
思い返してみれば、高校に入学して千里と再会の約束を取りつけたとき、千里は妙によそよそしかった。
おばさんと相談し、会える日を水曜日に限定したことも腑に落ちなかった。
それに高校に入学してから、会いにきたときのおばさんの迷いのある表情にも疑問符が浮かんだ。
そのとき、僕はふたりの時間が続くことを願って千里にこう尋ねた。「僕と一緒にいるの、もし嫌じゃなかったら、ずっとでもいい?」と。
千里の答えは、「まだ、そんなこと、わからないから」だった。けれど僕を歓迎していないというわけでもない。
だから千里には、僕に知られたくない将来の懸念があるのだと、ずっと思っていた。
確かめることのできない不安だけが砂埃のように心の中に積み重なってゆく。
そして僕は決定的な証拠に気づいてしまう。
初めて四人で出かけたとき、草すべりで転倒し千里の服がはだけた。そのとき僕は見てしまった。
千里のお腹の真ん中には、縦断するようなおおきな傷があったのだ。縫い目の跡があり、手術痕であることは間違いなかった。
それから高円寺さんに機を見て尋ねた。千里の病気がどんなものなのか、それから眼だけに起きるものなのかどうか。
高円寺さんの返事はこうだった。
『あんなに元気なんだから、なんにもないんじゃない?』
その答えには、まるでなにか悪いことが起きうることを知っているような気配があった。高円寺さんは父が医者、兄が医学部らしいから情報源は豊富なはずだし、第一、病名を当ててみせたのだから。
しかも、千里はしだいに外出を遠慮するようになってきた。明るく振舞っているけれど、動きが緩慢になり、かつてダンスを踊っていたときのキレの良さはなくなっていた。
僕の懸念はふたりの時間の中で、しだいに輪郭をあらわにしてゆく。
千里は背中合わせの朗読を終えると毎回、甘えて膝枕をせがむようになった。膝の上で涙をこぼしていた。
最初は物語に感動していたのかと思ったけれど、どうやら違うようだ。どんな物語であれ、必ず同じように泣いていたから、まるでこの時間を惜しんでいるかのように僕には感じられた。
そしてついに、いままで振り払ってきた悪い予感は現実のものとなって、僕に切っ先を突き付けてきたのだ。
僕の腕の中で呼吸を荒らげる千里のひたいは冷や汗にまみれ、顔色は真っ青だ。意識が朦朧としていて、明らかに危険な状態だった。僕は必死に声を振り絞る。
「高円寺さん、おばさんを呼んできて! 葉山は救急車を!」
「わかった!」
「すぐ呼ぶ! きたら外に運びだすぞ!」
千里を抱きとめる腕がひどく震えている。千里を失うという恐怖と、現実から目を背けていた自分への怒りが思考を奪い取る。
「千里……ッ! 頑張れ、頑張ってくれ! どうか、どうか……ッ!」
千里は喘ぐような呼吸をしていて、脈は頼りない細さで拍動している。
サイレンの音がようやっと近づいてきて、救急車が家の前で停まる。それまでの時間は、悠久のように長く感じられた。
僕らは三人で千里を抱き上げ部屋から運びだし、玄関前で救急隊のストレッチャーに乗せた。おばさんは救急隊に向かって必死に状況を伝えている。
救急車に乗せられてからは、向かう病院がすんなりと決まった。まるで最初から想定された事態なのだと思えるほどに。
「ぼっ……僕らも行きますっ! 行かせてください!」
僕らは三人で懇願したけれど、おばさんは冷静を装い僕らにこう返す。
「お願い、心配しないで。落ち着いたら後で連絡するから。それからごめんね、手助けしてもらっちゃって」
おばさんのその様子は、いくばくかの心構えがあったように思えた。
心配しないでいられるはずがない。けれど僕らはなにも言い返せない。おばさんのほうが絶対、辛い思いをしているのだから。
僕らは急いで荷物をまとめて家を出た。救急車はおもむろに動きだす。
千里を乗せた救急車を、僕らはただ、見送ることしかできなかった。
僕だけではできなかった、千里の新しい挑戦を、ふたりがもたらしてくれたからだ。
葉山は興味本位で千里に会いにきただけと思ったが、その行動力には驚かされた。
『マインド・コネクト・ゲーム』にはまんまと嵌められた。調べても見つけられないゲームだったから、きっと彼の作戦だったのだろう。けれど、まさか僕らだけで千里を屋外に連れだそうなんて。
無計画で能天気なやつかと思っていたけれど、彼は彼なりの苦悩を抱えていた。それが彼の外向的な性格の裏に隠されていたなんて意外だったし、知って不思議な気持ちが湧いていた。
不遜な侵入者と思っていた高円寺さんは、意外にも僕にしっかりと向き合い、千里と僕の大切な時間を尊重してくれた。千里の友達にもなってくれたし、ふたりは音楽でも気が合いそうだった。ミーハーなお嬢様かと思いきや、根は驚くほど真面目だった。
ふたりは不自由を抱える千里に対しても分け隔てなく気軽な友達として接してくれたし、楽しみを与える工夫も凝らしてくれた。千里の笑顔が増えたのは、彼らのおかげだと、今は素直に認められる。
僕の十字架は、ひとりで背負うにはあまりにも重すぎた。ふたりはそんな十字架を知らず知らずのうちに支えてくれていた。ふたりがもたらす千里の笑顔が、僕の十字架を軽くしてくれたのだ。
だからだろうか、僕はいつの間にか、ごく自然に笑えるようになっていた。
けれど、どうしても千里のことでは引っかかっていた。
思い返してみれば、高校に入学して千里と再会の約束を取りつけたとき、千里は妙によそよそしかった。
おばさんと相談し、会える日を水曜日に限定したことも腑に落ちなかった。
それに高校に入学してから、会いにきたときのおばさんの迷いのある表情にも疑問符が浮かんだ。
そのとき、僕はふたりの時間が続くことを願って千里にこう尋ねた。「僕と一緒にいるの、もし嫌じゃなかったら、ずっとでもいい?」と。
千里の答えは、「まだ、そんなこと、わからないから」だった。けれど僕を歓迎していないというわけでもない。
だから千里には、僕に知られたくない将来の懸念があるのだと、ずっと思っていた。
確かめることのできない不安だけが砂埃のように心の中に積み重なってゆく。
そして僕は決定的な証拠に気づいてしまう。
初めて四人で出かけたとき、草すべりで転倒し千里の服がはだけた。そのとき僕は見てしまった。
千里のお腹の真ん中には、縦断するようなおおきな傷があったのだ。縫い目の跡があり、手術痕であることは間違いなかった。
それから高円寺さんに機を見て尋ねた。千里の病気がどんなものなのか、それから眼だけに起きるものなのかどうか。
高円寺さんの返事はこうだった。
『あんなに元気なんだから、なんにもないんじゃない?』
その答えには、まるでなにか悪いことが起きうることを知っているような気配があった。高円寺さんは父が医者、兄が医学部らしいから情報源は豊富なはずだし、第一、病名を当ててみせたのだから。
しかも、千里はしだいに外出を遠慮するようになってきた。明るく振舞っているけれど、動きが緩慢になり、かつてダンスを踊っていたときのキレの良さはなくなっていた。
僕の懸念はふたりの時間の中で、しだいに輪郭をあらわにしてゆく。
千里は背中合わせの朗読を終えると毎回、甘えて膝枕をせがむようになった。膝の上で涙をこぼしていた。
最初は物語に感動していたのかと思ったけれど、どうやら違うようだ。どんな物語であれ、必ず同じように泣いていたから、まるでこの時間を惜しんでいるかのように僕には感じられた。
そしてついに、いままで振り払ってきた悪い予感は現実のものとなって、僕に切っ先を突き付けてきたのだ。
僕の腕の中で呼吸を荒らげる千里のひたいは冷や汗にまみれ、顔色は真っ青だ。意識が朦朧としていて、明らかに危険な状態だった。僕は必死に声を振り絞る。
「高円寺さん、おばさんを呼んできて! 葉山は救急車を!」
「わかった!」
「すぐ呼ぶ! きたら外に運びだすぞ!」
千里を抱きとめる腕がひどく震えている。千里を失うという恐怖と、現実から目を背けていた自分への怒りが思考を奪い取る。
「千里……ッ! 頑張れ、頑張ってくれ! どうか、どうか……ッ!」
千里は喘ぐような呼吸をしていて、脈は頼りない細さで拍動している。
サイレンの音がようやっと近づいてきて、救急車が家の前で停まる。それまでの時間は、悠久のように長く感じられた。
僕らは三人で千里を抱き上げ部屋から運びだし、玄関前で救急隊のストレッチャーに乗せた。おばさんは救急隊に向かって必死に状況を伝えている。
救急車に乗せられてからは、向かう病院がすんなりと決まった。まるで最初から想定された事態なのだと思えるほどに。
「ぼっ……僕らも行きますっ! 行かせてください!」
僕らは三人で懇願したけれど、おばさんは冷静を装い僕らにこう返す。
「お願い、心配しないで。落ち着いたら後で連絡するから。それからごめんね、手助けしてもらっちゃって」
おばさんのその様子は、いくばくかの心構えがあったように思えた。
心配しないでいられるはずがない。けれど僕らはなにも言い返せない。おばさんのほうが絶対、辛い思いをしているのだから。
僕らは急いで荷物をまとめて家を出た。救急車はおもむろに動きだす。
千里を乗せた救急車を、僕らはただ、見送ることしかできなかった。