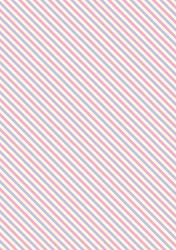というわけのわからないやりとりがあったりしたが、学校での甲斐は相変わらず休み時間は友だちと教室の真ん中にいて、俺と言葉を交わすことはない。
カツアゲ犯と被害者。俺と奴の関係はそれだけだ。
今のところ暴力をふるわれたことはない。(クッションの取り合いを除いて)
もう来ないでくれと言ったら、案外聞き入れられるかもしれない。
いやでも突然キレられるかもしれないし。フィジカルでいったら大人と子供くらい差があるし。
だから仕方なく、俺は今日も甲斐を迎え入れる。
仕方なく、前に来たとき「これうまいな」とあいつが言っていたドライジンジャエールを箱でポチる。
誰かのためにする買い物は、ちょっと楽しかった。
*********
化学と体育、移動教室を続けて組んだやつは死ねばいい。
俺に化学委員を押しつけた奴らも死ねばいい。
ある日の午後、俺は呪詛の言葉を唱えながら教室へ急いでいた。
要するに前の授業の片付けのせいで体育に遅刻しそうなのだ。
やっと教室へ向かう階段を上っているところで、いつも真ん中でたむろっている奴らが入れ違いに下りてきた。もうみんなジャージに着替え終わっている。
俺の姿に気がつくと、奴らの一人がにやっと口元に笑みを浮かべた。
それに気がついた全員が、だらだらっと階段の幅いっぱいに広がる。通れない。これから着替えないといけないっていうのに。
俺の弱者の嗅覚が嗅ぎつける。これ、わざとだ。
だいたい体のでかい奴は、フィジカルの強さ=優秀さと思っている節がある。
そういう生き物からしたら、高一にもなって身長が百六十にも届かない、ガリガリの痩せっぽちな俺は「特に根拠もなく嫌がらせをしていい超格下の相手」なのだ。
そして体育の教師も同じく俺には好意的じゃなかった。
理由は同じ。体が強い奴は弱い奴を軽んじる。授業に遅れたりしたら、また嫌味や当て擦りを言われるに違いない。胸の中に、じわっと不快感がわき出す。
そのとき。
「うわ、」
階段いっぱいに広がっていた連中のひとりが、突然つんのめった。
転がりおちる――寸前で、なんとか手すりに体を預けて大惨事を免れる。奴はすぐさま振り返って、怒声を飛ばした。
「なにやってんだてめえ!」
怒りの先――階段の上の踊り場に立っていたのは甲斐だった。
たぶん、さっきこいつがつんのめったのは、甲斐が後ろから蹴りをお見舞いしたからなんだろう。着崩したジャージのポケットに両手を突っ込み、足を振り上げたままの姿で固まっている。
「あ……」
おかしなことに、甲斐は「自分でもなんでこんなことをしたのかわからない」みたいな顔をしていた。
「悪ィ。俺の足が長かった」
「はあ!?」
「うける。なに言ってんの?」
蹴られた奴はキレ散らかし、誰かがそう混ぜ返す。
他の奴らの笑い声が重なり、幸い本格的ないざこざには発展しなかった。