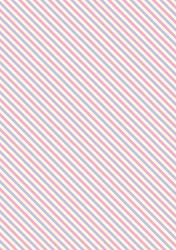そんなわけで、なぜかカツアゲ犯が家にやってきて、一緒に漫画を読むという日々がすっかり定着してしまった。
そんなある日。
漫画を読んでいた甲斐が急に険しい顔になって呟いた。
「……腹減ったな」
人の金で勝手に買い物して、勝手に上がり込んで、勝手に寝転んで、その上食料も要求できる強メンタル。マジで陽キャの脳味噌どうなってんだと思いつつ、俺はキッチンへ向かう。甲斐もあとから着いてきて、冷蔵庫を一緒に覗き込んだ。
色も形も同じにそろえたタッパーが整然と並んでいる様に、また目をぱちくりさせている。
親の依頼で、俺がいない間に家事代行サービスが栄養バランスを考えて作っていってくれた、野菜たっぷり料理だ。
「この辺の、適当に食べていいよ」
「マジか」
甲斐は一瞬顔を輝かせる。が、上から下まで眺め回すと「うーん」と唸った。
「ちょっとこういうのの気分じゃねえっつうか……」
「そりゃおまえの気分に配慮してないからね!?」
この上さらに注文をつけられるって、マジで凄い。
でも、と思う。
実はそんな甲斐の気持ちが、わからなくもなかった。
部屋でごろごろくつろぐ。そういうときに食べたいのは、なんというか、こういう「正しい食べ物」じゃない。
俺はシステムキッチンの一番下、薄い引き出しを開けた。あまり使われることのない、ホットプレートなんかがしまってある片隅にいつも隠してある、激辛ラーメンの袋を取り出す。
「あとはこんなのしかないけど」
甲斐の顔が、朝日を受けたみたいに輝く。
「それ好き!」
「……作るのは自分でやって」
俺はぶっきらぼうに告げる。
危なかった。……うっかり嬉しいとか思うとこだった。
カツアゲ犯なんかと好きなものが一緒だったからって、なんなんだ俺。
意外なことに甲斐は「オッケーオッケー。で、鍋は?」と軽く応じる。腕まくりまでして、やる気満々だ。
「この辺に……」
いつもの引き出しを開ける。が、そこに俺がいつも使う小さな片手鍋の姿はない。まさか勝手に捨てるはずはないから、片付ける場所を変えたのだろう。家事代行の人も母さんも、俺が勝手にくそジャンクなラーメンを作って食べているなんて知らない。
しばらく引き出しの中をごそごそまさぐったが、俺の愛しの片手鍋の姿はどこにもなかった。
と、なると、あとは上の棚か。苦々しい思いでちらっと見上げると、甲斐は目ざとくそれに気がついた。
俺の背後に回り、肩に手を添える。さっと俺の頭越しに手を伸ばす。
「この上?」
すぐ耳元で甲斐の声がする。
肩に触れる手も、やんわり、慈しむみたいな力加減。その仕草が「俺がやるから」と語っている。
教室の真ん中、乱暴に机の上に座って馬鹿騒ぎしている姿からは想像できないやさしい手つきに、俺は驚いていた。
『うちチビがたくさんいるから』
最初に押し入って来た日の言葉を思い出す。いつもこんなふうに下の子たちの世話をしてやってるのかもしれない。
そんなこと、教室で遠巻きに見てるだけじゃわからなかったな――
――ん?
うっかりほっこりしかけ、俺は眉根を寄せる。
ということは今俺「うちのチビ」と同格に扱われたってことか?
「――」
「? なんか急にテンション下がってね?」
などと言いながらも、甲斐は腕まくりすると手早くラーメンを作った。仕上げにスプーンで味噌をひとすくいして入れ、横着にそのまま鍋をかき混ぜる。慣れた手つきだ。
鍋のまま部屋に持っていき、床に座って交互に箸をつけた。
「あつっ。うまっ。あつっ」
「バニラアイスちょっとのせるのも美味いよ」
「悪逆の限りを尽くすって感じだな、内臓的に……」
たわいもないことを話しながら食べる具もないラーメンは、ばかみたいにうまかった。
そんなある日。
漫画を読んでいた甲斐が急に険しい顔になって呟いた。
「……腹減ったな」
人の金で勝手に買い物して、勝手に上がり込んで、勝手に寝転んで、その上食料も要求できる強メンタル。マジで陽キャの脳味噌どうなってんだと思いつつ、俺はキッチンへ向かう。甲斐もあとから着いてきて、冷蔵庫を一緒に覗き込んだ。
色も形も同じにそろえたタッパーが整然と並んでいる様に、また目をぱちくりさせている。
親の依頼で、俺がいない間に家事代行サービスが栄養バランスを考えて作っていってくれた、野菜たっぷり料理だ。
「この辺の、適当に食べていいよ」
「マジか」
甲斐は一瞬顔を輝かせる。が、上から下まで眺め回すと「うーん」と唸った。
「ちょっとこういうのの気分じゃねえっつうか……」
「そりゃおまえの気分に配慮してないからね!?」
この上さらに注文をつけられるって、マジで凄い。
でも、と思う。
実はそんな甲斐の気持ちが、わからなくもなかった。
部屋でごろごろくつろぐ。そういうときに食べたいのは、なんというか、こういう「正しい食べ物」じゃない。
俺はシステムキッチンの一番下、薄い引き出しを開けた。あまり使われることのない、ホットプレートなんかがしまってある片隅にいつも隠してある、激辛ラーメンの袋を取り出す。
「あとはこんなのしかないけど」
甲斐の顔が、朝日を受けたみたいに輝く。
「それ好き!」
「……作るのは自分でやって」
俺はぶっきらぼうに告げる。
危なかった。……うっかり嬉しいとか思うとこだった。
カツアゲ犯なんかと好きなものが一緒だったからって、なんなんだ俺。
意外なことに甲斐は「オッケーオッケー。で、鍋は?」と軽く応じる。腕まくりまでして、やる気満々だ。
「この辺に……」
いつもの引き出しを開ける。が、そこに俺がいつも使う小さな片手鍋の姿はない。まさか勝手に捨てるはずはないから、片付ける場所を変えたのだろう。家事代行の人も母さんも、俺が勝手にくそジャンクなラーメンを作って食べているなんて知らない。
しばらく引き出しの中をごそごそまさぐったが、俺の愛しの片手鍋の姿はどこにもなかった。
と、なると、あとは上の棚か。苦々しい思いでちらっと見上げると、甲斐は目ざとくそれに気がついた。
俺の背後に回り、肩に手を添える。さっと俺の頭越しに手を伸ばす。
「この上?」
すぐ耳元で甲斐の声がする。
肩に触れる手も、やんわり、慈しむみたいな力加減。その仕草が「俺がやるから」と語っている。
教室の真ん中、乱暴に机の上に座って馬鹿騒ぎしている姿からは想像できないやさしい手つきに、俺は驚いていた。
『うちチビがたくさんいるから』
最初に押し入って来た日の言葉を思い出す。いつもこんなふうに下の子たちの世話をしてやってるのかもしれない。
そんなこと、教室で遠巻きに見てるだけじゃわからなかったな――
――ん?
うっかりほっこりしかけ、俺は眉根を寄せる。
ということは今俺「うちのチビ」と同格に扱われたってことか?
「――」
「? なんか急にテンション下がってね?」
などと言いながらも、甲斐は腕まくりすると手早くラーメンを作った。仕上げにスプーンで味噌をひとすくいして入れ、横着にそのまま鍋をかき混ぜる。慣れた手つきだ。
鍋のまま部屋に持っていき、床に座って交互に箸をつけた。
「あつっ。うまっ。あつっ」
「バニラアイスちょっとのせるのも美味いよ」
「悪逆の限りを尽くすって感じだな、内臓的に……」
たわいもないことを話しながら食べる具もないラーメンは、ばかみたいにうまかった。