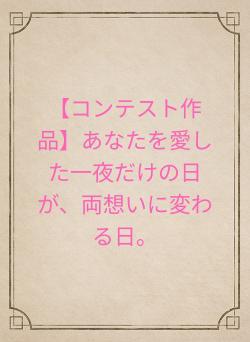「お疲れ、苺実(まいみ)」
「那月(なつき)、お疲れ」
私にとって那月は、ずっと仲のいい男友達だった。
那月とは本当に分け隔てなく話が出来て、私の恋愛相談にも乗ってくれて、フラレた時は慰めてくれるような、そんな人だった。
私はそんな那月のことを本当に友達として好きだった。 那月といると楽しくて、本当にイヤなことも忘れられる。
そんな那月だからこそ、信頼してる。那月がいるから、私は楽しく生きていられるんだと、そう思ってた。
でもその友達という関係が、終わりを迎えることになるなんてーーー。
「苺実、ビール?」
「いや、明日も仕事で朝早いから、烏龍茶でいいや」
目の前に座る私に「なんだよ。飲まねえのかよ」と文句を言われたが、「明日は大事な打ち合わせがあるの」と答えた。
「分かった。烏龍茶な」
「うん」
那月は烏龍茶とビールを注文し、私に「悪いな。突然呼び出して」とお絞りの袋を開ける。
「ううん。それより、話ってなに?」
那月はおしぼりで手を拭きながら、「まあ、ちょっとな」と言葉を濁す。
「苺実にさ、俺が苺実に好きな人いるって話したの、覚えてるか?」
那月にそう言われて、私は「うん。覚えてるけど……」とおしぼりの袋を開ける。
「それがどうかした?」
おしぼりで手を拭きながら聞くと、那月は「その好きな人ってさ……お前のこと、なんだよ」と言われる。
「……え?」
思わず那月の顔を見た。
「やっぱり、気付いてなかったんだな」
那月は運ばれてきたビールの半分を飲み、私に「まあ、そうだと思ってたけど」と私に告げた。
「えっ、待って待って。……私?」
えっ? 私……?
「そうだよ。俺の好きな人は、苺実。お前だよ」
那月が……私のことを好き? 私、想像したこともなかった。
「……冗談なんかじゃ、ないか」
「当たり前だろ」
私って……那月のことをどう思ってるんだろう? 確かに那月はイイヤツだし、優しい。
相談にも乗ってくれるし……アドバイスだって。でも……。
「……ちょっとまだ、信じられない」
「まあ、そうだろうな。俺だって今日初めて言ったし」
私は烏龍茶に口を付け、「あのさ……いつから?」と問いかけてみる。
「いつから……。そうだな。いつの間にかだったけど、多分出会った時から」
「出会った時から……?」
それってさ……一年前から、ってことだよね? 私たちが出会ったのは、一年前からだし……。
その時から、私のことを……?
「全然……気付けなかった」
「まあ、お前鈍感だしそうだと思ったけどね」
「なんか、ひどくない?」
でもでも……私は那月のことを本当に、友達としか思ってなかった。
友達だからこそ、一緒にいて楽なんだなって感じてた。だから今、私は困惑している。
「なんで那月は……私の恋愛相談、乗ってくれてたの?」
「まあ、友達だし? 正直……恋愛相談乗ってる時の俺は、友達としてはいられなかった。今すぐにでも、苺実のことを奪いたかったし」
「そっか……。そうだよね、普通は」
那月のことなんて、なんにも意識してなかった。そもそも、友達としてしか見てなかったし。
「だから苺実があの時フラレたって聞いた時……こんなこと言うのは本当にあれだけどさ、内心ホッとした」
ビールを飲み干した那月は、もう一度ビールを注文した。
「苺実のそばにいられるのはさ、やっぱり俺だけだと思うんだけど?」
「……那月、あのさ、私っ……」
那月のことは好きだ。友達として。
でも……那月がこれなら私の隣からいなくなるのは、イヤだなって思ってしまった。
那月に愚痴を聞いてもらえなくなることも、美味しいものを食べに行けなくなることも。
全部……イヤかもしれない。
「苺実が俺のことをそんな風に思ってないのは、よく分かってる。……でも、気持ちを抑えられなくてさ」
そんな悲しそうな顔をした那月は、初めて見たかもしれない。
那月といるとたくさん笑ってて、冗談とかも言い合ってて。……よく考えたら、楽しいことばかりだった。
だから那月がこんなに悲しそうな顔をする姿、見たことなかった。 こんな顔をさせたのは……私だ。
「だからさ、苺実」
「ん……?」
那月は私を見ながら、「俺ともう……友達やめね?」と言ってきた。
「……え?」
那月はだし巻き卵を食べながら、「俺はもう、お前とは友達ではいられねぇよ。……こんなに好きな女が目の前にいるのに、友達でいるとか……そんなの辛いって」と下を向いてしまう。
「ごめん……那月」
私は那月のことを、どう思ってるのだろうか……?
「謝られるとさ、俺余計に惨めになるって」
「……ごめん」
今の私には、「ごめん」としか伝えることが出来ない。
「俺はもう、苺実の友達としてそばにいることは出来ない。 苺実の気持ちを知ってるからこそ、そう思う」
那月が私のそばにいない人生なんて……私、考えられない。 那月がいないと、私は私じゃなくなる気がした。
那月がいることで、私は私らしくいられる。那月は、私にとって大切な存在だから。
これからもずっとーーーー。
「ごめんな、苺実。困らせて」
「え……?」
那月は「言ったら、苺実が困ることなんて分かってたんだよ。……でもさ、失恋したお前のそばにいる度に、俺の心はえぐられたんだよ。そんなにそいつのことが好きなのかって……問いかけたくなるくらい、俺の心はえぐられた」と私に告げると、再び料理に手を付ける。
「……那月、あのさ」
「ん?」
「あのさ……私は、那月がいないと困るの」
今までだって、那月がいないと寂しくて、那月と話したいとか、そう思ってしまっていた。
「苺実……?」
「だから、友達やめたいとか……言わないでよ」
私は烏龍茶を一気飲みすると、那月の顔を見る。
「那月……那月がいないと、私は楽しくないよ。那月がいるから、私は私らしくいられるの。 那月と笑って話したり、恋愛相談したり、くだらない話で盛り上がったり。そういう小さな出来事は、全部那月がいるから出来ることなんだよ? 那月が私と友達をやめたら、私はそれが出来ないじゃん……」
変なことを言っていることは、よく分かっている。自分勝手なのも分かってる。
「那月がいない人生なんて……考えられないよ、私」
「苺実……」
私は那月のことが大切だって思ってる。 でもそれは、私の独りよがりかもしれない。
それでも私は……那月と過ごした時間を大切にしたい。 これからだって、大切にしたいと思うの。
「ごめんね、自分勝手なこと言って。でも……那月とこれからも、私はずっと一緒にいたい」
那月に言われて気付いた。私って……那月のことなんとも思ってないフリしてたけど、本当はちゃんと思ってただってことを。
私って……わがままな女だな。
「……苺実は、俺のこと正直、どう思ってんの?」
「私は……那月と友達じゃ、イヤなのかもしれない」
だって誰よりもずっとそばにいてくれたのは、那月だった。 那月がそばにいると、私は安心したし、嬉しかった。
友達という関係が創り出したものだから、そう思い込んでいたのかもしれないけど……本当は違うのかもしれない。
「なんだよ。かもしれないって」
「ううん。……やだ。友達じゃイヤだ」
思わず那月の手を握ってしまう私に、「そんなことされると、俺勘違いしちゃうけど?」と見つめてくる那月に、私は「勘違い……じゃないよ」と答える。
「那月……二人きりになりたい」
「ん……?」
「二人きりになれる所、行きたい」
「おま、それって……」
私は那月に「行こう、那月」とカバンからお財布を取り出し五千円をテーブルに置いた。
「おい、苺実。待てって!」
先にお店を出た私の後を追いかける那月に、腕を掴まれる。
「苺実、本気か?」
「……本気だよ、私」
那月のことが好きなんだよ、私は。 だから多分、今までの恋愛がうまく行かなかったのは、那月のせいだ。
全部全部、那月のせい。
「なら俺も、本気で苺実のこと奪うけど……いいよな?」
「……うん、奪ってよ。 那月になら、奪われたい」
よく見たら、那月ってこんなにイケメンだったっけ? さっきまで全然、思ってなかったけど……。
那月になら、私の全てを奪われたいって本気で思った。
「その言葉、後悔するなよ」
「……え?」
那月に腕を引っ張られ、ぐっと那月との距離が縮まっていく。
「那月……?」
「じゃまずは、苺実の唇を奪うから、覚悟しとけよ」
「え……?」
その言葉の通り、那月の唇に、自分の唇を奪われてしまった。
那月とのキスは、結構ドキドキしてしまった。
「苺実、もしかしてドキドキした?」
「……うん、ドキドキした」
那月と初めてキスをした。でも、全然イヤじゃなかった。
むしろ、ドキドキしたし、なんだか嬉しかった。
「その顔、反則な」
「へ……?」
「その顔、俺以外の男には見せるなよ。 かわいすぎるから」
那月にかわいいと言われたことなんてなかったけど、それも嬉しかった。
「……ほら、行くぞ」
先を歩く那月の背中に、「うん」と返事をして歩き出す。
「ねえ、那月」
「どうした?」
私は那月に向かって「那月、髪の毛にゴミが付いてるよ?」と伝える。
「マジ?」
「取ってあげるよ」
「ありがとう」
那月の頭がしゃがんだ瞬間、私は那月の頭をぐっと下げて自分からもう一度、那月にキスをした。
「はっ……? えっ?」
困惑する那月に向かって、私は「さっきのキスの仕返し」と、再び歩き出す。
「おい、ちょっと待て、苺実!」
「早くしないと置いてくよー」
ねえ、那月? 私は那月と、これからは「恋人」としてそばにいていいんだよね?
だって那月、私の全てを奪うんでしょ? 私の全てを奪うその日まで、そばにいてよね。
じゃないと私、那月のそばにいられないんでしょ?
「那月、家まで送ってってよ」
「別にいいけど」
「じゃあ決まりね。……はい」
私は那月に左手を差し出すと、那月は「はっ?」と私を見る。
「手、繋いでくれる?」
那月は私の左手をそっと取ると、「繋ぐよ、いくらでも」と恋人繋ぎで手を繋いだ。
「これでもう、友達やめるとか言わないよね?」
「言わないよ」
「良かった」
私は那月と生きていくこれからの人生が、一番楽しくなる気がする。
【完結】