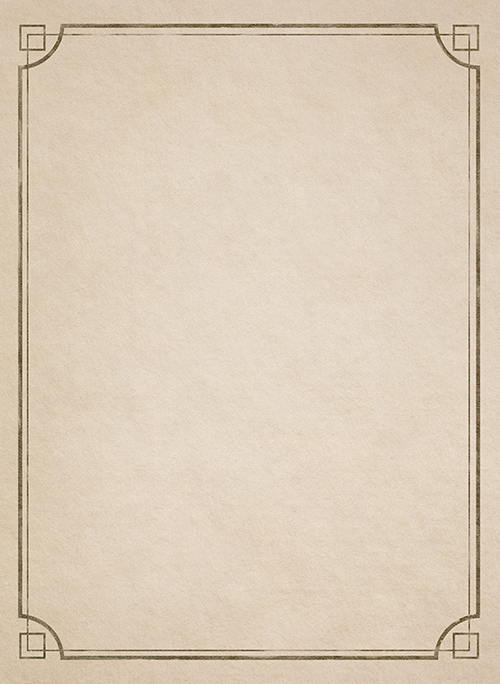ーーーーーーーーーーーーーーーーー
「――パパ……熱いよッ……!」
「助けて……パパ」
「あなた……ッ!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
――バッ!
「ハァ……ハァ……ハァ……ハァ……!」
くそッ……“また”か……。何時まで経っても最悪な目覚めだぜ全く……。
あの日からもう5年……。未だにあの時の光景が頭から離れねぇ。毎夜訪れる悪夢のせいで悲劇がつい昨日の事の様に感じる。何で俺だけ生きてるんだ……。
マリア……ミラーナ……ジェイル……それにパク……。きっと皆怒ってるし恨んでるよな……。そんな言葉じゃ言い表せないか。無理もねぇ……俺だけのうのうと生きてるんだからよ……。
目覚めから果てしない虚無感に襲われた俺は、僅かに残った昨日の酒を一気に飲み干した。
「……やっぱり美味くねぇ酒だな」
既に昨日味わっていたが、改めて飲んでもやっぱり美味くない。まぁ味の好みは人それぞれだけどな。俺は辺りに散らばる金貨を数枚適当に拾いポケットに突っ込んだ。動くのが面倒くさいから買い物はまとめて済ませる。何日分かの食料と無くてはならない大量の酒を買ってそれを消費。そして無くなったらまたまとめて買う。それの繰り返しだ。
そして今日はそのまとめ買いの日。正確には日付を跨いでいたが、こうして連続で外に出るなんて珍しい。いや、この5年の間にも片手で数えられるくらいだろう。なんの自慢にもならねぇがな。
微塵の変化もない今日という当たり前の1日。
毎回面倒だと思いながらも、俺は家の扉を開けて外に出た。
「――おい」
「うわッ⁉」
久々に大きな声を出した。出したというより思わず出た。だって、まさか扉開けていきなり人が立ってるなんて思わねぇだろ。しかもかなり“圧”を感じたし。そりゃ驚くって。目の前にいる奴がいくら知った顔でもな。
「何してんだよ朝っぱらから……エド」
連続で人と会って話すのも久しぶりだな。
「“返せ”よ」
「 は?」
「いいから早く返せ。お前だろ、“犯人”」
いきなり現れた挙句に何言ってるんだコイツ。
「何の話だよ」
「運搬車の荷台の防犯カメラに映っていたんだよ。“ボトル”を持っていくお前の姿がな、ジン」
ボトル……。ああ、昨日の酒の事か。思ったよりバレるの早かったな。っていうか防犯カメラなんて付けてたのかあのトラック。
「ボトルってあの“酒”の事か? 何だよ、酒の1本や2本別にいいだろ」
「良くねぇよ!」
エドにしては珍しく焦った表情をしている。しかも食い気味で言い返してきたし。
「やっぱ高い酒だったのか。それなら金はちゃんと払うからッ……「いいから返せ! しかも言っておくがアレは“酒じゃない”!」
え……? 酒じゃないの……?
俺が少し困惑した顔をするとエドは何かを察したのか、突如顔面蒼白の表情で俺の胸ぐらを勢いよく掴んできた。
「おいッ! まさかお前……アレ飲んだ訳じゃないだろうなッ⁉」
何かヤバそう。俺の直感はこれに尽きた。
エドとは出会ってから30年以上も経つが、正直こんな焦った顔を見た事がない。初めてだ。それ故に、察しの悪い俺でも何か尋常ではない空気を感じ取っている。
俺はこの時思った。
多分……アレ飲んじゃいけないやつだったんだ。
うん。絶対そう。じゃないとこの状況に説明が付かん。
「あー……アレな……俺には酒に見えたけどな……ハハ。そもそも酒じゃねぇとは……へー。
…………だったら何ですか⁇」
ぎこちなくも何とか絞り出した回答に、遂にエドがキレた。
「馬鹿野郎ォォォォォォォォォォォォッ‼‼」
♢♦♢
~リューテンブルグ王国・城~
あれから俺とエドは、王国のど真ん中に聳え立つリューテンブルグ王国の城に来ていた。当たり前だが此処には国王や王族が住んでいる城でもある。だから当然の如く国王もいるし、何なら今俺は城の中で1番広い玉座の間で静かに片膝を付いている。
何故かって? 当然だろ。目の前に国王が座ってるんだからよ。常識だ。
「――久しぶりであるな。ジンフリー・ドミナトルや」
「ご無沙汰しております。フリーデン様」
リューテンブルグ王国の国王であるシャロム・フリーデン。俺が物心ついた時からずっと国を平和に保っている。歳ももう90近い筈なのに元気だな。良い事なんだけど。
「先ず、元気そうで何よりじゃ。其方がリューテンブルグ王国誕生以来、最年少で騎士団の大団長になった事も私にとってはつい最近の事の様に感じる。人々が平和に暮らせてこれたのも其方のお陰じゃジンフリーよ。改めて礼を言うぞ」
「国王様にお礼を言われる程の事なんてしていないですよ」
「そう謙遜するでない。……あの時、其方が命を懸けて守ってくれたからこそ、ここまで復興の道を歩む事が出来ておるのじゃ」
フリーデン様の言葉に、周りにいた家来や護衛の騎士団員達も皆頷いていた。
一応理解はしてるつもり。5年前、死に物狂いで満月龍を止めたのは確かに事実。でも、それはあくまで結果論。あの時、俺にもっと力があれば……こんな事にはなっていなかった。大勢の人を救ったと称えられるがそうじゃねぇ。救えた筈の何千と言う命を、俺は救えなかった。1番守らなきゃいけない家族でさえも……。
「終焉を生むと言われる幻の満月龍……。多くの命が失ってしまったのもまた事実。しかしそれで其方を責める者など1人もおらぬ。大勢の人々が感謝しているのじゃ。最早ドラゴンは自然災害の1つ。人間の力など自然に比べれば無に等しいのじゃよ。悲しいがな。其方の家族も本当に残念じゃった……」
「自分に実力があれば全てを救えた。それだけの事です」
自分でも面倒くせぇ奴だなと思う。
周りからの感謝はこんな俺にもちゃんと伝わってる。気を遣ってるわけでもお世辞を言ってるわけでもない。皆心の底から“ありがとう”と言ってくる。助かったと。感謝してると。どれだけ言われたか分からない。そう思ってくれるのは本当に嬉しいが、自分の気持ちの整理が全く付けられないんだ……。
「私から話し出してしまったとは言え、何時までも自分を責めるでないぞ。そして時にジンフリーよ――」
静かに一呼吸の間が空いた。
皆の視線が自然とフリーデン様に集まる。
「わざわざここに足を運んでもらったのは他でもない。既にエドワード大団長から聞いていると思うが、余りに不測の事態に私も少々戸惑っておる……」
仰る通りです。俺もまさかこんなバツが悪い事態になるとは思っていませんでしたよ。それにしても……。
「その事に付きましては……まぁ何というか……私が言うのも可笑しな話ですが、結論、もう飲んでしまってどうにもこうにも返しようがありません。そしてフリーデン様……。
察しの悪い私でも、何かやらかしてしまったという事は分かっております。一体……私が酒だと思って飲んだアレは何だったのでしょうか……?」
これが1番の疑問。国王まで動くなんて只事じゃねぇ。
俺の率直な疑問に、何故かフリーデン様も困ったような表情でこう言った。
「ジンフリーよ。私も何処から説明すればいいのか悩んでおるが……結果から言うとな、其方が口にしたアレな……
“満月龍の血”なんじゃ――」
ん……??
「――パパ……熱いよッ……!」
「助けて……パパ」
「あなた……ッ!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
――バッ!
「ハァ……ハァ……ハァ……ハァ……!」
くそッ……“また”か……。何時まで経っても最悪な目覚めだぜ全く……。
あの日からもう5年……。未だにあの時の光景が頭から離れねぇ。毎夜訪れる悪夢のせいで悲劇がつい昨日の事の様に感じる。何で俺だけ生きてるんだ……。
マリア……ミラーナ……ジェイル……それにパク……。きっと皆怒ってるし恨んでるよな……。そんな言葉じゃ言い表せないか。無理もねぇ……俺だけのうのうと生きてるんだからよ……。
目覚めから果てしない虚無感に襲われた俺は、僅かに残った昨日の酒を一気に飲み干した。
「……やっぱり美味くねぇ酒だな」
既に昨日味わっていたが、改めて飲んでもやっぱり美味くない。まぁ味の好みは人それぞれだけどな。俺は辺りに散らばる金貨を数枚適当に拾いポケットに突っ込んだ。動くのが面倒くさいから買い物はまとめて済ませる。何日分かの食料と無くてはならない大量の酒を買ってそれを消費。そして無くなったらまたまとめて買う。それの繰り返しだ。
そして今日はそのまとめ買いの日。正確には日付を跨いでいたが、こうして連続で外に出るなんて珍しい。いや、この5年の間にも片手で数えられるくらいだろう。なんの自慢にもならねぇがな。
微塵の変化もない今日という当たり前の1日。
毎回面倒だと思いながらも、俺は家の扉を開けて外に出た。
「――おい」
「うわッ⁉」
久々に大きな声を出した。出したというより思わず出た。だって、まさか扉開けていきなり人が立ってるなんて思わねぇだろ。しかもかなり“圧”を感じたし。そりゃ驚くって。目の前にいる奴がいくら知った顔でもな。
「何してんだよ朝っぱらから……エド」
連続で人と会って話すのも久しぶりだな。
「“返せ”よ」
「 は?」
「いいから早く返せ。お前だろ、“犯人”」
いきなり現れた挙句に何言ってるんだコイツ。
「何の話だよ」
「運搬車の荷台の防犯カメラに映っていたんだよ。“ボトル”を持っていくお前の姿がな、ジン」
ボトル……。ああ、昨日の酒の事か。思ったよりバレるの早かったな。っていうか防犯カメラなんて付けてたのかあのトラック。
「ボトルってあの“酒”の事か? 何だよ、酒の1本や2本別にいいだろ」
「良くねぇよ!」
エドにしては珍しく焦った表情をしている。しかも食い気味で言い返してきたし。
「やっぱ高い酒だったのか。それなら金はちゃんと払うからッ……「いいから返せ! しかも言っておくがアレは“酒じゃない”!」
え……? 酒じゃないの……?
俺が少し困惑した顔をするとエドは何かを察したのか、突如顔面蒼白の表情で俺の胸ぐらを勢いよく掴んできた。
「おいッ! まさかお前……アレ飲んだ訳じゃないだろうなッ⁉」
何かヤバそう。俺の直感はこれに尽きた。
エドとは出会ってから30年以上も経つが、正直こんな焦った顔を見た事がない。初めてだ。それ故に、察しの悪い俺でも何か尋常ではない空気を感じ取っている。
俺はこの時思った。
多分……アレ飲んじゃいけないやつだったんだ。
うん。絶対そう。じゃないとこの状況に説明が付かん。
「あー……アレな……俺には酒に見えたけどな……ハハ。そもそも酒じゃねぇとは……へー。
…………だったら何ですか⁇」
ぎこちなくも何とか絞り出した回答に、遂にエドがキレた。
「馬鹿野郎ォォォォォォォォォォォォッ‼‼」
♢♦♢
~リューテンブルグ王国・城~
あれから俺とエドは、王国のど真ん中に聳え立つリューテンブルグ王国の城に来ていた。当たり前だが此処には国王や王族が住んでいる城でもある。だから当然の如く国王もいるし、何なら今俺は城の中で1番広い玉座の間で静かに片膝を付いている。
何故かって? 当然だろ。目の前に国王が座ってるんだからよ。常識だ。
「――久しぶりであるな。ジンフリー・ドミナトルや」
「ご無沙汰しております。フリーデン様」
リューテンブルグ王国の国王であるシャロム・フリーデン。俺が物心ついた時からずっと国を平和に保っている。歳ももう90近い筈なのに元気だな。良い事なんだけど。
「先ず、元気そうで何よりじゃ。其方がリューテンブルグ王国誕生以来、最年少で騎士団の大団長になった事も私にとってはつい最近の事の様に感じる。人々が平和に暮らせてこれたのも其方のお陰じゃジンフリーよ。改めて礼を言うぞ」
「国王様にお礼を言われる程の事なんてしていないですよ」
「そう謙遜するでない。……あの時、其方が命を懸けて守ってくれたからこそ、ここまで復興の道を歩む事が出来ておるのじゃ」
フリーデン様の言葉に、周りにいた家来や護衛の騎士団員達も皆頷いていた。
一応理解はしてるつもり。5年前、死に物狂いで満月龍を止めたのは確かに事実。でも、それはあくまで結果論。あの時、俺にもっと力があれば……こんな事にはなっていなかった。大勢の人を救ったと称えられるがそうじゃねぇ。救えた筈の何千と言う命を、俺は救えなかった。1番守らなきゃいけない家族でさえも……。
「終焉を生むと言われる幻の満月龍……。多くの命が失ってしまったのもまた事実。しかしそれで其方を責める者など1人もおらぬ。大勢の人々が感謝しているのじゃ。最早ドラゴンは自然災害の1つ。人間の力など自然に比べれば無に等しいのじゃよ。悲しいがな。其方の家族も本当に残念じゃった……」
「自分に実力があれば全てを救えた。それだけの事です」
自分でも面倒くせぇ奴だなと思う。
周りからの感謝はこんな俺にもちゃんと伝わってる。気を遣ってるわけでもお世辞を言ってるわけでもない。皆心の底から“ありがとう”と言ってくる。助かったと。感謝してると。どれだけ言われたか分からない。そう思ってくれるのは本当に嬉しいが、自分の気持ちの整理が全く付けられないんだ……。
「私から話し出してしまったとは言え、何時までも自分を責めるでないぞ。そして時にジンフリーよ――」
静かに一呼吸の間が空いた。
皆の視線が自然とフリーデン様に集まる。
「わざわざここに足を運んでもらったのは他でもない。既にエドワード大団長から聞いていると思うが、余りに不測の事態に私も少々戸惑っておる……」
仰る通りです。俺もまさかこんなバツが悪い事態になるとは思っていませんでしたよ。それにしても……。
「その事に付きましては……まぁ何というか……私が言うのも可笑しな話ですが、結論、もう飲んでしまってどうにもこうにも返しようがありません。そしてフリーデン様……。
察しの悪い私でも、何かやらかしてしまったという事は分かっております。一体……私が酒だと思って飲んだアレは何だったのでしょうか……?」
これが1番の疑問。国王まで動くなんて只事じゃねぇ。
俺の率直な疑問に、何故かフリーデン様も困ったような表情でこう言った。
「ジンフリーよ。私も何処から説明すればいいのか悩んでおるが……結果から言うとな、其方が口にしたアレな……
“満月龍の血”なんじゃ――」
ん……??