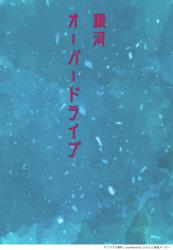私たちは空を見上げた。そこには私たちには似合わないくらい綺麗な夕空が広がっていた。私は空を見つめたままで言葉を発した。一瞬だけ白い息が見えた。
「夜まではまだ少しだけ時間があるね」
「そうだね」
彼女もまた空を見上げていた。だから、この時彼女がどんな顔をしていたのか私にはわからない。それでも楽しそうな声で彼女が嬉々とした気持ちになっていたのはわかっていた。
「見られるといいな」
「そうだね。どんなふうに見えるか私は楽しみ」
これは私の心の底からの言葉だった。
「私も初めて見るからすごい楽しみ」
「いよいよだね」
「うん、これで旅が終わる」
「そうだね……」
この時の私はやはり彼女のサイゴの旅という言葉がどうしても気になっていた。それが彼女にとってどれくらいの価値があるのか私には計りかねたからだ。
空はどんどん暗くなっていった。そろそろ空に星が見えるか見えないかの頃になった。私たちは何も言わずに空を見上げ続けた。このままの時間が永遠に続けば良いのに。そうすれば旅も終わらない。だから、お願い神様。終わらないで。と私は思っていた。
「ねえ、見れるまでまだ時間があるから、しりとりでもしようよ」
咲が唐突に提案してきた。
「急だね」
私は笑った。お互いの白い息が見えていた。
「いいよ。じゃあ咲の方から」
「ハサミ」
「ミスド」
「ドクター」
「た、太鼓」
「小鉢」
「ち、ち……、チアリーダー」
「ダイヤモンド」
「ドラマ」
「マリオネット」
「トイ、トイプ……」
その瞬間だった。どこか遠くの方からパトカーのサイレンの音が聴こえてきた。時間切れだった。
私たちは三十秒くらい何も言えなくなった。それから、咲の方がポケットの方からナイフを取り出した。
「時間切れみたい……」
「そうだね……」
「まだ夕方だね」
「夜まであと少しだったのに……」
この時、私は神様や世界の仕組みなどという存在に対して彼らはなんて残酷なんだと感じた。なんでこんなところで警察に見つかってしまうのだろうか。この世には残酷な運命があるということを痛感した。私たちにはこんな運命しか残っていないのか。悲しい結末しか残っていないのか。なんて悲しい世界なんだ。私は私たちの運命を悔やんだ。
私は悔しかった。ここまで来て、まさか孔雀座を見れそうにないことが。彼女もまた悔しそうだった。
「私はこうなった代償を払わなくちゃいけないのかもしれないね」
咲は苦しそうに空を見上げた。夜までにはほんの少し時間がありそうだった。それが悔しかった。
「ねえ、私は友美をさ……」
「言わなくていいよ。わかってる」
「ありがとう。でも、あなたを巻き込んでしまった……」
彼女には後悔の気持ちがあったのだと思う。結果的に友美を殺してしまったこと。私を巻き込んでしまったこと。それが彼女の罪である。とても十六歳の少女には背負いきれない罪だったと思う。一方で私にも罪がある。それは、友美を止めることができなかったこと。彼女をここまで連れてきてしまったこと。
「ねえ、由香里。あなたは何にもしてない。だからあなたが罪を背負う必要はないよ。私が全部の代償を払わなくちゃいけないんだ」
「でも、ここまで来たら私にも罪はある。だから、私も何か代償を払わなくちゃ」
咲は苦しそうだった。おそらく、頭の中でずっと悩んでいたのだ。私たちは何か代償を払わなくちゃいけない。それについて彼女はずっと悩んでいた。
咲は何かを確かめるような目で私のことを見つめた。
「ねえ、改めて言うけど、私たちは友達だよ」
「当たり前だよ。私たちは友達」
「ありがとう」
彼女は目を閉じて深呼吸をした。私も目を閉じた。決意しなくてはいけなかった。ここで全てを終わらせないと。私たちは知っていた。ここで自分達は終わりだと。だからこそ、最後の戦いが迫っていた。私たちの運命を賭した最後の戦いが。
咲は目を開けた。それから折り畳み式ナイフの刃先を出した。
「じゃあ、私たちでこの事件を起こした代償を払おう」
ナイフの刃先が私の方に向けられた。彼女なりに悩みに悩んだ末の決断だったと思う。私はそれに同意するしかなかった。私にも罪はある。だから、私はナイフを向けられなくちゃいけなかった。なぜなら、私は向けられるべき存在だから。
「ここから先は崖よ。端の方まで行きましょう」
咲はナイフをこちらに向けて歩き始めた。
「わかった」
私は崖の方を向いて歩き出した。
耳に残るサイレンの音が遠くから聞こえてくる。私たちを追いかけている警察官たちがすぐそこまで来ているという合図だった。星空が見え始めた一月の夕暮れ。広大な海が目の前に広がり、少し荒れた潮風が流れてきて塩っぱい味が口の中に入ってくる。私は両手を上げて背中を気にしていた。背後には血に塗れたナイフが突きつけられている。ナイフを突きつけている咲の表情は複雑だった。
私を連れ去ったことで逃げきれなかったことへの後悔と、もうすぐ楽になれるという安堵の思いが同時に込み上げているように私は感じる。彼女の顔は数時間前よりさらにやつれていた。一方で私も背中にナイフを突きつけられている恐怖と彼女の死の気配を察して複雑な顔をしていたのだと思う。私と咲は一歩ずつ前へと進む。暗がりから微かに見える彼女のナイフを握る手は汗ばみ震えていた。
「由香里、もうすぐお別れだね」
「お別れって、どういうこと?」
「飛び降りようと思うの。この先から」
「そんな……」
悲しげだけど喜んでいるような調子で彼女はこう言った。彼女の言葉には普段から多くの含みがあった。この時もおそらくいくつかの意味があったと思うのだが、私はすぐに彼女の本意には気づけなかった。なぜならば、私たちは断崖絶壁の先の方へと歩んでいるからだ。私はこのまま彼女と飛び降りることになるのだろうか? 少なくとも私はそう感じた。
死への恐怖が私の心に芽生えたが、同時に、ああ、私はこのまま彼女に突き落とされても仕方のない人間なのだとも考えた。だって、私は彼女の苦しみにずっと気づけなかったから。私たちは一歩、また一歩と崖の先へと歩んでいく。
「孔雀座は結局見れなかったな……」
彼女は残念そうにしながらも呑気な声で一言呟いた。咲がどうしてここまできたのかを私は知っていたが、この言葉に私は何も言えずにいる。なんて言えばいいのかが咄嗟に判断できなかった。一歩、一歩と進むと次第に崖の先の全てを飲み込むような荒波が下の方から私たちを覗き込んできた。
私はこのまま助かるのだろうか。それとも彼女と共に死ぬのだろうか。日が沈み、近くにある灯台の灯りだけが私たちを照らしている。日が沈んだことで彼女の顔が見えなくなっていく。その暗闇の中で彼女はすすり泣いていた。彼女の涙をすする音が聞こえてくるのだ。
サイレンの音がさっきよりも近づいてきた。数分後にはこの辺りは警察官たちに囲まれているのだろう。咲は私と一緒に崖の下へと飛び降りようとするかもしれない。まもなく全てが終わろうとしている。太陽が沈んでいった海の遠くの水平線を眺めながら私は彼女との死を覚悟した。
何台ものパトカーが遂に私たちの後ろまで到達し、取り囲んだ。私と彼女の周りは一瞬のうちに明るくなって、後ろに目を向けると彼女の覚悟決めた顔が見てとれた。パトカーの群れから大勢の警官が現れた。警官の一人が叫ぶ。
「警察です! こっちに来て話を聞いてください!」
咲はそれを聞くと、私の首元を掴んでから体を警官たちの方に向けた。それから私の体を自分の方へ近づけてナイフを首元に突きつけて、警官たちに向かって叫んだ。
「動かないで! 動いたらこの子を殺す!」
私たちの最後の戦いが始まった。
「夜まではまだ少しだけ時間があるね」
「そうだね」
彼女もまた空を見上げていた。だから、この時彼女がどんな顔をしていたのか私にはわからない。それでも楽しそうな声で彼女が嬉々とした気持ちになっていたのはわかっていた。
「見られるといいな」
「そうだね。どんなふうに見えるか私は楽しみ」
これは私の心の底からの言葉だった。
「私も初めて見るからすごい楽しみ」
「いよいよだね」
「うん、これで旅が終わる」
「そうだね……」
この時の私はやはり彼女のサイゴの旅という言葉がどうしても気になっていた。それが彼女にとってどれくらいの価値があるのか私には計りかねたからだ。
空はどんどん暗くなっていった。そろそろ空に星が見えるか見えないかの頃になった。私たちは何も言わずに空を見上げ続けた。このままの時間が永遠に続けば良いのに。そうすれば旅も終わらない。だから、お願い神様。終わらないで。と私は思っていた。
「ねえ、見れるまでまだ時間があるから、しりとりでもしようよ」
咲が唐突に提案してきた。
「急だね」
私は笑った。お互いの白い息が見えていた。
「いいよ。じゃあ咲の方から」
「ハサミ」
「ミスド」
「ドクター」
「た、太鼓」
「小鉢」
「ち、ち……、チアリーダー」
「ダイヤモンド」
「ドラマ」
「マリオネット」
「トイ、トイプ……」
その瞬間だった。どこか遠くの方からパトカーのサイレンの音が聴こえてきた。時間切れだった。
私たちは三十秒くらい何も言えなくなった。それから、咲の方がポケットの方からナイフを取り出した。
「時間切れみたい……」
「そうだね……」
「まだ夕方だね」
「夜まであと少しだったのに……」
この時、私は神様や世界の仕組みなどという存在に対して彼らはなんて残酷なんだと感じた。なんでこんなところで警察に見つかってしまうのだろうか。この世には残酷な運命があるということを痛感した。私たちにはこんな運命しか残っていないのか。悲しい結末しか残っていないのか。なんて悲しい世界なんだ。私は私たちの運命を悔やんだ。
私は悔しかった。ここまで来て、まさか孔雀座を見れそうにないことが。彼女もまた悔しそうだった。
「私はこうなった代償を払わなくちゃいけないのかもしれないね」
咲は苦しそうに空を見上げた。夜までにはほんの少し時間がありそうだった。それが悔しかった。
「ねえ、私は友美をさ……」
「言わなくていいよ。わかってる」
「ありがとう。でも、あなたを巻き込んでしまった……」
彼女には後悔の気持ちがあったのだと思う。結果的に友美を殺してしまったこと。私を巻き込んでしまったこと。それが彼女の罪である。とても十六歳の少女には背負いきれない罪だったと思う。一方で私にも罪がある。それは、友美を止めることができなかったこと。彼女をここまで連れてきてしまったこと。
「ねえ、由香里。あなたは何にもしてない。だからあなたが罪を背負う必要はないよ。私が全部の代償を払わなくちゃいけないんだ」
「でも、ここまで来たら私にも罪はある。だから、私も何か代償を払わなくちゃ」
咲は苦しそうだった。おそらく、頭の中でずっと悩んでいたのだ。私たちは何か代償を払わなくちゃいけない。それについて彼女はずっと悩んでいた。
咲は何かを確かめるような目で私のことを見つめた。
「ねえ、改めて言うけど、私たちは友達だよ」
「当たり前だよ。私たちは友達」
「ありがとう」
彼女は目を閉じて深呼吸をした。私も目を閉じた。決意しなくてはいけなかった。ここで全てを終わらせないと。私たちは知っていた。ここで自分達は終わりだと。だからこそ、最後の戦いが迫っていた。私たちの運命を賭した最後の戦いが。
咲は目を開けた。それから折り畳み式ナイフの刃先を出した。
「じゃあ、私たちでこの事件を起こした代償を払おう」
ナイフの刃先が私の方に向けられた。彼女なりに悩みに悩んだ末の決断だったと思う。私はそれに同意するしかなかった。私にも罪はある。だから、私はナイフを向けられなくちゃいけなかった。なぜなら、私は向けられるべき存在だから。
「ここから先は崖よ。端の方まで行きましょう」
咲はナイフをこちらに向けて歩き始めた。
「わかった」
私は崖の方を向いて歩き出した。
耳に残るサイレンの音が遠くから聞こえてくる。私たちを追いかけている警察官たちがすぐそこまで来ているという合図だった。星空が見え始めた一月の夕暮れ。広大な海が目の前に広がり、少し荒れた潮風が流れてきて塩っぱい味が口の中に入ってくる。私は両手を上げて背中を気にしていた。背後には血に塗れたナイフが突きつけられている。ナイフを突きつけている咲の表情は複雑だった。
私を連れ去ったことで逃げきれなかったことへの後悔と、もうすぐ楽になれるという安堵の思いが同時に込み上げているように私は感じる。彼女の顔は数時間前よりさらにやつれていた。一方で私も背中にナイフを突きつけられている恐怖と彼女の死の気配を察して複雑な顔をしていたのだと思う。私と咲は一歩ずつ前へと進む。暗がりから微かに見える彼女のナイフを握る手は汗ばみ震えていた。
「由香里、もうすぐお別れだね」
「お別れって、どういうこと?」
「飛び降りようと思うの。この先から」
「そんな……」
悲しげだけど喜んでいるような調子で彼女はこう言った。彼女の言葉には普段から多くの含みがあった。この時もおそらくいくつかの意味があったと思うのだが、私はすぐに彼女の本意には気づけなかった。なぜならば、私たちは断崖絶壁の先の方へと歩んでいるからだ。私はこのまま彼女と飛び降りることになるのだろうか? 少なくとも私はそう感じた。
死への恐怖が私の心に芽生えたが、同時に、ああ、私はこのまま彼女に突き落とされても仕方のない人間なのだとも考えた。だって、私は彼女の苦しみにずっと気づけなかったから。私たちは一歩、また一歩と崖の先へと歩んでいく。
「孔雀座は結局見れなかったな……」
彼女は残念そうにしながらも呑気な声で一言呟いた。咲がどうしてここまできたのかを私は知っていたが、この言葉に私は何も言えずにいる。なんて言えばいいのかが咄嗟に判断できなかった。一歩、一歩と進むと次第に崖の先の全てを飲み込むような荒波が下の方から私たちを覗き込んできた。
私はこのまま助かるのだろうか。それとも彼女と共に死ぬのだろうか。日が沈み、近くにある灯台の灯りだけが私たちを照らしている。日が沈んだことで彼女の顔が見えなくなっていく。その暗闇の中で彼女はすすり泣いていた。彼女の涙をすする音が聞こえてくるのだ。
サイレンの音がさっきよりも近づいてきた。数分後にはこの辺りは警察官たちに囲まれているのだろう。咲は私と一緒に崖の下へと飛び降りようとするかもしれない。まもなく全てが終わろうとしている。太陽が沈んでいった海の遠くの水平線を眺めながら私は彼女との死を覚悟した。
何台ものパトカーが遂に私たちの後ろまで到達し、取り囲んだ。私と彼女の周りは一瞬のうちに明るくなって、後ろに目を向けると彼女の覚悟決めた顔が見てとれた。パトカーの群れから大勢の警官が現れた。警官の一人が叫ぶ。
「警察です! こっちに来て話を聞いてください!」
咲はそれを聞くと、私の首元を掴んでから体を警官たちの方に向けた。それから私の体を自分の方へ近づけてナイフを首元に突きつけて、警官たちに向かって叫んだ。
「動かないで! 動いたらこの子を殺す!」
私たちの最後の戦いが始まった。