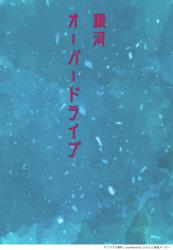バスケットボールの試合、第三クォーターが残り1分に差し掛かり、私は意地を見せた。チームメイトの真希ちゃんからボールを貰って、相手のゴールへと進む。相手チームの防御をかわしてゴールへ近づき高く飛んだ。ボールは見事にゴールへと入り、地面に目掛けて落ちていく。着地した私の髪が少し揺れた。私の周りで歓声と拍手が起こる。それは体育館中に響く。観戦に来ていた何人かの引退した先輩たちが「よっ! 期待のエース!」なんて言って私のことを囃し立てていた。直後、休憩時間となった。第四クォーターを経て、最終的に試合は私たちのチームが勝利した。私たち一年生にとっての初陣であり、最初の勝利であった。
「今日は祝勝だ! えいえい」
昼下がり。学校からの帰り道。同じチームの石崎友美が勝鬨を挙げる。私たちはそれに応えて手を掲げて「おー!」と一斉に言った。友美は私たちのリーダー的な人だった。彼女は普段からさまざまな場面で私たちを取り仕切っていた。友美の横顔を見つめる。私は友美の顔立ちは──私の基準ではあるが──そこそこに整っていて、それと共にこの‘世界’を立ち回るのが上手な人だと思っていた。
「それで、どこで祝うの?」
仲間の真希ちゃんの素朴な疑問に全員がはっとした。私たちは慌てて祝勝会の会場を探した。宴の場所は二十分かけて探した末に安いファミリーレストランで開くことになった。私たちは高校生であるが故に十分なお金を持ち合わせていなかった。だから、普段はなるべく注文をしないようにしていたが、今日ばかりはお金遣いが荒くなった。
「すみません! ナポリタンください!」
「すみません! ティラミスください!」
次々と注文する私たち。お酒は飲んでないのに次第に盛り上がって気づけばメンバーの何人かが大声で笑い転げていた。もちろん周りの客たちにはとんでもない迷惑になっていたと後になって気づいたが、そんなことが察せないほどに私たちの心は幼かった。
宴での会話は次第に普段の学校のことにもなっていった。
「この前さ、二組の秋山を見たの。そしたら、秋山、他校の女子とデートしてた!」
「何それ、まじ!」
「ええ〜」
いつもそうなのだが、私は彼女たちの会話に次第についていけなくなっていた。だけど、彼女らの話は聞いていないと自分の地位が失われる。今もまた、秋山君という一人の男子のランクが彼女たちの中で低下した。
「キモいね」
「うん、キモい」
私は彼女たちの言葉を聞くだけで、ただオレンジジュースを一口、また一口と飲んだ。私たちのいる‘小さな世界’には目に見えない大きなヒエラルキーが存在した。誰が作ったのかはわからない、おそらく自然にできた見えないピラミッド。私を含め全員がそのピラミッドにしがみついている。ある者は些細なことで誰かに蹴落とされ、ある者は容姿だけで上位に登っていく。そんな世界に私たちは身を置いていた。私はそれはこの国、この街では当たり前に起こっていることで、その世界に身をおいて過酷な競争を生き残っていくしかないのだと思っていた。目の前にいる彼女らとは同じシャツを着て共に試合を戦い抜いて引退して、卒業したら離れていくのだと心のどこかで考えていた。後から思えば私たちの世界はとても虚しいものだった。
「そうだ、由香里。同じクラスの倉持咲ってわかる?」
「うん。わかるけど、どうした?」
ソーダを飲みながら友美が私に尋ねてくる。私はオレンジジュースを口に含みながら話を聞いた。
「いや、あいつ気をつけた方がいいかも……」
「というと」
「彼女、なんていうかよく分からなくない?」
「まあ、そうだけど」
友美が話している私のクラスメイト、倉持咲は心に無限の闇のような物を抱えていた人だった。普段から髪は乱れていて、おしゃれに気を使っているようには見えず、何を考えているのかが私達には把握できなかった。そんな倉持咲のことを石崎友美は常にどこか警戒しているような素振りをしていた。
「よくわかんないから、関わらない方がいいと思うよ」
「そうかなあ。私はそんなに考えたことないけど」
正直言って私には、倉持咲のことなどこの時はどうだってよかった。向こうが話しかけてきたらそれは話をするし、話しかけてこなかったらそれから何もしないくらいにはどうだってよかった人だった。だけど、友美の持っている感情は私のとはだいぶ違っていた。まるで、彼女は何かから逃げるように、隠すようにこの話を喋っている。そのことに私は少しの違和感が生じた。
「はっ?」
私の返事に彼女はただ、そう言った。まるで、自分とは相容れない意見を聞いて激情するドラマの悪役のような口調だった。私は咄嗟にまずいと思った。今、彼女のいうことをただ聞かないと、私はピラミッドから蹴落とされてしまう。そうしたら、彼女らバスケ部の仲間たちとは一緒にいれなくなる。私は慌てて取り繕った。
「ごめん。ごめん。じゃあ、関わらないでおくよ」
「よかった! よろしくね」
彼女は自分の意見が通ったことで上機嫌になった。グラスに入っていたソーダの残りを一気に飲み干して、すかさずに新しいソーダを注文した。それから私は残ったオレンジジュースをちびちびと飲んで宴が終わるのを待った。
宴が終わったのは日が暮れて夜になった頃だった。私はファミレスの前で仲間たちと別れて家へと直行する。歩いて帰るにはもう遅い時間だったので、近くにあるバス停でバスを待った。待っている間は暇だったのでスマホを眺めた。ネットを開くと、大好きなアイドルの次のコンサートのこととか、東京にあるおしゃれなスイーツ屋がこの近辺に出店したとかのニュースが流れている。私はそれを意味もなく眺めた。少し待っていたらバスがやって来たので、私は乗車した。バスは街にある小さなビルや商店街が一瞬のうちに通り過ぎてゆく。私たちが暮らしているのは近畿にある小さな街だった。どこにでもある普通の街で、治安はそこそこ、衣食住に不便はしないところだった。私や友美はこの小さな街にある高校の中の大きなヒエラルキーに支配されている。バスの中で改めてそのことを考えると、自分たちの生きる場所はちっぽけなのだなと思った。
家の最寄りのバス停で私は降りた。家は三分とかからない場所にあったが、辺りが暗かったので少し道に迷った。少し迷ってから家のあるアパートの真下に着いて、郵便受けを見る。家は、建てられてからそこそこの年月が経っていると思われる四階建てのアパートの最上階だった。傾斜のきつい階段を、疲れた体には少し負担になる重さのリュックを背負って、試合終わりの疲れた足で上がりきり、鍵を取り出して扉を開けた。
「ただいま」
「おかえり」
お母さんがリビングから出迎えてくれた。お母さんの顔を見ると、化粧っけがあった。おそらくさっきまで外に出ていたのだろう。リビングに入ると中を一杯に詰められた買い物袋がテーブルの上に置かれている。
「今、ご飯作るからちょっと待っててね」
お母さんは忙しなさそうにそう言った。
「わかった」
私はそう返して、自分の部屋へと入った。部屋に入って家着に着替えを済ませた私はお母さんの手伝いをすることにした。
「お母さん、手伝うよ。何すればいい?」
「ありがとう。じゃあ、お米研いでくれる」
「了解〜」
お米を研いでいるとお母さんが野菜を切りながら聞いてきた。
「ねえ、今日の試合どうだった?」
「勝ったよ。 私のシュートが決まったからね」
「それはよかった」
お母さんの野菜を切る音がリズム良く聞こえてくる。私が試合に勝ったと聞いて喜んでいるようだった。それだったら私も嬉しいと思った。私がお米を研ぐ音とお母さんが野菜を切る音が部屋中に響く。その音が私は心地よかった。研ぎ終えたお米を炊飯器に入れて炊き始めた。一方でお母さんも今度は肉を取り出して切り始めた。私はこの日の晩御飯は肉野菜炒めだとわかった。
「お米、炊き始めたよ」
「ありがとう由香里。もういいよ、自分のことでもやっておいて」
「うん」
私は自室に入った。さっきそのままにした今日の荷物を片付けて、それから通学用のバックから勉強用具を取り出した。文房具とノート、問題集を机に広げる。そういていると、スマホに幾つかの通知が来ていることに気がついた。通知の内容はメッセージアプリのグループチャット、私が所属するバスケ部からの会話だった。
『今日はお疲れ様! また月曜日に!』
そうメッセージを残していたのは友美だった。それに続いて他のメンバーが返信をする。
『お疲れ! また月曜に!』
『また来週!』
これは返信しなくてはと思った私は即座にメッセージを打った。
『お疲れ〜 また月曜日に』
メッセージを送信すると瞬く間に既読がついた。既読数はどんどん一つ、二つと増えてゆく。その様は誰か一人のリーダーに着いて行く群集だった。その群集たちに意思はない。ただ、誰かの言葉に付き従っているだけだ。それが私にとって当たり前のことではある。思うところは、無いと言えば嘘になる。嘘にはなるが、それを心の表に出したら全てを失うような気がしていた。そうだったから、何もできずにいた。
「ご飯だよ!」
お母さんの声がしたので、私はリビングに戻った。テーブルには肉野菜炒めとご飯と味噌汁が二人分並べられていた。我が家はお父さんとお母さんと私の三人家族だった。この日、お父さんは休日出勤で夜遅くまで帰れないとのことだった。だから先に二人で食べることにした。
「いただきます」
「いただきます」
お母さんが作る肉野菜炒めは美味しい。その味には昼間にみんなで食べたファミレスの料理たちよりも安心感があった。安心したので、今日あったことを話すことにした。
「今日さ〜」
「うん」
「試合初めて出たけど、勝てたよ。自分で掴んだ勝利だったから嬉しかった」
「それさっきも聞いたよ」
「ごめんごめん……」
私は微笑んだ。それで、本当に言いたかったことである部活の仲間たちのことで感じる小さな違和感について何も言えずに心の中でつっかえたままになった。お母さんはそのことにに気づいたのか、こんなことを言った。
「まあ、もし部活が嫌になることがあったら、いつでも部活は辞めていいからね」
「う、うん」
この時、私にはその言葉をすぐに、真っ直ぐに理解できなかった。あの世界だけが自分の全てで、そこから逸れたら何もかもが終わりだと思っていたから。
「ごちそうさま」
私はご飯を食べ終えて、部屋に戻った。この日は少しだけ心がざわついた一日だった。私は無心になって勉強を始めた。
「今日は祝勝だ! えいえい」
昼下がり。学校からの帰り道。同じチームの石崎友美が勝鬨を挙げる。私たちはそれに応えて手を掲げて「おー!」と一斉に言った。友美は私たちのリーダー的な人だった。彼女は普段からさまざまな場面で私たちを取り仕切っていた。友美の横顔を見つめる。私は友美の顔立ちは──私の基準ではあるが──そこそこに整っていて、それと共にこの‘世界’を立ち回るのが上手な人だと思っていた。
「それで、どこで祝うの?」
仲間の真希ちゃんの素朴な疑問に全員がはっとした。私たちは慌てて祝勝会の会場を探した。宴の場所は二十分かけて探した末に安いファミリーレストランで開くことになった。私たちは高校生であるが故に十分なお金を持ち合わせていなかった。だから、普段はなるべく注文をしないようにしていたが、今日ばかりはお金遣いが荒くなった。
「すみません! ナポリタンください!」
「すみません! ティラミスください!」
次々と注文する私たち。お酒は飲んでないのに次第に盛り上がって気づけばメンバーの何人かが大声で笑い転げていた。もちろん周りの客たちにはとんでもない迷惑になっていたと後になって気づいたが、そんなことが察せないほどに私たちの心は幼かった。
宴での会話は次第に普段の学校のことにもなっていった。
「この前さ、二組の秋山を見たの。そしたら、秋山、他校の女子とデートしてた!」
「何それ、まじ!」
「ええ〜」
いつもそうなのだが、私は彼女たちの会話に次第についていけなくなっていた。だけど、彼女らの話は聞いていないと自分の地位が失われる。今もまた、秋山君という一人の男子のランクが彼女たちの中で低下した。
「キモいね」
「うん、キモい」
私は彼女たちの言葉を聞くだけで、ただオレンジジュースを一口、また一口と飲んだ。私たちのいる‘小さな世界’には目に見えない大きなヒエラルキーが存在した。誰が作ったのかはわからない、おそらく自然にできた見えないピラミッド。私を含め全員がそのピラミッドにしがみついている。ある者は些細なことで誰かに蹴落とされ、ある者は容姿だけで上位に登っていく。そんな世界に私たちは身を置いていた。私はそれはこの国、この街では当たり前に起こっていることで、その世界に身をおいて過酷な競争を生き残っていくしかないのだと思っていた。目の前にいる彼女らとは同じシャツを着て共に試合を戦い抜いて引退して、卒業したら離れていくのだと心のどこかで考えていた。後から思えば私たちの世界はとても虚しいものだった。
「そうだ、由香里。同じクラスの倉持咲ってわかる?」
「うん。わかるけど、どうした?」
ソーダを飲みながら友美が私に尋ねてくる。私はオレンジジュースを口に含みながら話を聞いた。
「いや、あいつ気をつけた方がいいかも……」
「というと」
「彼女、なんていうかよく分からなくない?」
「まあ、そうだけど」
友美が話している私のクラスメイト、倉持咲は心に無限の闇のような物を抱えていた人だった。普段から髪は乱れていて、おしゃれに気を使っているようには見えず、何を考えているのかが私達には把握できなかった。そんな倉持咲のことを石崎友美は常にどこか警戒しているような素振りをしていた。
「よくわかんないから、関わらない方がいいと思うよ」
「そうかなあ。私はそんなに考えたことないけど」
正直言って私には、倉持咲のことなどこの時はどうだってよかった。向こうが話しかけてきたらそれは話をするし、話しかけてこなかったらそれから何もしないくらいにはどうだってよかった人だった。だけど、友美の持っている感情は私のとはだいぶ違っていた。まるで、彼女は何かから逃げるように、隠すようにこの話を喋っている。そのことに私は少しの違和感が生じた。
「はっ?」
私の返事に彼女はただ、そう言った。まるで、自分とは相容れない意見を聞いて激情するドラマの悪役のような口調だった。私は咄嗟にまずいと思った。今、彼女のいうことをただ聞かないと、私はピラミッドから蹴落とされてしまう。そうしたら、彼女らバスケ部の仲間たちとは一緒にいれなくなる。私は慌てて取り繕った。
「ごめん。ごめん。じゃあ、関わらないでおくよ」
「よかった! よろしくね」
彼女は自分の意見が通ったことで上機嫌になった。グラスに入っていたソーダの残りを一気に飲み干して、すかさずに新しいソーダを注文した。それから私は残ったオレンジジュースをちびちびと飲んで宴が終わるのを待った。
宴が終わったのは日が暮れて夜になった頃だった。私はファミレスの前で仲間たちと別れて家へと直行する。歩いて帰るにはもう遅い時間だったので、近くにあるバス停でバスを待った。待っている間は暇だったのでスマホを眺めた。ネットを開くと、大好きなアイドルの次のコンサートのこととか、東京にあるおしゃれなスイーツ屋がこの近辺に出店したとかのニュースが流れている。私はそれを意味もなく眺めた。少し待っていたらバスがやって来たので、私は乗車した。バスは街にある小さなビルや商店街が一瞬のうちに通り過ぎてゆく。私たちが暮らしているのは近畿にある小さな街だった。どこにでもある普通の街で、治安はそこそこ、衣食住に不便はしないところだった。私や友美はこの小さな街にある高校の中の大きなヒエラルキーに支配されている。バスの中で改めてそのことを考えると、自分たちの生きる場所はちっぽけなのだなと思った。
家の最寄りのバス停で私は降りた。家は三分とかからない場所にあったが、辺りが暗かったので少し道に迷った。少し迷ってから家のあるアパートの真下に着いて、郵便受けを見る。家は、建てられてからそこそこの年月が経っていると思われる四階建てのアパートの最上階だった。傾斜のきつい階段を、疲れた体には少し負担になる重さのリュックを背負って、試合終わりの疲れた足で上がりきり、鍵を取り出して扉を開けた。
「ただいま」
「おかえり」
お母さんがリビングから出迎えてくれた。お母さんの顔を見ると、化粧っけがあった。おそらくさっきまで外に出ていたのだろう。リビングに入ると中を一杯に詰められた買い物袋がテーブルの上に置かれている。
「今、ご飯作るからちょっと待っててね」
お母さんは忙しなさそうにそう言った。
「わかった」
私はそう返して、自分の部屋へと入った。部屋に入って家着に着替えを済ませた私はお母さんの手伝いをすることにした。
「お母さん、手伝うよ。何すればいい?」
「ありがとう。じゃあ、お米研いでくれる」
「了解〜」
お米を研いでいるとお母さんが野菜を切りながら聞いてきた。
「ねえ、今日の試合どうだった?」
「勝ったよ。 私のシュートが決まったからね」
「それはよかった」
お母さんの野菜を切る音がリズム良く聞こえてくる。私が試合に勝ったと聞いて喜んでいるようだった。それだったら私も嬉しいと思った。私がお米を研ぐ音とお母さんが野菜を切る音が部屋中に響く。その音が私は心地よかった。研ぎ終えたお米を炊飯器に入れて炊き始めた。一方でお母さんも今度は肉を取り出して切り始めた。私はこの日の晩御飯は肉野菜炒めだとわかった。
「お米、炊き始めたよ」
「ありがとう由香里。もういいよ、自分のことでもやっておいて」
「うん」
私は自室に入った。さっきそのままにした今日の荷物を片付けて、それから通学用のバックから勉強用具を取り出した。文房具とノート、問題集を机に広げる。そういていると、スマホに幾つかの通知が来ていることに気がついた。通知の内容はメッセージアプリのグループチャット、私が所属するバスケ部からの会話だった。
『今日はお疲れ様! また月曜日に!』
そうメッセージを残していたのは友美だった。それに続いて他のメンバーが返信をする。
『お疲れ! また月曜に!』
『また来週!』
これは返信しなくてはと思った私は即座にメッセージを打った。
『お疲れ〜 また月曜日に』
メッセージを送信すると瞬く間に既読がついた。既読数はどんどん一つ、二つと増えてゆく。その様は誰か一人のリーダーに着いて行く群集だった。その群集たちに意思はない。ただ、誰かの言葉に付き従っているだけだ。それが私にとって当たり前のことではある。思うところは、無いと言えば嘘になる。嘘にはなるが、それを心の表に出したら全てを失うような気がしていた。そうだったから、何もできずにいた。
「ご飯だよ!」
お母さんの声がしたので、私はリビングに戻った。テーブルには肉野菜炒めとご飯と味噌汁が二人分並べられていた。我が家はお父さんとお母さんと私の三人家族だった。この日、お父さんは休日出勤で夜遅くまで帰れないとのことだった。だから先に二人で食べることにした。
「いただきます」
「いただきます」
お母さんが作る肉野菜炒めは美味しい。その味には昼間にみんなで食べたファミレスの料理たちよりも安心感があった。安心したので、今日あったことを話すことにした。
「今日さ〜」
「うん」
「試合初めて出たけど、勝てたよ。自分で掴んだ勝利だったから嬉しかった」
「それさっきも聞いたよ」
「ごめんごめん……」
私は微笑んだ。それで、本当に言いたかったことである部活の仲間たちのことで感じる小さな違和感について何も言えずに心の中でつっかえたままになった。お母さんはそのことにに気づいたのか、こんなことを言った。
「まあ、もし部活が嫌になることがあったら、いつでも部活は辞めていいからね」
「う、うん」
この時、私にはその言葉をすぐに、真っ直ぐに理解できなかった。あの世界だけが自分の全てで、そこから逸れたら何もかもが終わりだと思っていたから。
「ごちそうさま」
私はご飯を食べ終えて、部屋に戻った。この日は少しだけ心がざわついた一日だった。私は無心になって勉強を始めた。