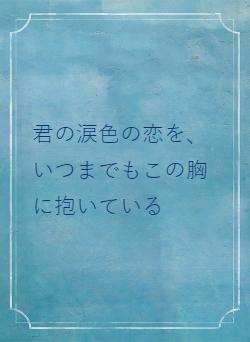1
このノートの中には、後悔が眠っている。
自宅アパートの屋上で長い髪を風になびかせながら、私はふーっと長いため息を吐いた。
周りに高い建物がないので、低い青空に薄く長い雲が伸びているのがよく見える。十月に入り、徐々に日差しが和らいできていた。長かった残暑もようやく終わりそうだ。
さっきまで、外は引っ越し作業で賑やかだった。どうやら、二階の空き部屋に新しい住人がやって来たらしい。築三十年の三階建てアパートは外も中も古びて色あせていて、だけど家賃が相場よりずっと安いから、空き部屋が出てもすぐに埋まる。
穏やかな秋の日曜日。だけどこの季節になると、私はあることを思い出してしまう。花柄の可愛いノートを胸にぎゅっと抱き、私は小さな声で謝罪した。
「ごめんなさい……お母さん」
と、近くから足音が聞こえた。屋上へ続く階段を昇る音。私はハッとして振り返る。こんな何もない屋上へ来る物好きは私くらいで、今まで誰にも会ったことがなかったのに……。
屋上の入り口にある柵をそっと開ける姿を見て、私は思わずノートを取り落としそうになった。
「えっ?」
休日の静かな午後に不似合いの、大きな声を出してしまう。目の前の人物も、目を見開いて私を見つめていた。
「藤原さん?」
不思議そうに名前を呼ばれ、私はようやく我に返ると、こくんと頷いた。
「うん……こんなところで会うなんて、びっくりしたよ。桜沢君」
そこにいたのは、クラスメイトの桜沢玲二君だった。すらっとした長身に、サラサラの黒髪。メタルフレームの眼鏡を掛けていてクールな印象だけど、実際は誰にでも優しくて、おまけに成績優秀の優等生だ。同い年ながら、クラスでは頼れるお兄さんって感じで皆に慕われている。今年初めて同じクラスになったけど、そこまで交流のない私にも親切だ。
「屋上に藤原さんがいるってことは……このアパートに住んでいるの?」
いつも通りの穏やかな声で問われ、私も素直に頷いた。
「そうだよ。桜沢君は、どうしてここにいるの?」
すると、桜沢君は気まずそうに黙り込んだ。いつも堂々としている彼にしては、こういう態度は珍しい。私が首を傾げていると、
「玲二ー! 早く荷解きを手伝いなさい!」
階下から女性の明るい声が桜沢君を呼んだ。彼はぱっと顔を上げると、
「今行くから!」
声のした方へ返事をしてから、目を伏せて私に向き直った。
「……そういうこと。俺も、今日からここに住むんだ。よろしく」
「え……」
戸惑う私をよそに、桜沢君は踵を返すとさっさと屋上を出て行ってしまった。ちょっとの間を置いて、ようやく私は、さっき引っ越してきた人たちが桜沢君一家であることに気付いた。
2DKの自宅に戻り、キッチンで一人夕食を作りながら、私はついさっきあったことを思い出していた。
「桜沢君が、このおんぼろアパートに……? 信じられない……」
信じられないも何も、私は本人の口からその事実を聞いている。でも、彼の様子は、そのことを誰にも知られたくなかったように見えた。それはそうだろう。桜沢君は、学校でも有名なセレブなのだから。
彼のお父さんは、有名な大手商社に勤めている。桜沢君はお父さんの駐在先のイギリスで生まれて、三歳の時に日本に帰ってきた。
もちろん、桜沢君は自分が裕福な生まれであることをひけらかしたりはしない。だけど、ブレザーの中に着ているブランド物のニットや、艶々のローファー、輸入物の文房具なんかを見れば、彼の生活レベルの高さが見て取れた。
確か今の住居は、湾岸地域のタワーマンションだったはず。そんな桜沢君が、老朽化の激しいうちのアパートに引っ越してきただなんて、本当にあり得ない話だけど……。
そんなことを考えていると、外廊下を誰かが歩いてくる音がした。ほどなくしてドアの鍵が開き、スーツ姿の父が姿を現した。
「お父さん、おかえり」
「ただいま。悪かったね、穂乃香。休日なのに家事を任せきりにして」
申し訳なさそうな顔をする父に、私は笑って首を横に振った。父の会社は普段は土日休みなのだが、今日はイベントの手伝いで休日出勤だったのだ。
「お仕事なら仕方ないよ。お米は……あと二十分で炊ける。お腹空いてるんだったら、冷凍ご飯温めるけど」
「いや、炊けてからで大丈夫だよ。そういえば、さっきそこで、新しく引っ越してきた人と挨拶したよ」
「えっ!」
思わず大声を出してしまった私を見て、父は怪訝そうな顔をした。
「どうしたんだい? そんなに驚いて」
「ううん、何でもない。それで、どんな人だったの?」
「篠塚さんといって、華やかな見た目の女の人だったよ。息子さんと二人暮らしだそうだ。ああ、息子さんは、穂乃香と同じ高校二年生だと言っていたな」
「篠塚さん……」
名字が違う。だけど、きっとその女の人は、桜沢君のお母さんなのだろう。二人暮らしということは、お父さんとは……。
私はそこで考えるのをやめた。自分の生活を勘ぐられるつらさは、よく知っている。このことは、お父さんにも、クラスの皆にも秘密にしておこう。そう思った。
「お父さん。それ、新しいお花?」
父が手にしていた透明の手提げ袋には、コスモスを中心としたミニブーケが入っていた。
「そうだよ。実穂乃さんの好きなコスモスの季節がやってきたからね」
そう言って、父はダイニングの一角に置かれた小さな棚に向き直った。そこには、三年前に病気で他界した母の写真と位牌を置いてある。花が好きだった母のために、父はいつも季節のミニブーケを供えていた。
写真立ての中で朗らかに笑う母を眺めながら、私は複雑な気持ちになっていた。
母・藤原実穂乃は小説家だった。ペンネームは美園呉羽。十七歳でデビューした当時は中高生向けの青春小説を、結婚して私が生まれてからは大人の女性向けの恋愛小説を書いていた。
とはいっても、そこまで売れていたわけではない。読書好きの人に美園呉羽について尋ねても、知らない場合がほとんどだろう。母は昔から病弱だったから、活動年数に比べて著書の数も少ない。
それでも、母も父も私も、小説家・美園呉羽を誇りに思っていた。初期の作品に多かった、女子中高生がいじめなどの理不尽な状況にも負けずに戦う話には、私も随分と元気づけられたものだ。手紙をくれる熱心なファンもいて、母はそのファンレターを大事そうにファイルにしまっていた。
そんな母に憧れていた私は、小五の頃から自分でも小説を書くようになった。母はいつも、私の書いた物語を楽しそうに読んでくれた。
「穂乃香、このお話も面白いわ。案内役のシロが、茶目っ気があって魅力的ね」
「そうでしょ? あのね、このワンちゃんはね、ミカちゃんが飼っているマルチーズをモデルにしているんだよ。この子、お腹が空くと『ごはん!』って喋るんだって!」
「まあ、それで、言葉を喋る犬の設定にしたのね。穂乃香は想像力が豊かで、本当に素晴らしいわ」
笑顔で私をたくさんほめてくれる母。そんな優しい母に後押しされて、私も小説家を目指すようになったのに……。
中二の秋、ちょうど今時期だ。私は病床の母にひどいことを言ってしまった。謝る機会を逸したまま母は他界し、私は今でも深い後悔の中にいる。
2
翌朝。桜沢君のことを気に掛けながらも、いつも通りに身支度をした。十月から冬服期間になったものの、長袖のブレザーはまだちょっと暑い。茶色掛かった長い髪は、いつもハーフアップにしている。いくつか持っているバレッタの中から、今日は秋らしいベロアの赤いリボンのものに決めた。
父は既に出勤している。ダイニングの母の写真に「行ってきます」と手を振ってから、私も部屋を出た。
アパートの外階段を降りた私を、誰かが呼び止めた。
「藤原さん」
振り返ると、二階の外廊下から桜沢君が顔を覗かせている。
「あ……おはよう、桜沢君」
昨日のこともあって、どんな素振りをすれば良いのか分からない私に、桜沢君は穏やかに微笑んだ。
「おはよう。駅まで一緒に行ってもいいかな?」
「うん、いいけど……」
おずおずと頷くと、桜沢君も階段を降りてきた。並んで歩き出すと、彼はこう切り出した。
「昨日はごめん。素っ気なくしちゃったなって、後から反省したんだ」
「ううん、気にしてないよ」
「……ありがとう。びっくりしただろ? お金持ちって噂の俺が、突然、普通のアパートに引っ越してきてさ」
「……えっと」
確かに驚いたし、うちのアパートは「普通」レベルにも満たない、格安おんぼろアパートだ。だけどそのことを、率直に言うのも失礼な気がする。口ごもっていると、桜沢君は笑みを崩さずに言った。
「うちさ、両親が離婚したんだ。それで、俺と母さんでここに住むことにした。もう父さんを頼ることは出来ないからな。これからは、生活をかなり切り詰めることになりそうだ」
「そうなんだ……」
桜沢君の事情は分かったけれど、やっぱり、何を言って良いのか分からない。曖昧な相槌を打つ私に、桜沢君は続けた。
「昨日、母さんが、藤原さんって男の人に挨拶をしたって言っていたから、もしかしたら、藤原さんのお父さんかなって思ったんだけど」
「うん、そうだよ。うちのお父さん。そっか、だから篠塚さんって名字なんだね」
「そう、母さんの旧姓。俺も本当は、桜沢じゃなくて篠塚なんだけど……俺さ、このことをクラスの皆には黙っておこうと思うんだ」
「えっ」
意志を込めたようなしっかりとした声に、私は弾かれたように桜沢君の顔を見た。眼鏡の奥の瞳も、声同様に真っすぐ私を見返す。
「事情を知られたら、周りに気を使わせちゃうからな。名字も桜沢のままでいく。だから、これはお願いなんだけど……藤原さんも、両親の離婚のことと、俺たちがこのアパートに住んでいることを秘密にしてもらえないかな?」
「それは、構わないけど……」
私と桜沢君はそんなに親しいわけでもないし、秘密にするのは容易いだろう。だけど、本当に良いのだろうか? ご両親の離婚の理由は知らないけれど、生活がこんなに変化して、桜沢君だって不安なはずだ。そんな時に、周りの人に心の内を話せたのなら、どんなにか楽になるだろうに。
私の考えを見透かしたのか、桜沢君は安心させるような笑顔を向けてきた。
「俺なら大丈夫。離婚して母さんも大分元気になったし、俺は今の生活で良かったって思ってるから」
「それならいいけど……でも、せっかくご近所に住んでいるんだし、何か困ったことがあったら言ってね。実は私も、お母さんが死んじゃった時に、アパートの人たちに随分助けられたの」
「そうだったのか……うん、ありがとう」
桜沢君は素直に頷くと、心配そうな顔で私を見た。
「藤原さんも大丈夫?」
「えっ?」
「昨日、アパートの屋上で会った時、泣きそうな顔をしていたから。何か嫌なことでもあった?」
クラスで見せるような大人びた優しい眼差しに、私の心はじわりと温かくなった。だけど私の後悔は、お父さんにも親しい友達にも話していない一番の秘密だ。話すわけにはいかない。
「大したことじゃないよ。ありがとう、桜沢君」
無理して笑ってみせる。私の嘘に桜沢君が気付いた様子はなかった。
「藤原さんこそ、俺で力になれるのなら、何でも言って。俺の秘密を守ってもらっている恩もあるし。あと、俺のことは玲二でいいよ。友達もそう呼んでる。それに俺はもう、桜沢じゃないからな」
ぼそっと呟かれた最後の言葉に、彼の複雑な感情が透けて見えた。
「分かった……玲二君。私のことも穂乃香でいいよ」
「うん。これからよろしく、穂乃香」
互いに微笑み合う。秘密を共有した私たちは、今までよりちょっとだけ仲良くなれた気がした。
放課後。私は友達からの遊びの誘いを断って、図書室の自習スペースで勉強していた。頭を必死で働かせながら、数学の文章問題を解いていく。
私の希望進路は、地元の国立大学の経済学部だ。父になるべく負担を掛けずに大学に行こうとすれば、どうしても学費の安い国公立大学を選ぶことになる。この大学は家から通える距離にあるし、経済学部は就職に強いと評判だ。何としてでも入りたい。
それなのに、私の成績は伸び悩んでいた。受験までまだ時間はあるとはいえ、このままの偏差値だと合格は難しいだろう。特に、経済学部受験には必須の数学が大の苦手だ。なので、最近ではこうして勉強する時間を増やすようにしている。
一時間ほど集中して問題集に取り組んでいたけれど、さすがに疲れてきた。ひと休みしようと、ブレザーのポケットからいちごミルク味の飴を取り出す。個装を開けて口に入れると、甘さが頭の中まで染み渡るのを感じた。
ふうっと息を吐いてから、私は鞄から一冊のノートを取り出した。勉強用ではない。十四歳の時から使っている、表紙にピンクの小花柄が散りばめられた可愛いノートだ。
このノートには、自分で考えた小説の構想や設定などのメモを書き留めている。どんな状況で、どんな人物が、どんな行動を起こすのか。小説家になるためには、そういった執筆前に考える段階も重要だと母が教えてくれた。
「そうして思いついたことを、このノートに書き留めておくのよ。きっと、穂乃香の小説の可能性を広げてくれるわ」
そう言って、母はこのノートを私にプレゼントしてくれた。中二の夏休み頃の話だ。
「ありがとう、お母さん。でも、小説の構想だなんて、すごく難しそうだね。私はいつも、行き当たりばったりで書いているから……」
「無理やり考えようとしなくてもいいわ。上手い小説を書こう、なんて気負う必要もないわよ。これまで通り、楽しんで、自由に書くことを忘れないでね。穂乃香は今のままでも充分、素敵な物語を紡げるんだから」
母は私の目をじっと見つめて言うと、ウインクを一つした。
あれから三年ちょっとが経つ。私はノートを開くと、これまで書いてきたメモを眺めた。初めの方は、書きかけで終わっているページが多い。自分でも設定の作り方を本やネットで調べてみたのだけど、上手くいかなかったのだ。
どうすればちゃんと書けるのか悩んでいた時、ふと、母の「楽しんで、自由に書くことを忘れない」というアドバイスを思い出した。それからは、形式にこだわらずに自由に書くようにしている。思い浮かんだシーンを片っ端から書き連ねたページや、登場人物のイラストや架空の地図が描かれているページもある。頭の中の物語を具体化してから執筆に入ると、今までより筆が乗った。私は一層、小説執筆にのめり込むようになったのだった。
中二の秋口に母が持病を悪化させて入院してからは、生活が大変で書くペースはぐんと落ちた。けれど、母は病室で私の書く小説を読むのを楽しみにしていたので、執筆を止めることはしなかった。それなのに……。
あるページで視線が止まる。私の心は三年前の十月、母がまだ存在している病室に飛んだ。私の書いた設定を楽しそうに読んで、アドバイスをくれた母。そんな母に私は、言葉のナイフを振りかざしてしまった。
「今のお母さんが書く小説なんて、コンビニで買える安いチョコレートみたいだよ」
「穂乃香、大丈夫?」
ハッと意識を現在に戻す。私は高校の自習室で、誰かに声を掛けられていた。ぼんやりとした気持ちで、傍らに立つ人物を見上げる。
「……玲二君」
いつの間にいたのか、玲二君が心配そうに私を見下ろしていた。
「図書委員の仕事で自習室の見回りに来たんだけど、穂乃香が具合悪そうに見えたから」
「あっ、うん、大丈夫。ちょっと疲れてぼーっとしちゃっただけ」
苦笑して片手を振ると、玲二君もホッとしたように笑った。
「そうか。今は季節の変わり目だから、疲れやすいよな。無理して風邪でも引いたら大変だし、今日はもう帰ったら?」
「うん。そうする」
優しい彼にこれ以上気を使わせたくなかったので、素直に頷いて帰り支度を始める。すると玲二君は、机の上の構想ノートに目を留めた。
「穂乃香って、小説を書いているのか?」
頬がサッと熱くなる。慌ててノートを閉じると、玲二君は気まずそうな顔をした。
「あ、ごめん。許可もなしに見られたら嫌だよな……」
「ううん。私が小説を書いていること、友達にも言ってなかったから、何だか恥ずかしくて」
そう言うと、玲二君は意外そうに私を見た。
「別に恥ずかしくないだろ。純粋にすごいと思うよ。俺、小説好きでよく読むけど、自分で書けるかっていったら、何も思い浮かばないし」
「さすがに、プロの小説家が書くような話は、私にも書けないよ」
「いやいや。自分なりに考えて形に出来るだけでもすごいって。今はどういう話を書いているの?」
ニコニコと興味深そうに聞いてくる玲二君。彼に悪気が一切ないのは分かっているのに、
「あの、私、もう帰って休みたいから」
つい、冷たい態度を取ってしまった。
「そうだよな。ごめん、疲れている時に色々聞いちゃって」
申し訳なさそうな顔の玲二君を見て、しまったと思う。だけど私の口は、もう素直な言葉を話してはくれなかった。
「じゃ、行くね」
短く挨拶した自分の声も尖っていて、だけどそれを訂正する心の余裕もない。
「ああ。またな、穂乃香」
玲二君がいつも通りの微笑みを見せてくれたのが、せめてもの救いだった。
3
十七歳でデビューした彼女の処女作は、女子高生が転校先でクラスメイトにいじめられ、それでも心折れることなく戦い抜く話だった。その後も、不遇な家庭や閉塞的な学校など、初期の美園呉羽の小説では、主人公はいつも何かしらの理不尽と戦っていた。
少女向け小説のレーベルから出ていたそれらの作品を、私は十歳くらいから当たり前のように読んで育った。いずれの小説も最終的に問題は解決し、主人公は前を向いて理解者と共に力強く生きていく。
私は幸運にも人間関係には恵まれて育ったけれど、それでも友達とすれ違ったり、クラスメイトとの間に誤解が生まれることはあった。そんな時、母の小説はいつも私を助けてくれた。自分から一歩踏み出す勇気を、美園呉羽の作品は与えてくれたのだった。
そんな母の作風は、二十五歳で結婚して私が生まれてからガラリと変わった。大人の女性をターゲットにした恋愛小説を書くようになったのだ。具体的には、健気で可愛らしい女性が容姿も性格も完璧な男性に愛されるという、現代のおとぎ話のようなストーリーだ。以前の作品に漂っていた不穏さは鳴りを潜め、甘い雰囲気が物語を彩った。
……はっきり言うと、私は母の作風の変化を好まなかった。中学生になって、初めて母の書く恋愛小説を読んだ時、これまでの作品とのあまりの違いに驚いた。お約束の展開とハッピーエンドは、私には物足りなく感じてしまった。
「別の人が書いたお話みたい。どうしてこんなに変わっちゃったの?」
率直に母に聞くと、「そうねぇ」とのんびりした声が返ってきた。
「昔は『書くこと』が、私の唯一の味方だったのよね」
「味方?」
「そうよ。私と一緒に戦ってくれる存在」
母の言うことは、当時の私には難しかった。だけど、大事なことを語ってくれている気がしたから、私は真面目に耳を傾けた。
「私は小説を書いて、一人きりで自分の周りにある世界と戦っていたのよ。物語を紡ぐことで、自分が強くなれたような気がしたのよね。でもね、お父さんという頼もしい味方が現れてくれて、穂乃香という、自分が一番の味方になってあげたい存在も出来て……小説に対する考えが変わったわ。二人がくれた優しさを、作品にも加えたくなったの。そうやって、書きたい話が変わっていったのよね」
「ふうん……」
母の言うことを、きちんと理解は出来ていなかったかもしれない。それでも母にとって、作風の変化が良いことだというのは分かった。私と父が、母にとって大切な存在だということも。そんな母を、私も大切にしたいと思ったはずなのに……。
中二の十月。あの時、私の心は酷く不安定だった。母の入院が長引き、今後どうなるのか怖くて仕方がない。思ったよりも医療費が掛かり、父は働きづめ。近所の人たちの助けがあったとはいえ、家事と勉強の両立は目まぐるしく、遊ぶ時間なんてない。ましてや、家族団らんの時間なんて皆無だ。病床の母のために、せめて楽しい物語を書こうとするのだけど、常に気が急いているからか、今までにないくらい筆が進まない。
それでも頑張って、小説の設定だけは作った。引っ込み思案の女子が、人気者の男子に好かれて人の輪に入っていく恋愛小説だ。ありきたりなストーリーかもしれないけれど、現実が暗いものだったから、せめて明るい話を、と思って作った。
病院のベッドの上で、母はニコニコと設定が書かれたノートを読んだ。そしていつも通りの穏やかな口調で言ったのだ。
「素敵なお話ね。主人公の心の動きに心惹かれるわ。ぜひ、穂乃香の言葉で小説にしてほしいわね。お相手の男の子も爽やかでカッコいいけど……そうね、もう少し恋愛の要素を増やしてみてはどうかしら? 男の子の魅力と絡めた、ロマンチックなシーンをね」
どうしてだろう。母の何気ないそのアドバイスで、私の頭にカッと血が昇ってしまったのだ。
「別にどう書いたっていいじゃない」
私の鋭い声が、真っ白な病室を刺した。
「サイトに載せるだけで、別に公募に出すわけじゃないんだから、好きにさせてよ。それに、私はあんな甘々の恋愛小説は目指してないの。今のお母さんが書く小説なんて、コンビニで買える安いチョコレートみたいだよ」
醜い言葉が、次から次へと私の口から飛び出す。私は完全に我を失っていた。
今思えばあの怒りは、暗い現実に対する悲鳴のようなものだったのかもしれない。私は単に、誰かに八つ当たりしたかったのだ。つらくて苦しいと、訴えたかったのだ。だけど私は、一番八つ当たりしてはいけない相手に怒りの矛先を向けてしまった。
母は憂いを帯びた表情で黙って私を見つめていた。そして、感情ごちゃ混ぜで何も言えなくなっている私に声を掛けた。
「そうね。あなたがどんなお話を書いたとしても、そこには穂乃香だけの光があるわ。私はなるべく多く、その光を見ていたいのよ」
それはとても小さな声で、当時の私の心には入っていかなかった。
それからの母はいつも通りのにこやかな様子で、私も何事もなかったかのように優しく接した。その時には、母に残された時間が少ないのを知らされていたから、殊更明るく振る舞うようにしていた。
けれど、ほどなくして母が他界し、葬儀を全て終えて少し経った頃……ふと、自分は間違っていたのではないか、と思った。あの時に口から出した言葉を消すことは出来ない。だけど、優しい言葉を重ねて、母の心に刺してしまった棘を抜き取ることは出来たのではないか、と。
だけどそれはもう叶わない。私は永遠に、母に謝罪する機会を失ってしまったのだ。
このノートの中には、後悔が眠っている。
自宅アパートの屋上で長い髪を風になびかせながら、私はふーっと長いため息を吐いた。
周りに高い建物がないので、低い青空に薄く長い雲が伸びているのがよく見える。十月に入り、徐々に日差しが和らいできていた。長かった残暑もようやく終わりそうだ。
さっきまで、外は引っ越し作業で賑やかだった。どうやら、二階の空き部屋に新しい住人がやって来たらしい。築三十年の三階建てアパートは外も中も古びて色あせていて、だけど家賃が相場よりずっと安いから、空き部屋が出てもすぐに埋まる。
穏やかな秋の日曜日。だけどこの季節になると、私はあることを思い出してしまう。花柄の可愛いノートを胸にぎゅっと抱き、私は小さな声で謝罪した。
「ごめんなさい……お母さん」
と、近くから足音が聞こえた。屋上へ続く階段を昇る音。私はハッとして振り返る。こんな何もない屋上へ来る物好きは私くらいで、今まで誰にも会ったことがなかったのに……。
屋上の入り口にある柵をそっと開ける姿を見て、私は思わずノートを取り落としそうになった。
「えっ?」
休日の静かな午後に不似合いの、大きな声を出してしまう。目の前の人物も、目を見開いて私を見つめていた。
「藤原さん?」
不思議そうに名前を呼ばれ、私はようやく我に返ると、こくんと頷いた。
「うん……こんなところで会うなんて、びっくりしたよ。桜沢君」
そこにいたのは、クラスメイトの桜沢玲二君だった。すらっとした長身に、サラサラの黒髪。メタルフレームの眼鏡を掛けていてクールな印象だけど、実際は誰にでも優しくて、おまけに成績優秀の優等生だ。同い年ながら、クラスでは頼れるお兄さんって感じで皆に慕われている。今年初めて同じクラスになったけど、そこまで交流のない私にも親切だ。
「屋上に藤原さんがいるってことは……このアパートに住んでいるの?」
いつも通りの穏やかな声で問われ、私も素直に頷いた。
「そうだよ。桜沢君は、どうしてここにいるの?」
すると、桜沢君は気まずそうに黙り込んだ。いつも堂々としている彼にしては、こういう態度は珍しい。私が首を傾げていると、
「玲二ー! 早く荷解きを手伝いなさい!」
階下から女性の明るい声が桜沢君を呼んだ。彼はぱっと顔を上げると、
「今行くから!」
声のした方へ返事をしてから、目を伏せて私に向き直った。
「……そういうこと。俺も、今日からここに住むんだ。よろしく」
「え……」
戸惑う私をよそに、桜沢君は踵を返すとさっさと屋上を出て行ってしまった。ちょっとの間を置いて、ようやく私は、さっき引っ越してきた人たちが桜沢君一家であることに気付いた。
2DKの自宅に戻り、キッチンで一人夕食を作りながら、私はついさっきあったことを思い出していた。
「桜沢君が、このおんぼろアパートに……? 信じられない……」
信じられないも何も、私は本人の口からその事実を聞いている。でも、彼の様子は、そのことを誰にも知られたくなかったように見えた。それはそうだろう。桜沢君は、学校でも有名なセレブなのだから。
彼のお父さんは、有名な大手商社に勤めている。桜沢君はお父さんの駐在先のイギリスで生まれて、三歳の時に日本に帰ってきた。
もちろん、桜沢君は自分が裕福な生まれであることをひけらかしたりはしない。だけど、ブレザーの中に着ているブランド物のニットや、艶々のローファー、輸入物の文房具なんかを見れば、彼の生活レベルの高さが見て取れた。
確か今の住居は、湾岸地域のタワーマンションだったはず。そんな桜沢君が、老朽化の激しいうちのアパートに引っ越してきただなんて、本当にあり得ない話だけど……。
そんなことを考えていると、外廊下を誰かが歩いてくる音がした。ほどなくしてドアの鍵が開き、スーツ姿の父が姿を現した。
「お父さん、おかえり」
「ただいま。悪かったね、穂乃香。休日なのに家事を任せきりにして」
申し訳なさそうな顔をする父に、私は笑って首を横に振った。父の会社は普段は土日休みなのだが、今日はイベントの手伝いで休日出勤だったのだ。
「お仕事なら仕方ないよ。お米は……あと二十分で炊ける。お腹空いてるんだったら、冷凍ご飯温めるけど」
「いや、炊けてからで大丈夫だよ。そういえば、さっきそこで、新しく引っ越してきた人と挨拶したよ」
「えっ!」
思わず大声を出してしまった私を見て、父は怪訝そうな顔をした。
「どうしたんだい? そんなに驚いて」
「ううん、何でもない。それで、どんな人だったの?」
「篠塚さんといって、華やかな見た目の女の人だったよ。息子さんと二人暮らしだそうだ。ああ、息子さんは、穂乃香と同じ高校二年生だと言っていたな」
「篠塚さん……」
名字が違う。だけど、きっとその女の人は、桜沢君のお母さんなのだろう。二人暮らしということは、お父さんとは……。
私はそこで考えるのをやめた。自分の生活を勘ぐられるつらさは、よく知っている。このことは、お父さんにも、クラスの皆にも秘密にしておこう。そう思った。
「お父さん。それ、新しいお花?」
父が手にしていた透明の手提げ袋には、コスモスを中心としたミニブーケが入っていた。
「そうだよ。実穂乃さんの好きなコスモスの季節がやってきたからね」
そう言って、父はダイニングの一角に置かれた小さな棚に向き直った。そこには、三年前に病気で他界した母の写真と位牌を置いてある。花が好きだった母のために、父はいつも季節のミニブーケを供えていた。
写真立ての中で朗らかに笑う母を眺めながら、私は複雑な気持ちになっていた。
母・藤原実穂乃は小説家だった。ペンネームは美園呉羽。十七歳でデビューした当時は中高生向けの青春小説を、結婚して私が生まれてからは大人の女性向けの恋愛小説を書いていた。
とはいっても、そこまで売れていたわけではない。読書好きの人に美園呉羽について尋ねても、知らない場合がほとんどだろう。母は昔から病弱だったから、活動年数に比べて著書の数も少ない。
それでも、母も父も私も、小説家・美園呉羽を誇りに思っていた。初期の作品に多かった、女子中高生がいじめなどの理不尽な状況にも負けずに戦う話には、私も随分と元気づけられたものだ。手紙をくれる熱心なファンもいて、母はそのファンレターを大事そうにファイルにしまっていた。
そんな母に憧れていた私は、小五の頃から自分でも小説を書くようになった。母はいつも、私の書いた物語を楽しそうに読んでくれた。
「穂乃香、このお話も面白いわ。案内役のシロが、茶目っ気があって魅力的ね」
「そうでしょ? あのね、このワンちゃんはね、ミカちゃんが飼っているマルチーズをモデルにしているんだよ。この子、お腹が空くと『ごはん!』って喋るんだって!」
「まあ、それで、言葉を喋る犬の設定にしたのね。穂乃香は想像力が豊かで、本当に素晴らしいわ」
笑顔で私をたくさんほめてくれる母。そんな優しい母に後押しされて、私も小説家を目指すようになったのに……。
中二の秋、ちょうど今時期だ。私は病床の母にひどいことを言ってしまった。謝る機会を逸したまま母は他界し、私は今でも深い後悔の中にいる。
2
翌朝。桜沢君のことを気に掛けながらも、いつも通りに身支度をした。十月から冬服期間になったものの、長袖のブレザーはまだちょっと暑い。茶色掛かった長い髪は、いつもハーフアップにしている。いくつか持っているバレッタの中から、今日は秋らしいベロアの赤いリボンのものに決めた。
父は既に出勤している。ダイニングの母の写真に「行ってきます」と手を振ってから、私も部屋を出た。
アパートの外階段を降りた私を、誰かが呼び止めた。
「藤原さん」
振り返ると、二階の外廊下から桜沢君が顔を覗かせている。
「あ……おはよう、桜沢君」
昨日のこともあって、どんな素振りをすれば良いのか分からない私に、桜沢君は穏やかに微笑んだ。
「おはよう。駅まで一緒に行ってもいいかな?」
「うん、いいけど……」
おずおずと頷くと、桜沢君も階段を降りてきた。並んで歩き出すと、彼はこう切り出した。
「昨日はごめん。素っ気なくしちゃったなって、後から反省したんだ」
「ううん、気にしてないよ」
「……ありがとう。びっくりしただろ? お金持ちって噂の俺が、突然、普通のアパートに引っ越してきてさ」
「……えっと」
確かに驚いたし、うちのアパートは「普通」レベルにも満たない、格安おんぼろアパートだ。だけどそのことを、率直に言うのも失礼な気がする。口ごもっていると、桜沢君は笑みを崩さずに言った。
「うちさ、両親が離婚したんだ。それで、俺と母さんでここに住むことにした。もう父さんを頼ることは出来ないからな。これからは、生活をかなり切り詰めることになりそうだ」
「そうなんだ……」
桜沢君の事情は分かったけれど、やっぱり、何を言って良いのか分からない。曖昧な相槌を打つ私に、桜沢君は続けた。
「昨日、母さんが、藤原さんって男の人に挨拶をしたって言っていたから、もしかしたら、藤原さんのお父さんかなって思ったんだけど」
「うん、そうだよ。うちのお父さん。そっか、だから篠塚さんって名字なんだね」
「そう、母さんの旧姓。俺も本当は、桜沢じゃなくて篠塚なんだけど……俺さ、このことをクラスの皆には黙っておこうと思うんだ」
「えっ」
意志を込めたようなしっかりとした声に、私は弾かれたように桜沢君の顔を見た。眼鏡の奥の瞳も、声同様に真っすぐ私を見返す。
「事情を知られたら、周りに気を使わせちゃうからな。名字も桜沢のままでいく。だから、これはお願いなんだけど……藤原さんも、両親の離婚のことと、俺たちがこのアパートに住んでいることを秘密にしてもらえないかな?」
「それは、構わないけど……」
私と桜沢君はそんなに親しいわけでもないし、秘密にするのは容易いだろう。だけど、本当に良いのだろうか? ご両親の離婚の理由は知らないけれど、生活がこんなに変化して、桜沢君だって不安なはずだ。そんな時に、周りの人に心の内を話せたのなら、どんなにか楽になるだろうに。
私の考えを見透かしたのか、桜沢君は安心させるような笑顔を向けてきた。
「俺なら大丈夫。離婚して母さんも大分元気になったし、俺は今の生活で良かったって思ってるから」
「それならいいけど……でも、せっかくご近所に住んでいるんだし、何か困ったことがあったら言ってね。実は私も、お母さんが死んじゃった時に、アパートの人たちに随分助けられたの」
「そうだったのか……うん、ありがとう」
桜沢君は素直に頷くと、心配そうな顔で私を見た。
「藤原さんも大丈夫?」
「えっ?」
「昨日、アパートの屋上で会った時、泣きそうな顔をしていたから。何か嫌なことでもあった?」
クラスで見せるような大人びた優しい眼差しに、私の心はじわりと温かくなった。だけど私の後悔は、お父さんにも親しい友達にも話していない一番の秘密だ。話すわけにはいかない。
「大したことじゃないよ。ありがとう、桜沢君」
無理して笑ってみせる。私の嘘に桜沢君が気付いた様子はなかった。
「藤原さんこそ、俺で力になれるのなら、何でも言って。俺の秘密を守ってもらっている恩もあるし。あと、俺のことは玲二でいいよ。友達もそう呼んでる。それに俺はもう、桜沢じゃないからな」
ぼそっと呟かれた最後の言葉に、彼の複雑な感情が透けて見えた。
「分かった……玲二君。私のことも穂乃香でいいよ」
「うん。これからよろしく、穂乃香」
互いに微笑み合う。秘密を共有した私たちは、今までよりちょっとだけ仲良くなれた気がした。
放課後。私は友達からの遊びの誘いを断って、図書室の自習スペースで勉強していた。頭を必死で働かせながら、数学の文章問題を解いていく。
私の希望進路は、地元の国立大学の経済学部だ。父になるべく負担を掛けずに大学に行こうとすれば、どうしても学費の安い国公立大学を選ぶことになる。この大学は家から通える距離にあるし、経済学部は就職に強いと評判だ。何としてでも入りたい。
それなのに、私の成績は伸び悩んでいた。受験までまだ時間はあるとはいえ、このままの偏差値だと合格は難しいだろう。特に、経済学部受験には必須の数学が大の苦手だ。なので、最近ではこうして勉強する時間を増やすようにしている。
一時間ほど集中して問題集に取り組んでいたけれど、さすがに疲れてきた。ひと休みしようと、ブレザーのポケットからいちごミルク味の飴を取り出す。個装を開けて口に入れると、甘さが頭の中まで染み渡るのを感じた。
ふうっと息を吐いてから、私は鞄から一冊のノートを取り出した。勉強用ではない。十四歳の時から使っている、表紙にピンクの小花柄が散りばめられた可愛いノートだ。
このノートには、自分で考えた小説の構想や設定などのメモを書き留めている。どんな状況で、どんな人物が、どんな行動を起こすのか。小説家になるためには、そういった執筆前に考える段階も重要だと母が教えてくれた。
「そうして思いついたことを、このノートに書き留めておくのよ。きっと、穂乃香の小説の可能性を広げてくれるわ」
そう言って、母はこのノートを私にプレゼントしてくれた。中二の夏休み頃の話だ。
「ありがとう、お母さん。でも、小説の構想だなんて、すごく難しそうだね。私はいつも、行き当たりばったりで書いているから……」
「無理やり考えようとしなくてもいいわ。上手い小説を書こう、なんて気負う必要もないわよ。これまで通り、楽しんで、自由に書くことを忘れないでね。穂乃香は今のままでも充分、素敵な物語を紡げるんだから」
母は私の目をじっと見つめて言うと、ウインクを一つした。
あれから三年ちょっとが経つ。私はノートを開くと、これまで書いてきたメモを眺めた。初めの方は、書きかけで終わっているページが多い。自分でも設定の作り方を本やネットで調べてみたのだけど、上手くいかなかったのだ。
どうすればちゃんと書けるのか悩んでいた時、ふと、母の「楽しんで、自由に書くことを忘れない」というアドバイスを思い出した。それからは、形式にこだわらずに自由に書くようにしている。思い浮かんだシーンを片っ端から書き連ねたページや、登場人物のイラストや架空の地図が描かれているページもある。頭の中の物語を具体化してから執筆に入ると、今までより筆が乗った。私は一層、小説執筆にのめり込むようになったのだった。
中二の秋口に母が持病を悪化させて入院してからは、生活が大変で書くペースはぐんと落ちた。けれど、母は病室で私の書く小説を読むのを楽しみにしていたので、執筆を止めることはしなかった。それなのに……。
あるページで視線が止まる。私の心は三年前の十月、母がまだ存在している病室に飛んだ。私の書いた設定を楽しそうに読んで、アドバイスをくれた母。そんな母に私は、言葉のナイフを振りかざしてしまった。
「今のお母さんが書く小説なんて、コンビニで買える安いチョコレートみたいだよ」
「穂乃香、大丈夫?」
ハッと意識を現在に戻す。私は高校の自習室で、誰かに声を掛けられていた。ぼんやりとした気持ちで、傍らに立つ人物を見上げる。
「……玲二君」
いつの間にいたのか、玲二君が心配そうに私を見下ろしていた。
「図書委員の仕事で自習室の見回りに来たんだけど、穂乃香が具合悪そうに見えたから」
「あっ、うん、大丈夫。ちょっと疲れてぼーっとしちゃっただけ」
苦笑して片手を振ると、玲二君もホッとしたように笑った。
「そうか。今は季節の変わり目だから、疲れやすいよな。無理して風邪でも引いたら大変だし、今日はもう帰ったら?」
「うん。そうする」
優しい彼にこれ以上気を使わせたくなかったので、素直に頷いて帰り支度を始める。すると玲二君は、机の上の構想ノートに目を留めた。
「穂乃香って、小説を書いているのか?」
頬がサッと熱くなる。慌ててノートを閉じると、玲二君は気まずそうな顔をした。
「あ、ごめん。許可もなしに見られたら嫌だよな……」
「ううん。私が小説を書いていること、友達にも言ってなかったから、何だか恥ずかしくて」
そう言うと、玲二君は意外そうに私を見た。
「別に恥ずかしくないだろ。純粋にすごいと思うよ。俺、小説好きでよく読むけど、自分で書けるかっていったら、何も思い浮かばないし」
「さすがに、プロの小説家が書くような話は、私にも書けないよ」
「いやいや。自分なりに考えて形に出来るだけでもすごいって。今はどういう話を書いているの?」
ニコニコと興味深そうに聞いてくる玲二君。彼に悪気が一切ないのは分かっているのに、
「あの、私、もう帰って休みたいから」
つい、冷たい態度を取ってしまった。
「そうだよな。ごめん、疲れている時に色々聞いちゃって」
申し訳なさそうな顔の玲二君を見て、しまったと思う。だけど私の口は、もう素直な言葉を話してはくれなかった。
「じゃ、行くね」
短く挨拶した自分の声も尖っていて、だけどそれを訂正する心の余裕もない。
「ああ。またな、穂乃香」
玲二君がいつも通りの微笑みを見せてくれたのが、せめてもの救いだった。
3
十七歳でデビューした彼女の処女作は、女子高生が転校先でクラスメイトにいじめられ、それでも心折れることなく戦い抜く話だった。その後も、不遇な家庭や閉塞的な学校など、初期の美園呉羽の小説では、主人公はいつも何かしらの理不尽と戦っていた。
少女向け小説のレーベルから出ていたそれらの作品を、私は十歳くらいから当たり前のように読んで育った。いずれの小説も最終的に問題は解決し、主人公は前を向いて理解者と共に力強く生きていく。
私は幸運にも人間関係には恵まれて育ったけれど、それでも友達とすれ違ったり、クラスメイトとの間に誤解が生まれることはあった。そんな時、母の小説はいつも私を助けてくれた。自分から一歩踏み出す勇気を、美園呉羽の作品は与えてくれたのだった。
そんな母の作風は、二十五歳で結婚して私が生まれてからガラリと変わった。大人の女性をターゲットにした恋愛小説を書くようになったのだ。具体的には、健気で可愛らしい女性が容姿も性格も完璧な男性に愛されるという、現代のおとぎ話のようなストーリーだ。以前の作品に漂っていた不穏さは鳴りを潜め、甘い雰囲気が物語を彩った。
……はっきり言うと、私は母の作風の変化を好まなかった。中学生になって、初めて母の書く恋愛小説を読んだ時、これまでの作品とのあまりの違いに驚いた。お約束の展開とハッピーエンドは、私には物足りなく感じてしまった。
「別の人が書いたお話みたい。どうしてこんなに変わっちゃったの?」
率直に母に聞くと、「そうねぇ」とのんびりした声が返ってきた。
「昔は『書くこと』が、私の唯一の味方だったのよね」
「味方?」
「そうよ。私と一緒に戦ってくれる存在」
母の言うことは、当時の私には難しかった。だけど、大事なことを語ってくれている気がしたから、私は真面目に耳を傾けた。
「私は小説を書いて、一人きりで自分の周りにある世界と戦っていたのよ。物語を紡ぐことで、自分が強くなれたような気がしたのよね。でもね、お父さんという頼もしい味方が現れてくれて、穂乃香という、自分が一番の味方になってあげたい存在も出来て……小説に対する考えが変わったわ。二人がくれた優しさを、作品にも加えたくなったの。そうやって、書きたい話が変わっていったのよね」
「ふうん……」
母の言うことを、きちんと理解は出来ていなかったかもしれない。それでも母にとって、作風の変化が良いことだというのは分かった。私と父が、母にとって大切な存在だということも。そんな母を、私も大切にしたいと思ったはずなのに……。
中二の十月。あの時、私の心は酷く不安定だった。母の入院が長引き、今後どうなるのか怖くて仕方がない。思ったよりも医療費が掛かり、父は働きづめ。近所の人たちの助けがあったとはいえ、家事と勉強の両立は目まぐるしく、遊ぶ時間なんてない。ましてや、家族団らんの時間なんて皆無だ。病床の母のために、せめて楽しい物語を書こうとするのだけど、常に気が急いているからか、今までにないくらい筆が進まない。
それでも頑張って、小説の設定だけは作った。引っ込み思案の女子が、人気者の男子に好かれて人の輪に入っていく恋愛小説だ。ありきたりなストーリーかもしれないけれど、現実が暗いものだったから、せめて明るい話を、と思って作った。
病院のベッドの上で、母はニコニコと設定が書かれたノートを読んだ。そしていつも通りの穏やかな口調で言ったのだ。
「素敵なお話ね。主人公の心の動きに心惹かれるわ。ぜひ、穂乃香の言葉で小説にしてほしいわね。お相手の男の子も爽やかでカッコいいけど……そうね、もう少し恋愛の要素を増やしてみてはどうかしら? 男の子の魅力と絡めた、ロマンチックなシーンをね」
どうしてだろう。母の何気ないそのアドバイスで、私の頭にカッと血が昇ってしまったのだ。
「別にどう書いたっていいじゃない」
私の鋭い声が、真っ白な病室を刺した。
「サイトに載せるだけで、別に公募に出すわけじゃないんだから、好きにさせてよ。それに、私はあんな甘々の恋愛小説は目指してないの。今のお母さんが書く小説なんて、コンビニで買える安いチョコレートみたいだよ」
醜い言葉が、次から次へと私の口から飛び出す。私は完全に我を失っていた。
今思えばあの怒りは、暗い現実に対する悲鳴のようなものだったのかもしれない。私は単に、誰かに八つ当たりしたかったのだ。つらくて苦しいと、訴えたかったのだ。だけど私は、一番八つ当たりしてはいけない相手に怒りの矛先を向けてしまった。
母は憂いを帯びた表情で黙って私を見つめていた。そして、感情ごちゃ混ぜで何も言えなくなっている私に声を掛けた。
「そうね。あなたがどんなお話を書いたとしても、そこには穂乃香だけの光があるわ。私はなるべく多く、その光を見ていたいのよ」
それはとても小さな声で、当時の私の心には入っていかなかった。
それからの母はいつも通りのにこやかな様子で、私も何事もなかったかのように優しく接した。その時には、母に残された時間が少ないのを知らされていたから、殊更明るく振る舞うようにしていた。
けれど、ほどなくして母が他界し、葬儀を全て終えて少し経った頃……ふと、自分は間違っていたのではないか、と思った。あの時に口から出した言葉を消すことは出来ない。だけど、優しい言葉を重ねて、母の心に刺してしまった棘を抜き取ることは出来たのではないか、と。
だけどそれはもう叶わない。私は永遠に、母に謝罪する機会を失ってしまったのだ。