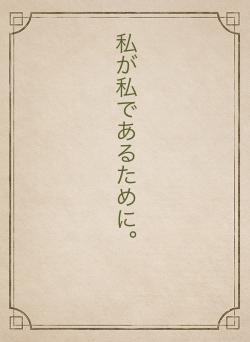「えー、今日は中学校の復習も兼ねて、補色について、説明していきたいと思います」
桜の花弁が舞う春、高校に入学してからの初授業はまさかの美術だった。
説明する美術教師の服装も、オレンジ色のカーディガンに青みの強いジーンズ生地のロングスカート、つまり補色だ。
僕はそんなどうでも良いことを考えながら頬杖をついて窓の外を見る。説明なんて、聞かなくてもわかる。何年やってると思ってるんだ、舐められても困る。
補色。それぞれの色によって決まっていて、お互いを引き立て、鮮やかに見せる色合いのこと。
例えば、赤と緑とか。まあ考え出すときりがない。
ただし――。
「黒に補色は…」
――ない。無彩色だからだ。
僕は一瞬だけ授業に目を向けたけど、またすぐに目線を逸らした。
桜の花弁が舞う春、高校に入学してからの初授業はまさかの美術だった。
説明する美術教師の服装も、オレンジ色のカーディガンに青みの強いジーンズ生地のロングスカート、つまり補色だ。
僕はそんなどうでも良いことを考えながら頬杖をついて窓の外を見る。説明なんて、聞かなくてもわかる。何年やってると思ってるんだ、舐められても困る。
補色。それぞれの色によって決まっていて、お互いを引き立て、鮮やかに見せる色合いのこと。
例えば、赤と緑とか。まあ考え出すときりがない。
ただし――。
「黒に補色は…」
――ない。無彩色だからだ。
僕は一瞬だけ授業に目を向けたけど、またすぐに目線を逸らした。