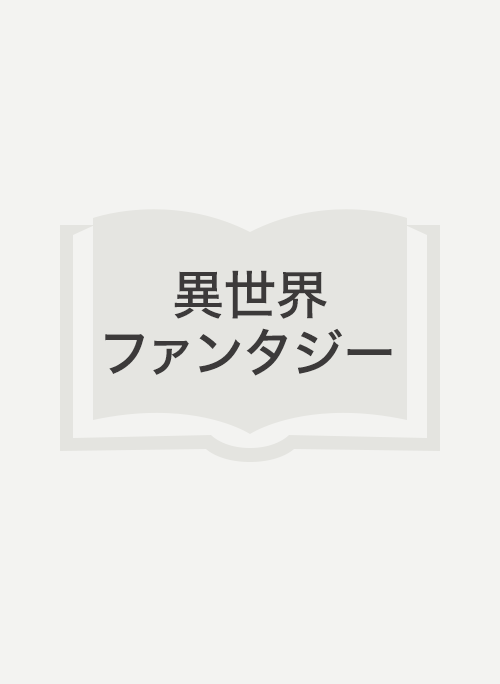前回のあらすじ
あれだけてこずった館からひょっこり出てくるウルウ。
彼女の言うマナーとはいったい。
手順、そう言われて、あたしたちは、ウルウのするようにしてみることにした。
まず、リリオが少し背伸びをして、打ち金を鳴らすと、先ほどまであんなにもかたくなに閉ざされていた扉が、いともたやすくあっけなく開いてしまった。
「うそぉ……」
「言っただろう、一応礼儀じゃないかって」
そりゃあ、打ち金があったら打ち金を鳴らして来訪を告げるのは当たり前と言えば当たり前だ。でもまさか、そんな簡単なことで開くようになるとは思わないじゃない。それも、あんな乱暴に追い出されて、しかも仲間が一人だけ取り残されているような、そんな状況で。
「先に乱暴を働いたのは君たちだろう」
「あたしたちが?」
再度応接室を訪れて、緊張に視線を泳がせるあたしたちに、ウルウは笑った。
「招かれもしない客が、家内で武器なんか抜いたら、賊と思われても仕方がないだろう」
「そりゃあ、普通は、そうかもしれないけど」
「じゃあ、普通だったらこの光景をどう見る?」
そう言われて、あたしは卓に改めて並べられた湯気を立てる甘茶と焼き菓子を見やった。
これは、つまり、そういうことなのだろうか。
「あたしたちをもてなしているってわけ?」
「その通り。安心して。毒見は済ませてあるから」
ウルウは勝手知ったると言わんばかりに長椅子に腰を下ろして、甘茶を楽しみ始めた。
こいつ、さてはあたしたちが苦労している間、こうして優雅に過ごしていやがったのだろう。
そう思うと途端になんだか馬鹿らしくなって、あたしも、リリオも長椅子に腰を下ろしてお茶とお茶菓子を楽しむことにした。
ウルウが上機嫌になるだけあって、甘茶は上等なものだった。
まず茶葉がいい。きっと客人用と蓋に書かれているようなとっておきの茶葉を、しっかりと蒸らして入れた上質な甘茶だ。
どうやったらこんな短時間で出せるのか、ぜひとも教えを請いたいくらいだけれど、多分それも館の不思議の一つなんだろう。
リリオが美味しそうにほおばる焼き菓子も、実際見事なものだった。たっぷりの乳酪を混ぜ込んだらしい生地はさっくりとして軽やかな歯ごたえで、そしてまた重すぎない甘さがついつい後を引くのだった。
あたしたちが焼き菓子を楽しみ、そしてお茶を飲み終えると、再び扉が開き、行く先を示すかのように明かりがともった。
「さあ、突然の客人をもてなして、次は何かな」
何やらウルウは楽しそうで結構だ。なんだかんだこういうことを楽しむのはリリオよりもウルウだ。あたしはそれについていくので精いっぱいよ、全く。
さらに奥の部屋の扉が開き、あたしたちは楽しげなウルウの後に続いて足を踏み入れた。
「ここは……書斎、でしょうか」
リリオが言う通り、そこは書斎のように思えた。入って正面に飴色に年を経た書き物机が鎮座しており、部屋の左右の壁は立派な本棚になっていた。これだけの棚に詰め込まれた本というのは、物にもよるけれど、ひと財産だろう。
ざっと背表紙を目で追ってみたけれど、みな難しそうな学問の本のようで、私には中身までは察せられなかった。
あたしたちが書き物机に近づいてみると、そこにはてのひらに乗るような小さな自鳴琴が歌っていた。
銀細工の箱に、木陰で遊ぶ少女の図案が彫り込まれた、見事な一品だった。
そしてその音色は、この町に来てから付きまとうようになった、あの厳かで、静けさすら感じさせるような音色だったのだ。
「この自鳴琴が、異変の原因っていうこと?」
「恐らくね」
あたしにはこの本当に小さな自鳴琴が、町全体を襲うような大それた異変の原因とはとても思えなかった。しかし実際に不思議な音色はいまもこの自鳴琴が奏で続けており、それらは無関係なのだとはとても言えなかった。
「なんだか……なんだか、寂しそうですね」
「そうね……ずっと、ひとりで、ひとりっぽっちで、こうして歌っていたのね」
ウルウは名残を惜しむように、そっと自鳴琴の蓋に手をかけて、ぱたりと閉じた。
それきり音色は夜の町から消え去って、そうして二度と町の人々を悩ませることはなかった。
一晩明けて、あたしたちはあの不動産屋さんに、自鳴琴を持ち込んで事の顛末を話してみた。他の誰も知らないままで終わるよりは、せめて館の主を弔ってくれたこの人にくらい、知っておいてもらいたかったのだ。
不思議なこともあるもんですなあ、と不動産屋さんはしみじみと自鳴琴を眺めて、それからこう言ったのでした。
「もしかしたら自鳴琴というより、館の幽霊の仕業だったのかもしれませんなあ」
「館の、幽霊?」
「死んでいるわけじゃないから、幽霊というのも変ですがね。長く大事にされたものには魂が宿ることがあるんだそうで、そう言う家や館なんてのが、たまにあたしらの業界で聞かれるんですなあ」
不動産屋さんはどこかいつくしむように自鳴琴を撫でて、思いやるように言葉を紡いだ。それはまさしく、主を失った館への思いやりのようだった。
「何しろ館の主人は、ひとりっぽっちで亡くなっちまって、弔いもあたしと神官だけの寂しいもんでした。その間、町の連中は何にも知らずに賑やかに騒いでいたんですから、館の方でも怒っちまったのかもしれませんな。弔いの間くらいは、静かにしろってね」
それはいつぞやあたしが思い浮かべた、うるさい、だまれ、しずかにしろ、と言っているかのようだという想像の通りだった。
あたしたちがようやく、形ばかりでも館の主に敬意を払ったことで、館は満足したのかもしれなかった。
これは、そんな、奇妙な話だった。
用語解説
・館の幽霊
付喪神のようなものだろうか、この世界でも、長く使われた道具に魂が宿るという考え方があるようだ。
あれだけてこずった館からひょっこり出てくるウルウ。
彼女の言うマナーとはいったい。
手順、そう言われて、あたしたちは、ウルウのするようにしてみることにした。
まず、リリオが少し背伸びをして、打ち金を鳴らすと、先ほどまであんなにもかたくなに閉ざされていた扉が、いともたやすくあっけなく開いてしまった。
「うそぉ……」
「言っただろう、一応礼儀じゃないかって」
そりゃあ、打ち金があったら打ち金を鳴らして来訪を告げるのは当たり前と言えば当たり前だ。でもまさか、そんな簡単なことで開くようになるとは思わないじゃない。それも、あんな乱暴に追い出されて、しかも仲間が一人だけ取り残されているような、そんな状況で。
「先に乱暴を働いたのは君たちだろう」
「あたしたちが?」
再度応接室を訪れて、緊張に視線を泳がせるあたしたちに、ウルウは笑った。
「招かれもしない客が、家内で武器なんか抜いたら、賊と思われても仕方がないだろう」
「そりゃあ、普通は、そうかもしれないけど」
「じゃあ、普通だったらこの光景をどう見る?」
そう言われて、あたしは卓に改めて並べられた湯気を立てる甘茶と焼き菓子を見やった。
これは、つまり、そういうことなのだろうか。
「あたしたちをもてなしているってわけ?」
「その通り。安心して。毒見は済ませてあるから」
ウルウは勝手知ったると言わんばかりに長椅子に腰を下ろして、甘茶を楽しみ始めた。
こいつ、さてはあたしたちが苦労している間、こうして優雅に過ごしていやがったのだろう。
そう思うと途端になんだか馬鹿らしくなって、あたしも、リリオも長椅子に腰を下ろしてお茶とお茶菓子を楽しむことにした。
ウルウが上機嫌になるだけあって、甘茶は上等なものだった。
まず茶葉がいい。きっと客人用と蓋に書かれているようなとっておきの茶葉を、しっかりと蒸らして入れた上質な甘茶だ。
どうやったらこんな短時間で出せるのか、ぜひとも教えを請いたいくらいだけれど、多分それも館の不思議の一つなんだろう。
リリオが美味しそうにほおばる焼き菓子も、実際見事なものだった。たっぷりの乳酪を混ぜ込んだらしい生地はさっくりとして軽やかな歯ごたえで、そしてまた重すぎない甘さがついつい後を引くのだった。
あたしたちが焼き菓子を楽しみ、そしてお茶を飲み終えると、再び扉が開き、行く先を示すかのように明かりがともった。
「さあ、突然の客人をもてなして、次は何かな」
何やらウルウは楽しそうで結構だ。なんだかんだこういうことを楽しむのはリリオよりもウルウだ。あたしはそれについていくので精いっぱいよ、全く。
さらに奥の部屋の扉が開き、あたしたちは楽しげなウルウの後に続いて足を踏み入れた。
「ここは……書斎、でしょうか」
リリオが言う通り、そこは書斎のように思えた。入って正面に飴色に年を経た書き物机が鎮座しており、部屋の左右の壁は立派な本棚になっていた。これだけの棚に詰め込まれた本というのは、物にもよるけれど、ひと財産だろう。
ざっと背表紙を目で追ってみたけれど、みな難しそうな学問の本のようで、私には中身までは察せられなかった。
あたしたちが書き物机に近づいてみると、そこにはてのひらに乗るような小さな自鳴琴が歌っていた。
銀細工の箱に、木陰で遊ぶ少女の図案が彫り込まれた、見事な一品だった。
そしてその音色は、この町に来てから付きまとうようになった、あの厳かで、静けさすら感じさせるような音色だったのだ。
「この自鳴琴が、異変の原因っていうこと?」
「恐らくね」
あたしにはこの本当に小さな自鳴琴が、町全体を襲うような大それた異変の原因とはとても思えなかった。しかし実際に不思議な音色はいまもこの自鳴琴が奏で続けており、それらは無関係なのだとはとても言えなかった。
「なんだか……なんだか、寂しそうですね」
「そうね……ずっと、ひとりで、ひとりっぽっちで、こうして歌っていたのね」
ウルウは名残を惜しむように、そっと自鳴琴の蓋に手をかけて、ぱたりと閉じた。
それきり音色は夜の町から消え去って、そうして二度と町の人々を悩ませることはなかった。
一晩明けて、あたしたちはあの不動産屋さんに、自鳴琴を持ち込んで事の顛末を話してみた。他の誰も知らないままで終わるよりは、せめて館の主を弔ってくれたこの人にくらい、知っておいてもらいたかったのだ。
不思議なこともあるもんですなあ、と不動産屋さんはしみじみと自鳴琴を眺めて、それからこう言ったのでした。
「もしかしたら自鳴琴というより、館の幽霊の仕業だったのかもしれませんなあ」
「館の、幽霊?」
「死んでいるわけじゃないから、幽霊というのも変ですがね。長く大事にされたものには魂が宿ることがあるんだそうで、そう言う家や館なんてのが、たまにあたしらの業界で聞かれるんですなあ」
不動産屋さんはどこかいつくしむように自鳴琴を撫でて、思いやるように言葉を紡いだ。それはまさしく、主を失った館への思いやりのようだった。
「何しろ館の主人は、ひとりっぽっちで亡くなっちまって、弔いもあたしと神官だけの寂しいもんでした。その間、町の連中は何にも知らずに賑やかに騒いでいたんですから、館の方でも怒っちまったのかもしれませんな。弔いの間くらいは、静かにしろってね」
それはいつぞやあたしが思い浮かべた、うるさい、だまれ、しずかにしろ、と言っているかのようだという想像の通りだった。
あたしたちがようやく、形ばかりでも館の主に敬意を払ったことで、館は満足したのかもしれなかった。
これは、そんな、奇妙な話だった。
用語解説
・館の幽霊
付喪神のようなものだろうか、この世界でも、長く使われた道具に魂が宿るという考え方があるようだ。