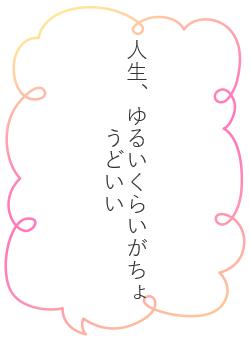7月(湊士パート)
いつもの電車内であるポスターを見つける。それは湊士の学校の近くで8月に祭りがあるというものだ。
(彼女を誘えたらなあ……。でもなあ……)
初めて会話した梅雨の時期から1か月。あれから電車内で目線を合わせて会釈こそするが会話は全くなかった。
(嫌われてはないと思うけど……。もしかして、異性として眼中にない!?)
そう思うと誘うのが途端に怖くなった。断られたら今の関係が壊れそうで嫌だった。
「はあ……」
思わずため息が出る。
ここ最近バスケの練習にも身が入っていない。これではダメだと思いながらも、頭の中では、どうやって美白との距離を縮めるかしかなかった。
ここ最近、学校でも友人二人がポンコツではなくチキンと煽ってくるようになった。
「ようチキン」
「それやめろ。マジで」
「だったらせめて名前くらい聞いて来い」
「ぐぬぬ……」
「おっすー、野郎どもー」
「よお藤宮」
「ちっすー、藤宮―」
「…………」
昴は、登場するなり二人を見比べた。
「……? どったの?」
「あ、うん……。ちょっとね……」
「?」
湊士と凌悟は顔を見合わせて首を傾げた。そして昴からある要求をされる。
「ねえ、平賀くん」
「なに?」
「畠山くんのこと呼んでみて」
「は?」
「いいから」
わけがわからなかったが、とりあえず従っておくことにする。
「おい凌悟」
「なんだチキン」
「よーしケンカだな。買うぜ? ただしバスケでな!」
「チッ」
「おやおや~? 伸び悩んでる俺に勝てない凌悟くんどったのかな~?」
「うっぜえ」
「そうよね」
「? なにが?」
いきなり会話に入り込み、勝手に納得する昴。
「平賀くんは畠山くんを名前で呼ぶわよね?」
「そりゃ、おな中だし」
「そうよね。でさ、もうそろそろいいんじゃないかなって」
「だからなにが?」
「あたしも二人を名前で呼びたい」
ポカンとする湊士と凌悟。何言ってんだと言わんばかりに湊士が口を開く。
「いや、普通に呼べばいいじゃん? 俺ら嫌だって言わねえし」
「そうだな」
「そうなんだ。いや、こういうのってさ。タイミングわかんなくて」
「あー、確かに」
「ん、まあ、そうだな」
「でしょ? で、もう夏だしいいかなって」
別に呼ばれて困ることもなかったので、湊士は快諾する。
「別にいいぞ。じゃあ俺らも昴って呼んでいいか?」
そう言うと、昴はぱあっと表情を明るくして喜んだ。
「もちろん!」
「そんな喜ぶことか?」
「だって二人は最初から名前呼びだったじゃん? 実はずっとハブられてる気がしててどうしようって思ってったの」
「そうだったのか。わりいな。気付けなくって」
「いいわよ。そんなの言われなきゃわかんないでしょ」
「確かに」
これまで昴とは良好な関係だったと振り返る湊士。しかし、今にして思えば、もっと踏み込んでツッコミを入れたりしていい場面があったことを思い出す。今回で言えば湊士のチキンいじりなどがそうだ。
「言わなきゃわからない、か」
「? なにかあったの?」
「あ、いやー、夏祭りがなあ……」
その言葉で察してくれたのか、相談に乗ってくれた。
「そうねえ……。誘っていいんじゃない? って言いたいところだけど……」
「ん? どした?」
歯切れの悪い昴に、何かあるのかと聞いてみる。
「なんていうか……。それって完全にデートじゃん? よっ友クラスの人と二人きりって難しいと思うの」
「だよなあ……」
「それともう一つ」
「なに?」
ちょっと恥ずかしそうにしながら、昴は自分の要求を申し出る。
「あたしたち、一応友人だと思うのよ」
「一応どころか親友だと思ってるぞ」
「ありがと。そう思うのなら、あたしたちとも一つくらい思い出があってもいいと思うの」
「あー、そうだなー。……あー、なるほど」
湊士が昴の言いたいことに気付く。それは凌悟も同じようだった。
「つまりこの3人で夏祭りに行きたいと?」
「まあ、そういうこと。……どう?」
昴に言われ、二人は顔を見合わせる。特にバスケ部員で行こうという話はなかった。なので断る理由もなし。
「いいぜ。友人同士で思い出作りといきますか!」
「ありがと!」
昴はかなりテンションを上げていた。その様子を見て、湊士は嬉しかった。いつも相談に乗ってもらってばかりで、なにか恩返しできないかと常々思っていたからだ。
とはいえやはり電車に乗るたびに、正確に言うなら美白を見るたびにやっぱり一緒に行きたいという欲求に駆られる。そんなある日、車椅子のお婆さんが電車に乗ってきた。湊士は自分のスペースが一番おさまりがいいかなと考え、場所を譲ろうとした。
「お婆さん、ここどうぞ」
「あら、ありがとね」
「いえいえ」
そう言ってお婆さんは車輪を器用に回して湊士が立っていた場所に移動する。
「どこまで行くんですか?」
「いやね。うちの庭でこけちゃって。足のけがを診てもらいに病院へ行くのよ」
車椅子でこける? とどういう状況かわからない湊士に、お婆さんは付け加える。
「ああ、最近こけたわけじゃないの。半年前にこけた怪我の具合を診てもらいにね。この年になると怪我の治りが遅くてねえ」
「ああ、なるほど」
湊士は納得した。しかし、付き人が一人もいないのが気になった。
「あの、お婆さん一人ですか?」
「そうよ。でも、今日転院してね。初めて行く病院だから地図を見ないと迷子になりそうだわ」
それを聞いて湊士は少し考える。そしてある提案を申し出た。
「あの、よかったら俺が病院まで送りましょうか?」
お婆さんは驚いた表情をしたが、笑って断った。
「いいのよ。学校があるでしょ?」
「1回くらい遅刻してもいいですよ。お婆さんも1回病院に行けば次から場所わかるでしょ?」
「でもねえ……」
お婆さんが自分のせいで学生を連れ回すことに抵抗を感じており、なかなか承諾してくれない。
もちろん、湊士は絶対についていきたいわけじゃない。単純に困っている人を放っておけないだけだった。そんな湊士の姿を見たからなのか、美白も援護してくれる。
「あの、私は生徒会に所属しているので、病院から学校側に連絡を入れれば学校も許してくれると思いますので、大丈夫ですよ」
お婆さんもそうだが、湊士も美白が付いてきてくれることに驚いていた。
結果、お婆さんは若者二人の情熱に押され、助けてもらうことに決めたようだった。
「悪いわねえ。じゃあ、お願いしようかしら」
「はい!」
そうして3人は病院を目指した。
その間に、二人はお婆さんからいろいろ身の上話を聞かされた。息子がいるが、仕事で付き添いは無理なこと。孫はちょうど湊士たちと同い年くらいなので学校へ行っていること。
車椅子は湊士が押し、美白がスマホでナビしてくれる形で賑やかに病院を目指した。
その間、美白はちょうどいいところで相槌を打ったり、時折質問してみたりと、かなりの聞き上手であることがわかった。
そうこうしていると、あっという間に病院へ到着した。
「ありがとね。おかげで助かったわ」
「いえいえ」
「それじゃあね」
そう言ってお婆さんは病院へ入っていった。
「あの、私も病院から学校側に連絡を入れるんですけど……。平賀くんはどうします?」
「ああ、俺も連絡入れとこうかな」
「じゃあ、行きましょうか」
そうして二人も病院の受付に説明し、学校に連絡を入れてもらえることになった。
「じゃあ、重役出勤といきますか」
「ふふっ、そうですね」
帰りは前の時とは違い、いろんな話が弾んだ。
バスケ部のこと。学校のこと。そして夏祭りの話題が出る。
「そういえば今度の夏祭り、君は行くの?」
「うん。友達と一緒に」
「そっか」
いっしょに行けなくて残念、と思ったが恋人と一緒じゃないというだけで元気が出た。
こんなに話したのは初めてで、今なら名前を聞けるんじゃないかと思ったが、それはそれでナンパみたいで嫌だと湊士は思った。
「平賀くんは?」
「え?」
「夏祭り。誰かといくの?」
「ああ、俺も友人と」
「そうなんだ」
湊士は、気のせいかと思ったが、美白がどこか嬉しそうにしていると感じていた。
そうして二人は学校へ向かう。電車内では、さっきまでいろいろ話していたのが嘘のように美白は黙ってしまった。しかし、湊士は気まずいとは思わなかった。というか、湊士にも美白のことが少しわかるようになった。だから電車内のマナーに気を使っていると察して、掃除もそれに習った。
湊士が電車を降りるとき、美白に会釈する。美白も同じように返してくれたとき、「ああ、やっぱり」と湊士は思った。
「で、結局チキって名前は聞けずじまいと」
「ちきたんんじゃないですぅー。モラルを持ってこうどうしただけですぅー」
案の定、凌悟が茶化してきた。昴もあきれ果てて頭を抱えていた。
「てかさ。向こうが友達と夏祭りに行くならあたしたちと一緒でいいじゃん。なんで誘わなかったの?」
昴の質問に、湊士は当たり前のように答える。
「だって今回は俺らの思い出作りだろ? だから今回は俺らだけ。彼女とて例外じゃない」
「ふーん。あたしに気を使ってくれたんだ?」
「そういうわけじゃないけどさ」
「まあいいわ。一応お礼言っとく。ありがと」
「別にいいけど。どういたしまして」
そんなやりとりを見て、凌悟がボソッと呟く。
「ほんと、お前は一手先を行くな」
「ん? なんか言った」
「いーや、なにも」
湊士は何だろうと思ったが、凌悟なら言いたいことがあるなら言うだろうと思い、気にしないことにした。
「そういえば平賀くん――じゃなかった。湊士さ」
「なんじゃらほい」
そこで湊士はあることに気付く。
「あれ?」
「どうしたの?」
「今日病院行ったときさ。彼女と一緒だったんだけど」
「知ってる」
「でさ、確か平賀くんって呼ばれたような……」
「気のせいじゃない? だって教えてないんでしょ?」
「そうなんだよな……。やっぱり気のせいか」
しかし、湊士が美白との会話を忘れるわけがなかった。なぜ自分の名前を知っていたのか。気になるが、あまり詮索すると失礼かと思い、気のせいということにしておくのだった。
いつもの電車内であるポスターを見つける。それは湊士の学校の近くで8月に祭りがあるというものだ。
(彼女を誘えたらなあ……。でもなあ……)
初めて会話した梅雨の時期から1か月。あれから電車内で目線を合わせて会釈こそするが会話は全くなかった。
(嫌われてはないと思うけど……。もしかして、異性として眼中にない!?)
そう思うと誘うのが途端に怖くなった。断られたら今の関係が壊れそうで嫌だった。
「はあ……」
思わずため息が出る。
ここ最近バスケの練習にも身が入っていない。これではダメだと思いながらも、頭の中では、どうやって美白との距離を縮めるかしかなかった。
ここ最近、学校でも友人二人がポンコツではなくチキンと煽ってくるようになった。
「ようチキン」
「それやめろ。マジで」
「だったらせめて名前くらい聞いて来い」
「ぐぬぬ……」
「おっすー、野郎どもー」
「よお藤宮」
「ちっすー、藤宮―」
「…………」
昴は、登場するなり二人を見比べた。
「……? どったの?」
「あ、うん……。ちょっとね……」
「?」
湊士と凌悟は顔を見合わせて首を傾げた。そして昴からある要求をされる。
「ねえ、平賀くん」
「なに?」
「畠山くんのこと呼んでみて」
「は?」
「いいから」
わけがわからなかったが、とりあえず従っておくことにする。
「おい凌悟」
「なんだチキン」
「よーしケンカだな。買うぜ? ただしバスケでな!」
「チッ」
「おやおや~? 伸び悩んでる俺に勝てない凌悟くんどったのかな~?」
「うっぜえ」
「そうよね」
「? なにが?」
いきなり会話に入り込み、勝手に納得する昴。
「平賀くんは畠山くんを名前で呼ぶわよね?」
「そりゃ、おな中だし」
「そうよね。でさ、もうそろそろいいんじゃないかなって」
「だからなにが?」
「あたしも二人を名前で呼びたい」
ポカンとする湊士と凌悟。何言ってんだと言わんばかりに湊士が口を開く。
「いや、普通に呼べばいいじゃん? 俺ら嫌だって言わねえし」
「そうだな」
「そうなんだ。いや、こういうのってさ。タイミングわかんなくて」
「あー、確かに」
「ん、まあ、そうだな」
「でしょ? で、もう夏だしいいかなって」
別に呼ばれて困ることもなかったので、湊士は快諾する。
「別にいいぞ。じゃあ俺らも昴って呼んでいいか?」
そう言うと、昴はぱあっと表情を明るくして喜んだ。
「もちろん!」
「そんな喜ぶことか?」
「だって二人は最初から名前呼びだったじゃん? 実はずっとハブられてる気がしててどうしようって思ってったの」
「そうだったのか。わりいな。気付けなくって」
「いいわよ。そんなの言われなきゃわかんないでしょ」
「確かに」
これまで昴とは良好な関係だったと振り返る湊士。しかし、今にして思えば、もっと踏み込んでツッコミを入れたりしていい場面があったことを思い出す。今回で言えば湊士のチキンいじりなどがそうだ。
「言わなきゃわからない、か」
「? なにかあったの?」
「あ、いやー、夏祭りがなあ……」
その言葉で察してくれたのか、相談に乗ってくれた。
「そうねえ……。誘っていいんじゃない? って言いたいところだけど……」
「ん? どした?」
歯切れの悪い昴に、何かあるのかと聞いてみる。
「なんていうか……。それって完全にデートじゃん? よっ友クラスの人と二人きりって難しいと思うの」
「だよなあ……」
「それともう一つ」
「なに?」
ちょっと恥ずかしそうにしながら、昴は自分の要求を申し出る。
「あたしたち、一応友人だと思うのよ」
「一応どころか親友だと思ってるぞ」
「ありがと。そう思うのなら、あたしたちとも一つくらい思い出があってもいいと思うの」
「あー、そうだなー。……あー、なるほど」
湊士が昴の言いたいことに気付く。それは凌悟も同じようだった。
「つまりこの3人で夏祭りに行きたいと?」
「まあ、そういうこと。……どう?」
昴に言われ、二人は顔を見合わせる。特にバスケ部員で行こうという話はなかった。なので断る理由もなし。
「いいぜ。友人同士で思い出作りといきますか!」
「ありがと!」
昴はかなりテンションを上げていた。その様子を見て、湊士は嬉しかった。いつも相談に乗ってもらってばかりで、なにか恩返しできないかと常々思っていたからだ。
とはいえやはり電車に乗るたびに、正確に言うなら美白を見るたびにやっぱり一緒に行きたいという欲求に駆られる。そんなある日、車椅子のお婆さんが電車に乗ってきた。湊士は自分のスペースが一番おさまりがいいかなと考え、場所を譲ろうとした。
「お婆さん、ここどうぞ」
「あら、ありがとね」
「いえいえ」
そう言ってお婆さんは車輪を器用に回して湊士が立っていた場所に移動する。
「どこまで行くんですか?」
「いやね。うちの庭でこけちゃって。足のけがを診てもらいに病院へ行くのよ」
車椅子でこける? とどういう状況かわからない湊士に、お婆さんは付け加える。
「ああ、最近こけたわけじゃないの。半年前にこけた怪我の具合を診てもらいにね。この年になると怪我の治りが遅くてねえ」
「ああ、なるほど」
湊士は納得した。しかし、付き人が一人もいないのが気になった。
「あの、お婆さん一人ですか?」
「そうよ。でも、今日転院してね。初めて行く病院だから地図を見ないと迷子になりそうだわ」
それを聞いて湊士は少し考える。そしてある提案を申し出た。
「あの、よかったら俺が病院まで送りましょうか?」
お婆さんは驚いた表情をしたが、笑って断った。
「いいのよ。学校があるでしょ?」
「1回くらい遅刻してもいいですよ。お婆さんも1回病院に行けば次から場所わかるでしょ?」
「でもねえ……」
お婆さんが自分のせいで学生を連れ回すことに抵抗を感じており、なかなか承諾してくれない。
もちろん、湊士は絶対についていきたいわけじゃない。単純に困っている人を放っておけないだけだった。そんな湊士の姿を見たからなのか、美白も援護してくれる。
「あの、私は生徒会に所属しているので、病院から学校側に連絡を入れれば学校も許してくれると思いますので、大丈夫ですよ」
お婆さんもそうだが、湊士も美白が付いてきてくれることに驚いていた。
結果、お婆さんは若者二人の情熱に押され、助けてもらうことに決めたようだった。
「悪いわねえ。じゃあ、お願いしようかしら」
「はい!」
そうして3人は病院を目指した。
その間に、二人はお婆さんからいろいろ身の上話を聞かされた。息子がいるが、仕事で付き添いは無理なこと。孫はちょうど湊士たちと同い年くらいなので学校へ行っていること。
車椅子は湊士が押し、美白がスマホでナビしてくれる形で賑やかに病院を目指した。
その間、美白はちょうどいいところで相槌を打ったり、時折質問してみたりと、かなりの聞き上手であることがわかった。
そうこうしていると、あっという間に病院へ到着した。
「ありがとね。おかげで助かったわ」
「いえいえ」
「それじゃあね」
そう言ってお婆さんは病院へ入っていった。
「あの、私も病院から学校側に連絡を入れるんですけど……。平賀くんはどうします?」
「ああ、俺も連絡入れとこうかな」
「じゃあ、行きましょうか」
そうして二人も病院の受付に説明し、学校に連絡を入れてもらえることになった。
「じゃあ、重役出勤といきますか」
「ふふっ、そうですね」
帰りは前の時とは違い、いろんな話が弾んだ。
バスケ部のこと。学校のこと。そして夏祭りの話題が出る。
「そういえば今度の夏祭り、君は行くの?」
「うん。友達と一緒に」
「そっか」
いっしょに行けなくて残念、と思ったが恋人と一緒じゃないというだけで元気が出た。
こんなに話したのは初めてで、今なら名前を聞けるんじゃないかと思ったが、それはそれでナンパみたいで嫌だと湊士は思った。
「平賀くんは?」
「え?」
「夏祭り。誰かといくの?」
「ああ、俺も友人と」
「そうなんだ」
湊士は、気のせいかと思ったが、美白がどこか嬉しそうにしていると感じていた。
そうして二人は学校へ向かう。電車内では、さっきまでいろいろ話していたのが嘘のように美白は黙ってしまった。しかし、湊士は気まずいとは思わなかった。というか、湊士にも美白のことが少しわかるようになった。だから電車内のマナーに気を使っていると察して、掃除もそれに習った。
湊士が電車を降りるとき、美白に会釈する。美白も同じように返してくれたとき、「ああ、やっぱり」と湊士は思った。
「で、結局チキって名前は聞けずじまいと」
「ちきたんんじゃないですぅー。モラルを持ってこうどうしただけですぅー」
案の定、凌悟が茶化してきた。昴もあきれ果てて頭を抱えていた。
「てかさ。向こうが友達と夏祭りに行くならあたしたちと一緒でいいじゃん。なんで誘わなかったの?」
昴の質問に、湊士は当たり前のように答える。
「だって今回は俺らの思い出作りだろ? だから今回は俺らだけ。彼女とて例外じゃない」
「ふーん。あたしに気を使ってくれたんだ?」
「そういうわけじゃないけどさ」
「まあいいわ。一応お礼言っとく。ありがと」
「別にいいけど。どういたしまして」
そんなやりとりを見て、凌悟がボソッと呟く。
「ほんと、お前は一手先を行くな」
「ん? なんか言った」
「いーや、なにも」
湊士は何だろうと思ったが、凌悟なら言いたいことがあるなら言うだろうと思い、気にしないことにした。
「そういえば平賀くん――じゃなかった。湊士さ」
「なんじゃらほい」
そこで湊士はあることに気付く。
「あれ?」
「どうしたの?」
「今日病院行ったときさ。彼女と一緒だったんだけど」
「知ってる」
「でさ、確か平賀くんって呼ばれたような……」
「気のせいじゃない? だって教えてないんでしょ?」
「そうなんだよな……。やっぱり気のせいか」
しかし、湊士が美白との会話を忘れるわけがなかった。なぜ自分の名前を知っていたのか。気になるが、あまり詮索すると失礼かと思い、気のせいということにしておくのだった。