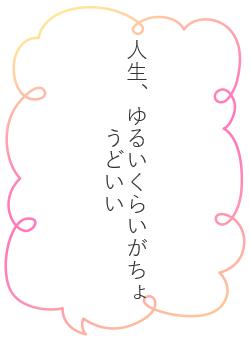5月(湊士パート)
陽光眩しく、暖かな風がなびく中、湊士はデパートに向かうべく電車を待っていた。
「ぬぁぁ……」
時期は金色キラキラゴールデンウィーク。だというのに、相反するように盛大な溜息をついていた。
それもそのはず、休みということは愛しの彼女に会えないということと同義だからだ。
期間にして1週間。今までなら手放しで喜んでいたが、今はそうではない。それほどまでに、湊士は彼女に恋していた。
デパートは学校方面とは逆方向であり、いつもと違い2番ホームということもあり、普段と違う景色に、本当に同じ駅なのかと錯覚する。
いつもと違うホーム。
いつもと違う人混み。
いつもと違う行先。
そんな中、女子高生らしき話し声が聞こえてくる。しかし、周りを見渡しても人混みでよくわからなかった。同い年くらいの女の子の声を聞くだけで美白を連想してしまう自分は、実は変態なのではないかと思い、思わず頭を叩く。
そうこうしているうちに、電車がやってくる。電車の色だけは、見慣れたものだった。
湊士は電車に乗り込むが、予想以上の混雑に辟易としていた。通学のときのいつものポジションに立てなかったので、仕方なく吊革につかまる。
目的地まで各駅停車で4駅なため、我慢できなくはないがそれでも満員電車とは慣れないものだと感じる湊士。基本的に今向かっている方面の方が賑わっているため、平日休日共にこっちが混雑しがちである。逆に通学方面は特別人が集まるような施設はないため湊士と同じ学生しか見当たらない。だから手すりというぼっち御用達の場所は容易に確保できていた。
だが、今は違う。みんなが少しでも楽をしたくてドアにもたれかかったり、人混みを少しでも避けるため、あえて座席前の通路まで進んで立っている人もいる。
湊士は唐突に、電車ってスゲーなと思っていた。
同じ駅から乗ったにも関わらず、こんなにも姿を変えるものなのかと驚きを隠せないでいた。
目的地を変えるだけで様変わりする電車。それは、湊士の心を映しているかのようだった。美白と出会う前、朝練するまでの4月冒頭は1番ホームだった。普通の学生が向かう一般的な方向。そして今は2番ホーム、恋という人混みに心をかき乱されているような感覚だった。
そんなことを考えてしまったのは、電車内でカップルが多かったせいだろう。遊びに行くとしたらこっち方面なので、自然とそういう人も多くなる。湊士は彼女に想いを馳せながら、またもため息をつくのだった。
ようやく目的地に到着し、電車を降りる。改札を出て、駅前にある大型デパートへ向かう。
湊士は目的を果たす前に寄り道することにする。
行先はスポーツ用品店。そこで真新しいバッシュを眺めていた。
「うおっ! このモデル新しいの出たのかよ! くぅ~、テンション上がるなあ!」
湊士はあっちこっちとバッシュを手にとっては試し履きをする。しかし、それらを買う余裕などない。バッシュのみならず、スポーツ用の靴は結構なお値段だからだ。今日は別に買わなければならないものがある。だからこれはただのウィンドウショッピング。湊士は自分にそう言い聞かせて今だけの楽しみとはしゃいでいた。
一通り満足した後、目的の買い物に行こうとしたとき、一人の少年に目が行く。年は小学生高学年と言ったところだろう。同じくバッシュを眺めているところを見るに、バスケ経験者なのだろう。しかし、少年の顔は曇っていた。
「へい少年。そんな暗い顔してどうしたの?」
湊士はしゃがみ込み、視線を合わせながら少年に声をかける。少年は「だれ?」と言いたげな表情を浮かべたが、ぽつりと言葉を漏らす。
「このバッシュが欲しいんだけど、高くってさ……」
少年が指さした先には『NEW!』と書かれたポップが踊る子供用のバッシュがあった。
湊士は値札を確認すると、9,800円と書いてある。確かに小学生には厳しい額だ。
「お父さんかお母さんは?」
「今、夕飯の買い物してる」
「そっか。おねだりできないの?」
「無理。今月新しいゲーム買ってもらったばっかりだし」
「なるほどね」
流石にそりゃ無理だと思う湊士。だからと言って自分が買ってあげるには高すぎる買い物だ。しかし、同じバスケ好き同士何とかしてあげたいと思っていた。
「うーん……」
湊士が辺りを見回すと、とある人混みが目に入る。
「あれ、なんだろう」
「イベントだよ。10回連続でゴール出来たら商品券がもらえるんだ」
少年の言うとおり、参加者らしき男性がチャレンジしていたが、ちょうどミスっているところを目撃する。
「ああーっと! 残念! あと2回だっただけに悔やまれますね!」
司会者の声が湊士たちの方へも聞こえてくる。チャレンジャーの男性も悔しそうにしていた。
「へえ……。あれ、クリアしたらいくらもらえるんだろ?」
「1万円分の商品券だって。ここでしか使えないけど」
「スゲーじゃん! チャレンジしないの?」
湊士がはしゃいでいると、少年はがっくり肩を落とす。
「さっきやってきた。1回目で失敗しちゃった」
「あちゃー……。そっかー……」
湊士が頭を抱えると、少年は今にも泣きそうな顔になる。それを見た湊士は少年の頭にぽんっと手を置く。
「なあ少年。悔しいのはバッシュが買えないから? それともミスしたことが?」
少年は、小刻みに震えていた。やがて乱暴にぐしぐしと目をこすって答えた。
「…………両方」
「そっか。あのバッシュじゃないとダメなのか?」
「ううん。でも、今使ってるバッシュ、サイズが合わなくなってきてさ。新しいの欲しいんだ」
「なるほどな。そりゃ、欲しくもなるよな」
湊士は腰を上げると、イベント会場へ歩を進める。
「え、ちょっと、お兄さん?」
「ふははー。ここはお兄さんに任せとけ」
湊士は自信満々に答え、ニカっと笑ってみせた。
湊士が会場に着くと、でっかいボードが目に付いた。そこには、
『10回連続ゴールで商品券1万円プレゼント!』
と書かれていた。そして小さく、有効期限はゴールデンウィーク中のみだということ。この店でしか使えないことなど、細かな注意書きがなされていた。恐らく4月に新生活を送った学生がすでにスポーツ用品を一式購入済みで、追加で購入する人が少ないから始めたイベントであること。そしてこういうイベントで盛り上げることでお祭り効果で買い物してくれたら御の字ということだろう。そしてなにより――
「ったく、ひでえな、こりゃ」
湊士がゴールを見て悪態をついた。それもそのはず、ゴールの高さが明らかに大人用の高さに設定されてあったからだ。
小学生・中学生用のスポーツ用品は大人用に比べて安い傾向が多い。だからこれは最初から大人向けに用意されたイベントなのだ。子供が寄ってきて、自分に無理だと思ったらダメ元で父親に頼むなどするだろう。しかし、その父親が経験者ならまだしも素人なら問題外だ。さらに経験者であっても、ブランクありで10回連続ゴールは厳しい。なら高校生はというと、この時期に新しいグッズを買うやつは少ないし、強豪校ならそもそも練習しているだろう。湊士のような公立校の生徒ならぶっちゃけ遊んでいる。
万が一ゲットした人が現れても、それはそれで盛り上がって店にとってはいいこと尽くめという訳だ。
さらには元を取るためか、『参加費500円』と書かれている。つまり単純計算で20人に1人クリアできてもトントンなのだ。
湊士はため息をつきながら、ゴールを睨みつける。そして、
「まあ、やることやるだけか」
そう言って湊士は大声で司会者に声をかける。
「あのー! 参加したいんですけどー!」
湊士の声に、司会者が反応する。
「おーっと! またも挑戦者が現れたぞ! では、こちらへどうぞー!」
司会者の案内で受付に参加費を支払い、ボールを受け取る。そして、フリースローラインに立つ。
司会者がいろいろ言って場を盛り上げているのがわかる。そして同時に、これは参加者の集中を乱す罠でもあった。だから湊士はいつもどおりの平常心に戻ることにする。
ボールをシュルシュルっといわせながら回転させ、ダムッと1回ドリブルする。そして、シュートの体勢を取ってボールを放る。
ザシュっといい音をさせながらボールはきれいにゴールを潜り抜ける。
「おめでとう! さあ、まずは1本だ!」
司会者の声でギャラリーが沸く。周りから「これはいけるんじゃ?」みたいな声もちらほら聞こえる。しかし、湊士の耳には届かない。完全に集中モードに入っている。
そして、続く2本目、3本目と難なく決めていく。全く同じ軌道でゴールに吸い込まれていくボールに、少年は唖然としていた。
「すぅー、ふぅー」
深呼吸してしっかり間を取る。湊士は当たり前のようにシュートを成功させていく。そして、ついにラスト1本ということろまできた。
いつの間にかギャラリーの数は増え、成功する瞬間を今か今かと待っていた。
「さぁー! ラスト1本です! ここで決めれば商品券1万円! では張り切っていきましょう!」
司会者がこれでもかと盛り上げてくる。しかし、熱を帯びた空気とは反対に、湊士の心は冷静だった。ラスト1本で商品券をゲットできる、などという気持ちは一切ない。そこにはただ、シュートを通学路を歩くように当たり前にこなそうとする高校生がいた。
湊士はまたも、ボールをシュルシュルっといわせながら回転させ、ダムッと1回ドリブルする。毎回やっていたので、ここからシュートを打つことが周りにも伝わる。すると一変して場は静まり返る。聞こえてくるのは運営が用意したドラムロールの音。
湊士は同じフォームで気負うことなくシュッとボールを放つ。そして――
――ザシュ
ボールはきれいな弧を描いてゴールした。
「おめでとうございまーっす! チャレンジクリアー!」
司会者の声と同時に周りから歓声が上がる。そこでようやく我に返る湊士。
「…………え、あ、終わったのか」
今更になって指先がピリピリ痺れてくる。自分では気が付かなかったが、相当緊張していたようだ。
「いやー、すごいですね! もしかしてバスケ経験者ですか?」
司会者が湊士にマイクを向けて質問してくる。
「あ、はい。一応、現役でバスケやってます」
「なるほどー、バスケ部員でしたか! 素晴らしい! ぜひお名前をお聞かせください!」
「えっと……平賀湊士です。クリアできてよかったです」
「ありがとうございましたー! こちら、チャレンジクリア商品となります!」
そう言って渡されたのは、この店限定の商品券。ご丁寧に小綺麗な封筒に入っていた。
「ちなみに何に使うかは決まってますか?」
司会者がそう訊ねてくると、湊士は真っ直ぐ少年の方へ歩いていく。
「ほら、これでバッシュが買えるな」
「――え?」
少年はキョトンとした表情で湊士を見上げる。
「おや? 先ほどチャレンジされたお子さんですね。弟さんですか?」
「いえ、名前も知らない子です。今日ここで会いました」
会場が一気にざわつく。それもそのはず、見知らぬ少年にせっかくの商品券を渡すなど、どういうつもりなのか誰もわからなかったからだ。
司会者を含めた全員の疑問に答えるかのように、湊士はニカっと笑って商品を少年に渡した。
「俺はただの代理人ですよ。この子のリベンジを代わりにやった。それだけです」
周りがポカンとした感じで静まり返る。しかし、どこからともなく、拍手の音が鳴り、やがて周りに広がっていく。
「なんということでしょう! この素晴らしき青年に盛大な拍手をお願いします!」
司会者が煽ってくれたおかげで、一躍この店のスターとなった湊士。そして、湊士は少年にある提案をした。少年は嬉しそうに快諾し、目的のバッシュを求めて商品棚へ向かっていった。
「何かなさるんですか?」
司会者が疑問に思ったのか、湊士に何をするつもりなのか聞き出そうとする。
「特別な事、ですね。特にバスケ選手にとっては」
訳が分からないといった様子の司会者をよそに、バッシュを買ってきた少年が湊士の元にやってくる。
「お待たせ!」
「おう。じゃあバッシュ履いてみ?」
「うん!」
少年は嬉しそうに真新しいバッシュを履く。そして、
「じゃあお願い!」
「おう」
そう言って湊士は靴を脱ぎ、バッシュを踏んだ。その様子を見て、司会者も流石に理解した。
バッシュは真新しいと硬いため、怪我をしやすい。そのため、少し使い古した感じにすることによって怪我の防止をする風習がある。そして、基本的にはチームメイトがやってくれることが多いのだが、湊士の希望でぜひ自分が最初にやりたいと申し出たのだ。
「なあ、俺もいいか?」
どこの誰だろうと声の主を見ると、湊士の前に失敗したチャレンジャーの人だった。彼は嬉しそうに二人を見つめていた。
「俺もバスケが好きでね。会社でバスケクラブに入ってるんだが、いやはや……。見事だったよ」
「ありがとうございます」
湊士は丁寧にお辞儀をする。少年は少し緊張したようにペコっと頭を下げた。
「キミのルーティーンは完璧だね。俺は基本的にそういうのをしないから、集中が乱されてしまったよ」
「いえいえ、たまたまですよ」
湊士とおじさんが会話していると、湊士の手をぐいぐいと少年が引っ張った。
「ん? どした?」
「ねえ、るーてぃーん? ってなに?」
「ああ、ルーティーンってのはね。特定の動作をすることだよ」
「???」
少年はまだよく理解できていないようだった。
「えっと、俺の場合、シュート前にボールを回転させて1回ドリブルしてたろ?」
「うん」
「あれってシュートを打つのに関係ない動きだろ?」
「うん。でもそういうことやってる友達けっこういるよ」
「そう。それがルーティーン。基本的にバスケだとフリースローの時くらいかな? 練習中にシュートを打つ前に自分だけの動作をやっておくんだ。そしたら試合でも練習と同じ気持ちでシュートを打てるから成功率が上がるんだよ」
「へぇー」
「まあ、気持ち程度だけど、やらないよりマシかな」
「じゃあ俺も同じのやる!」
「ははっ、じゃあお揃いだな」
「うん!」
「おーい、俺のことも忘れないでくれよ」
おじさんが話しかけてきて、湊士は慌てて謝る。
「すいません! バスケのことになると熱くなちゃって……」
「ははは、いや、いいんだ。それで少年。俺にもバッシュを踏ませてくれないか? もちろん靴は脱ぐよ。泥で汚れるからね」
「おじさんも相当バスケ好きですね」
「まあね。で、どうだい?」
おじさんに提案されて、少し迷っていたが、やがてコクンと頷き、足を差し出す。
「ありがとう。では」
おじさんがバッシュをギュッと踏む。そこには若いバスケ選手を応援するエールが込められていた。
「じゃあ、俺はこれで」
「はい。では」
おじさんは手を振りながら去っていった。続いて少年も家族の元へ帰るようで、店を出ようとする。
「じゃあね、お兄ちゃん! また会おうね!」
「おう!」
そう言い残し。少年は去っていった。少年を見送った後、湊士はハッとしスマホを見る。
結構な時間が経っていたらしく、慌てて本来の目的を果たそうとする。
「いっけね」
湊士は早歩きで目的の花屋へ向かった。
色とりどりの花と木製のモダン風な看板が特徴の花屋へ到着する。
「いらっしゃいませ」
女性の店員の声が聞こえて、湊士は質問してみる。
「あのー、カーネーションありますか?」
「はい、ございますよ。何本ご入用ですか?」
「あ、じゃあ1本で」
「かしこまりました」
ただの1本の花だというのに、店員は丁寧に梱包してくれる。
「学生さんですか?」
「え? あ、えっと、高校生です」
「そうなんですね。これは母の日用に?」
「ええ、まあ」
店員は嬉しそうに話しかけてくる。
「まだ若いのに感心ですね。でも、母の日って来週なんじゃ?」
「あ、来週は部活があって買い物に行けないんですよ。だから前倒ししようかなって」
「なるほど、きっとお母さんも喜ぶと思いますよ」
そんな会話をしているとあっという間に包装紙で包んでくれて、しかもピンクのバラまでついていた。
「え? あの……これ……」
「こっちは私からのサービスです」
「あ、ありがとうございます」
物珍しい薄ピンク色のバラに、湊士は目を奪われていた。
「気に入っていただけました?」
「はい! どうもありがとうございます!」
「それはよかった」
湊士は会計をしている時も、バラの方に夢中で心ここにあらずといった様子だった。
「そこまで気に入っていただけるとよかったです。ありがとうございました」
店員に見送られて店を出る。そして湊士は帰路につくことにした。その間、花が折れてしまわないか慎重に持って帰ろうとした。
帰りの電車の中で、湊士は美白のことを考えていた。
(花、かあ。今時バラを渡すなんて、キザったらしいよなあ。女の子って花を贈られると喜ぶって聞くけど、あの子はどうだろう? 花は好きかな。好きならどんな花が好きだろう)
湊士はバラを眺めながら悶々と想像力を発揮し、いろんなシチュエーションを考える。
その度に恥ずかしくなって顔を真っ赤にさせていた。
(まあ、名前も知らないやつから花を貰ったら恐怖か)
冷静さを取り戻し、ため息をつく湊士。
地元の最寄り駅にたどり着くと、不思議な感覚に包まれる。
いつもここから彼女との時間はスタートする。でも、今日はこれで終わり。そんな日々ももうすぐ終わる。いや、むしろまた始まるのだ。通学路で、彼女との時間を共有できる唯一の時間。湊士にはそれが待ち遠しくて、思わず1番ホームを眺めていた。
陽光眩しく、暖かな風がなびく中、湊士はデパートに向かうべく電車を待っていた。
「ぬぁぁ……」
時期は金色キラキラゴールデンウィーク。だというのに、相反するように盛大な溜息をついていた。
それもそのはず、休みということは愛しの彼女に会えないということと同義だからだ。
期間にして1週間。今までなら手放しで喜んでいたが、今はそうではない。それほどまでに、湊士は彼女に恋していた。
デパートは学校方面とは逆方向であり、いつもと違い2番ホームということもあり、普段と違う景色に、本当に同じ駅なのかと錯覚する。
いつもと違うホーム。
いつもと違う人混み。
いつもと違う行先。
そんな中、女子高生らしき話し声が聞こえてくる。しかし、周りを見渡しても人混みでよくわからなかった。同い年くらいの女の子の声を聞くだけで美白を連想してしまう自分は、実は変態なのではないかと思い、思わず頭を叩く。
そうこうしているうちに、電車がやってくる。電車の色だけは、見慣れたものだった。
湊士は電車に乗り込むが、予想以上の混雑に辟易としていた。通学のときのいつものポジションに立てなかったので、仕方なく吊革につかまる。
目的地まで各駅停車で4駅なため、我慢できなくはないがそれでも満員電車とは慣れないものだと感じる湊士。基本的に今向かっている方面の方が賑わっているため、平日休日共にこっちが混雑しがちである。逆に通学方面は特別人が集まるような施設はないため湊士と同じ学生しか見当たらない。だから手すりというぼっち御用達の場所は容易に確保できていた。
だが、今は違う。みんなが少しでも楽をしたくてドアにもたれかかったり、人混みを少しでも避けるため、あえて座席前の通路まで進んで立っている人もいる。
湊士は唐突に、電車ってスゲーなと思っていた。
同じ駅から乗ったにも関わらず、こんなにも姿を変えるものなのかと驚きを隠せないでいた。
目的地を変えるだけで様変わりする電車。それは、湊士の心を映しているかのようだった。美白と出会う前、朝練するまでの4月冒頭は1番ホームだった。普通の学生が向かう一般的な方向。そして今は2番ホーム、恋という人混みに心をかき乱されているような感覚だった。
そんなことを考えてしまったのは、電車内でカップルが多かったせいだろう。遊びに行くとしたらこっち方面なので、自然とそういう人も多くなる。湊士は彼女に想いを馳せながら、またもため息をつくのだった。
ようやく目的地に到着し、電車を降りる。改札を出て、駅前にある大型デパートへ向かう。
湊士は目的を果たす前に寄り道することにする。
行先はスポーツ用品店。そこで真新しいバッシュを眺めていた。
「うおっ! このモデル新しいの出たのかよ! くぅ~、テンション上がるなあ!」
湊士はあっちこっちとバッシュを手にとっては試し履きをする。しかし、それらを買う余裕などない。バッシュのみならず、スポーツ用の靴は結構なお値段だからだ。今日は別に買わなければならないものがある。だからこれはただのウィンドウショッピング。湊士は自分にそう言い聞かせて今だけの楽しみとはしゃいでいた。
一通り満足した後、目的の買い物に行こうとしたとき、一人の少年に目が行く。年は小学生高学年と言ったところだろう。同じくバッシュを眺めているところを見るに、バスケ経験者なのだろう。しかし、少年の顔は曇っていた。
「へい少年。そんな暗い顔してどうしたの?」
湊士はしゃがみ込み、視線を合わせながら少年に声をかける。少年は「だれ?」と言いたげな表情を浮かべたが、ぽつりと言葉を漏らす。
「このバッシュが欲しいんだけど、高くってさ……」
少年が指さした先には『NEW!』と書かれたポップが踊る子供用のバッシュがあった。
湊士は値札を確認すると、9,800円と書いてある。確かに小学生には厳しい額だ。
「お父さんかお母さんは?」
「今、夕飯の買い物してる」
「そっか。おねだりできないの?」
「無理。今月新しいゲーム買ってもらったばっかりだし」
「なるほどね」
流石にそりゃ無理だと思う湊士。だからと言って自分が買ってあげるには高すぎる買い物だ。しかし、同じバスケ好き同士何とかしてあげたいと思っていた。
「うーん……」
湊士が辺りを見回すと、とある人混みが目に入る。
「あれ、なんだろう」
「イベントだよ。10回連続でゴール出来たら商品券がもらえるんだ」
少年の言うとおり、参加者らしき男性がチャレンジしていたが、ちょうどミスっているところを目撃する。
「ああーっと! 残念! あと2回だっただけに悔やまれますね!」
司会者の声が湊士たちの方へも聞こえてくる。チャレンジャーの男性も悔しそうにしていた。
「へえ……。あれ、クリアしたらいくらもらえるんだろ?」
「1万円分の商品券だって。ここでしか使えないけど」
「スゲーじゃん! チャレンジしないの?」
湊士がはしゃいでいると、少年はがっくり肩を落とす。
「さっきやってきた。1回目で失敗しちゃった」
「あちゃー……。そっかー……」
湊士が頭を抱えると、少年は今にも泣きそうな顔になる。それを見た湊士は少年の頭にぽんっと手を置く。
「なあ少年。悔しいのはバッシュが買えないから? それともミスしたことが?」
少年は、小刻みに震えていた。やがて乱暴にぐしぐしと目をこすって答えた。
「…………両方」
「そっか。あのバッシュじゃないとダメなのか?」
「ううん。でも、今使ってるバッシュ、サイズが合わなくなってきてさ。新しいの欲しいんだ」
「なるほどな。そりゃ、欲しくもなるよな」
湊士は腰を上げると、イベント会場へ歩を進める。
「え、ちょっと、お兄さん?」
「ふははー。ここはお兄さんに任せとけ」
湊士は自信満々に答え、ニカっと笑ってみせた。
湊士が会場に着くと、でっかいボードが目に付いた。そこには、
『10回連続ゴールで商品券1万円プレゼント!』
と書かれていた。そして小さく、有効期限はゴールデンウィーク中のみだということ。この店でしか使えないことなど、細かな注意書きがなされていた。恐らく4月に新生活を送った学生がすでにスポーツ用品を一式購入済みで、追加で購入する人が少ないから始めたイベントであること。そしてこういうイベントで盛り上げることでお祭り効果で買い物してくれたら御の字ということだろう。そしてなにより――
「ったく、ひでえな、こりゃ」
湊士がゴールを見て悪態をついた。それもそのはず、ゴールの高さが明らかに大人用の高さに設定されてあったからだ。
小学生・中学生用のスポーツ用品は大人用に比べて安い傾向が多い。だからこれは最初から大人向けに用意されたイベントなのだ。子供が寄ってきて、自分に無理だと思ったらダメ元で父親に頼むなどするだろう。しかし、その父親が経験者ならまだしも素人なら問題外だ。さらに経験者であっても、ブランクありで10回連続ゴールは厳しい。なら高校生はというと、この時期に新しいグッズを買うやつは少ないし、強豪校ならそもそも練習しているだろう。湊士のような公立校の生徒ならぶっちゃけ遊んでいる。
万が一ゲットした人が現れても、それはそれで盛り上がって店にとってはいいこと尽くめという訳だ。
さらには元を取るためか、『参加費500円』と書かれている。つまり単純計算で20人に1人クリアできてもトントンなのだ。
湊士はため息をつきながら、ゴールを睨みつける。そして、
「まあ、やることやるだけか」
そう言って湊士は大声で司会者に声をかける。
「あのー! 参加したいんですけどー!」
湊士の声に、司会者が反応する。
「おーっと! またも挑戦者が現れたぞ! では、こちらへどうぞー!」
司会者の案内で受付に参加費を支払い、ボールを受け取る。そして、フリースローラインに立つ。
司会者がいろいろ言って場を盛り上げているのがわかる。そして同時に、これは参加者の集中を乱す罠でもあった。だから湊士はいつもどおりの平常心に戻ることにする。
ボールをシュルシュルっといわせながら回転させ、ダムッと1回ドリブルする。そして、シュートの体勢を取ってボールを放る。
ザシュっといい音をさせながらボールはきれいにゴールを潜り抜ける。
「おめでとう! さあ、まずは1本だ!」
司会者の声でギャラリーが沸く。周りから「これはいけるんじゃ?」みたいな声もちらほら聞こえる。しかし、湊士の耳には届かない。完全に集中モードに入っている。
そして、続く2本目、3本目と難なく決めていく。全く同じ軌道でゴールに吸い込まれていくボールに、少年は唖然としていた。
「すぅー、ふぅー」
深呼吸してしっかり間を取る。湊士は当たり前のようにシュートを成功させていく。そして、ついにラスト1本ということろまできた。
いつの間にかギャラリーの数は増え、成功する瞬間を今か今かと待っていた。
「さぁー! ラスト1本です! ここで決めれば商品券1万円! では張り切っていきましょう!」
司会者がこれでもかと盛り上げてくる。しかし、熱を帯びた空気とは反対に、湊士の心は冷静だった。ラスト1本で商品券をゲットできる、などという気持ちは一切ない。そこにはただ、シュートを通学路を歩くように当たり前にこなそうとする高校生がいた。
湊士はまたも、ボールをシュルシュルっといわせながら回転させ、ダムッと1回ドリブルする。毎回やっていたので、ここからシュートを打つことが周りにも伝わる。すると一変して場は静まり返る。聞こえてくるのは運営が用意したドラムロールの音。
湊士は同じフォームで気負うことなくシュッとボールを放つ。そして――
――ザシュ
ボールはきれいな弧を描いてゴールした。
「おめでとうございまーっす! チャレンジクリアー!」
司会者の声と同時に周りから歓声が上がる。そこでようやく我に返る湊士。
「…………え、あ、終わったのか」
今更になって指先がピリピリ痺れてくる。自分では気が付かなかったが、相当緊張していたようだ。
「いやー、すごいですね! もしかしてバスケ経験者ですか?」
司会者が湊士にマイクを向けて質問してくる。
「あ、はい。一応、現役でバスケやってます」
「なるほどー、バスケ部員でしたか! 素晴らしい! ぜひお名前をお聞かせください!」
「えっと……平賀湊士です。クリアできてよかったです」
「ありがとうございましたー! こちら、チャレンジクリア商品となります!」
そう言って渡されたのは、この店限定の商品券。ご丁寧に小綺麗な封筒に入っていた。
「ちなみに何に使うかは決まってますか?」
司会者がそう訊ねてくると、湊士は真っ直ぐ少年の方へ歩いていく。
「ほら、これでバッシュが買えるな」
「――え?」
少年はキョトンとした表情で湊士を見上げる。
「おや? 先ほどチャレンジされたお子さんですね。弟さんですか?」
「いえ、名前も知らない子です。今日ここで会いました」
会場が一気にざわつく。それもそのはず、見知らぬ少年にせっかくの商品券を渡すなど、どういうつもりなのか誰もわからなかったからだ。
司会者を含めた全員の疑問に答えるかのように、湊士はニカっと笑って商品を少年に渡した。
「俺はただの代理人ですよ。この子のリベンジを代わりにやった。それだけです」
周りがポカンとした感じで静まり返る。しかし、どこからともなく、拍手の音が鳴り、やがて周りに広がっていく。
「なんということでしょう! この素晴らしき青年に盛大な拍手をお願いします!」
司会者が煽ってくれたおかげで、一躍この店のスターとなった湊士。そして、湊士は少年にある提案をした。少年は嬉しそうに快諾し、目的のバッシュを求めて商品棚へ向かっていった。
「何かなさるんですか?」
司会者が疑問に思ったのか、湊士に何をするつもりなのか聞き出そうとする。
「特別な事、ですね。特にバスケ選手にとっては」
訳が分からないといった様子の司会者をよそに、バッシュを買ってきた少年が湊士の元にやってくる。
「お待たせ!」
「おう。じゃあバッシュ履いてみ?」
「うん!」
少年は嬉しそうに真新しいバッシュを履く。そして、
「じゃあお願い!」
「おう」
そう言って湊士は靴を脱ぎ、バッシュを踏んだ。その様子を見て、司会者も流石に理解した。
バッシュは真新しいと硬いため、怪我をしやすい。そのため、少し使い古した感じにすることによって怪我の防止をする風習がある。そして、基本的にはチームメイトがやってくれることが多いのだが、湊士の希望でぜひ自分が最初にやりたいと申し出たのだ。
「なあ、俺もいいか?」
どこの誰だろうと声の主を見ると、湊士の前に失敗したチャレンジャーの人だった。彼は嬉しそうに二人を見つめていた。
「俺もバスケが好きでね。会社でバスケクラブに入ってるんだが、いやはや……。見事だったよ」
「ありがとうございます」
湊士は丁寧にお辞儀をする。少年は少し緊張したようにペコっと頭を下げた。
「キミのルーティーンは完璧だね。俺は基本的にそういうのをしないから、集中が乱されてしまったよ」
「いえいえ、たまたまですよ」
湊士とおじさんが会話していると、湊士の手をぐいぐいと少年が引っ張った。
「ん? どした?」
「ねえ、るーてぃーん? ってなに?」
「ああ、ルーティーンってのはね。特定の動作をすることだよ」
「???」
少年はまだよく理解できていないようだった。
「えっと、俺の場合、シュート前にボールを回転させて1回ドリブルしてたろ?」
「うん」
「あれってシュートを打つのに関係ない動きだろ?」
「うん。でもそういうことやってる友達けっこういるよ」
「そう。それがルーティーン。基本的にバスケだとフリースローの時くらいかな? 練習中にシュートを打つ前に自分だけの動作をやっておくんだ。そしたら試合でも練習と同じ気持ちでシュートを打てるから成功率が上がるんだよ」
「へぇー」
「まあ、気持ち程度だけど、やらないよりマシかな」
「じゃあ俺も同じのやる!」
「ははっ、じゃあお揃いだな」
「うん!」
「おーい、俺のことも忘れないでくれよ」
おじさんが話しかけてきて、湊士は慌てて謝る。
「すいません! バスケのことになると熱くなちゃって……」
「ははは、いや、いいんだ。それで少年。俺にもバッシュを踏ませてくれないか? もちろん靴は脱ぐよ。泥で汚れるからね」
「おじさんも相当バスケ好きですね」
「まあね。で、どうだい?」
おじさんに提案されて、少し迷っていたが、やがてコクンと頷き、足を差し出す。
「ありがとう。では」
おじさんがバッシュをギュッと踏む。そこには若いバスケ選手を応援するエールが込められていた。
「じゃあ、俺はこれで」
「はい。では」
おじさんは手を振りながら去っていった。続いて少年も家族の元へ帰るようで、店を出ようとする。
「じゃあね、お兄ちゃん! また会おうね!」
「おう!」
そう言い残し。少年は去っていった。少年を見送った後、湊士はハッとしスマホを見る。
結構な時間が経っていたらしく、慌てて本来の目的を果たそうとする。
「いっけね」
湊士は早歩きで目的の花屋へ向かった。
色とりどりの花と木製のモダン風な看板が特徴の花屋へ到着する。
「いらっしゃいませ」
女性の店員の声が聞こえて、湊士は質問してみる。
「あのー、カーネーションありますか?」
「はい、ございますよ。何本ご入用ですか?」
「あ、じゃあ1本で」
「かしこまりました」
ただの1本の花だというのに、店員は丁寧に梱包してくれる。
「学生さんですか?」
「え? あ、えっと、高校生です」
「そうなんですね。これは母の日用に?」
「ええ、まあ」
店員は嬉しそうに話しかけてくる。
「まだ若いのに感心ですね。でも、母の日って来週なんじゃ?」
「あ、来週は部活があって買い物に行けないんですよ。だから前倒ししようかなって」
「なるほど、きっとお母さんも喜ぶと思いますよ」
そんな会話をしているとあっという間に包装紙で包んでくれて、しかもピンクのバラまでついていた。
「え? あの……これ……」
「こっちは私からのサービスです」
「あ、ありがとうございます」
物珍しい薄ピンク色のバラに、湊士は目を奪われていた。
「気に入っていただけました?」
「はい! どうもありがとうございます!」
「それはよかった」
湊士は会計をしている時も、バラの方に夢中で心ここにあらずといった様子だった。
「そこまで気に入っていただけるとよかったです。ありがとうございました」
店員に見送られて店を出る。そして湊士は帰路につくことにした。その間、花が折れてしまわないか慎重に持って帰ろうとした。
帰りの電車の中で、湊士は美白のことを考えていた。
(花、かあ。今時バラを渡すなんて、キザったらしいよなあ。女の子って花を贈られると喜ぶって聞くけど、あの子はどうだろう? 花は好きかな。好きならどんな花が好きだろう)
湊士はバラを眺めながら悶々と想像力を発揮し、いろんなシチュエーションを考える。
その度に恥ずかしくなって顔を真っ赤にさせていた。
(まあ、名前も知らないやつから花を貰ったら恐怖か)
冷静さを取り戻し、ため息をつく湊士。
地元の最寄り駅にたどり着くと、不思議な感覚に包まれる。
いつもここから彼女との時間はスタートする。でも、今日はこれで終わり。そんな日々ももうすぐ終わる。いや、むしろまた始まるのだ。通学路で、彼女との時間を共有できる唯一の時間。湊士にはそれが待ち遠しくて、思わず1番ホームを眺めていた。