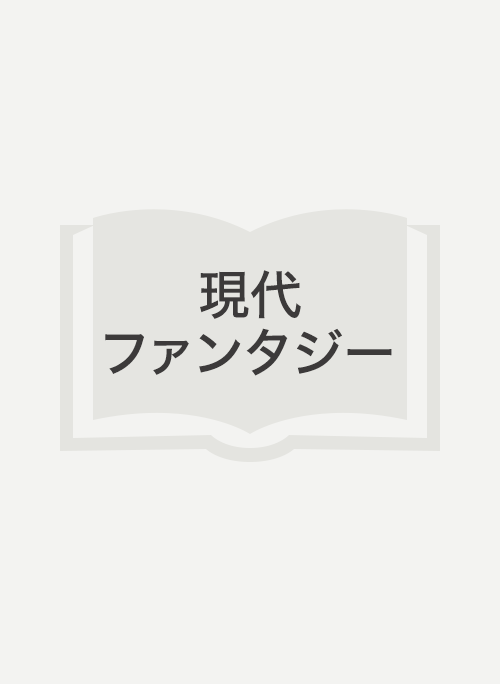感染症対策の効果である。今の取り組みをずっと続ければ、インフルエンザは根絶できそうだ。
10月1日から衣替えになる。上着を着ると暑くなるかもしれない。
筋トレと柔軟体操を欠かさないせいか自分は暑がりである。
とりあえず上着をいつでも着られるように、ズボンを冬用に替えた。
------------------------- 第18部分開始 -------------------------
【サブタイトル】
秋の気配を感じる虫の声
【本文】
8月20日頃からコオロギが鳴き始める。
昼間は蝉が鳴き、夜は秋の虫が鳴くという塩梅だ。
家の中にカマドウマも入ってきた。足と触角が異様に長い、不気味な虫だ。
小学生のときには、平気で虫を触っていたが、中学生くらいから触るのが苦手になってきた。
虫を見て嫌だとは思わないのだが、何となく触りたくない。
小学生のとき、田園地帯に住んでいたので、バッタやイナゴ、カマキリなどが子どものおもちゃになっていた。
捕まえるとよく、足がもげた。
青っぽい体液が出て、宇宙人のようだと思った。
大人でも真顔で、
10月1日から衣替えになる。上着を着ると暑くなるかもしれない。
筋トレと柔軟体操を欠かさないせいか自分は暑がりである。
とりあえず上着をいつでも着られるように、ズボンを冬用に替えた。
------------------------- 第18部分開始 -------------------------
【サブタイトル】
秋の気配を感じる虫の声
【本文】
8月20日頃からコオロギが鳴き始める。
昼間は蝉が鳴き、夜は秋の虫が鳴くという塩梅だ。
家の中にカマドウマも入ってきた。足と触角が異様に長い、不気味な虫だ。
小学生のときには、平気で虫を触っていたが、中学生くらいから触るのが苦手になってきた。
虫を見て嫌だとは思わないのだが、何となく触りたくない。
小学生のとき、田園地帯に住んでいたので、バッタやイナゴ、カマキリなどが子どものおもちゃになっていた。
捕まえるとよく、足がもげた。
青っぽい体液が出て、宇宙人のようだと思った。
大人でも真顔で、