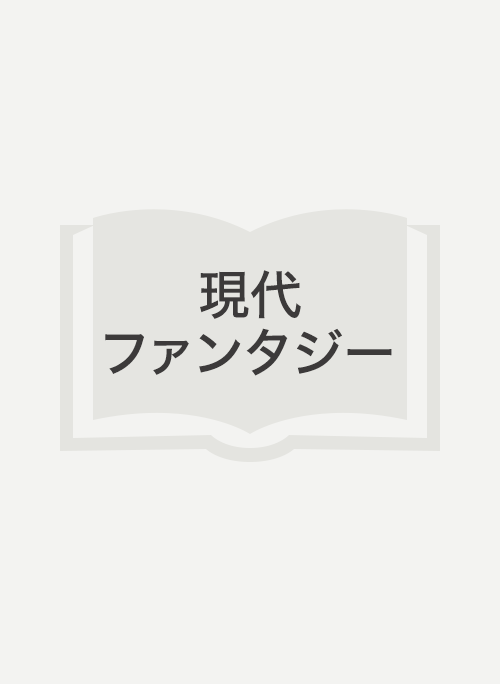完成して、パイプオルガンが演奏される様子をこの目で見て聞きたい。
------------------------- 第11部分開始 -------------------------
【サブタイトル】
火★最近は小学校の理科の実験でホットプレートを使うらしい
【本文】
火★最近は小学校の理科の実験でホットプレートを使うらしい
「そういえば、うちはオール電化だから火を使わなくなったな」
台所に立ったとき、ふと思った。
「そうだね。子どもが火を知らずに育つのは怖いね」
「クリスマスと誕生日ケーキのろうそくに火をつけるとき使ったな」
「キャンプとかあれば見るかも知れないけど」
「俺は小さい頃からガスコンロで、即席ラーメン作って食べてたよ」
妻と台所にいるとき、こんな話題がのぼった。
「キャンプ場でカレーでも作りに行くか」
「カレーはキャンプの定番だね」
「キャンプ場へ行けば、材料も道具も全部あるから簡単だよ」
最近の家はオール電化が増えてきた。
我が家もオール電化なので、コンロはIHである。熱するとき赤い電気が光だけで火は出ない。
------------------------- 第11部分開始 -------------------------
【サブタイトル】
火★最近は小学校の理科の実験でホットプレートを使うらしい
【本文】
火★最近は小学校の理科の実験でホットプレートを使うらしい
「そういえば、うちはオール電化だから火を使わなくなったな」
台所に立ったとき、ふと思った。
「そうだね。子どもが火を知らずに育つのは怖いね」
「クリスマスと誕生日ケーキのろうそくに火をつけるとき使ったな」
「キャンプとかあれば見るかも知れないけど」
「俺は小さい頃からガスコンロで、即席ラーメン作って食べてたよ」
妻と台所にいるとき、こんな話題がのぼった。
「キャンプ場でカレーでも作りに行くか」
「カレーはキャンプの定番だね」
「キャンプ場へ行けば、材料も道具も全部あるから簡単だよ」
最近の家はオール電化が増えてきた。
我が家もオール電化なので、コンロはIHである。熱するとき赤い電気が光だけで火は出ない。