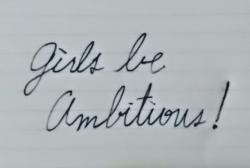それでも、
「二人で行くランチの予約したよ」
とだりあは、大介に少しでも好意を持ってもらいたい部分はあったらしく、はたで見てもいじましいぐらいに健気なところさえ見せた。
「先生はだりあさんのことを、どう見てますか?」
みのりに問われた大介は、
「まぁ素直やし、自分の意見はしっかり持っとるし、タイプに近いと言やぁ近いんやけど、やっぱり百合香と比べてまうし、百合香を超えるほどではないというか」
関係性を知るみのりに大介は、殻を割ったような話し方をした。
「百合香さん、優しかったもんね…」
みのりも百合香がいなくなって、喪失感だけは拭えずにいた。
「人は見た目だという者もあるけど、話してみな分からんことかてある。百合香は最初おとなしそうやったけど、あれでパキパキ物は言いよるし、でも腹が立たんかったんは、何か血がかよってる感じがあったからなんかなって最近は思う」
だりあには、それがあまり感じられなかったらしい。