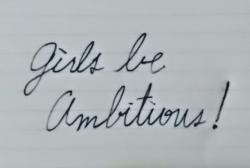彦根の実家に寄らなかった大介は、京都のカプセルホテルに泊まった。
横浜ナンバーのあざやかなブルーのカスタムカブなので、同じカスタムカブで旅をする、名前の分からないライダーから、
「横浜からですか」
と声をかけてもらったりもした。
一台、札幌ナンバーのカスタムカブもいた。
「彼女に振られたんで、人生リセットするつもりで、小樽からフェリーに乗って敦賀から来た」
という大学生で、その日はその大学生と痛飲して、
「自分はこれから西へ行きます」
「うちは横浜へ帰るけど、まぁまた会えたら会おうや」
ひさびさに穏やかな笑顔を取り戻せたような気がした大介は、笑って大学生と別れた。